■東信堂20231212
故早川和男氏が提唱した「居住福祉」は、従来の福祉サービスや生活保護などの福祉と異なり、その前に「安心して暮らせる」ことが人間の幸せの基盤になると説いた。そんな「居住福祉」をになう「居住福祉資源」として、住むための家だけではなく、人々とのつながりをつくる寺社やカフェなどにまで視野を広げた。ビビッドで新鮮な議論だった。
「居住福祉」の基盤には、宇沢弘文のいう「社会的共通資本」、あるいはコモンズなどがある。
「居住福祉」のあり方を支える概念として「生活資本」を提示する。①生活の基盤となる住宅、②生活を支える社会的機能、③生活を支える機能や資源を使いこなす能力、④生活環境を構築する力で構成されるという。
明治以降の政治や経済の流れを見ると、なにが「居住福祉」が阻んできたのかが見えてくる。
明治維新は中央集権体制をつくったが、各地方には、みずから鉄道をしき、産業をおこし、銀行を生み出すというエネルギーがあった。ところが1920年代からの恐慌と不況の連続で、国家の政策的介入が増えて、国家による統制が強まり戦時体制に突入する。
戦後も中央集権がつづき、「出世志向の体質」という「資本主義体制一般ではなくその日本的問題点」が残存しつづける。そして、経済が停滞して出世ポストが減ると、上位者への「忖度」が経営(政治)を支配し、問題をつきつめて考えて事態に最適な解決を導き出す努力を怠るようになる。その結果が現代の閉塞状況だという。
阪神大震災の被害者は生活支援を訴えたが、中央官庁は「住宅は個人の資産であって国の税金を私有財産の形成に投入することは憲法違反」と拒んだ。これもまさに「忖度」による思考停止だった。
一方、小田実や早川らの「市民立法」のとりくみによって1998年に「被災者生活再建支援法」が議員立法で成立した。さらに鳥取県知事は2000年の地震の際、住宅再建に300万円、修理に150万円を援助する制度を創設した。「憲法25条には基本的人権の尊重とある」「住宅支援がダメと憲法に書いているのか?」と中央の思考停止を片山知事は指摘した。
東京一極集中で首都圏は過密にともなうさまざまな弊害がおきてくる。それを打開するため、鉄道新線や高速道路がつくられ、さらなる集中をよびこむ。高い住宅費や保育所不足は少子・高齢化に拍車をかける。首都圏への投資の集中は、地方にも悪影響をおよぼす。
ムダが大きいほどGDPは増大するが、人々の幸福につながらない投資や消費は、財政赤字として蓄積され、教育や福祉への配分を減らし「真の経済成長」を阻害する。経済社会全体を「不効率」にしてきた結果が「失われた30年」だという。
ではどうすればよいのか。
居住福祉資源(社会的ストック)を大切にする社会に転換し、持続的な「居住福祉産業」を育てることだという、居住福祉資源を基盤とした社会資本の整備は、低成長・低賃金・消費低迷・地方衰退という悪循環から地域の「居住福祉資源」を蓄積する経済への回復につながる。コロナにともなう都市から地方への「田園回帰」はそのきっかけになりうる。
具体的になにをどう改善できるのだろう。
震災などをとおして日本の避難所の環境は、ほかの先進国より悪いことがわかってきたが、日常的に居住空間を大切にするようになれば、避難所の環境も改善するはずだ。
WHOは「健康」の定義を「肉体」「精神」「社会」の三分野にわけて考えた。とくに「社会的健康」は新しい概念だ。社会的なつながりの維持や構築が居住福祉の評価軸として浮かび上がってきた。その視点から見ると、避難所の「2年」という年限や、強制的な追いだしなどの問題点が浮き彫りになる。 避難所の国際的な基準である「スフィア基準」もここ数年、注目されるようになってきた。
ウトロでは強制退去の判決が下ったが、韓国で支援がひろがり、韓国政府が土地購入代金を予算化し、京都府や宇治市も居住の事実をみつとめ、公営住宅を建設した。
ヨーロッパ諸国は公的制度として家賃補助がある。コロナで収入減少すると家賃補助は実質的に家賃給付となった。家賃補助があれば、少なくとも居住は維持できることがわかった。
国際的・客観的・普遍的な「人にふさわしい居住水準」を認識し、国際的に連携して行動すれば、日本の居住水準も劇的に改善するのではないか、と結論づけている。
============−
▽13 バルセロナにおける水道の再公営化
▽33「そーね大曽根」の例。生活を支える資源と活動。居住者の生活資本を構築する。
うあるべきかのか、
▽43 2000年ごろ、高齢者、障碍者、外国人などに入居を受け入れるアパートなどの情報を提供するとりくみがはじまる。2006年に「あんしん賃貸支援事業」、2017年に「改正住宅セーフティーネット法」これ以降、空き家を福祉転用する民間のアイデアもひろがっている。
▽73 障碍者施設とのコンフリクト。欧米諸国では、コンフリクトは関係性や状況を前進させるよい機会であるととらえられてきた。……成熟した社会では、コンフリクトが合意形成に至ったあとも、友好的・協力的な関係のもとでさらなる努力がなされる。
……コンフリクトは、施設を地域にとりこんだ、新しい福祉コミュニティを形成する重要な契機。
▽77 施設へのコンフリクト発生の割合がもっとも高いのは「古くからの住宅街」よりも「新興住宅街」だった。
▽82 「地域包括ケアシステム」は、1970年代に広島の旧御調町の医師が提起。
▽83 介護ニーズと死亡者がピークに達すると予測されるのが2040年。
▽きらくえんのとりくみ。施設の社会化が地域包括ケアシステムにつながる。個別援助から、地域包括ケアシステムの構築へ
▽100 神野「経済発展・政治意識」
明治維新は中央集権の体制をつくったが、各地方にはエネルギーがあって、鉄道をしき、産業をおこし、銀行が生まれ……「江戸末まで許されなかった瓦葺きが全戸に普及したということは、明治以降にそれだけの財の蓄積があったことを示す」
▽107 1951年には厚生省の「厚生住宅」奉安と、建設省の「公営住宅」法案が提出され、公営住宅法が成立し、厚生省は住宅行政から撤退することに。
▽108 松下圭一の「シビル・ミニマム」論 福祉施設や、公園・上下水道_地下鉄などのインフラなどの目標値をかかげた自治体計画を作作成し、市民に明示する。革新自治体が主導。宮本憲一の「シビル・マキシム」論。
▽112 松下は、政党・官僚・知識人たちの「出世志向の体質」という「資本主義体制一般ではなくその日本的問題点」が集権的成長政策の基盤。
経済が行き詰まると、出世ポストも減り、上位者への「忖度」が経営を支配するようになる。そこでは「問題をとことんまでつきつめ、それによってその事態にもっとも適合しtあ解決を導き出す」努力を怠るようになる。
▽119 居住福祉資源(社会的ストック)を大切にする社会への転換を。社会全体を活性化させ経済的にも好循環をうむことになる。持続的な「居住福祉産業」への転換を。
▽129 「人権としての居住」は「住居」があるだけではなく、人と人とが支え合う関係があってこそなりたつ。コミュニティの「資源(ストック)」と社会保障の現物給付(フロー)を融合して理解することが重要。
▽133 島根県浜田市弥栄街には「本物の田舎」の暮らしを求め、新住民が集まる。
▽141 居住福祉資源を基盤とした社会資本の整備は、低成長、低賃金の固定、消費の低迷、地方の衰退という、悪循環から地域の「居住福祉資源」を蓄積する実体経済への回復へと好循環軌道に移行する道標の役割を果たせる。コロナウイルス……で、都市から地方に人材が向かう「田園回帰」現象を生み出そうとしている。
▽144 高崎市の山名八幡宮 境内にカフェやパン屋、児童発達相談所をもうけている。
▽161 イギリス ホームレス対策 救貧的な性格から、居住政策の中心へ。
▽164 ヨーロッパ諸国は家賃補助をしている。コロナで収入減少すると、家賃補助は実質的に家賃給付となり、その期間が争点となった。日本には「住居は人権」という認識が一般化していない。一般的な家賃補助は実施されず、「家賃補助」は企業への補助を意味した。……。家賃補助があれば、居住は維持できる。空き家活用の計画があれば住居の困窮を解消できる。





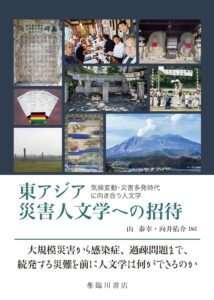


コメント