ちくま文庫 20081001
筑後川の上流、阿蘇山北麓の志屋という小さな集落に、下筌ダムと松原ダムという2つのダム建設計画がもちあがった。
主人公の山林地主・室原知幸は、大正デモクラシーの時代に早稲田で政治を学び、「大学さま」と呼ばれる部落唯一のインテリだった。ダム計画を知った住民たちは憤激し、大学さまに先頭に立ってくれるよう懇願する。村人の覚悟をたしかめて、室原は決断する。
反対運動は、建設省を揶揄する狂歌をばらまくことからはじまり、幟をはためかせ、鳴らし物をたたいて部落から部落を練り歩く。九地建(建設省の出先)が測量を強行しようとすると、蜂の巣橋の対岸の山にプレハブ式の小屋を次々に築き、それを一夜にして移動させる。行政側が強制的に建物などを撤去するには、その位置を特定しなければならない。それを妨害する作戦だった。小屋と小屋の間には渡り廊下を巡らせた。籠城生活を豊かにするようツツジを植え、生け簀をこしらえ、お地蔵さんもまつった。いつしか「蜂の巣城」と呼ばれるようになった。強大な国家権力と知力を尽くして対決する室原の姿は、楠木正成や真田幸村を彷彿とさせる。
だが闘いが長引くにつれて、部落の人々の不安が募る。殿様・室原の独断専横で妥協のない態度への反発もでてくる。2年、3年の年月をへて、反対派がわかれ、敗色が濃くなるにつれて大半の住民は離反していった。
そのかわりに支援したのが、革新勢力だった。東京では60年安保闘争が盛り上がり、隣県の三池炭鉱では巨大な闘争が繰り広げられていた。それらが敗れたあと、孤塁を守って抵抗をつづける蜂の巣城は反権力の象徴となった。
だが、室原自身はリベラリストではあっても左翼ではない。なにより、山林地主の「殿様」である。敗北が明らかになるにつれて革新勢力も離れていく。
最後に心をかよわせたのは、不思議なことに九地建の現地トップの副島たちだった。室原は、土地収用法などの法律を精査してその穴を突き、最後の最後まで訴訟をしかけつづけた。だが一方で、すでに建設がはじまったダムとその周辺をよりよくするための協力は惜しまなかった。
四国の石鎚山で観光道路開発反対運動を展開し、行政と徹底的にたたかいながらも、完成した道路を改善するため、信頼できる行政マンへの協力を惜しまなかった峰雲行男氏と似ている。
強大な国家権力に立ち向かう「一揆」は、一時的に盛り上がったとしても、長引けば退潮し、仲間が離反することは避けられない。非妥協的な闘争を展開する主人公の孤独はいわば宿命だった。だが、闘争についてなにも知らされないまま、夫の命令に従い、友人が次々に去っていくのをただ耐えるしかなかった主人公の妻はさらに孤独だった。そのつらさ、寂しさ、人間らしいあたたかみが、現地の方言の独白によってひしひしと伝わってくる。
これだけ心に染みわたる作品を書けたのは、無力感に苛まれながら、火力発電所反対運動をつづけた筆者の体験があったからだろう。
==================覚え書き・抜粋=====================
▽20 わが町(中津市)の火力発電所建設反対運動が孤立していくにつれて……私たちは海に陸に懸命な阻止行動を展開したが、忽ち海上保安庁の巡視艇に制圧され、陸では機動隊に制されて封じられてしまった。……巨艦に対し、叫びさえ届かぬ徒手空拳のこのむなしい座りこみが、なんの意義を持つのかという苦渋に満ちた自問を振り切って、いや無意味でもいい、一個の反対意志の尊厳をその海岸に屹立させ続けるのだという意地だけに私は必死に執していた。……眼前のクレーン船の群れに憎しみの視線を刺しつつ、私はこの小柄な老人(室原)の勁さをしきりに思い続けた。
▽24
▽32 ダム建設の説明会 水没すると知り、驚きと不安と怒りとが噴出する。華族にどのように話せばいいのか……。 (国家権力がいきなり躍りかかる)
▽43
▽72 「おれには誰も教えちくるるもんがおらん」 田中正造を描いた荒畑寒村の「谷中村滅亡史」を一人朗読する。
▽75
▽79 測量にきた九地建。山腹をよじのぼってきたのを、杉の枯れ枝に火をつけていぶし追い払う。
▽84 柚の皮の砂糖煮をつくっていた ……考えちみますと、人間のしあわせちゅうつは、喪われたあとに気付くごとありますね。柚子椀いじ、柚子搾っち、柚子ん皮をぐつぐつ煮て……そげなこつは、そん頃はしあわせともなんとも気付かん、あたりまえん冬支度みたいなもんでございましたばってん、今になっちみますと、なんかしらん、たまらんごつなつかしゅうしてですねえ、なんか、おとうさんも闘いん大将におさまっちょるつより、……柚子搾りよった方がにおうちょった気がしてなりませんもん。
(石鎚村〓)
▽101
▽121 安部公房が現地へ。が、面会を拒否。「大体、土地収用法第14条がなんであるかも、ろくすっぽ知らないくせに、私に会いたいだなどというのは横着過ぎる。……」ルポルタージュを執筆。
▽134 土地収用法が表からも裏からも、批判され検討されたことは、この下筌ダム論争以前には起こらなかった……国家は室原にてこずった結果を大いに生かして、その後の土地収用法を巧みに改竄していくことで2人目の室原の出現を封じていった。
▽142 土地収用法14条は、測量にあたって障害物を除去できると定めているが、その障害物を「植物若しくはかき、さく等」と限定して記述している。これを字義通り読み取れば、蜂の巣城の小屋は伐除の対象外になるはずだと考えた。民法上の権利を設定すべく居住性を具備した小屋をますます増やしていく。
小屋作りも組立ハウス方式を採用し、夜の内に組み立てた。障害物伐除には障害物1個1個の所在位置・形状等を特定せねばならない。その記録を攪乱する狙いがあった。
▽146 強烈な殿様、室原への反発がふくらむ。だが知将室原と共に在る限り、この闘いに勝つかもしれない。勝利した暁には、闘いに非協力だった者は村八分にされるだろう……
▽149 安保でもの規制に全警察が集中していたため、蜂の巣城の立ち入りはそれ以降になった。国家権力がすさまじい敵意で学生達を叩き伏せていく光景。自分達が対決している国家の正体が剥き出しとなって迫り、一人一人の心中を震え上がらせていた。
(山の中の闘いが否応なく全国とつながっていく)
▽198 村人は平和的に解決してほしいが、室原はそれを許さない。三池の騒動が他人事でなくなった。……ダム反対の指導層が部落の人からだんだん外部の人に変わっていく。その人達は単に利用しているのではないか。……或時期になれば当然三池の第二組合的な発生する事になろう。部落内同士のいがみ合いが起こるのではないか。
▽203 「守れ墳墓の地」のスローガンの下に結束して来たイデオロギー抜きの土着闘争が変質し始める。九地建職員の視点「ダム建設の結果、山林地主、室原氏を中心とする封建的支配体制が崩壊して、水没者が生活の再建の途を講ずるとすれば、現在の補償体系しかのがれ路がない……封建的支配から解放せられて自由な生活が出来るという点よりして、革新陣営からは協力を得ることはあっても……」
▽212
▽219 しだいに部落内部から九地建側に内応する者がでてくる。表だって分裂する3年前から。「国がもっと強硬に攻め込んでくれると、自分達も砦から離脱し易くなるのだが」
▽236 砦の生活を耐えやすくするため、地蔵を探しもとめ、お大師さんが夢枕にたつ話もつくりあげた。……砦の暮らしを村そのもののように日常化したいと考えた。生け簀を築き鯉や鱒を放ったり、あひるを飼い、菜園をつくり、ツツジを植え込み……
▽255
▽268 国は判決の1カ月前に既に勝訴の情報を得ていた。石田裁判長は室原を勝たせたいと思っていたが、両陪席が説得して国を勝訴させることになった。
▽270 「石田さんが、兄貴に無言で抱きついて来てですな……済まんじゃった、ゆるして呉れちゅうて謝ってですなあ……」 現職の裁判官がわざわざ謝りに……
▽274 控訴審は、公判期日に出廷を怠り……休止満了で終わってしまった。室原と弁護士の関係が疎遠になっていたからだろう。
▽289 庭石にも植木にも池にも鯉にも補償金が付く、と、茶の木を植え、杉を植え、大きな石を運び込み……
平和な共同体が音をたてて破綻していく。(伊方原発と同じ)
▽307 部落の者達が砦を降りたのと入れ替わりに革新労働組織の支援が本格化する。「下筌の戦いの本質は池田政府の軍国主義、帝国主義復活の経済的基盤、すなわち所得倍増計画の根幹をつき、これに反対する戦いであることがあきらかになりました。……」
しかし谷間の者達にはこのような趣旨は理解を超えていた。
▽315 大島渚「この闘争には階級的視点が感じられません。まあ、室原さんのお遊びみたいなもんでしょう」。気鋭の大島が蜂の巣城に籠もる革新オルグについ放ってしまった痛烈な揶揄。室原は「共産党も社会党も応援に来るのが遅すぎたくらいじゃ。自民党はまだこんのか--」没イデオロギー。オルグ側は、この闘争を彼ら独自の革新戦略に基づく労農提携の戦線として色づけようと腐心している。
▽360 新河川法は、室原にてこずった国が新法を以て河川管理者を従来の県知事から一級河川に限り建設大臣の直轄と変える事を定めた。(沖縄の特措法改正)
▽369 墓も倒されていき、土葬されて朽ちた先祖の骨が泥にまみれて掘り揚げられると、その場で金網に載せられて炎々と焼かれた。それは白昼悽愴な光景であった。
……原野に突如現出した小国町黒淵蓬莱団地〓を「長者村」と報道。「一家にテレビ2台というのはザラ、車も全部で20台を越す……」
▽430 敵方の最前線の指揮者・副島健、敗訴判決をくだした石田哲一と耶馬渓へ小旅行。恩讐の彼方に突き抜けた心境なのだろう。ダム反対の節はいささかも枉げることなく争訟に熱意を燃やす一方で、ダム建設に協力さえしはじめている。反対意志を訴訟記録の中に刻みつけていくことで節を通し、しかし現実に堰堤がそびえ立ち始めている以上、そのダムをせめてより良きものにする知恵を九地建に貸そうとする。副島もまた、室原の提言に謙虚に耳を傾けようとしている(石鎚と同じ構図〓)
▽450 おとうさんはもう半ば無意識で、「かあちゃんよい、かあちゃんよい」ちゅうてですね、……わたしん手え握って放さんですたい。
▽455 零細な豆腐屋として、働き続けた13年間、私は全く家ごもりの生活に縛られて来た。一人の友も持てぬまま、気付いてみれば孤独な20代は終わっていた。自分には、ついに青春がなかったという焦燥が私を駆り立てた。世事を日記に書き写すことで、おのが卑小で単調な生活に彩りを添えるというひそかな慰藉も、もうむなしかった。私も社会とつながってみたいという念いがこうじた果てに、唐突に豆腐屋を廃業した。
「周防灘開発問題研究市民集会」から反対運動に踏み切る……だが、勢いよく燃え上がった反対運動も、わずか1年足らずで消えこんでいった。誰しもがお世話になっている電力という公共性に抵抗するだけの強靱な反開発思想を広く全体化できなかったからである。……埋め立ての進行する海岸に、毎日座りこみに通った。私の孤独は濃かった。その時である。私の視線が縋るようにあの老人へと向かったのは。眼前に巨大なダム堰堤の壁がそびえてゆく時、あの老人の孤独はいかに極まっていたろうか。あんな老人が居たと思うことがその夏の私の支えだった。
▽460 生活に疲れ、孤立に耐えきれずに、もういっそ安穏な制AK津に埋もれてしまいたいとひそかに思うこともあるひとりの時間を、どんな猛々しい闘争者もきっと持っているのだと猛。そういう哀しみをかくしもたぬ闘争者を私は同志として信じ切れないという気がする。
……ヨシさんの話を聴き取るのに、私は1年をかけた。




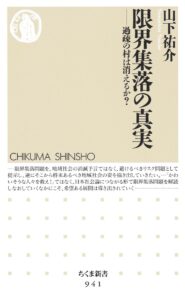
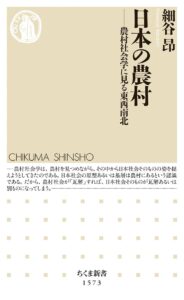


コメント