文春文庫 20081008
日本では、年間3万人が自殺している。3年間で10万人の市がひとつ消滅すると考えると、そのすさまじさがわかる。たぶん自殺未遂や、けがして生き残った人はこの何倍にものぼるのだろう。
世界を見比べると、ロシアや東欧などは日本・韓国と同様、自殺が多く、逆に自殺が少ないのはラテンアメリカ諸国、とりわけメキシコという。
自殺をはかり、ネズミに助けられたニューヨークの日本人調理師タカハシが、自殺をしないメキシコの秘密をさぐるため、ネズミとともに4つの宝をさがす冒険にでるという物語だ。
野生のトマトや緑のトマト(食用ホオヅキ)、唐辛子、インゲン豆など、メキシコを代表する食材が登場し、それを料理する描写も鮮やかで食欲を刺激される。とりわけ第一の宝である野生トマトを見つける過程は楽しい。
周囲とつながりの切れた人間社会はモノトーンある。だから、「色」を取り戻すことが必要だという。甘い・辛い・うれしい・悲しいというような循環がなくなると、生命同様ココロも腐ってしまう。だから、そういう循環(喜怒哀楽)をとりもどさなければならないという。
著者は「ドリアン助川」の名でバンド活動をしていたが、食べていけるようになった頃には、伝えたいものが見つからない空っぽ状態になってしまった。「プロというのは飽きる事がない人間のことだよ」と、空っぽな自分を受け容れるようたしなめる言葉も聞いたが、彼はその状態に耐えられなかった。「次の一歩を踏み出すには、食べられなくしてやるしかない」と、言葉もわからないアメリカに渡った。もう若くはない自分に直面させられ何度も自死を考えたという。
伝えたいものがなくなり空っぽになる感覚、とてもよくわかる。そこで一歩踏み出す人と、踏み出せない人と……。「カラッポという状態に飽きる事がないプロたち」た吹きだまっているのが、今のカイシャなのだろう。
「人生の大きな波に巻かれたら、抵抗しちゃだめだ。呼吸だけでいいんだ。流されてもいいんだよ」という言葉も、自殺の淵にいる人の心にきっと響くだろう。
小説としては完成されていないが、彼の体験がベースになっているだけ、迫力と説得力がある。
====================
▽289 野生のトマト ピンピネリフォリウム
▽349 色 自殺率が高い旧共産圏社会では、社会の閉塞とともに街から色が失われていった。皆さんは、苦しい時ほど、色に囲まれ、色に生きようとした。色を楽しむという行為は、周囲とつながるという行為。色を食べるという行為は、独りでは生きていくことのできない私たちが他の命の恩恵を受けるという行為と同義。
▽351 サルサベルデはトマトルという食用ホオズキから。第二の宝はトウガラシ
▽419 モナーク蝶(オオカバマダラ) シエラマドレ山脈のアンガンゲオに集団越冬地。
▽530 循環こそ命の本質。心とて生命の本質。本来は甘い辛い、辛い甘いの循環をせなんだら腐ってしまうはずなのに、近代は恐怖や悲しみから逃れるためにかえって心を硬直化させてしまう者が跡を絶たん。心の循環が滞っておる。トウガラシ
▽556 「人生の大きな波に巻かれたら、抵抗しちゃだめだ。呼吸だけでいいんだ。流されてもいいんだよ」
▽578 インゲンマメ 必須ミネラルのかたまりだから、精神安定に非常に優れておる。
▽615 小惑星が激突して、恐竜は絶滅し……それから数百万年たって、津波が襲った場所から新しい植物が生えてきた。トマト、トウガラシ、豆、カカオ……さあ、これを食べろ、これを食べて生き延びろって。
▽620 ドリアン助川 90年代の10年間、バンドを組んで詩を叫んだり歌ったりしていたが、食べられるようになった頃にはその純粋なマグマが途絶えていた。空洞としてのうつろな表現者である。「プロというのは飽きる事がない人間のことだよ」と言われたが、ボクは飽きた。何もなかった。すっからかんだった。
そうなった以上、次の一歩を踏み出さねばならなかった。それはつまり、食べられなくしてやること。
▽621 WHOの自殺率統計 日本はきわめて高く、メキシコは最低。摂取タンパク質量中における豆タンパクの割合 インゲンマメに頼らない国、すなわち繊維摂取率が低く便秘に苦しみがちな国(露西亜や中央欧州)ほど自殺率は高い。



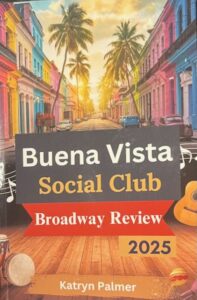




コメント