ミシマ社 200809
中国数千年の歴史をつらぬく「パターン」(=変化する仕方)として、まず、「易姓革命論」をあげる。王朝の天命が尽きれば王位を譲らなければならない。譲位を拒否した場合は、その王を伐つことは天理にかなった行為とされる。だから巨大な革命がおきる。
中国で体制の大変動があるとすれば、清朝が滅びて中華民国が起こり、さらに中華人民共和国ができたときの体制変動と同じパターンを描くことになるという。それ以外に、国民的な政治的熱狂は動員できないからだ。
こうした「革命」を日本人は経験していない。明治維新でも、徳川家は華族となった。天皇家は、武烈天皇のあとの継承者がおらず、応神天皇5代の孫という継体天皇が皇位につくが、これは現在で言ったら「ほとんどあかの他人」である。なのに日本人は「万世一系」と信じ、開闢以来ずっと同じ政体のままという物語を信じた(敗戦だけは別。政体の本質として連続していた何かがとぎれた)。
もうひとつ、中国の歴史をつらぬくパターンは中華思想・王化の思想である。
周辺の「蛮族」が朝貢してきたら、下賜品は来貢した品物を質量において圧倒した。日本をふくめた周縁の「えびす」たちと、精神的な主従関係にあった。
琉球は島津が武力支配をしていたが、明清にも朝貢して官位をうけていた。王化の周縁にはこういう帰属関係があいまいなエリアができる。中華思想には国境線という概念が存在せず、「化外の地」はまだ王化がおよんでいないだけだからだ。
こうした中華思想のありかたが、明治以後の日本と清の摩擦の背景にあった。清朝は王化の周縁というあいまいな地域として朝鮮をとらえ、日本は欧州由来の国際法を盾にとって明確な線引きをもとめた。
日中国交回復の際、周恩来は、中国人民と日本人民はともに軍国主義の被害者であるという「フィクション」を採用することで、日本に対する賠償請求を放棄した。これはまさに「王道政治」だ。ちなみに日本は日清戦争のあと2億両を請求し、日露戦争後は賠償請求を放棄させられて大騒ぎになった。韓国との間で決着した対日賠償請求無償贈与3億ドル、借款5億ドルについては「対日屈辱外交」として韓国全土で抗議行動が展開した。中韓日の賠償請求権についての態度の違いは、政治的エートスのちがいを示している。
自分たちがとれるときは賠償金をとりながら、とられる側になると「チャラ」にしてもらってすませられるのは、現代日本人にも「王化」戦略になじんできた祖先の血が流れているからだという。だから今もアメリカを中華とする華夷秩序の辺境の位置にあり、かつて漢籍を学んだのと同様に、小学生から英語を習わせようとしている。
一方、中華思想は近代化にはマイナスに働いた。
日本は昔は「和魂漢才」、近代にはいってからは「和魂洋才」を旨とした。外の知識や技術を必死に学ぼうとする「辺境」人の心構えである。中国は「中体西用」と称した。あくまで中心は中国で、西洋的なものは道具として功利的に利用する、という態度だ。西洋技術を見下し、中国の能力の高さを誇示することに軸足を置いてしまう。大躍進や文化大革命は、「中体」たる民衆の精神力頼みで、機械の利用や合理的な生産計画は「西用」として低く見たせいで破綻した。
「農村が都市を包囲する」戦略をとった毛沢東は、周縁のほうが中心よりもイデオロギー的にも生産力においても優位にあるという「物語」を採用した。「王化」とは逆の道をとることで、中心に集中していた権力や財貨を全土を分配しようとした。中心=周縁の位階差が生じさせる専門分化も毛沢東は否定し、総合的・百科全書的な知性と能力をもつ国民を創り上げようとした。
だが、大躍進の失敗で人民公社は再編されて「分業化」される。改革開放政策で人民公社は消滅する。鄧小平の「先富論」は、地域差・階層差・分業を受容し、「王化戦略」を呼びもどすものだった。
中国の王朝のような絶対権力と異なって、日本の江戸時代の幕藩体制は、狭隘な国土を300近い政治単位にわけて、ある程度自立的な活動を展開し、幕末には、洋式軍隊や軍艦や製鉄所はいくつかの藩が独自につくった。こうした「リゾーム」状組織こそが、幕末から維新直後の荒波を乗り切るうえで有効だったといい、「中央集権国家をつくり富国強兵をはかったから近代国家に生まれかわれた」という俗説を否定する。
中央集権的「ツリー」状組織は、予測できる範囲のリスクには効率的に対応できるが、予測できない種類の危機には脆い。「リゾーム」状組織は、ルーティン的処理は効率が悪いけど、リスク・ヘッジという点ではすぐれている。現にそれ以後、中央集権化が進むにつれて、柔軟性と創造性を失って、最後は「翼賛体制」の完成と同時に壊滅してしまった……。リゾーム状組織によって成功した典型がアメリカであるという。
筆者は、中華思想と日本の「辺境」的あり方をくらべて善悪を論じているのではない。まったく異なる精神構造なんだから、それを踏まえたうえでつきあいましょう、という構造主義的な提言である。
==============覚え書き・抜粋===============
▽44 メルヴィルの「白鯨」 捕鯨船の乗組員は、インディアンと人食い人種の王子とアジア人。西部開拓のカウボーイとして中国人が深くコミットしたことは、忘れ去られている。カウボーイは、人種障壁の少ない職業だったから、黒人もインディアンも日本人もなれた。が、映画に映ることはない。一種の歴史の歪曲。(書かれたものだけが記憶される)
▽46 梅棹忠夫「変化する仕方は変化しない」 中国には「易姓革命論」があり、天命によって統治する王朝の天命が尽きれば王位を譲らなければならない。王が譲位を拒否した場合は、その王を伐つことは天理にかなった行為とされる。……「革命」の語に相当するような巨大な王朝交代を日本人は経験していない。
明治維新でも、徳川家は華族となり、幕臣も重用される。天皇も「万世一系」ではない。武烈天皇のあとの継承者がいなくて、応神天皇5代の孫という継体天皇が皇位につくが、今の民法に照らしたら、「ほとんどあかの他人」。……日本では幻想的には開闢以来ずっと同じ政体のまま。「変化の仕方は変化させない」
敗戦だけは別。政体の本質として連続していた何かがとぎれた。
▽54 中国で体制の大変動があるとすれば、清朝が滅びて中華民国が起こり、それが本土を逐われて、中華人民共和国ができたときの体制変動とおそらく同じパターンを描くことになる。それ以外に、国民的な政治的熱狂は動員できない。
▽66 アメリカによる東アジア共同体「儒教圏」の切り崩しの切り札は、情けないことに日本。これから先、アメリカの東アジア戦略は、日本と他の東アジア諸国のあいだにくさびを打ちこむというかたちで展開するはず。
▽75 中華思想 周辺の「蛮族」が朝貢してきたら、下賜品は来貢した品物を質量において圧倒するのが常だった。周縁の「えびす」たちは中国に実質支配されているわけではないが、精神的な主従関係にある。(卑弥呼など)
琉球も。15世紀以降、明清と日本に同時的に服属するというあいまいな政治的位置をとる。島津が武力支配をしていたが、同時に明清にも朝貢して官位をうけていた。王化の周縁にはこういう帰属関係があいまいなエリアができる。それが日本と清の摩擦の背景にある。清朝は王化の周縁というあいまいな地域をもち、日本は国際法をたてにとった。
近代的な帝国主義を前にしたとき、中華思想がいかに外交戦略として脆いか。
▽80 近代的な国民国家は宗教戦争以降。ウェストファリア条約の国境線は各領地の領主が信仰する宗派に基づいて確定された。私とイデオロギーの違う人間は殺してもいい、という考え方が「非常識」ではなくなってから後の話。この国民国家観はたかだか300年。中華思想は3000年の歴史がある。
中華思想には国境線という概念が存在しない。「化外の地」はまだ王化が及んでいないだけ。
▽88 周恩来は、中国人民と日本人民はともに日本軍国主義の被害者であるという「フィクション」を採用することで、日本に対する賠償請求を放棄した。ああいうのを「王道政治」。これが逆の立場なら日本は果たして賠償請求を放棄したろうか。日清戦争のあとの下関条約では2億両を請求した。日露戦争後も賠償請求を放棄させられて大騒ぎになった。
韓国との間で決着した対日賠償請求無償贈与3億ドル、借款5億ドルについては「対日屈辱外交」として韓国全土で抗議行動が展開した。
中韓日の賠償請求権についての態度の違いは、各国の政治的エートスの違いを表しているように思える。
▽98 自分たちが中国から取れる側にいるときはきっちり賠償金を取りながら、取られる側になると「チャラ」にしてもらって、「あ、どうも」ですませてられるのは、現代日本人の中にも「王化」戦略になじんできた祖先の血が流れているのでは。現に今、アメリカを中華として、日本を夷とする別の華夷秩序のなかにいる。安保ただ乗り論は、王を太平洋の向こう側に移し替えて辺土(周縁)のポジションを東西入れ替えただけ。小学生から英語を習わせるというのも、全部「そういうこと」。昔は漢籍を学んだ。
▽104 「私はオリジナルではありません」という立ち位置自体が儒教の教え。孔子の教えも、周の伝説的名君の徳治を回顧するもの。孔子はその継承者という立ち位置を選んだ。「創始者ではなく祖述者にすぎない」と。祖述者は「私はできないけど、できた人が昔はいた」と言い抜けられる。創始者は自分にできることしか教えられないけれど、祖述者は自分の力量を超えることを教えることができる。だいたい昔から教育法とは「そういうもの」。
▽119 清末中国 義和団事件。籠城戦のときの日本兵の勇敢さと連合軍の北京占領後の軍紀の厳正さ(このころは戦闘が終わると根こそぎ略奪を行うのがヨーロッパの軍隊の通弊だった)が英国に高く評価され、日本の国際的威信を高め、それがやがて日英同盟に結実する。(なぜその後ダメになるか〓。周縁から中央への立ち位置の変化?〓)
▽126 幕藩体制は、狭隘な国土を300近い政治単位にわけて、ある程度自立的な活動を許した。幕末に洋式軍隊や軍艦や製鉄所をつくったのは、藩ごとに自主的に行った。「リゾーム」状組織は、外界の変化への適応力が高い。幕末から維新直後の短期間での近代化の行程では、世界史上でもまれなほどの有効性を発揮した。
中央集権的「ツリー」状組織は、予測できる範囲のリスクには効率的に対応できるが、予測できない種類の危機には脆い。「リゾーム」状組織は、ルーティン的処理は効率が悪いけど、リスク・ヘッジという点ではすぐれている。
日本の近代化は、幕藩体制期に「近代化の下絵」はもう描かれており、明治政府の強権的政治運営よりも近代化にとっては決定的だった。
現にそれ以後、中央集権化が進むにつれて、フレキシビリティと創造性を失って、最後は「翼賛体制」の完成と同時に壊滅する。
……日本を300ほどの藩に戻したらどうか。小さな政府をたくさん、というオプションで成功しているのがアメリカ。
▽132 五稜郭で死んだ土方歳三の死に方はフランス人将校に印象を残し、「武士道」に対するひそかな敬意の感情をフランスに伝えた。義和団事件での柴五郎中佐の示した武士的エートスは、イギリス公使に印象を残し、日英同盟に結実する。幕末の危機を奇跡的に生き延びることができた理由のひとつは、「蛮地」に乗りこんできたつもりの英仏人がそこで、自分たちと伍し、あるいは自分たちよりすぐれた知性、高い倫理規範をもつ人間と出会ってしまったという事実がある。幕末から維新にかけて来日したヨーロッパ人の多くが人心の穏やかさに感動している。最終的に列強の侵略を免れたのは、日本の文化の高さによってだと思う。知的リソースが中国のように中央集権的に特権的階層にだけ集中していたのではなく、広く日本のすみずみにまでゆきわたっていたことが、日本を救ったのでは。
▽133 日本は昔は「和魂漢才」近代にはいってからは「和魂洋才」。
中国は「中体西用」。この場合あくまで中心は中国で、西洋的なものは道具として功利的に利用するだけ。西洋技術を見下す視線がビルトインされている。中国の能力の高さを誇示することに軸足を置いてしまう。
大躍進や文化大革命は、そのあらわれ。「中体」たる民衆の精神力頼みで、機械の利用や合理的な生産計画は「西用」として低く見たせいで、大躍進は1年で破綻。
▽144 日本で軍国主義が復活するのは100%不可能。にもかかわらず中国は起こるはずのないことに対して激しい反応を示す。そこには別の政治的狙いがある。
清朝の滅亡依頼、全中国人が団結した時期は存在しない。唯一、抗日戦だけが例外。唯一の「国民的統合」の記憶。
日本人には、そこに立ち戻れば必ず自信を取り戻せるような国民的統合の記憶の核がない。司馬遼太郎は、明治の青年たちの時代を回帰すべき民族的記憶の原点として提示した。が、それは失敗する。司馬の意図を継いだイデオローグの面貌にも挙措にも、彼らが再興しようととしている「武士」的なエートスが名残をとどめていない。彼らが司馬的な物語をほめたたえるのは、国民的統合を成就するためではなく、ほとんどの場合は彼らに反対する人間を黙らせるため。
▽148 華夷秩序と国民的統合というストラテジーは原理的に両立しない。毛沢東は「農村が都市を包囲する」戦略。周縁のほうが中心よりもイデオロギー的にも生産力においても優位にあるという「物語」が前提になっている。王化秩序とは逆の物語を処方することによって毛沢東は中心に集中していた権力や財貨を拡散させて全土を均質化しようとした。専門分化すれば、そこに中心=周縁の位階差が生じるから、専門分化を毛沢東は否定した。総合的・百科全書的な知性と能力をもつ国民を創り上げようとした。
大躍進の失敗で人民公社は解体再編されてただちに「分業化」される。改革開放政策で人民公社は解体され、80年代に消滅する。トウショウヘイの「先富論」は、地域差・階層差・分業を受容する。毛沢東が中国から消そうとした「王化戦略」を呼び戻した。
▽161 中国は明代には、航海術も科学技術全般も世界最先端だった。帆船の縦帆も竜骨も羅針盤も火薬も印刷術もオリジナルは中国。
▽191 1970年代までは日中・日韓・日台、どこにでも公式の政府とのパイプとは別に政治家たちのパイプがあった。利権とも結びついていた。日中のパイプを牛耳ったのは田中派。台湾バナナ輸入を特定業者に制限することでもうけて河野一郎は派閥を維持した。韓国は岸信介。
▽197 日本人には植民地経営についてリアルかつクールに総括するという知的習慣がない。「悪」と決めつけて判断停止するシンプルな左翼と、「インフラ整備をしてあげた」と言い立てるシンプルな右翼しかいない。英仏人は、自国の植民地経営の当否を歴史的に分析する知的な用意がある。そうでなければ、インドシナ半島への90年代からのフランスの文化的進出戦略なんか策定されるはずがない。ベトナムでのフランス語学習者に巨額の財政的支援をしている。フランスとつながりをもつエリートが20年30年後にベトナムの中枢を占めるように投資している。
▽210 ニクソン訪中の後に日本(田中首相)は対中アクションを起こしたにもかかわらず、アメリカよりも先に中国を承認した。アメリカの鼻先で、アメリカの外交戦略の先手を取ったといのは、日本の戦後政治史において例外的。キッシンジャーは激怒した。
▽222 人類館事件 北海道アイヌ、台湾の生蕃、琉球、朝鮮、支那、印度、ジャワなど7種族の「土人」が展示された。
中国人がこれに抗議する。「印度や琉球は英日の奴隷であり、朝鮮は露日の保護領で、ジャワや蝦夷、台湾の生蕃は世界最低の人種で……われわれ中国人は劣ってはいても、これら6種と同じにされなくてはならぬのか……」と。


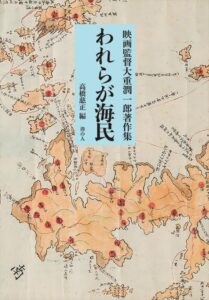

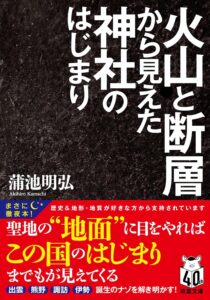

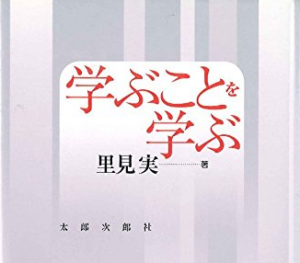

コメント