■街場の共同体論<内田樹>潮出版社 20170908
子どものころ、人のために尽くす人こそが「えらい人」だと素朴に信じていた。すし屋さんや自転車屋さん、お百姓さん……といった仕事によって近所のおじさんたちを「すごい人だなあ」と思っていた。
1980年代を契機に、「何をつくるか」という労働行動ではなく「何を買うか」という消費行動によって人間を見るようになってきた。
80年代、官民を挙げて「できるだけ活発に消費活動をすること」を目標に掲げ、消費主体が家族から個人に移行することを要請し、家族と共同体の解体を推し進めた。それが社会のありかたを決定的に変えてしまったという。
日本の伝統文化では、「清貧を楽しむ風儀を知っている人間」のほうが「金はあるけれど使い道を知らない人間」よりも高く評価されてきた……という部分を読んで、1988年にアメリカでホームステイした時のことを思い出した。
お世話になったファミリーは、週末は湖でモーターボートを乗り回していた。カネでレジャーを買うアメリカ文化に強烈な違和感を感じ、俳句をつくったり、絵を描いたり、将棋をしたり、外でおにぎりを食べたりする日本の週末のほうがよほど文化的だと思った。たが、私も含めて今の日本人の週末はアメリカ的なレジャーが主流になり、貧しくても豊かな「遊び」がすっかり減ってしまった。「身の程を知る」という知恵を失ってしまった。
学校に市場原理を持ちこむことで、「受験に関係ない教科なんか勉強しなくていい」という親子が増えてきた。僕らの年代にもその傾向はあったが、今は、友達の試験の点数が上がりそうな恐れがある話はしない…という状況になっているそうだ。にわかに信じがたいが、内田先生が言うならそうなのだろう。こうした「努力」の積み重ねによって、「無教養」と「反知性主義的傾向」が蔓延してきたという。
学校は本来、未来の共同体を支える人を育てるためにつくられた。その社会的合意が忘れられ、「自己利益の追求だけに専念する人間の育成」の場になってしまった。たしかにその通りだと思う。
子どものころ、冬の夜は「マッチ1本、火事のもと」と大人たちが拍子木をたたいて歩いていたが、いつの間にかいなくなった。今はそういう仕事は行政がやることになり、近所づきあいの必要もなくなってしまった。私の実家の周辺から火の用心が消えたのも1970年代末から80年ごろだったと思う。
「ひとりでもいきられる社会」をつくりあげることで、「他者と共生する能力」を失ってきたーーと指摘する。
個々人がばらばらになり、「自己決定・自己責任」のイデオロギーが蔓延しているが、社会の上層には、結束の強い共同体が存在しているという。
たとえば政治家は、自己決定や自己責任ではなく、「神輿」として担がれるという「滅私」の覚悟でによってその道に進んでいる。現代の成功者の大半は「自己決定してない」人であり、成功の秘訣は、ある共同体のなかで自分が果たすべき役割を忠実に演じたことだという。
「人に頭を下げるな、ものを聞くな、ものを教わるな、自分のことは自分で決めろ」というイデオロギーが、下の階層に広がった結果、階層が下に行くほど人間が狭量になり、意地悪になり、怒りっぽくなる。「社会的に上昇しようとしたら、師や先達を探して、お願いします。教えて下さいというのが、最も効率的な道なわけですけれど、その道を自分でふさいでしまっているんですから」と言う。
では今後どうすれば共同体を再生できるのか。
先行世代が後続世代の成長を支援するために存在する縦軸の人間関係を再建する。そのための場をつくっていくしかないようだ。
===============
▽ 絶望的な状態に置かれたときには、足もとの瓦礫を拾いあげるところからはじめる。
▽22 少年の凶悪犯罪の発生件数が一番多かったのは1950年代末から60年代初めにかけて.性犯罪も多かった。強姦件数は60年代半ばがピーク。発生件数は、現在ではその当時の6分の1まで減少しています。
▽26 自殺率もピークは1958年。10万人あたり25.7人。これは当時世界一の数値でした。
▽28 1958年に自殺者や犯罪者が多かった理由の一つは、核戦争の切迫ではないかと僕は思っています。足もとから世界が崩れるような、存在論的な不安を身体の奥で感じてしまった人たちが…
▽32 親子関係は昔から疎遠だった。昔の人は疎遠であることを「困ったことだ」と思っていなかった。…疎遠である形がちがうだけ。
▽42 「父権制を倒せ」と言ってきた世代は、年を取るにつれて「まともなおとな」になるかわりに、進んで「倒されべき父親」をめざすようになる。「あんなやつははやく退場してほしい」と言われるような人間になるように刻苦勉励することになる。同じことが世界の先進国で起きていたんだと思います。
「おとなになり損なう」ということが、僕たちの世代においては世代的義務として観念されていた。
…構造的に家父長の権威は地に墜ちた。
▽45 圧倒的な支配力を持つ母親の誕生。
父親が「子供の好きなようにさせてやれば」と気弱な提言をして、母親が進学先や就職先について断固たる意見を述べる、ということが増えています。昔は逆。子供のわりと夢見がちな要望を汲み上げる役は、母親が引き受けていた。父親が頭ごなしに「世間知らずが何を言うか!」と一喝し…。だから、子供が本音を告白するのはもっぱら母親に対してであって…。
▽49 かつての家父長は子供の運命を左右する権利はあったけれど、自分の子供が何ものであるかについてはよく知らなかった。家父長が「かくあるべし」という指示は、システマティックにとんちんかんなものになった。だから息子たちは、自分の欲望の実現を家父長に阻まれたときには、ため息をついて「まったくオヤジはなにもわかっちゃいないんだから…」とお互いの不運を嘆き合うことができました。
母親が子供について決定権を持っている現代家庭では、もうその「嘆き合い」が成立しません。母親は子供のことを、子供自身以上に「知っている」からです。
…母親が子供に向ける指示に、子どもたちは反論することができない。
▽54 母親の育児戦略は、「弱者デフォルト」なものになる。「群と共にあれ」です。
▽56 親の育児戦略がちがい、子供の潜在可能性についての評価がずれていると、子供のほうにも「立つ瀬」があります。父と母の力が干渉し合って、相殺されて、ゼロになる場所がある。そういう「息のつける隙間」で子供は成長したのです。
▽71 昔は、先生がかなり人間的に問題のある人でも、教師である限り、生徒も保護者もそれなりの敬意をもって接していた。その結果として、学校が教育的に機能したわけです。(〓師をもつ場の力)
▽85 野球のプレーボールの礼も、…超越的なものに対する畏敬の念が、あらゆる礼節の基本なんです。
…「礼」の基本。人間たちの住む世界とは別の世界からのシグナルを聴き取ろうとする構えのことです。だから「礼」と「祈り」は身体の形が似ているんです。
▽92 身体の共同化、想像力の共同化
▽93 (子どものころ)学校が終わってから、晩ご飯の時間になるまでほんとうに長かったんです。このエンドレスの午後の時間をつぶすのが本当に大変だった。(今は塾で忙しい)だから、身体的な接触も、何もないところで遊びをつくりだす工夫がもうできない。
▽96 毎日毎週同じことを繰り返す。ルーチンの反復が、成長するときには必要なんです。子供自身が劇的に変化するときだからこそ、枠組みのしっかりした、儀礼的・定型的な場に置かれたほうがいいんです。……子供に必要なのは、もっと静かで、安定的で、内省的な時間なんです。
▽103 関川夏央さんが「共和的な貧しさ」という言葉で、戦後の日本社会を形容していますけど、それに再び近づいているのかもしれません。だんだん貧しくなっているから、お互いに支え合っていかないと生きていけない。…共和的な貧しさの知恵の必要性を感じはじめている
▽106 家族と共同体の解体を全力で推し進めてきた。1980年代、官民を挙げて「できるだけ活発に消費活動をすること」を国家目標に掲げました。家族が国策的に、組織的に解体に向かったのはこの時からです。
▽109 何かを買うときに、他の家族に説明する責任があった。説明責任が、消費活動を強く抑制してきました。
▽111 消費主体が家族から個人に移行すること。それを市場は強く要請しました。
▽112 バブル期以前まで、自分が「何もの」であるかは、消費行動によってではなく、労働行動によって示すものだと教えられてきました。「何を買うか」ではなく「何をつくりだすか」によって、アイデンティティは形成されていた。
…それが「何をつくるか」ではなく「何を買うか」を基準に、人間を値踏みするようになった。その場合、原資となるカネをどのように手に入れたかは、原則的に不問に付されます.「金に色はついていない」というのは、バブル紳士たちが良く口にした言葉です。
▽116 学校教育に市場原理を持ちこんではならない。…「受験に関係ない教科なんか勉強しなくていい」と豪語する、無駄なことはしない、という人がいるでしょう。
…受験勉強でも、最も効率の良い学習法を血眼で探す。
…友達の試験の点数が1点でも上がりそうな恐れがある話は絶対にしない。…この一乗的努力の積み重ねの上に、現代日本人の恐るべき「無教養」と「反知性主義的傾向」が構築されているのです。
…「競争相手の足を引っぱる」という競争戦略が可能なのは、例外的に豊かで安全な社会において「だけ」
▽123 1960年代の半ばまで、冬の夜になると「マッチ1本、火事のもと」と歩いていました。(〓いつのまにかいなくなった)
今は、そういう仕事は行政がやってくれることになった。地域共同体はもう、治安や消防や公衆衛生サービスを自力でおこなう必要がない。だから近所づきあいをする必要もなくなった。
▽127 出生率の減少に関与するふたつの要素。家庭の教育投資額が増えるほど子供の数が減る。女性の学歴が上がるほど晩婚化・少子化が進む。出生率のV字回復を望むなら二つしか手だてはない。教育費を無償にするか、女性があまり知的向上を願わないように仕向けるか。
… 日本の教育予算の対GDP比でのOECD調査では、世界最低レベル。それでもなお、教育費を削ろうと、学校に対して「コストカットの努力が足りない」とがみがみしかり続けています。
▽130 「ひとりでもいきられる社会」に住み慣れている間に、日本人は「他者と共生する能力」を育てる努力を怠ってしまった。そのことが「ひとりでも生きられる社会」システムの自壊を招き寄せました。
▽149 日本の伝統文化の文脈では、「清貧を楽しむ風儀を知っている人間」のほうが「金はあるけれど使い道を知らない人間」よりも高く評価されてきた。
(〓アメリカに行ったとき、金でレジャーを買う文化に違和感を感じたが、今の日本はそうなってしまった。貧しくても教養のある人が見えなくなってきた〓。自分の遊び方も)
▽151 「身の程を知る」というのは、手持ちの資源で何ができるかをやりくりすること。現代人はそんな知恵を失ってしまいました。キャベツとモヤシがあるから野菜炒めが「作れる」という風に考えるのが「身の程を知る人」であり、キャベツとモヤシはあるが豚肉がないから肉野菜炒めが「作れない」と渋面を作るのが「身の程を知らない人」です。
▽169 共同体を支え、次の世代へと受け渡すことのできる若者を育てる。そのために学校教育はつくられた。その社会的合意が失われた。それが「学校制度の根本が病んでいる」という言葉で僕が言いたいことです。今、人々が学校教育に求めるのは、
国家須要の人材の育成」ではなく、「自己利益の追求だけに専念する人間の育成」です。
▽178 「戦争のない平和な社会の成熟した市民」という、見たこともない市民を造型しなければならない。学校教育はそのためのものでした。子どもたちの享受しうる最大の自己利益は「もう戦場に行かなくてもいい、もう空襲の下を逃げ回らなくてもいい」というころでした。そのために学校教育はあるべきだという正論に異議を唱える人を子どものころの僕は見たことがありません。ですから、保護者たちは学校教育に実に熱心にコミットしておりました。教師たちとPTAの役員が口角泡を飛ばして議論し、地域社会全体で学校を作りあげていこうという危害がありました。「君たちがこれからの日本を担うのだ」という言葉を、僕らの世代は本当に繰り返し聞かされました。
学校教育は、未来を担う子どもたちを育成するための場であるという集団的合意は、日本が平和で豊かな国になるにつれて、しだいにわすれられてゆきました。地域共同体なんか「あっても邪魔なだけのもの」になりました。
▽190 コミュニケーション能力とは、コミュニケーションを円滑に進める力ではなく、コミュニケーションが不調に陥ったときに、そこから抜け出すための能力。
▽195 コミュニケーションがうまくゆかない人たちは、「ルールを破る」ことのできない人です。立場が異なる者同士がお互いにわかり合えずにいるのは、それぞれが己の「立場」から踏み出さないからです。自分の「立場」が規定する語り口やロジックに絡め取られているからです。
武道では、「立場にしがみついていること」を「居着き」と言います。居着く人は、危機的状況に際会したときも「どうしていいかわからない自分」に居着いてしまう。「恐怖している自分」「混乱している自分」に居着いてしまう。…さまざまな制度は僕たちにむかって「居着け」と命令している。「お前の立場から逸脱するな」「ジョブ・ディスクリプションに書いてある以外のことをするな」……短期的には効率的に見えるのかも知れないが、長期的にみると、それが引き起こしているコミュニケーション失調のせいで、社会制度はあちこちでほころび始めています。
▽207 派閥のボスの意義。
▽224 縦軸の人間関係を取り戻す。主従関係、師弟関係、あるいは親子関係でも、先行世代が後続世代の成長を支援するために存在する仕組みを、もう一度賦活する。……僕たちが先行世代から贈与され支援されてきたことへの「お返し」。「パス」されたから「パス」を回す。……人間関係を商取引としてしか構想できない人間には理解できない「物語」です。
▽231 先行世代から受け継いだものを後続世代にひきついでゆく、そういう垂直系列の統合軸をもった相互扶助・相互支援的な共同体が、もう一度、局所的にではあれ再建されなければならないと思います。
▽234 今の40代以上は…グローバル資本主義のエートスを深く内面化してしまっているので、どうしても師弟関係が苦手なんです。「消費者としての主体」に居着いている。
師について修業するというのは「居着き」から逃れるための方法なんですけど、その理路がわからない。「師について修業すると、オレにはどんなメリットがあるんですか」という問いを手放せないかぎり、師弟関係ははじまらないのに。だから、社会人経験が長い男性ほど、ものを習うのがへたですね。
▽246 ツイッターの本質は受信なんです。…誰かが質の良い情報源を発見するとリツイートして告知する。それがさらにリツイートされてひろがっていく。ですから「質のいい情報源を発見できる才能」は、すでに「質のいい情報源」の資格を満たしていることになる。自分が何を発信するかよりも、「誰をフォローしているか」が問題になるわけです。
…参加者たちがどれほど質の良い情報の「通り道」であるかが問題なのです。…これは「学ぶ」という行為の本質に深いところでつながっていると思います。
▽268 社会の上層には、結束の強い共同体が厳として存在します。…政治家を見ても、自己決定で政治家になり、自己責任で政治的たちを決めた人なんか一人もいませんよ。みんな「家産」を受け継ぎ、「家風」を伝えることで、位人臣をきわめた。「神輿」として担がれるという「滅私」の覚悟があったからこそ、この地位に立つことができたんです。
現代日本の成功者たちって、ほとんど「自己決定してない」人たちなんです。…彼らの成功の秘訣は、「自分らしさ」を追求したことではなくて、ある政治共同体のなかで自分が果たすべき役割を忠実に演じたことです。
▽272 「人に頭を下げるな、ものを聞くな、ものを教わるな、自分のことは自分で決めろ」という自己決定・自己責任のイデオロギーが、階層下位に向けて選択的にアナウンスされています。
だから階層が下に行くほど、人間が狭量になり、意地悪になり、怒りっぽくなる。社会的上昇をしようとしたら、まず自分の非力や無知を認めて、それを補正し、自己陶冶を果たすために、師や先達を探して、「お願いします。教えて下さい」というのが、最も効率的な道なわけですけれど、その道を自分でふさいでしまっているんですから。
▽287 広々とした「負けしろ」が、弟子というポジションの最大の贈り物です。今の自分の知見や技術に「居着かない」でいられる。…いくらでも冒険できる、いくらでも失敗できる、いくらでも脇道に入りこむことができる。…師に仕えることで弟子は途方もなく自由になるんです。
▽312 共同体はそれぞれの集団が置かれたときどきの歴史的環境に対応して変化します。…(解放の神学の大事なのは「共同体」であること〓)


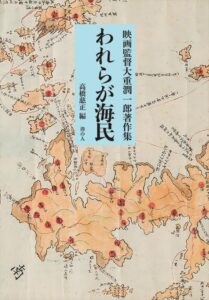

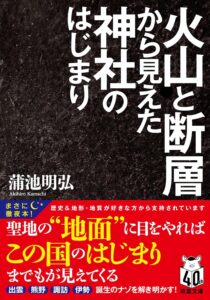

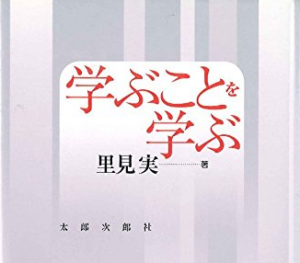

コメント