イルカ漁についての映画といえば、「ザ・コーブ」が有名だ。「残虐なイルカ漁」を告発して評判を呼び、アカデミー賞を受賞した。クジラを食べるのがあたりまえの私たちから見ると内容はとんでもなかったが、エンターテイメントとしてはおもしろかった。
この映画に反論する形で、日本人監督が「ビハインド・ザ・コーブ」をつくった。コーブへの反論、というストーリーが見えてしまった気がして映画館に足が向かなかった。
そして今回の「おくじらさま」。イルカをめぐるドキュメンタリーはあまり見たくなかったが、勧められて劇場に足を運んだ。
太地には、秋から春にかけての漁期になると、シーシェパードの活動家が監視と抗議に訪れる。
イルカを追い込む漁師たちに「恥を知れ!」などと罵声を浴びせ、捕獲場面を全世界にライブ配信する。知的水準の高い動物を人間に近い存在だと考える人々にその主張が広まっていく。日本人から見ると、狂信的な活動家にしか見えないけれど、世界動物園水族館協会(WAZA)を動かして、日本動物園水族館協会(JAZA)に圧力を加え、太地のイルカを水族館で購入できないようにしてしまった。
妥協の余地がない、取りあげるのが難しいテーマなのだ。
この映画の監督は、その難しいテーマを、太地に住みついたアメリカ人ジャーナリストを「主人公」に据えることで解きほぐそうと試みる。
彼は漁師と親交を深め、シーシェパードや日本の反捕鯨団体も丹念に取材する。彼の姿を追うとともに、ザ・コーブなどの過去の映像資料も駆使して、何が対立点なのかを浮き彫りにしていく。
シーシェパードの主張は「絶滅危惧種だから守れ」といった資源問題からの主張ではない。高等な動物には人間に準じた権利が認められるべきだという、ある種宗教的な主張だ。欧米で一定の支持を得る理由はわかる気がする。
一方、シーシェパードに対する反発は、「日本独自の文化をふみにじられた」というナショナリスティックな主張になりがちだ。
宗教対民族主義という対立には妥協の余地がないように見える。
北朝鮮がミサイルを発射すると喜々として記者会見をする安倍首相じゃないけれど、政治家はナショナリズムをあおりがちだ。捕鯨問題はそのかっこうの素材でもある。
太地町は、戦前から多くの移民を輩出し、社会主義者や芸術家も生みだしてきた。全戸が出資して「水産協同組合」を結成し、利益を分け合うというシステムもつくりだした。昭和40年代には、将来捕鯨ができなくなることを見越して、観光拠点としてクジラ博物館をつくった。たんなる田舎の漁村ではなく、進取の気性のあるムラだった。
いま太地町は、世界的クジラの研究拠点にしようと取り組んでいる。ナショナリズムに流されず、食文化や伝統行事といった足もとの素材を大切にして、一方で、世界レベルの発信を目指すという弁証法的な思考に、太地の可能性が見えるような気がした。
目次






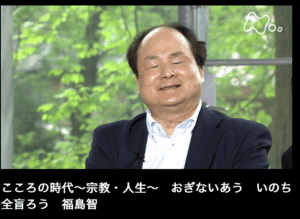

コメント