■風と波を知る101のコツ 海辺の気象学入門<森朗>枻出版 20161214
北半球の高気圧は時計回りに風が吹き出し、低気圧は半時計回りに風が吹き込む。コリオリの力があるからまっすぐに風は吹かない。向かってくる台風の左側に逃げると風が強く、右側に逃げると少しはましになる。
=============
▽10 コリオリの力 進行方向を北半球では右に、南半球には左に変える働き。
▽18 日本付近に限れば、天気図を見て緯度10度の間に等圧線が何本引かれているかを数え、それに3を掛けると海岸の風速の目安になる。
…高気圧では中心よりも周辺部、低気圧では中心に近いほど風が強く吹く。
▽22 大陸の冷たい空気は、インド洋に流れ出そうとするが、ヒマラヤに阻まれ、東の海の方へ流れ出す。この寒気がアリューシャン列島付近の低気圧に吸い込まれて日本列島を吹き渡る冷たい北西季節風となる。夏は、大陸で上昇気流が起こって、インド洋の蒸し暑い空気が沖縄、日本を通って大陸に流れこもうとする。太平洋上の高気圧も膨脹し勢力を強めるので、グアムあたりの空気も北へ進み、両者が日本のあたりで合流する。これが夏の季節風。…夏と冬でいれかわるアジアモンスーン。
▽24 移動性高気圧の西側は、ポンプのように南の空気を北に送り込む。北側はほとんどの場合低気圧か前線に。高気圧から吹き出した風を吸い込んでくれる。風がスムースに凪がれ、強風になることも。
▽26 温帯低気圧の特徴は、寒暖2種類の空気が渦を巻いているため、その境目に「前線」ができること。…低気圧から西あるいは南に伸びる寒冷前線の所は大きな積乱雲が発達する。
▽28 温帯低気圧は、違う性質をもった空気が混ざり合う現象。熱帯低気圧は、暑い空気だけでできた雲の渦巻き。だから前線が熱帯低気圧にはない。
▽30 低気圧が北側を通ると、突風や風向きの急変、落雷などへの備えが必要。
▽37 赤道に向かって吹き込む東風。海上貿易のための重要な航路だったため、「赤道貿易風」と呼ばれる。マゼランの世界1周もこの風のおかげ。
…赤道上から上昇した空気が南北に別れてやがて下降して高気圧をつくる。そこはずっと晴れ。サハラ砂漠のような砂漠をつくる。高気圧の縁では風が強く吹き出し、北半球では北東、南半球では南東の風がコンスタントに吹くことになる。
▽40 赤道付近の対流圏の厚みは北極や南極よりも厚いから、空気は赤道から極に向かって流れ出す。コリオリの力で、北半球では右へ、南半球では左へ進路を変えられ、最後は西風=偏西風にかわる。
…南半球では陸地が少ないために偏西風が海上まで届きやすくなる。このため「咆える0度」「狂暴な50度」「号泣する60度」というほど荒れることになる。
▽44 風速 10分間観測し続けた結果を平均して1秒あたりの値であらわす。最大瞬間風速は、最大風速の1.5倍から2倍になる。最大風速の世界記録は84メートル。最大瞬間風速は105.5メートル。
▽46 1ノットをm/sの直す0.514m/sになる。12ノットといえば6m/sという具合に、大体半分と覚える。ノットを時速に直すには1.852を掛ける。2倍して1割カット。
…風速5メートルは時速18キロ。10メートルというのは36キロ。
▽52 サイドショアの風も摩擦の多い陸地を避けて吹く。岬のように海に突き出したところでは、海岸に沿って吹く風と沖合を吹く風が一緒になって非常に風が強くなる。海峡のように陸地に挟まれて幅が狭くなっているところにサイドショアの風が吹き込むと、強くなる。こういう所では潮の流れも速いことが多く、多くの船舶が航行するため、世界の海の難所と言われているところは、大体このような形をしている。
▽65
▽82 飛行機雲で、上空の湿り具合がわかる。湿るためには、南の海上の空気がそこまで入りこんでいなければならない。ということはその場所が低気圧の東側にあたることになる。飛行機雲が広がってくるときはやがて低気圧がやってきて、風が強まってくるということになる。
▽98 潮位とは、海面の最低ラインにあたる基本水準面を基準に、実際の海面との差で表す。実際の潮位を平均したものを平均海面といい、陸地の標高はこの平均海面を基準に測られる。水深0メートルと標高0メートルとでは、実は基準となる高さがちがう分だけ水深0メートルの方が低くなる。
大潮の時の潮差は、太平洋や東シナ海で大きい。有明海は5メートルに及ぶ。日本海は0.1~0.2メートル。
▽106 波の周期。湾内の風波の場合は1〜2秒からせいぜい4〜5秒。台風から届くうねりの場合は14~16秒とかになる。沖合から来た波が、波長の2分の1の水深の所までくると、波は海底の影響を受けるようになって、その速さがだんだん遅く、波長は短くなりはじめる。水深が元々の波長の20分の1になると、今度は波の高さが高まってくる。波高は波長の7分の1の高さまで高くなると砕けてブレイクするから、周期が長く波長の長い波ほど沿岸では高くなる。
▽108 天気予報の波の高さ。高い方から3分の1の波の平均波高をを使う。これが「有義波高」(天気予報の波の高さ)。10波に1波は有義波高の1.3倍。100波に1波は1.6倍、1000波に1波は2倍の高さの波が現れる。逆に、有義波高は平均波高よりは高めだから、もっとも頻繁に起こる波は有義波高の半分くらい。天気予報で「2メートル」といったら、1メートルぐらいの波がもっとも多いことになる。
▽112
▽114 水深が波長の半分よりも浅くなると、波の形が変わって波長が短くなり、波の進むスピードが遅くなり、波と波の間隔が狭くなる。波の高さは波長の7分の1が限界なので、最後は波がトップから崩れ始めてブレークする。
▽116 波は海岸に近づくと海岸線に平行になってくる。湾内に進んできた波は次第に扇形に分散する。反対に、岬のように海岸線が突きだしているところでは、波が集まってくるので、波は高くなる。
▽120 大潮の時は潮流が非常に速くなる。この時、逆向きの風が吹いていると、潮流と風がぶつかって三角波が立つ。…河口付近でも、川からの水の流れと沖から進んでくる波がぶつかって波が高くなる。
▽126 津波は外洋ではたかだか数メートルの高さしかなく、しかも波長が極端に長いので、船に乗っていてもほとんどわからない。…深ければ深いほど速く進む。太平洋の平均深度4000メートルの場合、時速700キロ以上。
▽134 一般に、海水温が最も低くなる野は、沿岸部で2月、外洋では3月。高くなるのは沿岸部で8月後半、外洋では9月終わりから9月。
▽136 海水はマイナス1.3度にならないと凍らない。真水は4度の時が一番重いから、表面から凍る。海水は冷たいほど重いという性質がある。このため、海面の水がマイナス1.3度になっても、その下に温かい水があると、冷えた水は凍る前に潜り込んでしまう。海面まですべての層がマイナス1.3度にならないと凍らない。
ところが、オホーツク海だけは、アムール川という大河があり、オホーツク海の塩分濃度を下げる。そういう水は、ふつうの海水よりも軽いから冷えても底のほうまで沈めない。このため比較的簡単に凍ってしまう。これほど南で流氷が見られるのは、世界でもオホーツク海だけ。
▽138 高潮が起きるのは圧倒的に台風が接近した時、しかも海に向かって立った時に台風の中心が右側にある場合に起きる。オンショアの風。
▽143 地震雷火事親父。おやじ、というのは、台風のこと。「おおやまじ」が訛って「おやじ」になった。
▽154 台風は昔は中国では颶風(ぐふう)と呼ばれていた。この言葉がアラビアからヨーロッパに伝わる間にtyphoonにかわり、それが逆輸入された。
…風を背中から受けたときに左前方に台風の中心があるという法則がある。
▽156 昔から台風の進行方向の右側を「危険半円」、反対側を「可航半円」と言って、可航半円側に逃げ込むのが船乗りの常識となっている。
▽166 雲は高さ方向に発達する対流性の「積雲」と、水平方向に広がる「層雲」の2種類の大別される。層雲のうち、上層の雲は、髪の毛や羽毛のような形で現れる「巻雲」、別名うろこ雲などと言われる。…
▽170 夕焼けが見えるということは、太陽光線が差し込んでくるルート上に雲がないということ。地球の半径6380キロ、大気の層の厚さを13キロとして単純に計算すると、水平線に沈む太陽の真下はおよそ400キロ西。低気圧は1日におよそ1000キロの速さで西から東へ進むから、400キロというと9時間半先の天気を見ていることになる。
…ただしこれは、天気が西から東へ変わる秋から春の間しかあてはまらない。偏西風が弱まる夏は異なる。
▽172 雷の放電のときは、熱も発生する。そうすると空気が一瞬にして膨脹して大きな音が出る。これが雷鳴。
▽182 低気圧のエリートコースは、北寄りに進むコース。中心気圧が急激に下がって発達し、風が強まる。
高気圧のエリートコースは南よりのコース。次第にふくらんで勢力範囲を広げ、周辺部では風が強くなる。
▽184 西高東低。風は高気圧から低気圧の方へ等圧線をおよそ20度から30度の角度で横切りながら吹く。等圧線が南北に立っているときは、北西の風が吹き抜ける。
…東西に寝ているときは、西風になる。
▽186 春一番 シベリア高気圧に覆われていた日本海を、その年はじめて低気圧が通るようになると、全国的に強い南風が吹きあれることがある。
…日本海低気圧の風は危険。はじめ温かい南風が強く吹いていると思うと、寒冷前線が通過して、今度は真冬並みの冷たい北風が吹き始める。」
▽188 真冬の南岸低気圧。雪に。
▽198 小春日和。秋の移動性高気圧に覆われると、空気が澄んでよく晴れ、風も弱くぽかぽか陽気になる。
▽204 爆弾低気圧。もっとも風が強くなる低気圧は、発達の早い低気圧。1日で24ヘクトパスカル以上、1時間に1ヘクトパスカル以上中心気圧の下がる低気圧を「爆弾低気圧」と呼ぶ。南北の温度差が激しい、5月や11月。温帯低気圧は、台風並みの暴風をともない、台風よりも広い範囲に影響を及ぼす。





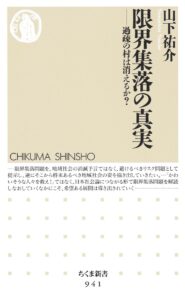
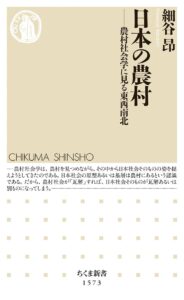

コメント