■家族農業が世界の未来を拓く<国連世界食糧保障委員会専門家ハイレベル・パネル> 農文協 20160618
かつて農業の規模拡大がすべてかのように論じられた。世界では緑の革命による増産がすすみ、国内では「海外の大規模経営に負けるな」と大規模化がめざされた。
だが世界では、化学肥料や農薬などで莫大なカネを豆乳する緑の革命路線によって農家の破綻が相次ぎ、日本でも企業経営が必ずしも合理的でないことがみえてきた。世界農業遺産の動きは、世界レベルで小規模農家の価値の見直しが進んでいることを意味している。兼業農家にも積極的な意味を見出している。
家族経営の農家は、労働生産性はともかく面積あたりの生産性が高く、環境面でも持続的である。家族レベルでは大きな投資ができないのが欠点だが、協同組合や政府、市民組織による何らかの援助によってそれを克服することができる。
ただ、マイクロファイナンスは、小規模農業への投資を支える手段としては効果的ではないことがわかってきた−−という指摘は意外だった。1年レベルの長期で資金を回収する農業では、家族レベルのミニ投資ではなく、もう少し上位の投資環境が必要なのかもしれない。
家族経営の農家の可能性をどうのばせばよいのか、という問題意識でつくられた報告書だ。
学術報告書だから読みにくく、すべてを読もうとは思えないが、ところどころの具体的なデータが役にたちそうだ。
=========
▽2 低い食糧自給率と、農業部門の高い高齢化率(2010年は60%以上)において、日本が置かれている状況は突出している。
…一方で日本は、小規模農業部門の経験を諸外国に提供できる存在である。農業生産者と消費者との直接的なつながりの日本モデルは「提携」と呼ばれ、世界の数多くの地域で類似の運動が広がるきっかけとなった。
▽19 世界食糧(食料?)保障委員会(CFS)は、専門家ハイレベル・パネル(HLPE)に対して「小規模経営の農業投資に制約があることについて比較研究をおこない、制約解決のために異なった文脈での政策的選択肢を示すこと…」を要請。
▽22 大規模農業と比較して、小規模農業が潜在的に効率的であることが幅広く報告されている。多様化した生産システムのなかで家族労働力を活用することによって、小規模経営が単位面積あたりでは高い生産水準を達成する能力を有している。
…効率的で持続的な小規模農業の事例が多数報告されている(中国、ベトナム、コスタリカ、グアテマラなど)
…中国は世界の農地の10%を占めるにすぎないが、食料生産では世界の20%を生産している。大規模農業に比べて、小規模農業が高い生産力を実現できることを示した重要な証拠である。
▽38 …小規模経営の発展は、市場の力と同時に先見性ある公共政策や、いくつかの国では生産者組織を含む強力な市民社会組織の行動によってつくりだされている。
▽46 中国やインドでは、大半の小規模経営は2ヘクタールよりもずっと小さい土地しか保有していないが、ブラジルの小規模経営では、その境界は50ヘクタールに及ぶだろう。
▽51 中国 集団的土地所有権が、各農村家族の農地利用権を保証することになった。2億戸近い小規模経営が存在しており、平均農場規模は0.6ヘクタール未満で、時の経過とともに縮小している。
…日本では、全体の55%が1ヘクタール未満、80%が2ヘクタール未満。
EU27カ国では、全体の49%が2ヘクタール未満。67%が5ヘクタール未満。
▽57 規模の大きな農場ほどうまくいくとは言えない。オランダ酪農の研究では、過去10年間で大幅に規模拡大した大型の企業か敵酪農経営が、高率の負債を背負っているという。(パイロットファームなど)
▽59 開発の真の目的は人間の可能性を拡げることであると提唱したセン。
▽69 構造調整が始まって以来、大半が高コストで低生産性である小規模農業を支援する公的事業計画・政策のほとんどが廃止される一方で、農業の進歩のための主な手段は市場であると奨励されてきた。…小規模経営を組織して交渉力を高めたり、政策決定に影響を与えたりする上で、小規模経営自身が設立する協働組合や教会が効果的な方法であることが明確になってきた。
▽81 多くの高付加価値作物、たとえば天然ゴム、果実、野菜は他の形態よりも十分発達した小規模農業においてこそ良好な成果を発揮している。。小規模農業は自営農業であるがゆえに労働にたいするインセンティブが有利に働く構造があるのに対し、雇用労働力を用いる場合は、膨大な取引・管理費用がかかるためである。
▽82 小規模経営が単位面積あたりで高い生産水準を達成する能力があることは、さまざまな場所や時代において立証されている。…議論の中心を生産モデルや生産規模の変化におくのではなく、生産要素や投入財へのアクセス制限・制約問題を小規模農業がどう克服するかにおくべきだと主張するのに十分な根拠を与えている。
▽83 コロンビアとインドのサトウキビの小規模加工業の可能性。
▽84 単位面積あたりの生産額が大規模農業のそれを上まわることも。これは、アジアの、稲作生産システムにおいて確かに見られる。…ブラジルでは、「家族農業」は全農地面積の24.3%しか占めていないが、農業総生産額の38%を生みだしている。
▽87 小規模経営世帯の戦略において農場は、危機の時には経済的な避難所としての重要な役割を果たしている。農外部門で職を失い、農場に戻ってくることもありうる。(大恐慌、ソ連のダーチャ)
▽88 日本のCSA(コミュニティが支援する農業=提携) 国際的に評価。
▽94 緑の革命で促進された、深刻な生態系不均衡。…インドでは女性たちが、農場現場で、在来種を保護するような生物多様性の地域保全システムを発展させてきた。今日の穀倉地帯には市場で重要視される作物が四つか五つか六つしかないが、過去には数百の作物があったのである。…小規模経営は、生物多様性や地域固有の育種の維持に重要な役割を担っている。
▽96 小規模経営の人びとは、芸術、音楽、出す、口承文学などをもっている。「地域の芸術」。こうした知の体系は時間をかけて発展してきたもので…
▽97 GDPおよび労働力において農業が占める割合は、開発の進展にともなって減少し、農業・農村社会から都市社会への移行が進む。「古典的経路」
▽106 OECDや旧ソ連では、機械化投資が国家によって支援されたことで、農業労働者一人あたりの農地面積が増加。
土地生産性ではアジアは全世界で最高水準。OECD諸国よりも高い。
▽121 サヘルの例
▽126 ボリビアのコチャバンバでは、農家はジャガイモの種芋を販売する際、他の農家に直接販売する場合もあるが、たいていは仲介業者に販売している。販売を担うのは女性であり、ジャガイモの貯蔵や運搬、転売を促進する役目を担っている。
…収穫後の損失を減らす金属製のサイロの導入がうまくいったのは、農村部で小規模製造業者の育成を推進したから。07年にエルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアで活動していた金属製サイロ製造業者数は892だった。そうした技術をより高度化するためには、民間業者の金属製サイロ製造への参入と農家のサイロ導入が不可欠。
▽129 オランダの協働組合銀行「ラボバンク」 今も協働組合。途上国で、協働組合銀行事業を構築するための支援もしている。その目的のひとつが「組合員の利益のために、市場の失敗による否定的な影響を是正・軽減すること」である。
▽130 農業に効果的な影響をもたらすためには、農家が自身の経営で、イノベーションを起こす気になるような金融サービスを構築しなければならない。
…マイクロファイナンスでは、農業ニーズをまったく満たせないことが明らかになっている。
▽134 契約農業 チリのトマト加工部門。グアテマラでは、大規模野菜輸出業者は80年代にプランテーション型の自社栽培から中規模栽培にシフトし、最終的には小規模経営との契約に転換したという。アジアでは、スリランカの紅茶業界が、垂直統合されたプランテーションから小規模経営へと仕入れ先をシフトしたという報告がある。茶葉の価格設定に関する透明性と安定性に対する政府の干渉、および労働組合の力が強いプランテーションにおける労働コストの上昇がその理由だった。
…小規模経営が、農家組織を設立したり、政府やNGOからの支援を受けることによって交渉力を獲得できなければ、自立を勝ち取るどころか、バリューチェーンにおける自律性を失うリスクを負う羽目になってしまうだろう。
▽136 大型小売りチェーンに対する小規模経営の経済的な力を強化する目的で、EU諸国では…フランスは08年の世界食糧危機後、主要な農産物や食品の価格とマージンを毎月監視し、ウェブサイトで公開することを決めた。
12年には最初の報告書が国会に提出されて、農家と大企業との間の偏った力関係について議論の質を高めることになった。
…国家による農地改革プログラムの実施は、小規模経営の契約農業スキームにとって欠かせない条件。
…効果的な販売協働組合を構築することで、企業に支払う取引コストを軽減できるだろう。グアテマラのクアトロ・ピノス協働組合〓。
…90年代初期に設立された、チリの「新世代協働組合」の多くが倒産にいたった。
▽138 グアテマラのクアトロ・ピノス協働組合 マヤの先住民グループに属する。約30年にわたり野菜の輸出ビジネスで成功している協働組合。
アジアの契約農業は、1960年代に導入された。アメリカの多国籍企業が、フィリピンのバナナとパイナップル部門に導入したのがはじまり。
▽142 道路網の整備は、小規模経営による市場へのアクセスおよび、農外での雇用を改善する。
▽156 中米農村地域開発戦略 コスタリカ主導のもと、中米7カ国とドミニカ共和国で導入された農村開発戦略。領域の特性に応じて開発を進めるのが特徴。狐崎知己「コスタリカにおけるテリトリアル農村開発 政策と理論の特徴」
▽160 これまでのところ、マイクロファイナンスは、小規模農業への投資を支える手段としては効果的ではないことがわかってきた。




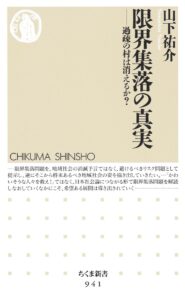
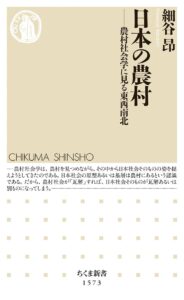


コメント