■街場の文体論<内田樹>文春文庫 20160404
神戸女学院での最後の年のクリエイティブ・ライティングの講義のまとめ。
よい文章とは? あたりまえでないこと。斬新なこと。でも斬新だといわれたシュールレアリズムも最初の宣言はすばらしいが、あとはそれをまねてしまってダメになった。
クリシェばかりではいけないが、しょせんはどこかで聞いたことがあるものを書くことになる。それをどう乗り越えるか。
講義では、あらかじめ決まった原稿を読むのではなく、ある考えが生成する場面を見てもらうようにしてきたという。文章も、あらかじめ書くものが決まっているのではなく、書いているうちに次々に生まれてくるようでないとつまらない。
そのためには、想定読者を宛先にして書く必要がある。その具体的なイメージがないテクストは、もごもごしてぼんやりしたものになってしまう。想定する読者がいると、身体と言葉がまさつをおこして文体も変化する。文体を一つしか持たない書き手は二流でしかない、ということなのだ。「一生懸命相手に届かせようとすること」が大事なのだという。
生き延びるためには、みんなは「向こう」に行くけど、自分は「こっち」に行ったほうがいいような気がする、という、おのれの直感に従うしかない。ものを書くことは、そういうセンサーを研ぎ澄ますための重要な訓練になるという。
だれかに向けて真剣に書くことで、他者と同期する。それによって自我がいったん解体して、より複雑でより精度の高い自我として再組織化される。文章を書いたり、外国語を学んだりする意味もそこにあるらしい。
養老孟司先生の「野蛮人の会」では、ふつうの人だったら「そんなこと、あるわけない」と鼻で笑うような話も「そういうことって、あるよね」と受け入れられる。ふつうの人は自分の知識では説明できない出来事について聞くと、「そんなことありえない」と反応をする。それよりも、まずは「信じる」ところから入った方が豊かになれるのに。
その通りだなあと思う。昔、宗教にはまった友人が金属の棒をコーヒーにかざして「味の変化を見て」と言ったとき、たしかに変化したのに、なにかタネがあって騙していると警戒して、そう感じないふりをした。典型的な文明人的な、自らの可能性を狭める行動だった。ありえないことがあるかもしれない、という感覚は若いころより今のほうがわかるようになってきた。
バルトののエクリチュールについての説明もわかりやすかった。
バルトは言語を、ラングlangue、スティルstyle、エクリチュールecritureの三つに分けてとらえた。ラングは母語であり、話者はそれを選択する権利はない。スティルは語感で、個人のなかに身体化されたもの。エクリチュールは2つの規制の中間に位置する。集団的言語運用という意味に近い。やくざの話し方や議員の話し方というのは選択することはできるが、一度選んだら、その社会集団から離れるまでは変えられない。エクリチュールの怖さは、その人の社会的なふるまいを規定してしまうという点にあるという。
日本人のエクリチュールは「おばさん」「やくざ」というように水平的だが、ヨーロッパは上下に階層化している。上層のほうがエクリチュールの標準化圧力が弱くて階層的な縛りから自由になれる。「上の人」は何を着ても、どんな言葉遣いをしてもよい。一方、下層の人は、誰と会ってもどこに行っても同じような言葉づかいで、同じようなふるまいをしてしまう。その自由度の差が、社会的に成功するチャンスに有意な差をつけている。
「もともとの教養をもつ者は、知らない、という平気で口に出せる。音楽でも美術でも、なにも知識がないままに「僕これ好き」といった屈託のない感想を口に出せる。後天的な努力によって身につけた人は、見たことない絵、聴いたことない音楽、飲んだことないワインについてもつい知ったかぶりをしてしまう」。なるほどなあ、自分は後者だなあと思う。階層の差が大きい欧州ではさらにそれが顕著なのだろう。
フランスのインテリは、自分の本を下層階級に理解してもらおうとは考えない。「寝ながら学べる構造主義」のような本は日本のような階層差がない社会だから受け入れられたという。
=============
▽20 僕は「書く」ということの本質は「読み手に対する敬意」に帰着するという結論に達しました。「情理を尽くして語る」こと。
▽25 自分のなかにいろいろなタイプの読者像を持っていること。単一の文体しか使えない人は、物書きとしては二流だと思います。
▽40 生き延びるためには、みんなは「向こう」に行くけど、自分は「こっち」に行ったほうがいいような気がするという、おのれの直感に従うしかない。そういうセンサーが必要。センサーを研ぎ澄ますためのきわめて重要な訓練が「ものを書く」ということ。「生きる知恵と力」を高める言葉と、生きる力を損なう言葉がある。前者だけを選択的にたどってゆく能力は必須のものだと思います。
▽ 「羊をめぐる冒険」の先達は、レイモンド・チャンドラーの「長いお別れ」。さらにその先行作品がスコット・フィッツジェラルドの「ザ・グレート・ギャッツビー」。
…3つの作品に通じるのは、「少年期との決別」という主題。そこを通過しないと少年は「大人」になれない。でもそれは自分のなかにある、みずみずしく、幼く、野性的な何かを切り捨てることなしには達成できない。
▽69 「宿命の本」になるには、誰かに勧められたわけじゃなくて、自分が自然にその本にひきつけられたという物語が必要になります。「偶然の出会い」じゃないといけない。電子書籍にはそれがありえない。
▽ ソシュールとアナグラム
▽103 司馬遼太郎 外国人が日本人の価値観や美意識や組織や権力構造を知ろうと思ったら、司馬遼太郎の「龍馬がゆく」「燃えよ剣」「坂の上の雲」を読むのが一番よい。日本人のことを研究したかったら、司馬遼太郎、藤沢周平、山本周五郎を読むのが効率的だと思う。でも、これらはなぜか翻訳がない。
…司馬は「身内のこと」を書いている。身内の悪口は言えない。本当に卑劣な人間については書かない。ノモンハンについて膨大な資料を渉猟し、生き残りの軍人たちにもインタビューしたけれど、ついに書くことができなかった。それは、ノモンハンにかかわった軍人たちのなかに、司馬が共感できる人物がひとりもいなかったからだ。そういう証言を読んだ記憶があります。
▽108 丸山真男は、大日本帝国の戦争指導部がなぜあれほど無能だったのか、怜悧に分析している。吉本と丸山は研究対象も近いし、結論もほとんど同じに見えます。でも、吉本隆明はひとつも翻訳がない。文体だけなら吉本のほうが詩人だから読みやすいのに。
丸山は軍国主義を戦前から批判していたから「超国家主義の論理と真理」は鮮やかに非情にきりさばく。吉本は軍国少年で20歳までに死ぬ覚悟を決めていた。だから、戦争に負けたというのが「ひとごと」じゃなかった。軍国少年として過ごした少年期のなかの「救えるもの」を切りだして、それを戦後につなげたいと願った。吉本や江藤淳に外国語訳がないのは、たぶん、外国の読者には、何をそんなに必死になっているかわからないから。
…戦争に負けたという事実が、日本人の書き物に手に負えない「わかりにくさ」を刻印してしまった。書いていることの核にあるのが「トラウマ」なんですから。
▽114 谷崎の「細雪」 東京人が関西にきて、さらさらと写生しているから、トラウマも欠落感もない。関西ネイティブでは書けない文章。だから翻訳される。アウトサイダーでないと書けない文章。外からの目線で書かれている。世界文学になるものは、自分がいるところを「外から見る」能力がないといけない。
…丸山は翻訳されるが、吉本がされないのは、「ローカル」だからではなく、吉本が「あらゆる国の人々が目を背けようとしている事象」を扱っているからなのだと僕は思います。
▽122 文章を書いてみたら、韻を踏んでいたり、575になっていたり、ダブルミーニングになっていたり、アナグラムが仕掛けてあったり、「自分にはそんなことをしたつもりのないこと」がぎっしり詰め込まれていた。…これが言語活動の霊妙不思議なところ。これについての一般理論をソシュールは立てようとした。つまり、脳はどうやって言語情報を処理しているのか、それについての一般理論をソシュールは求め果たせなかった。
…これに応えたのがロラン・バルト。「エクリチュール」という概念を提示。
バルトは言語を、ラングlangue、スティルstyle、エクリチュールecritureの三つの層に分けてとらえようとした。ラングは母語。そのなかにいるかぎり、話者にずいぶん広い自由が与えられるが、それを選択する権利はない。スティルは文体というより語感。言葉・記号に対する個人的な好悪の感覚。身体化されたもの。ラングは外的な規制、スティルは内的な規制。エクリチュールは2つの規制の中間に位置する。社会言語、あるいは集団的言語運用という意味に近い。やくざの話し方、議員の話し方…選択することはできるが、1回選んだら、その社会集団から離れるまでは変えられない。エクリチュールの怖さは、それが言語運用にとどまらず、その人の社会的なふるまい全域を規定してしまうという点にある。
…僕たちはエクリチュールを選ぶことができる。自分を幽閉する「檻」を選ぶことはできるが、一度選んだら、言葉遣いについての決定権を失ってしまう。エクリチュールが要請する言葉遣いで、エクリチュールとなじみのよいコンテンツを語ることを発話者はほとんど強制される。
…エクリチュールの及ぼす標準化圧力に対してあまりに無自覚だと、「いくらでも替えが効く」となり、人間としての扱われかたが雑になるというリスクを引き受けなければならない。
▽129 日本人のエクリチュールは「おばさん」「やくざ」というようなしかたで水平的に多様化している。でも、ヨーロッパは上下に階層化している。上層のほうがエクリチュールが「ゆるい」、標準化圧力が弱い。上流に行くほど階層的な縛りから自由になれる。「上の人」は何を着ても、どんな言葉遣いをしてもよい。
…そういうふるまいの自由は、下層に行くほど失われる。階層社会というのは、階層的にふるまうことを強いる標準化圧力そのものに格差がある社会。
下層の人は、誰と会っても、どこに行っても、自分の街にいるときと同じような言葉づかいで、同じようなふるまいをしてしまう。型にはまりすぎて脱げない。その自由度の差が、社会的に成功するチャンスに有意な差をつける。
▽134 エクリチュールの様態を分析するバルトらの書き物それ自体が階層下位の人たちには理解が難しい文体で書かれている。
▽145 日本は、知的な階層差をつくりたくないという社会的な要請が強い。
▽147 語り手の階級制も政治的立場も…なにひとつ痕跡を残さないような透明な語法を、バルトは仮説的に「無垢のエクリチュール」と呼んだ。それをめざす目標として掲げた。
▽201 生き延びるためのリテラシー 今のような雇用環境においては「就活なんてバカみたい」というリアクションをする学生のほうが「まっとう」。「変なこと」には「これは変だ」ときちんと言ったほうがいい。これはおかしい、とかいうことに関しては、自分の感覚を信じたほうがいい。
▽205 バルト「まずテクストが存在する」。僕が者を書くとき、掻き出す前に「これからこんなことを書こう」ということについて、けっして明確なプランがあるわけじゃない。ほとんどの場合はキーワードだけしかない。
…想定読者がいる。その人を宛先にして書く。その具体的なイメージがないとたたみかけるようには書けないんです。想定読者がいないテクストというのは、なんだかもごもごする。ぼんやりしたものになる。
▽211 文明人と野蛮人 養老孟司先生の「野蛮人の会」 そこの人たちは「あり得そうもない話」に対するハードルが低い。ふつうの人だったら「そんなこと、あるわけないだろう」と鼻先で笑うような話が、「そうそう、そういうことって、あるよね」となる。
…「何でも信じられる」というのは、けっこうすごい能力じゃないかと僕は思う。ふつうの人は自分の知識では説明できない出来事について聞くと、とりあえずは「そんなことありえない」という反応をする。それってちょっとつまらない。まずは「信じる」ところから入っちゃダメですかね。(清川の人は、とりあえず聞いてみる〓)
▽225 アメリカでは識字に問題がある人が人口の20%、フランスでも10%を超えている。漢字やひらがな、カタカナの3種を覚えなければいけない日本語話者の方が識字率が高い。表意文字と表音文字が併存するせいで、脳内の2カ所を使って手分けして言語処理をしていることとかかわりがあるんじゃないか。
▽245 言語における創造性 …言葉だけがあって、身体実感が伴わない、その逆に、身体実感はあるが、言葉にならない。この絶えざる不均衡状態から言葉は生まれてくる。むしろ、そこからしか言葉は生まれてこない。創造的な言語活動とは、この「絶えざる不均衡」を高いレベルに維持することではないか〓。(「昔はものをおもはざりけり」という言葉を知っていても、身体レベルでわかるのはだいぶ歳をとってから)
今の日本の言語状況は、非常に貧しい。自分が操っている言語と身体感覚の一致に安住しているように見える。
▽252「オリジナル神話」も「英語が使えるグローバル人材」も結局は「貨幣」という物神によって人間を操作しようとすることによって、すべての人間に本来備わっているはずの「外へ」というみずみずしい動きを傷つけている。
…自分の外側にある他者と同期すること、それによってそれまでの自我がいったん解体して、より複雑でより精度の高い自我として再組織化されること。(外国語を学ぶ意味も)
▽254 クリシェ(出来合の言葉) 鮮度の高い言語と、クリシェは似ている.自分ではオリジナルでユニークなことを語っているつもりで、出来合いのストックフレーズを話しているということがよくある。
▽268 身体化した定型は強い。母語の統辞法や修辞法や韻律の美しさ…を深く十分に内面化した人には、どのような破格も許される。破格や逸脱というのは、規則を熟知している人間にしかできない。悪魔は神学的には天子が堕落したものとされている。神の定めたすべてのルールを内面かしていないと、悪魔の仕事が果たせないから。(型にはまって、型を破る。鴎外か〓)
▽273 仏文学会を何年か前に退会した。若い仏文学者たちの発表を集中的に聞いて、この学会には先がないと思いました。
…フランス語で学会発表した若者は「これが理解できるヤツ以外は聴くなよ」と言っている。彼らには学術研究というのは本質的に贈与であるということがまったくわかっていない。彼が求めているのは、精度の高い査定と、それに見合う報酬です。
…翻訳というのは研究業績としては評価が低い。10年かけた翻訳より、1週間で書いたペーパーのほうが文科省的な基準では評点が高い。
…「寝ながら学べる構造主義」は同業者からは評価が非常に低かった。
▽282 明治期の知識人たちの超人的な知的活動を駆動していたのは、競争優位に立って「いい思い」をすることではない。国を救わなければならないという切羽つまった義務感です。「吾輩は猫である」は欧米の最先端の学知を一覧している。筒井康隆の「文学物准野教授」は、コメディの形を借りてハイデガーの存在論から、構造主義やラカンやデリダまで一覧したもの。〓。これは「猫」の系譜につながる業績。
…285 先頭に立って「道なき道」を進み、後に続く人があるやすくしておくこと、それが少なくとも明治40年代までは、学者や知識人に集団的責務として自覚されていた。
…敗戦後の日本の大学人はけなげでした。仏文学者たちも、泥臭い「雑巾がけ」仕事に打ち込んだ。学問研究の成果は社会に還元されなければいけないと考えた。
桑原武夫は、(軍国主義)同じことをもう二度と起こさないためには、学者たちはその専門領域を超えて共同戦線を構築しなければならないと考え、人文研が中心になって共同研究という新しいスタイルがつくられた。日本近代史で二番目の大きな「知識人の覚醒」の経験だった。(〓共同研究の背景=つながり)
…でも僕が東大の仏文に進んでみたら、もうこの「おじさん」たちの時代が終わっていた。秀才たちに埋め尽くされて、共同研究的なマインドなんか、もはやかけらもなくなっていた。
そのころから、人文科学の人たちが政治屋外国や国際問題について発言することがなくなった。「象牙の塔」に閉じこもって、重箱の隅をつつくような「国際的」な研究に打ち込むようになった。
▽291 「情理を尽くして語る」言葉、受信者の裾にすがりついて、「お願いだから、オレの話を聞いてくれ」という懇情の言葉だけが「外に向かう」ことができる。
▽293 レヴィナスの哲学的主題のひとつが「なぜ人は外部から到来する意味不明の言葉に聴き従うことができるのか」。
▽309 どうしたら「眠らせない」で授業を聴かせることができるか、ずいぶん研究しました。「今、目の前で言葉が生成している」と学生たちに実感してもらうこと。そのためには、振り絞るように、いま、ここで言葉を紡ぎ出さなければならない。おおかたは「すでに仕込んであるネタ」でも、何パーセントかはそのときはじめて、学生たちの前で思いついた「新ネタ」でなければならない。…どんなに支離滅裂でも、自分たちがその生成に関与している「とれたての説」の方につよく反応する。


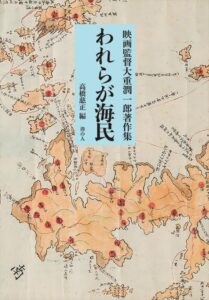

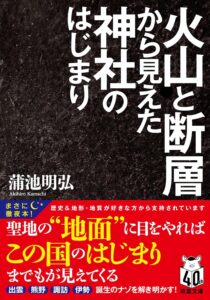

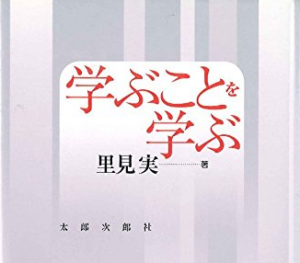

コメント