明石書店 20070127
イラク戦争における米国、旧東西ドイツ、イスラエルの兵役拒否のありかたを紹介するともに、その背後にあるキリスト教や近代哲学の流れをフォローしている。社会主義独裁とされてきた東ドイツで、教会を支えにした兵役拒否の運動があり、それが、政権の土台をゆるがす市民運動に育っていったこと、その運動をメディアが報道することで、兵役拒否者への人権侵害を弱める働きがあったこと……などの描写がとくにおもしろい。
兵役拒否のなかには、▽内面の自由に権力が介入しないという「自由主義的な兵役拒否」 ▽自らの内面のみではなく社会に目を向け武器をもつかわりに非戦闘的な役務につく「代替役務型兵役拒否」 ▽「民間役務型兵役拒否」 ▽「兵役完全拒否」 ▽非人道的行為を拒否する軍人による「選択的兵役拒否」……といった種類があり、権力との距離のとりかたがそれぞれ異なるという指摘も興味深い。
また、命令されておかした罪でも、実行者である下層の兵士の刑事責任が問われるようになってきたというのは、上官の命令よりも大切にするべき理念・哲学をもつことを個々の兵士にもとめるということだ。民間人虐殺の命令でさえも「陛下の命令」とされた旧日本軍ではこんな発想はでてこない。世俗権力から独立して存在するキリスト教という権威が、個人の「主体」や「個」の確立に寄与したのだろう。
会社の不利益になったとしても社会正義のための情報提供をもとめる公益通報制度にもつながる思想である。「上司の命令」によって生活保護を切ることは許されないし、年寄りに無理な金融商品を売りつけることも許されない。社会正義を内面化した「強い個人」がなかなか育たない日本のあり方はある意味絶望的ですらある。
------覚え書き-------
▽はるかに多くの残虐行為が、極悪人によってではなく、「命令に従った」だけの「まじめな」人たちによって行われてきた……ハンナ・アーレントは、悪の凡庸さについて、アイヒマンをとりあげて語っている。
▽米国では、兵役拒否者は、自分の倫理観に基づいて意思決定した勇気ある人とみなされる。これに対して脱走兵は、だらしなく、自分の任務を投げ出した信用できない人間だと断罪されがち。「自ら同意して結んだ契約を破るのは卑怯だ」と。
兵役拒否の申請を行えるのは事実上一部の人だけ。申請書の作成には一定程度の能力が必要だが、高等教育を受けてないと、こうした制度の存在さえ知らない場合が多い。
▽「市民的不服従」 国家の命令より、国際人道法や人権といった普遍的な理念を尊重して行動し……
▽第2次大戦に従軍した米軍兵士のうち80-85パーセントが敵に向けて発砲することができなかったという調査。これを受け、訓練を「改善」し、朝鮮戦争では45パーセントに。ベトナム戦争では5-10パーセントに減少した。(p44)
▽ベトナム戦争中、精神的・神経学的理由で撤兵させられた米軍兵士は5パーセントにすぎない。第二次大戦中の米軍では23パーセントだった。「戦争が終わるか、怪我をしなければ」帰還できなかった第二次大戦とは異なり、ベトナム戦争では、兵士の従軍期間に1年という明確な期限があった。危険な任務についている時間も限定的だった。……ところがPTSD
▽配偶者がイラク戦争に派遣された夫婦のうち20パーセントが、2年以内に離婚している。
▽バグダッドの若い女性の英語日記 Baghdad Burning しばらくブログが更新されないとき、世界の読者が安否を心配した。
どうやって見つける?
▽キリスト教の伝統「殺すな」 敵を愛し、暴力拒否。帝ローマ国への無条件の誓約、上官への服従は神に対する絶対的服従の義務に抵触した。コンスタンティヌスがキリスト教を公認するまで、古代教会はおしなべて平和主義の立場だった。p80
コンスタンティヌスが他の宗教に対するキリスト教の優位を保証し、ついでテオドシウスが国教化すると、キリスト者は皇帝の兵士となった。帝国が与える保護と引き替えに、教会は信徒に戦争への参加を義務づける。
▽「自由主義的な兵役拒否」は、国家にとっては、その政策の正当性を脅かす危険性をはらむものではなかった。
「代替役務型兵役拒否」クエーカー 武器をもつ役務を免除されるかわりに、非戦闘的な役務を認めるようになる。積極的に政治にかかわることで、権力のあり方をよりよくしようとした。……国家政策の正当性に疑問を差し挟む存在ではない。
「民間役務型兵役拒否」「兵役完全拒否」
「選択的兵役拒否」は軍人による兵役拒否。非人道的・非合法的な行為を拒否する権利および義務、という両面性がある。
▽98 兵役拒否を認める制度があっても「良心の審査」があれば、個人の内面の問題に国家が介入することになる。1983年ヨーロッパ議会決議では「……大多数のケースにおいて兵役拒否者の身分を保障するため、個人の動機の表明で足らねばならない」
しかし、このような完全な形で人権として保障されているのはデンマークだけ。
▽101 旧ユーゴ国際刑事裁判所、ルワンダ国際刑事裁判所につづく国際刑事裁判所の常設。人道に対する罪、戦争犯罪が上官の命令に従ったとしても、a上官の命令に従う法的義務を負っていて、かつ bその命令が違法であることを知らず、かつ、cその命令が違法であることが明白ではなかった場合、という3条件を満たさなければ個人の責任が問われることになった。……国際法は、人道に反する命令に対して、抗命義務を兵士に課している。
▽112 東ドイツ ナチス政権下の告白教会は国家に追随せず精神的自立を貫いた。東独の福音教会はそれにならい、社会主義であっても教会の自立を保つことを重視し、精神的自由を守ることを中心課題であるとした。軍務を拒否することを神学的に高く評価し、兵役拒否者らを支援した。それを可能にしたのは、伝統的に国家が教会に与えていた特権を、東独の教会が失っていた、という背景がある。
▽126 市民に存在さえ知らされず、兵役拒否者が配属された「建設部隊」。徴集年齢ぎりぎりの26歳で召集され、居住地から離れた場所に駐屯させられるなど、嫌がらせも。人民軍内の「怠け者」「同性愛者」といった誹謗中傷は日常的だった。除隊してからも教育や職業で差別を受け、大学進学はほぼ不可能だった。
▽135 「平和奉仕役務」を求める運動。教会が民間役務の法制化を要求し、それが西側メディアに流れると、完全拒否者に対して控えめな態度をとるようになる。あくまで教会との衝突を回避しようとした。(メディアと教会の力)
▽80年代になると、西側との経済格差が拡大し、西側への移住希望者が国外追放になることを望んで兵役拒否した。
教会が民間代替役務を要求。「社会主義のなかの教会」によって保たれていた教会・国家関係の安定が失われた。民間役務の立法化に着手……まもなく東ドイツ消滅。
▽140 建設部隊は「いかがわしい妥協」だったが、彼らは国家に対して「否」と言うことが可能であることを示した。彼らは社会を変革するとは思っていなかったが、社会の意識を変化させることに寄与した。……1990年2月には世界で最も進歩的な非軍事役務法を成立させた。7カ月後には無効になったが……
▽142 西独 基本法制定以前、さまざまな州憲法に、住民の平和主義の志向を反映して、強制される軍役を強く拒否する規定がもりこまれた。(日本で9条が歓迎された状況。草の根自治体がそれを先行したドイツ)。冷戦の激化を反映して基本法には「その良心に反して」との限定が加えられた(日本の「逆コース」)。
▽161 民間役務ツィバイ 連邦軍での役務に就いたものは、几帳面さ、自制心、チームワークの面で評価が高い一方、ツィバイの方が創造性、自律性、責任感といった経営に役立つ訓練を積んでいると考えられている。
2001年から、ドイツのツィバイが日本で「市民的奉仕活動」を行えるようになり、障害者施設や特養などで1年間働いている。
▽165 当初絶対的少数者だった兵役拒否者は、ツィバイとなっていまや多数者である。国家に対する「否」を示す存在ではなく、福祉国家を支える存在となっている。
……東西ドイツ、どちらの兵役拒否の展開についても、共通しているのは、一人ひとりの「内面の選択」がダイナミズムを生みだしているということである。
▽182 イスラエル 最も多いのは、占領地での任務に就かないとする選択的兵役拒否者。……占領地での任務拒否に対する刑期が安定しているのに対して、徴兵拒否者の刑期は長くなる傾向にある。刑期を終えても、すぐまた召集され、同様に拒否すると再び収監される。高校生で徴兵されることを拒否した若者5名は、03年からほぼ1年にわたって拘束されていた。
▽186 イスラエルで兵役を果たすことへの社会的圧力は非常に強い。公に拒否宣言することは、職場や友人関係も失いかねず、裏切り者として糾弾され、最も親しい人たちからのきびしい批判も覚悟しなければならない。……公然と拒否する人には厳しいが、予備役を回避する方法は無数にある。
(軍事国家)
▽190 国防のため兵役を果たすのは当然であるという認識。軍隊においても自分たちが主人公であるという意識。兵役拒否者もこの認識は共通している。……軍隊内にあっても、上官の命令一つ一つを自ら判断して執行するか否かを決定しようとする。「考える兵士」
▽216 日本 明治期には、公務員、所定学校生徒、留学経験者、家長などのほかに代人料を支払ったものも兵役が免除された。軍国主義が強まるにつれ、わずかの例外規定となった。……神道・仏教のどちらも兵役拒否の教えを伝えなかった。仏教では殺生を重い罪としているが、個々の信者が教えを守らなくても、仏によって罰せられることはない。キリスト教は、国家の意思に反して行動すべき強い基礎を提供しているが、仏教は国家に対抗する権威ではなかった。従うべき「主」はいない。「軍人勅諭」では、上官の命令は天皇の命令であるとした。日本軍は国民の軍隊ではなく天皇の軍隊であった。
▽219 自衛隊では「不当な命令」「瑕疵ある違法な命令」「重大な瑕疵ある違法な命令」と、命令を3区分し、不当な命令には服従すべきではなく、残りの2つの命令には一応「服従」してから異議を唱えることが「適当」とする教育が行われている。
▽224 2002年、民間技術者12人が自衛隊艦船のいる現地に派遣された。会社からの業務命令で派遣された技術者は、現場で何が起きても防衛庁の責任を問わないという誓約書まで書かされていたと報道された。
▽227 PKO協力法に基づく派遣では、「軍事作戦ではないから何でも公表する」原則に従い、公表された実施計画には派遣人数と武器の種類と数が明記されていた。しかし、イラク派遣は、実際に何人派遣されているのかさえ公表されていない。武器も、種類は明らかにされたが数は伏せられている。
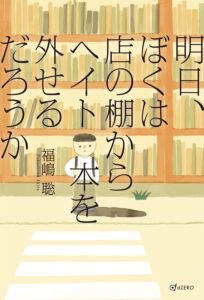
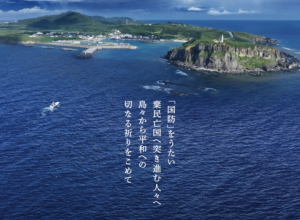

コメント