■熊楠の森−−神島<後藤伸、玉井済夫、中瀬喜陽>農文協 2011年 20151229
田辺市の沖に浮かぶ神島は、神社合祀の伐採計画から南方熊楠が守ったことで知られる。
高校教師だった筆者たちは、紀伊半島の自然を守る取り組みのなかで、神島の自然も調査してきた。
神島の森は熊楠の尽力で天然記念物になり、手つかずで守られた。だが、1960年代からウミウなどの群れが住みつくようになり、その糞害で巨木がつぎつぎに倒れていった。ドブネズミも大量に発生した。
熊楠の記録と比べると、タブノキやクロマツの多くが姿を消した。森を覆っていたタブノキが枯れることで、日当たりが好きなクスノキが増えたという。クスノキは照葉樹の代表と思っていたから、日当たりが好きな木とは思わなかった。
田辺湾で1960年代から養殖漁業がはじまり、同時に入り江の埋め立てが進んだ。輸入外材の樹皮の海上投棄も重なって富栄養化と汚染が進んだ。養殖筏から飼料が流れ出し、そこに小魚が集中し、それを狙って海鳥が群がるようになった。そうしてウ類やサギ類が神島の森をねぐらにするようになった。
鳥類の糞が葉に付着すると光合成ができなくなり、葉は枯れて落ちる。すると林床に日がさして、日陰を好む低木や下草が衰弱する。地表に糞が堆積してチッソやリンがたまると、大木は株元から腐敗して森林が壊滅していったという。
ウ類を音などで追い払う実験が奏功し、ドブネズミも、陸地からわたってきた狐などによって食べられて減った。今の神島の森は、壊滅か持続かの微妙なバランスをとっている状態にあるらしい。
=============
▽「魚つき保安林」制度。伐採を規制する制度だが、実際は、海岸線の森の多くが伐採された。「魚は緑色が好きやから、山に緑を残しといたら魚がそばへ寄ってくる」とおやじが言った。海岸に緑を残して老いたら、漁業はいつまでもできる、と考えられていた。
▽15 火事跡地や山崩れや崩壊跡などにヤマモモを植えた。寝に根粒バクテリアがついていて、自分で肥料をつくるから、痩せ地でも育つ。…皮は染料に。兵隊服のカーキ色は全部ヤマモモ。
…瀬戸内海の海岸林も全部ヤマモモかウバメガシが植えられ…明治の中頃までに、植えられた。
▽19 1946年の南海道大地震のときの大津波。当時は田辺湾の岸には深い入り江がいっぱいあって、…この入り江が津波のエネルギーをみんな消していった。
▽24 江須崎はもう助からない。1957年にまわりに道をつくったからです。たった1回伐っただけで、あとは順番に枯れてきた。…今、中心部だけに元の木が最後に残っている。その中心部の森はみんな曲がりくねった格好になっている。
▽30 神社合祀。基本金がないなら他へ合併せよ。…「基本金」や「神職」の有無を尺度に、廃合を断行した。
▽37 神島の森、野中の継桜王子社の社叢、那智の滝の原生林、引作神社の楠など、熊楠の説得で残された神社林もあることはあるが、たいていは姿を消してしまった。
▽55 神島はハカマカズラ(ワンジュ)の自生地。この実をを拾い集め数珠の材料として京都の仏具店に売り出した。
▽57 昭和31年、愛媛大学の森川国康に依頼して最初の学術調査。
▽61 神島の森はタブノキが極端に減っていた。
▽74 クスノキ 照葉樹林の代表のように考えられているが、実際は森の中には少なくて、林縁や単木として生えている。常緑樹のなかでは、日当たりのよい地に生える性質があるから、タブノキが神島を覆っていた昭和初期までは、成長が抑えられていた。
▽87 1955年までの江須崎は西南日本の照葉樹林を代表する大森林だった。
▽119 知多半島の鵜の山。地元の人たちはカワウの巣の下に筵を敷き詰めて、糞を集めた。果樹園の肥料とされ重宝された。化学肥料の普及で、カワウは邪魔者扱いされる。逃げ回っていたカワウの群れにとって、養殖漁業の発達は大繁殖のきっかけとなった。
目次





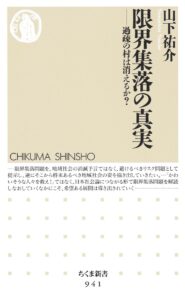

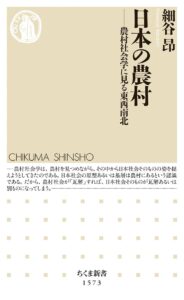
コメント