■明日なき森 カメムシ先生が熊野で語る<後藤伸講演録>20150611
栗栖太一という人は、遠くから山を見ただけで木の本数までわかってしまう。虫を捕まえるには、「そこで座って待ってろ。木になったら、向こうからやって来るさかな」。動物や植物のことを知るにはできるだけ地面に近いところで寝ればよい。「一人で寝てたら動物のほうから遊びに来るもんや」という。
谷に滝があって、上に魚がいなければ下のを持って上がった。何年かたって炭を焼くときにはまた食べられるようになった。
そういう知恵がかつては受け継がれていた。
ヨーロッパから入ってきた植林の手法に紀州の人は反対した。山の尾根は自然林に残す。谷間の緩やかなところだけ植林する。谷間にはスギ、中腹にはヒノキを植え、南向けの斜面は自然林として残すというのが、紀州人の掟だった。
戦後、「欧米には到底太刀打ちができん」と、今までの文化や知恵も捨ててしまった。植林1本いくらの補助金が出て、どんな崖でも植えまくった。
カメムシの大発生や花粉症の原因は、スギやヒノキの花や実が増えたからという。杉は本来千年以上生きる木だから条件のよいところに植えたら100年やそこらでは花も実もつけないという。
スギ・ヒノキは強い殺菌力があるから土の中の細菌がいなくなる。腐葉土が消えて粘土になる。だから雨水は地面をさっと流れ、山の保水力がなくなる。
広葉樹の根は地中深くに入るが、スギやヒノキの根は横に張るから根の板ができる。その下に水が入ると板ごと滑る。そういう予想が2011年の紀伊半島の大水害で現実になった。
熊野では、海岸にカモシカがいて、冬眠しないクマがいる。海抜30メートルにホンシャクナゲがあり、谷底に高山植物のヒメイワカガミがある。ウバメガシはほかでは海岸線にしかないが、紀伊半島だけは山奥まである。
潮岬は、最高気温がいちばん低くて、最低気温が一番高い。海があることと、森そのものが夏の暑さを防ぎ、冬の寒さも防ぐからだという。
======================
□栗栖太一物語(1995年に91歳で亡くなった)
▽27 木の本数を遠くから見ただけでわかってしまう。「向こうの山見て、何という木がどれくらい生えているかわからなんだら炭焼けるか…木の葉っぱ見て、茂り具合でなんの木がどれだけあるか見て、これで炭何俵ぐらい焼けるか考えて、それよりちょっとだけ少なめに言うて山主から山を買う」
▽31 「虫が来てから出かけていったら、虫逃げるに決まってる。ほやから、ほんまにええのとりたけりゃそこで座って待ってろ。木になったら、向こうからやって来るさかな」
▽33 谷に滝があって、上に魚がなかったら下のを持って上がる。そのうちに増えて、何年かたって炭を焼くときにはまた食べられる。
▽49 太一ちゃんに僕が聞いたのは、動物や植物のことを知るためにはまず山に寝ることです。できるだけ地面に近いところで寝る。一人で這って寝てたら動物のほうから遊びに来るもんや。
▽50 戦後の拡大造林で強引に植えたところは、やがて順番に崩壊していく。スギやヒノキの根は必ず横に張る。上で広がる広葉樹の根は深く入る。スギやヒノキは横に張るからしまいに根の板ができる。その下に水が入ると必ず滑る。太一ちゃん「二代目の植林が成木になったころ、ここ20年ぐらい先で、せっかく植えた植林地が大体滑る。あそこは滑る。あれも滑る。これももうじき滑る」
□虫たちからの告発
▽56 カメムシのにおい。カメムシ酸が傷口につくと大変。目に入ると猛烈に痛い。
これからお話しすることは、虫の立場から言いますので…(峰雲さんと同じ〓)
▽57 松が枯れ、梅や桜が枯れ、カシの木が枯れる。虫が悪い、と決めつけるが、虫に言わせたら「わしら木い枯れて餌ができたからついてん」と言ってるんですよ。
…大気汚染がウメ枯れの原因のように言われるが、日本でいちばん大気汚染が激しかったのは戦時中。あらゆるものが燃やされ、日本の上空に漂うて、毎日毎日赤い太陽が半年も続いたんです。でもその大気汚染では植物は枯れてない。豊かな自然林があったから空気をきれいにしていた。〓
▽63 DDTやBHCの時代に農業指導をやっていた人の大半はガンで亡くなりました。
▽65 チェーンソーが日本の気候を変えてしまった。さらに切り口に油を使うから、新たな芽が出ない。
…ヨーロッパから入ってきた植林事業のやり方に紀州の人は反対してきた。「国の言うことを聞かなかったら林業はうまいこといくんや」とかいうようなことを合言葉にやってきた。これが戦後の日本を救った。
…本来、植林は大きな山でもその3分の1ぐらいしかできない。山の尾根は自然林に残す。谷間の緩やかなところだけ植林する。谷間にはスギを上、中腹にはヒノキを植え、南向けの日の当たるところは自然林として残すというのが、紀州人の本来の掟だった。
…広葉樹は雨の酸性を中和する。スギやヒノキは元来古い時代の植物。その時代の地球の雨はそれほど酸性ではなかったんだろう。
▽68 一等地に植えた材木が悪くなっている。原因は、まわりの森林がなくなって全部植林になったから。
…スギヒノキを植えたのは、1本いくらの補助金が出たから。日当が5000円の時代に、山仕事をしたら1万円から1万5000円ぐらいもらえた。どんな崖でも植えまくる。ひどいときは何本も一緒に植えた。(〓農政と同じ。国のいうことを聞くとろくなことはない)
▽70 原生林では、あしもとに5、6万の虫がいる。ミカン畑は1000.ウメ畑は200ぐらい。ウメは落葉樹だから下草が生える。除草剤がミカンより多くなる。スギの植林は1000前後。
▽73 1種類の害虫を消したら2種類の害虫が増える。
▽84 スギやヒノキの実がカメムシの餌になる。スギヒノキがたくさんの球果をつけるのは、大半の植林地のスギやヒノキが枯れかかっているから。花粉症とカメムシの問題は根がひとつ。
▽86 100年前までの人は、山が荒れるとヤマモモを植えて自然を回復させた。
▽89 紀南農協・堀修実 カメムシ対策。先生は、ブラックライトという灯火でカメムシを呼んで、その下に置いた水盤に落ちてくるカメムシを溺れさせる。上富田農協管内ではブラックライト方式が一挙に普及。
…カメムシの大発生は、戦後の拡大造林に原因がある。
□常識を覆す生きものたち
▽海岸のカモシカ 冬眠しないクマ 野生のミツバチを誘い込む蜜桶。冬になるとクマはそれを食いに来る。
…海抜30メートルのホンシャクナゲ。谷底にヒメイワカガミ。
▽111 ウバメガシ。全国ではほとんど海岸線だが、紀伊半島だけは山奥まである。ウバメガシはナタできる。放置すると優占種になるシイなどはノコギリで切る。それを何百年つづけると、カシ中心になる。
▽115 古座川 ハリオの滝 体に20を超すヒルがついていて、転がり落ちてきたことがあった。古座川流域は「沖縄」であり、「北海道」。潮岬は、最高気温がいちばん低くて、最低気温が一番高い。海があることと、森そのものが夏の暑さを防ぎ、冬の寒さも防ぐ。
▽130 崖地に珍しい植物。
▽133 荒れたところは、コナラを中心。ほとんどが熊野古道の周辺。熊野文化が盛んだった千年前は本宮は大都市で人口も多かった。金銀の鉱山を掘る人も集まった。…このへんで当然生えるべき常緑のカシやシイの森が育たなくなった。
▽143 イチイガシ カシの仲間で最高の木。堅くて重くて強くて。本宮大社や祓戸に大木がある。…照葉樹林の森の中は夏は非常に涼しい。冬は非常に暖かい。熱帯計の昆虫がいちばん多いのは、潮岬ではなくむしろ山奥。寒いところの昆虫も同様。
▽150 日本の自然が壊れるにしたがってクヌギやコナラなど、冬に葉の落ちるカシ類が増える。それらの林は、寒いから、ではなく、自然が壊れたから。土に力がないから、冬に緑の葉を保つ力がない。
…ウバメガシの生まれ故郷はヒマラヤ。氷河期にやってきた。寒さに強く、乾燥に強い。
□生物の空間を創る
▽160 ヨーロッパの中心部は全部草地になって、非常に荒れている。だからそこにモミの木とか植えて自然を回復させてきた。そういうことを最初に手がけたのがドイツ。ドイツの植林が日本に入ってきたころには、ドイツではだめだということがわかり、広葉樹を植える仕事にかかっている。ところがそちらは日本に入ってこなかった。…ウィーンの森も人間の手でつくったもの。
▽163 ヨーロッパおn草原の文化を素晴らしい文化だと明治維新の連中が考え、日本がもっていた、森林と一緒に暮らすという本来の文化を捨ててしまった。
「草原の文化」や「砂漠の文化」とちがって、森の文化は、みんなが同じことをせんでも生きていける。草原では、みんな顔を見合わすことができる。相談して多数決して…草原であるがゆえの民主主義。
▽164 昔は田んぼの畔には、カエルとか蛇が踏むほどあった。無数の動物がすんでいたけど、昭和30年ごろを境に完全に消えてしまった。
…かつて、シラミ、ナンキンムシ、カイチュウ、ギョウチュウ…。その当時の子にはアレルギーはなかった。蚊にかまれても「薬塗って」とは絶対に学校で言わなんだ。日本でビオトープをやらんならんという事態になったことを、深刻にとらえんならん。
▽170 ソメイヨシノは植えて10年もたつとテングス病にかかって枯れていく。テングス病はカビだから、湿り気のおおいところはだめ。奇絶峡なんかに植えたら確実に枯れる。ソメイヨシノはクローン。300年以上たってる木やから強いはずはないね。もとは1本の木やから、こういう気温になったら花が咲くちゅうのちゃんと予想できるわけ。野生の植物だったら、そんなことできるはずない。
▽172 常緑の森っていうのは、冬越しに来る場所。姿隠せるような森出ないと野鳥には意味ないわけです。…鳥が雛を育てるときは、虫が必要。新芽がパッと吹いて、ワッと虫が発生するという、そういう落葉樹の森が、小鳥を育てるのにいいわけ。…新緑の季節だけで量ってみたら、落葉樹の方がはるかに緑の葉っぱをたくさんつける。(虫の目、鳥の目から、自然の仕組みを説明する。)
▽175 自然界の三本柱は「生産者」「消費者」「分解者」。なのに、学校では「分解」のことをとりあげない。ヨーロッパの草原の科学のなかでは、分解者というのはあんまり大きな影響がないから。生産者と消費者の二つで自然界ができていることになる。これがそのまま経済学に応用されて、需要と供給の理論ができてきた。需要と供給だけで理論を組み立てたら社会は急激に発達できる。ところが、これに分解を入れたら社会は発達できない。
かつての日本には分解の機構があった。江戸は、大都市でありながら、ゴミ問題や屎尿処理問題はなかった。循環システムができあがっていた。そのかわり、人口集中したのに、ヨーロッパの大都市のような発展はしなかった。
江戸から東京になり、日本のやり方をすかっとやめてヨーロッパ的になったとたん、ゴミ問題に苦しみはじめる。近代社会は、分解機構を考えないで発展してきた。
▽180 セイタカアワダチソウ。まずは毒を出してほかの植物を枯らしながらどんどん増える。しまいに自分ら同士で頃試合をする。やがて絶えてしまう。しまいにそおに木が生えて…森林に。
▽182 神島。カズラだらけ。台風で樹木が倒れたところをカズラが埋めた。そうしたら日陰の植物は枯れない。
▽185 日本には原生林の状態のブナ林がある。原生林だから水を蓄える力が大きい。しかし、常緑樹の原生林があったら、ブナ林よりはるかに水を蓄える力が大きい。そういう原生林はもうない。残ってたら、森の保水力なんてそら桁違いのもんになってるんです。
…200,300ミリの雨では、照葉樹林のまともな森林があったら水害のもとにはならん。
▽188 人間が人間になるまでに動物としての原体験が大事。芸術教育なんか子どもにやらせるより前に、風の音とか虫の声とか、木や花の香りとかいう自然のものの美しさを。
□巻き枯らしで森を取り戻せ
▽201 日置川。宮城谷 すごい森があったが、国有林になって伐採されて植林になってしまった。(熊楠の森はもうない)
▽204 ダムで山村が消える。 道路拡大が造林を促し、山の水が枯渇。日本の自然をよくわかっていた人たちが散り散りばらばらに。日本人本来の自然に対する考え方を受け継いできた人たちの意見が、昭和30~40年を境にして完全に少数意見になる。山あいでほそぼそと暮らしてきた人たちの、長い間培ってきた文化そのものが埋まってしまった。
▽206 イチイガシ 明治になったとき、すでにお宮さんの森にしか残っていなかった。そのお宮さんの森をまた全部きりました。行政側がイチイガシをきってひともうけしようと企業と組んでやったんです。
タブノキも、家具になるし、葉っぱまで全部粉にして線香にした。
▽215 シカがなぜ増えるか。植林したときに下草が増えるから。その草の量によって草食動物は子どもの数を変える。…やがて下草がなくなると、畑を荒らし、害獣になる。
▽216 一方杉は、千年も前に熊野詣に来た人が記念に植えたもの。
スギやヒノキは、今の時代、シイやカシと競争すると必ず負ける。実が小さいから大きくなるのに時間がかかる。カシやシイは種に大きい栄養をもっているから成長が早い。スギやヒノキは芽が出ても全部光をとられて生きていけない。だからスギやヒノキは、カシなどがはえない、岩の上や崖の上に自生している。
▽218 スギやヒノキのように高くまっすぐ伸びる木は、根は必ず横に張る.ヒノキの根なんて非常に浅くて1メートルぐらい。杉も2メートルぐらいまで。根が組み合わさって根の板ができる。その下を水が流れたら、全部、山の斜面を滑る。すべらないのは、以前に伐った広葉樹の株がわずかでも生きているから〓。でもやがて、植えた木が太くなるほど滑りやすくなる。山が裸になったからすべるのではなく、大きな成木林が滑る〓。滑らないように、植林の間に根が縦に深く入る広葉樹と混ぜることが大事。
昔は、植林によくないところは全部自然林で残していた。山のてっぺんなんかは全部自然林を残した。
…九州では山の崩壊がすでにかなり前からはじまっている。紀州は九州に比べると山が硬いから崩壊しにくい。でも、…危ない時期はもうじき来るはずです。僕が山を見たら「ああ、ここ崩壊する」って思うところがちょこちょこあるんですよ。
▽221 虫から見ると植林は「草地」。
…スギやヒノキは強い殺菌力がある。土の中の生きものがいなくなる。腐葉土がなくなって粘土になる。だから雨水は地面をさっと流れる。〓
▽224 昭和30年までは、自分の山でさえスギやヒノキに植え替えることは厳しく規制されてきた。「我々は昔からこうしてきた」と。大学の先生や県の林務課とかの話は聞かないほうが成功する…。
まわりに自然林があると、そのはたのスギやヒノキはいい木になる。少なくとも6,70%が自然林で、残りのいいところだけに植林すればいい木材ができる。
▽226 スギなんて千年も二千年も生きてる木やから、いいところに植えたら百年やそこらでは花も実もつけん。30年で花粉が飛ぶというのは、枯れかかっているという証拠です。〓
さらに、スギやヒノキの球果はカメムシの餌です。4,5年に一度大量に発生するおおもとの原因なんです。
▽227 皮でもはいでそっと枯らそうやないか。「巻き枯らし」。木の根元のほうの皮をはいで。国を挙げて植林したのだから、国をあえてやらんならんでしょう。〓
「伐倒しない」「枯らす」。ナタは使わず、ノコギリと大きめのマイナスドライバー、あるいは竹べらだけ。
□富田川で考える「水の自然」
▽236 シイには2種類あって、原生林のシイがスダジイで長い実をつける。実の丸いコジイは、山が荒れてくると元気になる。…富田川は水がおおすぎて、古道を歩く人が非常に難渋した。
昔の殿さんが、下流が災害を受けないように源流域の山を全部田辺藩の山にした。
明治政府になったとたん、御三家であった紀州は最初に国に取り上げられて国有林になってしもた。
▽244 北海道の原野も、開拓団が入る前は全部森林だった。
▽247 ウバメガシ。中国四国九州では海岸の崖山にしか残っていない。紀州だけは奥までずっとある。
ウバメガシの木はヨキで伐る。ノコギリは使わない。ほかのシイなど炭の材料によくないやつはノコギリで切る。そうしたらウバメガシだけがいつまでも残った。偉大な文化財です。
チェーンソーで春から夏までにウバメガシを伐ったらすぐ枯れる。生長しているときに油ぶっかけるからです。チェーンソーは冷やすために油をつけんならん。
…ウバメガシを回復させるために、昔の人はヤマモモを混ぜて植える。根に根粒バクテリアがあって、空気中のチッソを固定する。
…紀州っていうのは、ウバメガシみたいに難しい木でも大森林として残せるだけの山に対する知識があったから、スギやヒノキの植林に対しても深い研究がなされた。昭和20年までの山で働く人々は、一目見ただけで「ここは植林したらいい。こっちはダメだ」と見分ける能力があった。〓
政府は、明治から100年にわたって、この日本人の古い考え方をなくそうとした。ところが紀州の人間はそれを受け付けなかった。ところが、戦争に負けて、日本人としての自信をなくし、なにもかもいっぺんにやめてしまった。山に対する自然観とか川に対する考え方を全部捨ててしまった。
▽253 本当に記録的な大雨というのは、1日100ミリずつ1週間ふりつづいて、8日目に1100ミリ降ったという記録が田辺である(明治22年)。大台ヶ原ではひとつの台風で3000ミリも降ったことがある。〓
大雨は洪水になるけど、必ずしも災害になるわけじゃない。水には流す力はあるけど、壊す力はない。石が丸くなるのは、最上流の枝谷。石同士で削れてまるくなる。枝谷から出たら、どんな上流でも石は丸い。
▽256 植林地では、1週間にわたって50とか100ミリの雨が降ってじわじわしみこむと、しまいに根の下を水が流れるようになる。最後にとどめの500ミリというような大雨が降ったら、これがそのまま滑る。そのまますべって、土砂で谷を止めて自然のダムができる。これが崩れて土石流になる。土石流というのは泥が混じっているから水ではない。…泥と水が一緒に流れると、水ではなくこんにゃくのようになっているから、押されれば上に上がる。そのあたりの土を全部えぐる。次の曲がり角でまたえぐる。土石流は大きくなるばかり。
…怖いのは水じゃなくて山の崩壊なんです。
自然林ならば、根が下へ深く入るから全部一緒に崩れることはない。山腹が全部すべって大きな湖をつくったということはない。
▽261 ダム。底の半分以上が土砂で埋まっているから、崩壊したら必ず土石流になる。ダムがあるから危険。
▽262 濱口梧陵 安政の津波を見て、財産をなげうって堤防をつくった。「広村堤防」。観音開きの部分はいつも開けっ放し。
それから100年後、昭和21年に津波が来た。鉄の扉は動かない。でも波が来たら波の力でしまった。津波は横にいった。津波をシャットアウトするのではなく、津波の力を横向きに変えさせただけ。堤防を高くして水を入れまいとするのはまちがい。昔の日本人が考えたのは全部濱口さんのようなやり方。だから信玄堤なんかは今も残っている。
▽266 日本の20世紀の最大の間違いは、先祖から受け継いできた知恵を捨て去り、経済活動だけで行われた拡大造林や河川工事や護岸工事に代表される広範囲な土木事業などによって人と自然との穏やかな協調関係を完全につぶし、子どもたちに崩壊寸前の国土と環境温泉しか残せなかったこと。
手入れできない植林も、半分土砂で埋まったダムも、コンクリートで固められた河川や護岸も、今後大規模災害につながる「負の遺産」。





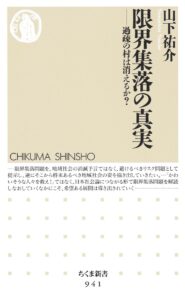

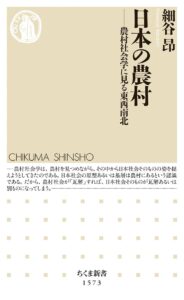
コメント