■江戸しぐさの正体<原田実>星海社新書 20141222
江戸時代の商人たちの行動哲学とされる「江戸しぐさ」。2007年に「NPO法人江戸しぐさ」が発足し、学校の道徳の授業にも採用されるようになっている。育鵬社の「新しいみんなの公民」教科書にもコラムで扱われている。
ところが、江戸時代にはそんなものはなく、昭和以降の風俗をもとに最近になって創作されたものであることを筆者は証明していく。
たとえば、道路ですれ違うときに傘を外側に傾けるという「しぐさ」については、江戸では傘が普及しておらず、雨具は笠や蓑だったはずだと指摘する。
江戸時代の商人は時間に正確だった、という話にたいしては、オランダ人が観察した「時間にルーズな日本人」の記録をぶつける。庶民レベルでの時間規律が浸透したのは大正期のことだという。
細かく切った野菜を弱火で長時間煮込んだという「江戸ソップ」は、1990年代に流行した野菜スープ健康法がネタもとだったらしい。江戸時代、貴重な燃料を無駄につかうはずがないからだ。ちなみに野菜スープ健康法の主唱者は「スープの怪人」と呼ばれ、医師法・薬事法違反で逮捕されているという。
江戸っ子は、880あるいは8800項目もある人間チェックテストに合格してはじめて「立派な江戸っ子」と呼ばれ「江戸講」に入れたと江戸しぐさの人々はいう。それについての文献がいっさい残っていないのは、明治期に徹底的な弾圧「江戸っ子狩り」があったからだと主張している。ここまでくると、フリーメイソンなどのユダヤ陰謀論に近い。
筆者の江戸しぐさ批判はいちいち説得力がある。でも、「江戸しぐさ」現象自体に興味がない人間には読んでもおもしろくないかもしれない。
===========
▽85 終戦後、糞尿を肥料にもちいると寄生虫媒介の原因になることが問題視され、化学肥料が普及しはじめた。1960年代くらいまでは、糞尿を用いず化学肥料だけで育てられた野菜が、八百屋の店頭で「清浄野菜」と明示された。
農村の人糞離れで引き取り手がない糞尿を海に捨てるようになり、海洋汚染の一因となった。
▽93 トロは脂身と呼ばれ、鮨屋で出せるような部位ではなかった。庶民はその脂身をもらってきて、ネギと一緒に煮て、油臭さをぬいたうえで食べていた。それがねぎま鍋だった。
トロが寿司に握られるようになったのは明治以降、脂が強い獣肉を食べなれることで日本人の嗜好が変わったからだ。トロは若衆が食べるもの、というのは、江戸時代の風物とは異質の考え方。
▽184 TOSS(教育技術の法則化運動) 水からの伝言 EM菌 いまでも授業でEM菌をまくところも。
かけ算について、1つぶんの数×いくつぶんの順番に数字を並べなければ答えがあっていても×をつけるという指導が広まっている。
▽198 日教組の組織率は25%にまで落ち込み、教育現場全般で抑止機能をはたすことはできそうにない。
目次
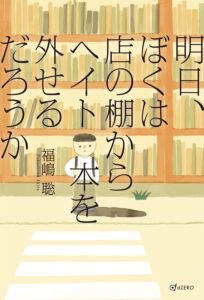
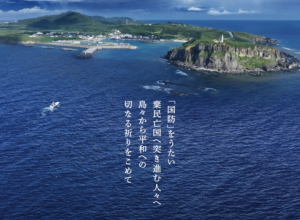

コメント