■居住福祉社会へ<早川和男>岩波書店 20141124
筆者は 人間の暮らしを支える「居住福祉資源」を求めて全国を旅してきた。とりわけ災害被災地などでは、どんな居住福祉資源が必要なのか浮き彫りになるという。
団地の建て替えによる強制立ち退きや、老いてからの転居は心身に大きなダメージを与える。大規模災害では多くの老人が転居を余儀なくされる。
中越地震で被災した新潟県山古志村の仮設住宅団地では集落単位にまとめることでコミュニティが再現した。岩手県大槌町では、仮設住宅住民の生きがいの場所として、農園を設け、人々の交流を育んだ。福岡県の玄海島は外部の人間による委員会をつくらなかった。区画整理事業を小規模住宅地区改良事業に変更して、住民の意見を島づくりに繁栄させた。10年たっても復興できなかった淡路島の例を反面教師にしたという。
人間は、人と人とのつながりのなかでしか生きられない動物なのであり、コミュニティづくりが暮らしの復興の肝であることがよく理解できる。
会社が従業員に提供する「社宅」の危険性は、失職と同時に住まいを失うことにあるが、それだけではなく、生活のコミュニティが会社のなかに囲い込まれるという面も大きいのだろう。
トイレについての指摘も新鮮だった。清潔な洋式トイレがある避難所では、健康を損なう人が極端に少なかった。巣鴨のとげぬき地蔵の成功の原因のひとつには、客が使えるトイレをたくさん用意したことにあった。実は一般家庭でもトイレは二つか三つあったほうがよいという。この本の登場人物は、健康面から複数トイレを主張しているが、それだけでなく「逃げ場」「隠れ場」しての意味もあるような気がした。
「逃げ場」と同様に、一見むだ見えるけど大事なのが「道草」だ。観光都市は「大人が道草をする場所」と筆者はいう。なぜ道草は大切なのか。「子どもに道草を禁ずることは、そぞろ歩きの楽しみを奪っている」という一節を読んで、そぞろ歩きの楽しみを奪うとは、人生の楽しみを奪うことなのだ、と思った。
競争に追い立てられ、小学校は中学への、中学は高校への、高校は大学への、大学は企業へのステップにすぎなくなっている。企業を退職すると自分という個人は何も残らない。定年後の濡れ落ち葉現象は、それまでの人生を通じての道草のなさが遠因となっている。ある意味、道草にこそ人生の本質があるともいえる。道草をしやすいまちもまた居住福祉資源なのだ。
居住福祉というのは、単に福祉や医療の基盤になるだけではない、人間の存在の根底を下支えするものなのだということが読み進めるうちに理解できるようになってきた。
戦後の日本は、安価で快適な住居というストックがしっかりつくられていないために、所得などのフローの要因が沈むとたちまち貧困に陥る「脆弱国家」になってしまったという。逆に、江戸時代以来変わらない暮らしをつづける農村の老人が、月3万円の年金でも生きられるのはストックとしての家と、生産の場としての畑があるからだ。
居住者が居住政策の策定に参加することで、「住む主体」による「住む能力」を発展させる必要があるという。それを「居住民主主義」と呼ぶ。
それに加えて、「消費者」になりがちな私たち一人ひとりが(農村の老人のような)生産者としての要素をもつこと、生産を基盤にした居住民主主義が大切なのではなかろうか。
終戦後の農村の生活綴り方運動や生活改善運動、あるいは最近はやりの「半農半X」などと居住福祉との関係も考えたらおもしろいかもしれない。
=============
▽家は神社だったが、継がなかった。そのことへの後悔が、近年頻りである。
▽9 貝原益軒「老後は、若い時の10倍の早さで時が過ぎていく。…むだに日を暮らしてはいけない。老後は多田の一日でも楽しまずに過ごすのは惜しい」
▽27 人々の生存と暮らしを支え、お年寄りの外出を誘うような社会資源(地域、住居、施設、行事、文化、人間関係等)を「居住福祉資源」と名づけ、全国各地の「居住福祉資源発見の旅」をつづけている。
東京・巣鴨地蔵通り商店街は、一種の「地域リハビリ空間=デイサービス・ストリート」
▽31 倉田正「家のトイレが一つでは、時間に追われている人は短い時間で排便しなければならない。…短い時間で排便しようとして気張りすぎて負担をかけるので肛門が壊れています。…家庭のトイレは二つか三つ必要です。外でも同じ。日本の街は公衆便所が極端に少ない」
…被災地の調査でも、避難所として使われた小中学校などで清潔な洋式トイレの備わっている場合、健康を損なった人が極端に少なかった。
▽37 道草 全国の観光都市は、観光客にとって「大人が道草をする場所」。子どもに「道草禁止」とすることは、そぞろ歩きの楽しみを子どもから奪っている。
子どもや若者はつねに競争に追い立てられている。小学校は中学校へ、中学校は高校へ、高校は大学への入学のステップにすぎなくなっている。大学は企業に入る手段となり、職業人生を終えたあとは、自分という個人は何も残らない、社会的役割を見いだせないということになる。つまりは、成長過程、そして人生における「居場所」の喪失があると考えられる。(道草とは居場所づくり、確認〓)
▽46 京都の母を東京に呼び寄せた。そのうち、ものを言わなくなった。…「家に帰る」と言って荷物をまとめかけたのが、最後の言葉であり、意思表示となった。…年を取ってからの転居が、新進に重大な影響を及ぼすと知ったのは、わたしが住まいのことを研究するようになってからであった。
▽55 団地のたてかえによる強制立ち退き後、転居先で生じた住民の疾患症状。
▽65 バリアフリーへの「異論」 障壁を越えようとする意識や運動能力を失うことも…。「2,3センチくらいのちょっとした段差はつまずきやすく危険なので、これは平らにした方がいい。しかし、階段のようなはっきりした段差は、足腰を鍛えるために積極的に活用するべきだと考えています」(天野彰)
▽66 阪神大震災。家屋が構造的に安全で、密集受託地が広がっていなければ、生じなかった犠牲。同規模のサンフランシスコ地震の死者は63人、ロサンゼルス地震は60人だった。
(〓シスコの高速道路が落ちているのを見て、日本のテレビでは、日本は耐震性がしっかりしているから大丈夫、と言っていた。それを信じていた)
▽80「きらくえん」は、復興公営住宅に生活援助員を派遣し、15年間にわたり孤独死ゼロを達成しつづけている。老人ホームは地域社会の福祉・防災資源としての役割を果たしている。
▽82 スウェーデンでは、すべての高齢者福祉施設は保育所・幼稚園・小学校・児童図書館などの近くに設けることが義務づけられている。
▽88 「生老病死」の見える居住地にしなければならない。
▽91 名古屋市の南医療生活協同組合経営の女性用グループホーム「なも」。見学者が多いと居住者は元気になり、少ないと元気がなくなるそうだ。
▽92 愛隣地区「サポーティブハウス連絡協議会」 「陽だまり」の宮地泰子さん。「野宿のときは町を汚していた彼らが今はそれをかたづけています。住居の安定があって初めて自己をとりもどすことができるのです」
▽98 新潟県山古志村の仮設住宅団地。コミュニティを再現。当初はバラバラに避難していた住民を入れ替えし集落単位でまとめることで、各避難所には住民がもどりやすくなり、もとのコミュニティが再現できた。仮設住宅の前庭に家庭菜園をつくった。長島・元村長「地域は生きるためのすべてが周りにある居住空間であります。ともに暮らしてきた家族のつながり、先祖とのつながり、コミュニティであり、生きるための海があり、農地があり、それらを利用した産業があり、生きていくためのすべてが集約された地域でありました」
▽102 中国の老人ホーム。入居者も働く。働くと賃金がもらえたり、入所料金が割引される。高齢になってもいかなる場所でも、働く機会が配慮され用意されることは、生きる支えになる。「ケアを受ける」というよりも「居住する」という色彩が強い。
▽105 岩手県大槌町 NPO法人遠野まごころネット。仮設住宅住民の生きがいの場所として、集団農園、家庭菜園、趣味のスペース、井戸端カフェなどを設け、外に出る動機になる支援活動にとりくんだ。「ここには農園があるから、仮設を出たくない」という人も。
▽106 長野県は、住民に対する公民館、図書館、博物館の数が全国一位。
▽115 ILOは1961年、「労働者住宅に関する勧告」を採択し、労働者の拘束的役割を果たす「使用者による住宅の供給」の禁止と、社会的責任による住宅供給を満場一致で採択した。だが日本政府は…
▽131 鳥取県西部地震と片山善博知事 「よく地震があると、この際だから今までできなかったまちづくりをしようと、区画整理や再開発を計画したりしがちですが、私はそれは間違っていると思います。…災害復興というのは、100年後、200年後の人のためにするんじゃない。目の前で被害に遭った、今、ここにいる本当に困窮を極めている、泣いている、その一人ひとりのためにするべきなのです。その辺が都市計画や街づくりと災害復興を混同して考えがちなのです」〓
▽133 玄海島の復興 2005年の地震後、阪神大震災の被災地の北淡町富島地区を視察した。「震災後10年以上経っても事業が完了しておらず、家屋が除去されたままになっている」状態を目にした。「行政主導による計画は失敗だった」と聞かされた。(区画整理は15年後の2010年に完成)。
玄海島は、外部の人間による委員会はつくらなかった。当初の区画整理を、小規模住宅地区改良事業に変更し…島民の意向調査やワークショップをつうじて、意見を島づくり案に反映させながら勧めた。
▽142 鎮守の復活 玄海島「島民の誰もが最初に言ったことは、自分の家より神社を復興するのが一番や」と。震災まもないころ、福岡市は市内にある100世帯ほどの公営住宅にみんな移れと言う提案をしたが、島民の「先祖代々の地を捨てられない」と一斉に上げた声に、移転する話は断ち切れた。「島は一つの国です。捨てたら二度と帰ってこれない。無人島になって荒廃する」
▽146 岩手県大槌町の「臼澤鹿子踊り」復活への取り組み。
▽156 震災関連死は福島が最多。
▽159 福島から福岡の久留米市の公営住宅に入った母親が子ども虐待で逮捕。
▽168 戦後の日本はストックがしっかり造られていないために、所得などのフローの諸要因がしぼむとたちまち貧困に陥る「脆弱国家」である。それが西欧福祉諸国家との根本的違いである(〓高度成長まではストックとしての「家」があった。デラシネによってますます脆弱に〓)
▽175 公共財としての住宅。住宅適地としての土地は限られている。需給関係を通じて良質の土地が大量に安く供給されることはない.土地価格は…とともに上昇するが、勤労者の賃金は年膨張とは無関係で地価騰貴に対応できない。…「勤労者の賃金に見合った良質の借地供給」は公的資金による社会住宅としてしか成立しない。
▽179 「住む主体」による「住む能力」の発展が必要。「能力の発展は、住む主体である居住者が居住政策の策定に参加することによって可能になる」。参加することも「居住の権利」。居住民主主義。
(=主体となること〓 消費者にならないこと。農村のつづりかたなど。)
▽190 「居住福祉産業への挑戦」 慶応病院の看護師が、快適な居住環境が病の回復に有効なことに気づき、建築家になり、…住宅や病院、福祉施設の設計に取り組んでいる例。マンション管理会社「イノーヴ」は看護師を管理人に採用し、乳幼児から高齢者にいたる十人の相談にのる。
目次





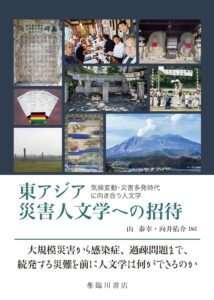


コメント