■世界農業遺産<武内和彦> 祥伝社新書 20131112
能登の会議の様子。
なるほど。
==============
▽12 阿蘇の世界農業遺産に向けて最初に行動を起こしたのは、宮本健真さんというイタリア料理のシェフ。2006年に熊本市内にレストラン。
▽15 野焼きだけでは、否定的は反応ばかり。伝統的な野焼きの方法が守られているだけでなく、それが実際の農業にどのような影響を与えているかという視点が必要。独自性のある農業に結びついているという、具体的な実証が必要だった。草原で赤牛を生産する伝統的な放牧の方法、草原から採取した草を堆肥に用いる野菜づくりなど、…ひとつの農業システムとして訴えていくことにして申請書は書きかえられた。
地元農家の大津愛梨さんは慶応技術卒業後、ドイツの大学で修士課程修了。宮本さんはイタリア語がぺらぺら。
▽27 会議史上はじめてFAO事務局長が出席。谷本知事みずからローマにで出向いてシルバ事務局長と話し合って能登開催を決定した。
▽31 FAOの目的は、食糧不足による飢餓から人々を救うこと。その象徴的な活動が「緑の革命」だった。一定の評価がなされる一方で、地域の暮らしや文化、生物多様性の維持といった価値観と、必ずしも調和的ではないという問いも提起されるようになった。模索の結果、もうひとつのアプローチとして生みだされたのがGIAHSの考えかた。
▽33 GIAHSは変わりゆく遺産であり、進化する遺産。それゆえに持続可能な農業を体現した遺産。認定するのは、表向きは伝統的な農法であったり、農業構築物であったりしますが、大切なのはあくまで、それを維持・管理する人たちと一体になったシステム。
▽34 フィリピンのイフガオの棚田。海抜1000メートルの険しい斜面。…棚田はもとは中国でおこなわれていたのが、フィリピンや日本に伝来したとみられる。
▽38 イフガオの棚田はハニの棚田とともに、ユネスコの世界遺産にもGIAHSにもダブルで登録された。「過去」と「未来」の両方。佐渡市がイフガオに中古の耕耘機を寄付しようとしたが、ユネスコの基準では、耕耘機が通れるような道をつくってはいけない。世界遺産とGIAHSの稚貝を象徴していた。
▽40 緑の革命の成功例がフィリピン・ロスバニョスにある「IRRI」(国際稲研究所)。66年にIR8という高収量の稲の開発に成功し、これが普及することで、アジアではほとんど飢餓がなくなった。
一方で、緑の革命によって、農地の悪化や地下水枯渇、砂漠化、土地の荒廃などの影響も。
…日本は穀物を大量に輸入している。大量の水を輸入しているようなもの。食糧の輸入によって大量の水を輸入している貿易の構造。
▽42 能登の会議に出席したインドのモンコブ・スワミナサン。いまでこそGIAHSの支持者だが、もとはインドで「緑の革命の父」と称された。食糧の安全保障の見地から緑の革命と距離をおくようになり、持続可能な農業の推進者となった。
…緑の革命に象徴される近代的な農業とGIAHSに象徴される伝統的な農業。それぞれのいいところをとった中間的な道をさぐるのが、今後の進むべき方向性では。
…途上国において「食料を全国民に行きわたらせること」と「持続可能な農業の道をとること」とが今すぐ両立するとは思っていない。しかし、日本のような先進国ではそれが可能かもしれない。
▽45 「包括的な富」の提唱者パーサ・グスグプタさん 〓包括的富指標による日本評価では、日本は自然資本をほとんど失っていない国。つまり消費される食料の半分、木材の過半は、外国で自然資本をすり減らしながら生産された農作物や木材を輸入して維持しているから。
▽48 GIAHSを受けると、途上国の場合はGEFから資金援助を受けられる。先進国はない。…なにより重要なのは、認定を受けた地域の農家や住民たちの価値観に転換がもたらされること。「古くて役に立たない」と否定的にとらえられていた農業技術やその文化が、世界的な評を与えられることで、自信や誇り、やる気を引き起こす。
▽50 伝統的な品種を遺伝子プールとしてもっておくことが重要。イフガオでは3種類の稲を栽培している。気候変動に対応する品種をつくるにも、古い品種を掛け合わせながらさがすしかない。
▽52 スリランカ「タンクシステム」。1000年異常もつづいてきた伝統的な灌漑システム。…スリランカではこれまできんだいてきな灌漑システムを導入してきたが、最近になって伝統的なしくみをうまく活かすハイブリッドの考え方を採り入れはじめた。
▽54〜アジアの農業遺産…
中国の水田養魚の維持と発展 浙江省青田県 この農法は中国全土でおこなわれている。コイの一種「田魚」。雑草や害虫を食べるから除草や農薬がいらない。排泄物が肥料になる。
宣化のブドウ栽培の都市農業遺産。ほかの都市農業としてはキューバの事例がある。「都市農業」という切り口〓。
▽64 GIAHSに一番熱心なのは中国。国レベルの、国家重要農業遺産システムという制度が構築されている。次に日本、さらに韓国が活動を本格化している。
…ヨーロッパには小規模農家を重視する伝統があり、人間が管理する自然の姿が息づいている。アメリカでもカリフォルニア州ナパバレーが有機農業に取り組み、GIAHS認定をめざしている。
▽68 済州島 わざと雑に積む石垣。風を受け流す。 青山島は、オンドル石のしくみを活用した水路。
アフリカ マグリブのオアシス
南米チロエの農業 ジャガイモの原産地
アンデスの農業 ジャガイモの原産地。
▽76 高い木下に果樹や農作物を植え、家畜を飼って…というアグロフォレストリーが、グリーンエコノミーの最良のモデルになりうるのではないか。…アマゾンのトメアスの日系人が守るアグロフォレストリー。いっときはコショウ栽培で富を築いたが、病虫害が発生して壊滅的な被害を受けた。そこで、先住民から学んではじめたのが、この地域のアグロフォレストリー。
▽78 私は農業の規模拡大じたいには賛成。しかし、単一作物で拡大しなくてもいいのではないか。非効率という人もいるが、コンピュータで最適に管理することで、複数の農作物や、木材、家畜などをモザイク状に効率的に生産できるはず。
フルッタフルッタの長澤誠さんはトメアスのアグロフォレストリーをGIAHSに認定できないかと奔走している。
▽79 掛川 電線や電柱、送風ファンが林立して景観を損なっている点が大きな問題になった。
▽81 日本独自の農業のクライテリアについて研究。第一が「レジリアンス」アグロフォレストリーのように変化に強い。第二が「ニューコモンズ」資源を管理する新しいしくみづくり。企業も含めて多様な主体の参加によって継承できるしくみづくり。第三が「ニュービジネスモデル」六次産業化。
ビジネスという視点が、世界のGIAHSには弱い。
中国雲南省のハニ族の棚田 棚田の全貌を見渡せる見晴台。ここの土産物店を経営しているのは農家ではなく観光業者。利益を農家に還元しているのかどうか…。棚田の集落には、農家民宿やレストランもある。
日本でも、千枚田などを訪ねるツアーが、域外の観光業者によって企画されているが、地元の農家の利益とつながっているものばかりではない。
□89 佐渡
トキの野生化。生物多様性を確保するとともに、農家の所得向上にもつなげていこうという農業。 平野があり集落があると思えば「谷地田」があり、ひとつの小宇宙が構成されている。谷地田とは、周囲を林地に囲まれた細長い土地につくられた田。関東では谷津田とか谷戸田と呼ばれている。
…2004年の台風で農作物が甚大な被害を受けた。耕作放棄地が拡大。jそれがきっかけ。佐渡市は、トキの餌場づくりを島全体の課題とし、島で生産された米を新たなブランドとして売り出す戦略に打って出た。
…トキは生態系の頂点に近い生物だから、それが生息できるということは、生態系が豊かなことを意味する。トキの野生化を成功させることは、非常に象徴的な自然の再生事業。
…ゴールドラッシュで人口10万人に。新田開発。その水をひくためにため池が1100カ所異常もつくられた。「小倉千枚田」などの開墾がおこなわれ、佐渡独特の美しい里地里山の景観をつくりだすことになった。
…集落単位で農道や農業用水を共同管理する組合をつくり、地区内で助け合って農業を営むスタイルが引き継がれている。
農薬・化学肥料を半減するため、新しく「魚道」と「ビオトープ」が導入された。魚道とは、田んぼと用水路をつなぐ水の道。水田の隣に常時、水を張った状態の「ビオトープ」を設置し、魚道でつないでいる。
在来の農法では「江」と「冬みず田んぼ」が見直された。江は、、あぜに沿って田んぼのなかに設けられた水深20−30センチの水路のような水たまり。かつてはトキの餌場となっていた。水田の水を排水するときに、江は水生生物の避難場所になる。冬みず田んぼ、は、秋から冬に代掻きをして、冬季の雪解け水を田んぼにためておいて、そのまま春の田植えをするというもの。
▽100 島ぐるみの米の認証制度。農協などは当初は賛成しなかったが、市が熱心にリードして実現した。
諦観やあきらめではなく、GIAHSに認定されるためには、さまざまな問題があるのは十分承知のうえで、問題を克服するにはどうしたらよいかと前向きに考える姿勢が大切。
(さすが佐渡もがんばっているなあ、能登以上に一体感のある活動ができている。多様性は能登ほどじゃないようだが〓)
▽104 2012年度には、認証制度に参加する農家数は684戸1367ヘクタールに。作付面積の25パーセントに達した。
▽106 佐渡の農村の「能」は世界無形文化遺産。プロではなく農家や市民が演じ手となっている。農村歌舞伎は全国的に分布しているが、農村の能は希少。
□能登
▽108 里地里山といえば独立した「谷地田」の風景を思い浮かべるが、能登では、それが連続的かつモザイク状につらなって「緑の回廊」を形成し、半島特有の山がちな地形から、里地里山と里海までが一体となって豊かな生物多様性を生みだしている。
▽111 能登の漁法には、定置網漁業にいよるブリやイカ、カニなどのほか、養殖されたナマコやカカキが水揚げされる。海女漁や岩のり採りやカキの養殖も。
穴水町では「イサザ漁」や「ボラ待ち櫓」
▽114 農作物のブランド化。地域をあげて六次産業化にとりくむ。「能登大納言」「大浜大豆」「中島菜」「沢野ゴボウ」「金糸瓜」など13種類の能登野菜がブランド化されている。
▽117 現在炭焼きを専業としているのは大野長一郎さんひとりだけ。
□阿蘇
▽126 農業はほとんど全国的に知られていない。…広大な草原は、1000年以上前から放牧地として利用。明治時代以降は「あか牛」とよばれる肉用牛が飼育されてきた。草は、飼料になるだけでなく、田畑の堆肥としても利用。
草原の管理は、約160ある牧野組合がおこなう。集落ごとに「入会地」が定められ、入会権をもつ9200の農家が共同で、野焼きや牛の放牧、採草などの作業を欠かさなかった。(〓成川は? 蛇塚は?)
▽128 1900年代初頭まで、国土の13パーセントは草地だった。1880年代の記録では、国土の約3割にあたる草地が利用されていた。人の手が入った「二次草地」。現在は3.6パーセント。
▽131 日本に残された二次草地の半分が阿蘇に集中。…草地維持のための「野焼き」。ダニなどの規制動物や病原菌を駆除し、新芽の出がよくなる。
…1950年代まで、阿蘇の草原は、入会地として集落ごとに管理されていた。草を刈る解禁日を定めた「口開け」や草刈り場を割り当てる「野分け」などのルールが決められた。
▽135 阿蘇の草原には、等高線のように縞模様ができているが、これは「牛道」。(これが段畑になった?=宮本)
2012年に熊本県が実施した調査によると、阿蘇地域に約160ある牧野組合の半数以上が、10年後には野焼きや輪地切りを続けることは困難になるだろうと答える。環境省では「牧野カルテ」(野草地環境保全計画)を作成。
「阿蘇グリーンストック」は、全国から野焼き支援ボランティアをつのり、初心者研修をしたうえで、各牧野組合に派遣する活動を展開。〓
▽136 日本では黒毛和種が180万頭いるのに対して、あか牛は2万5000弱しかいない。その4割の9500頭は阿蘇地域で飼育。
褐毛和種が黒毛よりすくないのは、霜降り賛美の傾向が強いから。牧草をえさにして、しっかりと運動した牛の肉は、赤身になり、肉本来のうまみがある。
▽137 輸入飼料を使っているために、日本の土壌が窒素過多になっている。江戸期は、江戸の屎尿を肥やしとして郊外にもどしたから窒素の循環がなりたっていた。が、輸入飼料によって、国土に窒素が蓄積されていく。
▽139 阿蘇 トマトやホウレンソウ、アスパラ、イチゴ、リンドウなどの花。阿蘇地域の牧草を堆肥にして栽培した農産物に「草原再生シール」を貼ってブランド化。
からし菜の一種である「阿蘇高菜」。塩漬けの高菜漬けは、広島菜と野沢菜とともに日本三大菜漬。
□静岡
▽141 茶草農法の茶は、稲わらを敷き込んでつくった茶よりも品質が高い。掛川地域全体では、約10平方キロメートルの茶畑と3平方キロメートルの茶草場が散在。とくに掛川市東山地区で茶草場の比率が高く、茶畑と茶草場の比率は10対7前後。
▽145 敷きこまれる茶草は1ヘクタールあたり6.8トン。茶生産の冬場の作業時間の6割におよぶ重労働。
地元では茶畑のことを「茶原」と呼ぶ(懐かしい)。
▽147 8割はやぶきただが、残る2割は「香駿」「つゆひかり」など61品種を栽培。
▽150
□大分・国東半島
▽152 日本最大のクヌギ林。15年のサイクルで再生。大分県は、原木栽培による「乾シイタケ」の年間生産量が約1500トンで日本一。
クヌギは3,4年にわたって椎茸栽培に利用されると、軟らかい土になり、保水層を形成。
国東半島・宇佐地域には、小規模なため池を連携させて用水を供給するシステムが維持されている。
…シイタケ栽培を軸に、クヌギの伐採と再生を繰り返すことで、森林の新陳代謝は促進される。日本の「アグロフォレストリー」。
▽155 シイタケ栽培には、原木を用いる方法と、おがくずや米ぬかなどを固めた菌床を用いる方法がある。原木栽培は大きな市場価値がある。
▽158 国東半島・宇佐地域にクヌギが植林されはじめたのは明治期。大分県にあるクヌギは、蓄積量で全国の22パーセントを占め、日本最大。
…クヌギは15年でふたたび原木として利用できるサイズにまで再生する。
▽ 国東半島は谷間の土地が狭小で、大規模なため池をつくることが難しかった。そこで、小さなため池をたくさん造り、水路で連携させて水を確保する技術をつちかってきた。たとえば国東市綱井地区では、6つのため池を連携させたシステムが江戸時代から運用されている。
地区内に1200のため池があり、地区ごとの会議で選ばれた「池守り」が、取水口の開閉などの管理をしている。
…平野部が少なく、大規模な水田ができないために、複合農業の知恵が生みだされた。
▽161 GIAHSが日本にあるメリット 1.市民の教育度が発達し、みんなで伝統的な小規模農業を考え支えていこうとする傾向になじみやすい。 2. 生活に余裕があり、農業の付加価値化というものを支えていける。 3. 国土が狭く農村と都市が近いから行き来がしやすい。
▽165 里山というのは1960年代になって、森林生態学者の四手井綱英さんが提唱。
▽169 「里海」九州大学の柳哲雄さんが提唱した新しい概念。「人手が加わることによって、生産性と生物多様性が高くなった海」…慶良間諸島で、人の手によるオニヒトデ駆除が、珊瑚礁の生態系を裕にしている現状。
▽171 環境省の自然環境基礎調査。08年の「重要里地里山選定等委託業務報告書」によると、1.農耕地、2.二次林、3.二次草原の合計面積が50パーセント以上をしめ、しかも3要素のうち2つ以上を有する地域を「里地里山的環境」とみなしている。
▽173 カタクリ 里山を代表する春植物だったが林に手が入らなくなって激減した。
▽177 里山の中心をなしているのは二次林といわれる森林形態。
▽180 阿蘇 野焼きが行われていたため、草原的な環境が維持され、氷河期に渡ってきた植物が絶滅せずに生き残った。
▽181 日本の山は濫用され、ほとんどはげ山だった。荒廃した環境でも育つアカマツが増えた。
鎌倉の大仏も、戦前は背後に松林が広がっていた。人の手が入らなかったため、現在は全部照葉樹になっている。
六甲山も明治期ははげ山。緑化復元事業で等高線にそってマツが植えられた。だがこれもふたたび放置されたとめ枯れてしまい、現在のうっそうとした照葉樹林になった。木が高く育ちすぎて、観光の目玉である夜景が見えなくなってしまった。
…自然と人間の関係が絶妙なバランスを保っていた時期は、それほど長くない。明治の終わりごろから、戦後になって燃料革命が始まるまでの、わずか半世紀ほどしかなかった。
▽191 2013年6月、山梨県富士吉田市で「国際コモンズ学会」
…かつて日本の里山はコモンズだったが、明治維新の土地所有制度の変更で、現在はほとんどが私有地になった。…必要なのは、私有地であっても共有地的な管理ができるような新たなしくみでは。所有権と利用権とを法的に分離する。
▽199 里地里山で生産された農作物を、地元の販売ルートにのせるとき、重要な役割を果たしているのが「道の駅」
▽202 生産者サイドのIT整備が必要「上流側のIT化」。1品目だけではダメ。里地里山では、地域の中で米や野菜をつくり、魚をとり、炭を焼くというように閉じたシステムで循環してきた。それをそのままITのなかに落としこめないか。地域の複合産業としての里地里山ビジネスをマネジメントするIT。
IT化は、里地里山を管理する組織でおこなうのが自然。「地域管理公社」。農協などでは特定の分野や産品に特化してしまうから、里地里山全体をカバーできない。大事なのは、地域の多様性や可能性を活かし、市場に対して表現すること。ニューコモンズ〓の実現。
…佐渡の農林水産業と観光とをトータルにブランド化して活性化すること。米・柿・寒ブリを売る前に「佐渡」という場所を売っていくこと。
▽206 SATOYAMAイニシアチブ 日本の里地里山のように、地域の人たちが自発的に産品をつぎつぎと開発し、多品目を生産するという方法は、特筆すべきシステム。発想は農水省ではなく環境省。
▽214 SATOYAMA「社会生態学的な生産のランドスケープ」。ランドスケープとは、人間と自然のかかわりの産物である景観。社会生態学は、自然科学と人文科学をつなぐ領野。
…ニュージーランドなど農産物輸出国からは、「WTOの精神に反している」と批判が出された。
▽218 環境サイドの環境政策は、手つかずの自然を守るところから始まったが、人の手の入った自然を尊重する方向へシフトしてきた。農林水産省サイドも、従来の一次産業保護から六次産業化という方向へとかわってきているから、双方は協同で政策をおこなうことができる。
私たちは、二つの活動を使い分けている。ひとつは、、GIAHSとFAOと農水省の系列、もうひとつは、SATOYAMAイニシアチブと生物多様性条約事務局と環境省の系列。
▽220 日本は、欧米の工業先進国が主導してきた農業と、開発途上国で守られてきた農業とが、ともにある希少な場所。




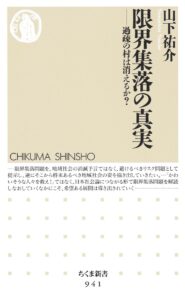
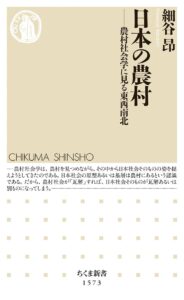


コメント