■日本の居住貧困 <早川和男・岡本祥浩編>藤原書店 201309
1991年以来、保健師養成学校で毎年2回、70ー80人の学生に対し、住居と安全、衛生、発達、福祉などの関係について講義をした。
提出されたレポートは15年間分。そのうち最近の6年分の368編を分析して構成したのが本書。
マンション エレベーターがあっても、エレベーター内で車いすが回転できず、ボタンを押せない。暗い長い廊下。外にでられないと子どもの発育にも悪影響。子どもの遊び場が有れば情報交換の場にもなる。
親同士が集まってはなせる場を提案した。(保健師の役割 住居を点検し、コーディネートする)
廊下が広く、階ごとに憩える空間が有れば交流の機会が増える。
スキップフロア。片手に乳児、片手に乳母車を手にして階段をのぼりおり。
================
▽39 公園は自然と仲間をつくれる場。近所と結びつきを深める場。
▽41 保健師は、母親同士、また子ども同士が交流できるような条件をつくらないといけない。
▽多胎児の母 外出が阻害される。
▽61 断熱性・機密性が向上。畳をあげたり家具を移動したりする大掃除をしなくなり。ハウスダストがあたまりやすく。
▽111 高層マンション 強風で扉を開けるのも大変。
親子を分断する間取り。
高層住宅でも、五階おき程度に遊び場をもうければ近隣との関係も自然とできるのでは。
▽117 家庭内事故による死亡者数は毎年1万人を上回り、交通事故死者数をはるかにうわまわる。〓
▽135 ハイハイの時期が大切なのに、部屋が狭いために、ハイハイをほとんどしないでつかまり立ちをする子が増えている。(保健師ならではの視点)
▽145 バリアフリーで簡単に開くドア。子どもには逆に危険に。危険の予知や回避能力を育てることに関して、昔ながらの日本家屋より劣るかも。がりかまちなどの段差を上がる機会が失われて筋力を減らす老人も。
ここまでは育児
ここからは高齢者
▽172 寝たきりでも、住宅改修で外出が可能に
▽189 狭い、精神障害者の作業所。精神的圧迫は症状の安定を悪化させるおそれ。
▽193 住宅を変えるには、本人や家族、経済面など、全体像を見て考えないといけない。全体を見る目の必要性。
▽土間を廊下にして車いすで移動できるように改修。寝室の畳をフローリングに。寝室にはリフトで外にでられるように。
▽229 バリアフリーマンションでも、風呂が狭いと家族が介助して入れない。浴槽も標準サイズでは、座位を確保できない人には危険。
風呂場を広く、浴室を浅くすることで快適になるのでは。トイレスペースも広く。
▽231 嫁の介護ストレス。家が狭くて。
▽255 地域保健法の制定。平成9年から権限移譲。保健所の集約化。94年848カ所だったのが2010年には494カ所に。
介護保険法 保健師は管理や調整業務が主体に。
家庭訪問の減少。
どんな住宅がよいのかモデルがほしい。
保健師の可能性。医者よりも広く見られる。住民の生活状況をもっともしうる専門職。医療、だけではない。住宅問題発見者としての保健師。





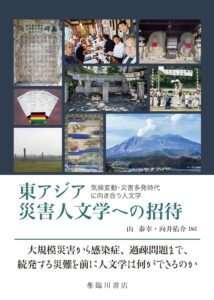


コメント