■レヴィ=ストロース講義<C.レヴィ=ストロース、川田順造、渡辺公三訳>平凡社ライブラリー 20110901
ルネサンス時代の人々が古代ギリシャ・ローマ世界を再発見し、イエズス会の人々がラテン語を教育の基礎に置き、本居宣長が中国と比べることで日本文化の本質を導き出したとき、他の文明と比べることなしには自らの文明を位置づけられない、という認識があった。それが人類学の原型だった。
ルネサンスの貴族的人文主義や19世紀のブルジョア人文主義といった、特権階級・特権的文明を出発点とする人文主義を乗り越え、人類学は普遍的な人文主義(ウマニスモ)となったと位置づける。私たちの生き方・価値観がすべてではないこと、異なる生活様式・価値体系によって幸福を実現した共同体が存在することを人類学は明らかにするからだ(相対主義)。私たちの常識が人類の「常識」でないことを明らかにし、逆に、数世紀にわたる広範な資料を収集することで、人類に「普遍的なもの」をさぐる。
そのうえで、辺境社会から何を学べるか探求することになる。
辺境社会は、神話や禁忌などで出生率を抑え人口変動がない。農耕民に比べてはるかに多様な、繊維とミネラルに富んだ生物種を食べており、伝染病以外の病気はほとんどない。「農耕」によって数種類の食品しか食べず、1回の凶作で食料不足となるようになり、農耕の伝播と伝染病の伝播には比例関係にあるという。農耕が飢饉を生じさせたと、日本の縄文時代の研究者も書いていた。農耕は必ずしも「進歩」ではないのだ。
人工授精や代理母など、現代の欧米の価値観をゆるがす問題についても、未開社会の例は参考になる。ある民族では、娘は夫と生活を始める前に愛人をもつことができ、愛人とのあいだの子は、夫との婚姻による最初の子として認められる。精子提供者による受精に相当する。女性のカップルが、男性から精子の提供を受けて子どもをつくり、一方が法的父になることができる社会もある。ホモセクシャルを認めている。
「民主主義」のあり方も西欧とは異なる。「未開社会」のほとんどが多数決の原理を認めず、全員一致に達するまで議論が繰り返される。宮本常一が対馬で見聞し、鶴見俊輔が評価する「土着の民主主義」だ。地域福祉や村おこしの分野でそうした意志決定のあり方が最近になって見直されている。
「変化」を求める西欧の社会とは逆に、「未開社会」は変化を芽のうちに摘み取る。「未開社会」は、わずかな秩序しか作りださないが、社会のなかにごくわずかなエントロピーしか作りださない。平等主義で、全員一致の原則にのっとっている。反対に自称文明人は、大量の秩序をつくりだす一方で、大量のエントロピーを生みだす。理想的なのは、文化面で多くの秩序を生みだしながら、社会におけるエントロピーの増大という対価を避けていくという第3の道だという。
人類学と集団遺伝学の発展は、人種差別の思想も克服しつつある。
20世紀半ばまで、人種は文化に影響を与えるか否かが問われてきたが、問題の方向は逆だった。それぞれの地域の人間の生活様式が、生物学的進化の方向をかなりの程度決定する。近隣住民との遺伝子交換の度合いを決定するのは、その集団の文化にほかならず、長い世代にわたる規則の実行の積み重ねが遺伝形質の差異を生みだすからだ。衣装や髪形などの文化が特定の身体的特徴を好むと、それが固定され広められていくこともあることがわかってきた。
レヴィ=ストロースは、雑種文化には二つの型があるという。ひとつは、外部から到来するすべてを全体を関連づけることなく飲み込むチグハグな文化。もうひとつは、日本のように、外部のものを借用しながら、一定期間とじこもり、外からの借り物を消化する文化だ。たしかに、遍路による技術の伝播やキリコ祭りなどにみる外部文化の消化のありかたにそれが見える。ただ、高度経済成長による変化は、吸収と同化どころか、吸収と破壊になっていないだろうか。
神話と歴史はどちらも客観的真理というより予断と希望の表明に近い、という部分で似ているが、神話は現在が過去の持続であることを期待するのに対して、「歴史」は現在が過去と異なることを期待する、という指摘も興味深かった。文字のある社会とない社会の違いなのだろう。
=======================
▽16 比較的近年まで西欧文明の影響にさらされずにいた、つつましい、長いあいだ蔑まれてきた社会は、人間一般について、さらには西欧型の文明について何かおしえてくえるのではないでしょうか。
そしてその答えを人類学に--なぜなら他の社会科学は、主に同時代の世界に関心を注いでおり、こうした問いには答えないからです--求めることになった。
▽28 後進的で進歩に「見捨てられ」、辺境にとどめられて消滅する運命にあるとされるこれらの社会は、外部から脅かされないかぎり、完全に存続可能。
これらの社会は、人口数十人から数百人の小集団で、互いに徒歩で数日の距離にあり、人口密度は1平方キロあたり0.1人というレベル。人口増加率は1%以下ときわめて低く、人口増加は死亡数とほぼつりあって、人口はほとんど変動がない。出産後の性的禁忌、女性の生理的リズムの回復を遅らせる長期にわたる授乳などにより、人口は一定に保たれる。
▽30 エイズは、アフリカでは数千年前から土着の住民人口と均衡して存在してきたのだろう。それが、歴史の偶然によってより規模の大きな社会に導入されたとき、重大な驚異になった。
一般に、こうした社会では、伝染性のない病気は見いだされない。農耕民に比べはるかに多様性に富んだ食料。食料となる生物種は、100種類あるいはそれ以上で、脂質が少なく、繊維とミネラルに富み、十分な蛋白質とカロリーを与える。肥満、高血圧、循環器系の病気は見あたらない。
▽34 ごく普通の人「常民」の社会生活が、個人的つながりや家族の絆、近所づきあいのうえに成り立っているかぎり、ひとことで言えば、口頭伝承の生き続ける小さな伝統的世界でありつづけるかぎり、それは人類学の研究対象となりうる。
▽40 日本人はすでに構成された自律的「自我」から出発するのではなく、あたかも自らの自我を、外部から出発して構成するかのよう。日本人の「自我」は、もともと与えられたものではなく、到達できるかどうかわからないままに求めた結果として得られるもののように思われる。(構造主義や実存主義では自我は後付けではないのか?)
▽46 ルネサンス時代の人々が古代ギリシャ・ローマ世界を再発見したとき、またイエズス会の人々がラテン語を大学やその他の学校教育の基礎に置いたとき、すでにひとつの人類学的生き方を示していなかったか。
ひとつの文明は、他のひとつあるいはいくつかの文明を比較対象とすることなしには、自らをかえりみることもできない、という認識があった。自らの文化を知るには、それを他者の視点から見る術を身につけなければならない。
▽48 本居宣長は、中国と比較対比することで、日本文化の本質を規定した。虚飾の排除、簡潔、謙虚、省略、もののあはれ、あらゆる知の相対性など〓。
……ルネサンス初期には、人間世界は地中海の周縁に限られており、それより外の世界の存在は、うすうす感じとられていたにすぎない。それでも、いずれの社会も人類社会のひとつの部分として、他を参照せずに自らを理解することもできない、ということはすでに認識されていた。
▽53 ルネサンスの貴族的人文主義、19世紀のブルジュワ人文主義のあと、人類学は、二重の意味で普遍的な人文主義となった。ウマニスモ。それまでのような特権階級のための特権的文明を出発点として生み出された人文主義を超え、民主的人文主義の基礎を築く〓。人間の認識を深めるためには分野を問わずあらゆる科学の方法と技術を動員して、一般化された人文主義のなかで人間と自然の和解を呼びかける。
▽54 人類学者は、私たちの生き方・価値観がすべてではないということ、私たちとは異なった生活様式・価値体系によって幸福を実現した共同体が存在することを明らかにする。(相対主義)
▽61 多くの慣習が、内的必然性や偶然の結果ではなく、近隣集団に対して後れをとりたくないという意志だけから生まれた。自分たちが規則で律しようなどと考えもしなかった思考や活動の分野に、近隣の人々が明確な規範を適用していることを知ったとき、こうした意志が働く。
▽63 それぞれの社会の慣習や信仰は、ある体系をなしている。そしてその内的均衡は、数世紀をかけて達成されたものであり、たったひとつの要素を除くだけでも、全体を解体させる危険がある。
▽67 人間社会にとって多様性はなくてはならないものだとしたら、今日世界をおおいつくそうとしているこの均質的な大文明の内部に、「差異」が生じてくるのではないか。あるいは差異はもう生まれはじめているのに、私たちがその意義を理解していないだけかもしれない。
▽87 人工授精、代理母……など。 精子提供者による受精という方法に相当するのは、ブルキナファソのサモ族に見られる。娘たちは、夫のもとで生活を始める前に、最高三年間は自分で選び、公にも認められた愛人をもつことができる。愛人とのあいだに生まれた最初の子どもをつれて夫のもとに嫁ぐが、この子どもは正式な婚姻による最初の子として認められる。
妻が不妊症である場合、夫はほかの女性に代償を支払って、次に生まれる子供の父として指名してもらうことができる。正式の夫は精子提供者であり、女性は別の男性や子どものない夫婦への子宮代替者となる。フランスのように子宮貸与は有償か無償かという問題は存在すらしない。
ホモセクシャルとも呼びうる女性のカップルが、男性から精子の提供を受けて子どもをつくり、一方が法的父、一方が生物学的になることができる社会も。
……子どもの家族的、社会的身分は、法的父(女性であっても)との関係で決まるが、それでも子どもは生物学的親が誰であるかを知っており、感情的絆も保っている。生物的親と社会的父が異なっていることや、両者の身元がわかっていることからくる葛藤はない。
▽93 第1に人類学は、私たちが「自然の理」とみなしているものが、私たちの文化に固有な精神的拘束や慣習にほかならないことを明らかにする。
第2に人類学者が収集する事実は、数世紀にわたって収集されたものであり、きわめて広範な人数の経験を代表している。これらの事実から人類学者は、人間の本性における「普遍的なもの」を明るみに出し、現在もなお方向の定まらない事態が、どのような枠組みのなかで展開していくのか、そしてそれを頭から偏向とか倒錯だときめつけるのは間違いであることを、示唆する。
▽94 法律家や道徳家の性急さに比べ、人類学者は自由主義と慎重さを重んじた助言を惜しまない。同性愛のカップルのための人工的出産……でも、他の社会でそれに相当することが、不都合なく行われている事実を指摘する。
人類学者は、なりゆきにまかせること、それぞれの社会の内的論理に従うことを望む。▽96 市場社会におけるあらゆる活動が経済法則に従っているのであれば、経済学は未来を予測し、対処できる真の科学となりだろうが、純粋に経済的に見える行動のなかにも、他の要因が介在し、経済学を惑わせている。これらの要因により大きな重要性を与えている社会を研究することで、それらを明るみに出すことができる。
▽98 コロンビアの農業体系は、紀元初頭から7世紀まで存続し、末期には、灌漑可能な耕地は20万ヘクタールもあった。集約農業によって1平方キロあたり1000人以上の人口を支えることが可能だった。
生産性への志向ともいうべきこうした大規模な遺構が存在する一方で、正反対の性格をもった事実も存在する。すなわち、ネガティブな方法で生産性を限定することをも知っていた。
特別な使命をもった首長や司祭らが、狩猟や漁労の開始日や期間を決める。動植物それぞれの種ごとに超自然的存在である「主」がいて、行きすぎた収奪を罰するという信仰は、きわめて広く見いだされる。
▽99 農耕は、ある視点からみると、退歩でもある。カロリーは多くても栄養素にとぼしい数種類の食品に限定されており、食品構成は悪化する。1回の凶作に見舞われるだけでも食料不足となる不安定さがある一方、多くの労力を必要とする。農耕の伝播とマラリアの伝播が、時間的にも空間的にも一致するというアフリカの例は、農耕が伝染病伝播の原因にもなりうることを示唆している。
▽105 いわゆる未開社会のほとんどが、多数決の原理を認めない。どのような変革よりも集団内部での社会的まとまりと相互理解が有線され、争いが起きると全員一致に達するまで、何度でも議論が繰り返される。(〓宮本常一の対馬の例。土着の民主主義)
▽107 不動産取引の忌避。先祖伝来の大地が彼らの「母」だから。北米のメイミニ・インディアンは、隣接するイロコイ族の農耕技術を知悉していながら、彼らの主食である野生稲に、その技術を応用することを拒んだ。「母なる大地を傷つける」から。
▽108 「未開社会」は、歴史的変化を芽のうちに摘み取ろうとつとめる社会。私たちの社会は、変化こそ構造原理であり作動原理でもあるのに対して、「未開社会」は、そのままであり続けるものとして、社会のメンバーによって考えられている。
▽112 文化とは、ある文明に属する人々が世界ととり結ぶさまざまな関係の全体であり、社会とは、それらの人々がお互いのあいだにとり結ぶさまざまな関係をさす。文化は秩序をつくりだす。逆に社会は、エントロピーを生みだし、エネルギーを浪費し、社会的葛藤や政争、心理的緊張によって消耗してゆく。最初は社会を支える価値体系であったものもいやおうなく摩耗する。
「未開人」と呼ばれる文字をもたぬ人々〓は、文化によってわずかな秩序を作りだすにすぎないが、彼らは社会のなかに、ごくわずかなエントロピーしか作りださない。平等主義で、全員一致の原則ののっとった社会。反対に自称文明人は、文化の内部に大量の秩序をつくりだす一方で、社会の内部に大量のエントロピーを生みだす。
理想的なのは第3の道。すなわち文化面ではこれまでと変わらず多くの秩序を生みだしながら、社会におけるエントロピーの増大という対価を避けていくといういきかた。
▽115 遺伝子バンクによって、私たちの文明とはまったく異なった生産様式によって数千年にわたってつくられ、現在も残っている植物の起源種を保存する努力。収量は大きいが、ますます病原体に弱くなっている現代農業の欠陥に備える。さらに、古代的生産様式が生みだした「成果」を保存するにとどまらず、それを可能にした方法(ノウハウ)が消滅しないよう、保存のための手を打つべき。(能登の価値=経済合理性では測れない〓=千枚田などの価値)
▽117 人類学は、人間のさまざまな構成要素を調和させる大切さを、理解させてくれる。工業文明がこの調和を破壊しようとするとき、人類学はつねに警戒を促し、調和を回復する道のいくつかを指し示す。
▽121 神話分析。数多くの物語群は、互いに対比されることによって意味の明らかになる、より少数の物語に置き換えられる。神話の意味は、他から切り離された個々の神話のなかにあるのではなく、互いの関係のなかではじめて明らかになる(構造言語学、相対〓)
▽122 神話と歴史。今日の状態を是とするか非とするかによって、フランス革命の解釈は異なり、将来の展望も異なる。近い過去、遠い過去について私たちが作りあげるイメージは、神話の性質にきわめて近い。
社会秩序と世界観に根拠を与え、……物事の現状を過去の状況によって正当化し、そこから将来を考える、という無文字社会で神話の果たしている役割はそのまま、私たちの文明が歴史に課しているもの。
ちがいは、神話が、それぞれ異なった物語を語っているように見えながら、挿話の配列を変えただけで、同一の物語であることが発見されるにの対して、「歴史」は、現在が過去の再生産であり、未来が現在の持続であることを期待させるのではなく、現在が過去と異なるように、未来も現在と異なるということを期待させるためのもの(文字のある社会とない社会の違い〓)
「未開人」の信仰と私たちの信仰を比較することで、現代文明の「歴史」が、客観的真理よりむしろ予断と希望の表明であることを明らかにしようとしてきた。
私たちの社会の過去は、唯一の意味だけが可能なわけではないこと、過去について絶対的解釈は存在せず、すべて相対的解釈にすぎないことを理解させてくれる。
▽126 ……宇宙の歴史は、死すべき人間にとって、ある種の神話の相貌を帯びてくる。なぜならそれは、一度限りの、繰り返しのきかないものとして、その現実性を検証することけっしてできないものだから。
17世紀以来、科学的思考は根底から神話的思考に対立し、やがて後者を駆逐してゆくものと信じられてきたが、今日、これと正反対の動きが始まっているのでは。科学的思考の進歩そのものが、科学的思考を歴史の側へと近づけているのではないか。
▽137
▽143 「社会は必要悪」社会はさまざまな恩恵を供すると同時に、きわめて負担の大きな隷属状態にほかならない。この隷属状態に対して、世界中の多くの神話が、ある種の「黄金時代」を想像のなかで対置しようとしている。
▽153 かつては嘲りの対象でしかなかった習慣や信仰に、客観的価値が認められるようになってきた。しかし人類学の土俵に集団遺伝学がのぼってきたことで、もうひとつの転換が生じた。
「未開社会」で、乳児を3,4歳まで授乳したり、必要なら嬰児殺しをすることで、人口の増加率を低くおさえてきた。
20世紀半ばまでは、人種は文化に影響を与えるかが問われてきた。このような問題設定からは答えが得られないことが確かめられ、問題の方向は逆であると考えられるようになった。それぞれの地域の人間の文化、生活様式が、人類の生物学的進化の方向とリズムをかなりの程度決定してきた。文化は人種に従属するどころか、人種と呼ばれている何ものか、こそ、文化のさまざまな働きのひとつだということがわかってきた。
近隣住民との遺伝子交換の度合いを決定するのは、その集団の文化にほかならない。
長い世代にわたって実行されてきたこうした規則が、遺伝形質の伝達に差異を生みださなかったはずはない。
……それぞれの文化が遺伝子的適性を選択し、それらの適性が文化にフィードバックして文化の方向づけに影響を及ぼす、と言うこともできる。
……文化的境界は遺伝子的障壁を先取りし予兆するとさえ言える。衣装や髪形、しぐさなどの文化的差異は、人種差とも比べられる差異を作りだしてみせる。文化が特定の身体的特徴を好むと、それが固定され、広められていくことさえある。
▽160
▽162 自分の住む社会とかけ離れた慣習・信仰・価値観を徹頭徹尾しりぞけるという傾向は遠い昔から存在する。古代ギリシャも中国も……自分たちの生活規範からはずれるものはすべて、文化の外にあるもの、自然の側にあるものとされてきた。
▽165 「未開社会」は自分たちの社会の過去だという誤った進化論。私たちは消滅した文明については、いくつかの側面しか知り得ないのに。
▽166 日本的「封建制」と呼ばれるものは、武士道精神に彩られ、動的で実用的精神に富んだものであり、西欧封建制とは表面的にしか類似していない。(日本のマルクス主義者が、日本の歴史をマルクス主義の時代区分に無理やりあてはめようとする愚)
▽170 人類の進歩は、一歩一歩階段を登るというよりは、運を託してさいころを投げることに似ている。歴史の累積は偶然の作用にすぎない。
私たちは、自分と似た方向に発展する文化をすべて、累積的と考える。それ以外の文化は、現実に停滞的であるからではなく、その発展の路線が私たちの依拠する座標では測ることができず、私たちにとって意味をもたないから、そのように見えるにすぎない。
ある文化を勢いのない、停滞的なものだ、と形容したくなったときは、私たちがその文化が何に本当の価値をおいているかを知らず、そのために動態を欠く状態に見えるのではないかと自問してみるべき。
▽176 19世紀半ばの西欧と米国は工業化と機械文明という点でもっとも先進国だったが、製鋼業や有機化学においては、日本の鍛造技術、醸造技術はぬきんでており、日本が今日バイオテクノロジーで先端を行く理由も、おそらくそこにある。
▽180 人類学者は、開発の障害となる古くさい慣習だけに関心を向けることでその存続を促しており、それは巧妙な植民地支配の延長にほかならない、と途上国の指導者がしばしば批判する。
▽182 工業文明の広がりや交通通信手段によって、言語、文化の壁は崩れ去った。創造に満ちた偉大な時代とは、遠く離れたパートナーと刺激を与えあえる程度に情報交換ができ、しかしその頻度と速度は、集団・個人間に不可欠の壁を小さくしすぎて交換が容易になり、画一化が進み多様性が見失われれない程度にとどまっていた時代だった。
現代の人類は「世界文明」へ向かっているように見えるが、その考え方そのものが、「文明」の理念に含まれ、また求められるもの、すなわち、可能なかぎり大きな多様性を示す諸文化の共存--と矛盾しないだろうか。
▽185 伝統的ノウハウの保存では、日本では「人間国宝」という制度をつくることで解決した。フランスでも同様の制度の準備を進めている。(〓能登の技術は)
▽186 日本の発展(明治維新は、フランスのように過去を破壊するかわりに王政復古でその活用をはかり、新たな秩序のための人的資源を動員した)。個別文化と人類の諸文化全体が、ともに存続し、繁栄してゆくには、外への開放と内へのひきこもりという二つのリズム、ときにはズレを生じ、ときには同調するこの2つのリズムが必要
▽200 雑種文化の二つの型 1つは、外部から到来するすべてをのみこんだ、全体を関連づけることのできないようなチグハグな文化。もう一つは外部に向かって開かれ、それを借用しながら、一定期間内にとじこもり、外からの借り物を吸収してわがものとする文化。(キリコ祭りに見る雑種と、高度成長とのちがい)
▽202 日本文化は、外部へ開かれた時期と内へと閉じこもる時期が交代して現れる。熱心に外部のものをとりいれる時期と、それに続く同化もしくは消化の時期。(戦後もその特徴はある? ナショナリズム、農への回帰……?)
▽204 秋山光和 古いものが常に回帰する、古いものの現代化、現代への適応を行う日本文化。下層の文化が定期的に上昇して表面に現れる。
▽213 人類が文化の融合を達成することが可能だろうか。世界文明がある均質性を実現するのに近づくほど、その内部にいままでとは異なった多様性が生みだされてくる。米国では、「アメリカ的生活様式」(均質性)といわれるものと、おびただしい数の異なった文化集団、多数の宗教団体の併存という事態。
文化の融合という理想は、つねに多様性を生みだしつつここまできた人類の生きかたとはあまりに矛盾するものであり、人類が古い障害を克服したその瞬間にも、予想もつかなかった文化の融合へのあらたな障害が生みだされている、ということになると思われる。
▽219 19世紀には、科学と知識の増大によって人類は、いっそうの幸福へいたると信じられてきたが、今は、あらゆる進歩にはそれなりの対価が払われること、ときにその対価はきわめて高くつくことに気づきはじめている。私たちが進歩に伴う諸問題を意識しはじめていること自体、ひとつの好機を提供している。
▽225 「構造人類学」(みすず書房)所収の「民族学における構造の概念」
▽228 歴史的に見た場合の日本が、外の文化に対してとってきた2つの態度。外に向かって開かれ、外来文化を吸収することに熱心な一面と、外からもたらされたものを同化し、それに自分のしるしを刻む時間をみずからに与えようとするかのように、自分自身の上にかがみこんできた一面、とのあいだに、均衡を保ってきたという指摘。
▽現代以後の世界を救済する知のあり方としての「第3のユマニスム」としての人類学は可能か、という問いかけ。ルネサンスのユマニスムや、オリエントや極東の文化の洗練された部分にだけ異国趣味的関心を払った、19世紀のブルジョワ・ユマニスムと異なり、第3のユマニスムとしての人類学は、地上すべての社会、とりわけこれまで文明の残滓としてかえりみられなかった社会に関心を寄せる。しかも、歴史学や文献学の方法と異なる、対象社会のなかに研究者が身を置いた個人的体験に基づく、真に普遍的なユマニスム。これまで不当におとしめられてきた社会から知的活力をえることによって、特権者のためのものでない民主的なユマニスムを築こうとしている。
▽230 「未開」社会の小集団が持っていた、環境への適応技術、人間を疎外しない労働観、小規模集団であるために病原体も小集団でありえたという衛生上の好条件……。だがこれらの「未開」社会の長所は、状況の変化によって、低開発と貧困の原因になってしまった。そして、「低開発」になった社会が求めているのは、ほかならぬ「開発」である。
▽238 人間が動物を食べることは、弱められたカニバリズムであり、狂牛病は人間が牛に肉食をしいた報いであるとする論。自然利用の効率として著しく不経済な家畜の肉を食べる行為がいきづまる、近い将来への警告。
……日本人があるときは人間を優先し、自然を犠牲にする権利を自らに与えるのも、おそらく自然と人間のあいだに、はっきりした区別が存在しないことによって説明されるのかも。自然と人間は、仲間同士なのですから。
▽242 「国民的」ナルシシズムを正当化するための「文化相対主義」ではなく、「人類の歴史のおそらく99%に当たる期間、そして地理的にいえば地球上で人の住む空間の4分の3で、ごく最近まで人々がどのように暮らしてきたか」を理解するための視点を「文化相対主義」と呼んでいる。たった1%の「歴史」だけを文化の母胎とみなし、地球上の4分の1で起きることを「世界」とみなす見方を改め、人類史にふさわしい尺度に引き戻して相対化するための基礎作業を意味している。99%の期間、人間が対話を続けてきた「自然」によって育まれた思考が、自然のさなかに生きる「野生の思考」であることを論証した。
▽254 川田順三「文化人類学のすすめ」 総合知「メタ・サイエンス」としての人類学の貢献。人類学における「総合」とは、比較を通じた「意味づけ」。目の前に展開する事象じたいは意味をもたない。それにかかわる人々が意味づけをしている。
目次


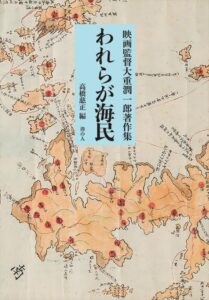

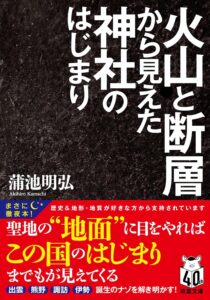

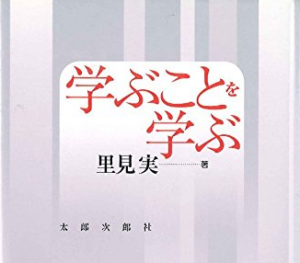

コメント