日本辺境論<内田樹>新潮新書 20100107
江戸時代までは中国を中心とした世界の「辺境」だった。明治以降は欧米中心の世界の「辺境」である。そうした辺境人としての地位が、日本人を一定の枠にはめているとみる。
辺境人は、中心に対して絶えず追いつこうとする。まったく知らない理解できない人を「師」と受け入れ、どん欲に吸収する。きわめて効果的に「学ぶ」。
一方で、自分で体系をつくったり、哲学をつくったり、世界観を確立することはできない。それをやろうと夜郎自大になると、破滅する。戦争はまさにそのパターンだった。
「辺境」という自覚がなくなり、「学び」の回路が発動しなくなったから日本は混迷しているという。
どうせ辺境人なのだから、それを自覚しようじゃないか、というスタンスだ。
日本語も、日本人の思考の枠をつくっている。欧米は表意文字であり、中国語は漢字で表意も表音もこなす。日本語だけが、表意の漢字と表音の仮名をもつ(ベトナム語やハングルは漢字を捨ててしまった)。漫画は、そういう日本語だからこそ伸びた分野だと見る。
一人称でもボク・私・オレ……などさまざまな言い方がある。それらはすべて相手によって変化する。「自分」が中心ではなく、相手に合わせるという日本人の特徴を示しているという。
ちなみに、漢字を真名と呼び、日本独自の文字を仮名と呼ぶのも、「本来のものは外にあり、自分のもっているものは仮のものにすぎない」という辺境人の心性だという。
=======================
▽17 「深層構造」が集合的なふるまいを方向づけているという直感。トーブさん「たしかにビッグ・ピクチャーは流行遅れかもしれない。だが、歴史はばらばらで意味がなく、未来は予測不可能という見方はあまりにも極端にすぎる」
▽21 日本人にも自尊心はあるが、反面、ある種の文化的劣等感がつねにつきまとっている。ほんとうの文化は、どこかほかのところでつくられるものであって、自分のところのは、なんとなくおとっているという意識である。……はじめから自分自身を中心にしてひとつの文明を展開することのできた民族と、その一大文明の辺境民族のひとつとしてスタートした民族とのちがいであろうとおもう」(梅棹忠夫「文明の生態史観」)
▽24 「完結的イデオロギーとして『日本的なもの』をとり出そうとすると失敗するけれども、外来思想の『修正』のパターンを見たらどうか。その変容のパターンにはおどろくほどある共通した特徴が見られる。……一般的な精神態度としても、私たちはたえず外を向いてきょろきょろして新しいものを外なる世界に求めながら、そういうきょろきょろしている自分自身は一向に変わらない」(丸山真男)
▽34 私たちは歴史を貫いて先行世代から受け継ぎ、後続世代に手渡すものが何かということについてほとんど何も語りません。代わりに何を語るかというと、他国との比較を語るのです。〓他国との比較でしか自国を語れない
……オバマの演説後、わが国の総理は「世界1位と2位の経済大国が協力してゆくことが必要だ」とコメントした。典型的な日本人的発言。「日本は世界の中でどのような国であるか」ということを言おうとしたとき、総理大臣の頭に浮かんだのは「経済力ランキング表」でした。……「第3位」や「第5位」になったら、対米関係が変わる可能性があるということを含意している。それを誰も「変だ」と思わなかったことが「変だ」。
「他国をもっては代えがたいわが国の唯一無二性」について言及すべきときに「ランキング」が浮かんだ。
▽38 右の端に「あの国」があり、左の端に「この国」があり、その間のどこかにわが国のポジションがある、という言い方でしか自国の立ち位置を言うことができない。日本は本態的にそういう国。オバマ後、新聞社説は「新大統領は日本に対して、親和的か威圧的か、日本の要求に耳を貸すか、軽視するか」をまず論じた。アメリカの東アジア戦略が「何であるか」よりも、「どういう口調で、どういう表情で、どういう物腰で」をまず論じられていた。
▽66 幕府は驚くほど簡単に大政奉還した。元首であることの軽さ。得じゃないならとっとと捨てる。版籍奉還でも、旧藩主たちは称号を捨てて首都で暮らす道を選んだ。政治的責任を免れ、現金収入が保証されたから。
日本列島は、辺境であるがゆえに、ローカルな事情にあわせて制度を加工することを許された。律令制度を導入しながら、科挙と宦官は知らぬふりをして導入しなかった。
劣位を逆手にとって、自己都合で好き勝手やる生存戦略は、戦後も成功した。9条と自衛隊の「矛盾」についての「思考停止」はその狡知のひとつ。アメリカは「軍事的に無害かつ有用な国であれ」と命令した。首尾一貫した対日政策を「矛盾している」と言い張るという技巧された無知によって、「アメリカの軍事的属国である」というトラウマ的事実を意識に前景化することを免れてきた。
「無知」を装った「狡知」。逆に、挙国一致的な努力が要されるときは「世間の常識を知らない田舎者のままでいいのか」「世界標準からこんなに遅れてるぞ」という言い方が採用される。自分たちが世界標準からずれているという認識が国民全員にあるから、この恫喝が有効になる。
▽79 明治の日本は、「いかなる責務を果たすために国際社会に参与しているか」という問を自らに向ける責務を免じられたまま「五大国」になった。その政治的未熟が、ヴェルサイユ講和条約で露呈し、平和主義・国際協調に向かう「新秩序」の潮流にあからさまに非協力的態度を示して、信頼を失った。ウィルソンの掲げた平和原則を無視し、19世紀的な帝国主義スキームにしがみついていたため、日英同盟解消にむかう。
人種や信教や文化を超えるような汎通性を持つような「大きな物語」を語る段になると思考停止に陥る。
▽89 日比谷焼き討ち事件など、明治末年の日本国民は無知だった。幕末は世界標準に追いつこうとした。明治末年の日本人は「世界標準を追い抜く」ことを要求された。日本人は効率よく先行事例を模倣するときは卓越した能力を発揮するが、先行者の立場から他国を領導するとなると思考停止に陥る。脊髄反射的に無能化する。
▽91 韓国併合、満州建国……は、30年も前に正確に予想されていた。日本は、ロシアだったらやりそうなこと、を、ほとんどそのまま満韓で再演した。「軍部の暴走」と言うが、暴走できたのは、すでに「下絵」が描かれていたから。ロシアが制定した「世界標準」へのキャッチアップだった。
▽113 「君が代」に最初に曲をつけたのは、イギリス公使館にいた軍楽隊長のジョン・ウイリアム・フェントン。宮内省の雅楽の伶人によって改作され、ドイツ人フランツ・エッケルトがアレンジした。「日本だけ国歌がないとまずい」とフェントンがアドバイスしたのが国歌制定のきっかけ。「世界標準ではこうなっているから」という理由で、ナショナル・アイデンティティを表象するものが誕生した〓。単なる「外圧」の結果だった。
▽116 日の丸。日ノ本というのは、「あるところから見て東方に位置するところ」ということ。「中国から見て東にある国」ということ。ベトナムが越南という称したのと同じロジック。だから、幕末の国粋主義者佐藤忠満は、「日本という国名は属国性をあらわにする国辱的呼称だから、捨てるべき」と主張した。
▽119 人が妙に断定的で、すっきりした政治的意見を言い出したら眉につばをつけて聞いたほうがいい。過剰に断定的になるのは、他人の意見を受け売りにしているときだから。自分固有の意見を言うとき、めったなことで「すっきり」したものにはなりません。他人の受け売りをしている人間は、意見が合わない人と、妥協点というものを言うことができない。妥協できないのは、それが自分の意見ではないから。「虎」とは交渉できても「虎の威を借る狐」とは交渉できない。
自分の意見を形成するに至った自己史的経緯を語れる人とだけしか、私たちはネゴシエーションできない。妥協できない人は、自説を形成するに至った経緯を言うことができないので「譲れない」。虎の威を借る狐は、虎の定型的なふるまいは熟知しているが、どうしてそのようなふるまいをするようになったのか、その経緯も深層構造も知らない。
日本人が「ほんとうは何をしたいのか」を言えないのは、私たちが「狐」だから。つねに他に規範を求めなければ、おのれの立つべき位置を決めることができない。
▽136 日本人の知的傾向に丸山真男は「きょろきょろ」という擬態語をあてた。「師を求める弟子の渇望」
▽139 論文形式 英米系では、序論で全体の構成と結論が予示される。それが「世界標準」と日本の学者は受け入れた。「自分の知性のパフォーマンスを最高化するためにはどのような文体が適切か」という問が学的主題になりうると考えている学者は日本人にはほとんど存在しない。本来そういうことをとことん問うのが「英米式」。みんながやってるから英米式に、というのは「日本式」。
▽145 もし好きな人がいて、その人を振り向かせようと思ったら「プレゼントをあげる」のではだめで「プレゼントさせる」べきであり、「仕事を手伝ってあげる」ではなく「仕事を手伝わせる」。
自分が取った態度が感情と矛盾するとき、行動はもう否定できない事実だから、心の状態を変化させることでつじつまを合わせようとする。
▽155 水戸黄門で、根拠のない権威の名乗りを頭から信じてしまうのは、ワルモノたちだけ。このワルモノたちこそ、「舶来の権威」を笠に「無辜の民衆」たちを睥睨してきた日本の多くの知識人の戯画。基礎づけを示さないまま、いきなりひれ伏すことを要求する人間を前にしたとき、どうしていいかわからない。それはまさに彼ら自身がやってきたことだから。
▽159 霊的辺境であるとする態度から導かれる最良の美質は宗教的寛容。日本ではさまざまな宗教が緩やかに共生している。一方で、霊的成熟はどこか他の土地の先駆者が引き受けるべき仕事と考え、緊張感のある宗教感覚の発達を阻む。遠方から到来する「まれびと」を歓待する開放性は今ここにおける霊的成熟の切迫とトレードオフされてしまう。「ここがロドスだ。ここで跳べ」という切迫が辺境人にはとぼしい。
日本人はどんな技術も「道」にしてしまう。「日暮れて道遠し」ということをのんびり言えるのは「日が没する前に道を踏破できなくても、別に構わない」という諦念と裏表。「道」は教育方法としては卓越した装置だが、「目的地」を絶対化するあまり、おのれの未熟・未完成を正当化している。「今ここでおまえが成就したものを提示して見せろ」という切迫をシステマティックに退けることができる。
▽168 親鸞は修行の「目的地」という概念を否定する。行の目的地から遠近によって「ここ」の意味が決まるのではない。「ここ」は「ここ」である。信仰者にとってはすべてが「ここ」で生起し「ここ」で終わる。「ここ」の意味を、「ここ」より相対的に上位の、「外部」とのかかわりで論じてはならない。
浄土往生はあってもよしなくてもよい。光の中に包まれているという自覚があれば、それで足りる。……何も約束されないにもかかわらず、目的地がないにもかかわらず、歩みは踏みだされなければならない。この踏みだしのことを大拙は「飛び込み」と呼ぶ。
。
▽183 時間の長さは、それまで過ごしてきた時間の総量を分母として考量される。5歳の子にとっての1年は人生の20%の時間。子どもにとっては、1日がひどく長い。波や蟻の群れ野草の花弁をじっと見つめていることがある。対象が意識野いっぱいに広画手しまっている。大人はちらりと一瞥して、そのまま記号的処理してしまう現象が、子どもにとっては、長い物語として経験されている。
▽191 辺境人にとって、外来の制度文物は貴重な資源。……
(遍路道が発展する論理は辺境人の論理? 他者を受け入れ……)
▽218 私たちの政治風土では、「私はあなたより多くの情報を有しており、あなたよりも合理的に推論することができるのであるから、あなたがどのような結論に達しようと、私の結論がつねに正しい」という恫喝の語法がつかわれる。自分のほうが立場が上であることを認めさせれば、メッセージの真偽はもう問われない。
何が正しいか、よりも、正しいことを言いそうな人間だれか、という問いの方が優先する。言いそうな人間とそうでない人間を見分ける客観的基準がないから、不自然なほど態度の大きな人間の言うことが傾聴される。
▽236 「真名」と「仮名」。外来の漢字が「真名」とされ正統の地位を占めた。さらに男性語と女性語というしかたでジェンダー化される。
▽242 明治初年に、自然科学や社会科学の術語のほとんどが訳語としてつくられた。自然も社会も科学も哲学も主観も概念も肯定も現象も芸術も……。欧米語の翻訳とは、日本語訳ではなく漢訳だった。外国語を外国語に置き換えた。日本語が二重構造をもっているからそれが可能だった。中国人は、新たな語彙を加えることは、自分たちの不完全性を認めることになるから嫌がった。だから、外来語の多くを音訳した。
日本は、外来語に「真名」の地位をゆずり、土着語を「仮名」という暫定的なものとする辺境特有の言語観になじんでいたから、「強者の種族の思想」である外来語の応接は手慣れたものだった。


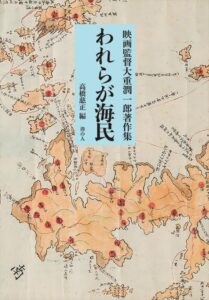

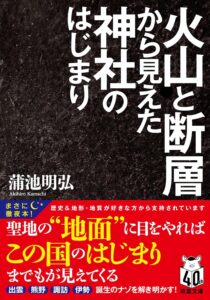

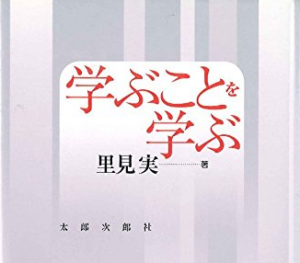

コメント