木星叢書 20080830
私たちの感受性も観察眼も属している文化によって規定さており、客観的な視点や歴史観などありえないことを説いた「構造主義」、あらゆる制度の起源に「身体的感覚」をもとめる思考と、「存在しないのだけれど、存在する」というねじれた形であらわれるというレヴィナス譲りの「他者」論という3つを縦横に駆使して、日本の文化や政治、社会を切っていく。たった3つの武器で、これだけ様々な現象を独特のひとひねりした視点で説明できることに驚かされる。
「まずモノがあって、それに対応して言葉ができるのではなく、命名することによってモノが立ち現れる」という構造主義言語学は、一般的に信じられている原因-結果が、実は逆である、というおもしろさがある。それと似たような事例がいくつも紹介されていて刺激的だ。白川静の漢字論も、漢字はコミュニケーションのために生まれたのではなく、呪術的な目的のために生まれ、それがコミュニケーションのあり方を形成した、という論だという。
たとえば、「穢れ」の概念は、ふつうに考えたら、死をおそれるといった感覚があって、それ故に生まれた二次的な感覚であると思ってしまうが、筆者は、「穢れ」という概念をもつことによって、人間はほかの霊長類と分岐した、と考える。
「穢れ」は、「すでに死んだ者」と「これから生まれてくる者」は、アンタッチャブル(=自分とはカテゴリーが異なり、共感の基盤もない「他者」)であることを教える。「他者」という概念をもつことで人間ははじめて共同体を構築することができ、交換や分業や欲望や言語を創出することができるたという。
……ちょっと難しい。でも、死者という他者を意識して生きることは、人間社会の存立基盤にかかわるほど重要なことなんだろうな、とは理解できる。「死」を意識から排除する現代の社会のゆがみも見えてくる。
こうした「逆転」の発想は、ほかにもある。
国民全員が思い通りの消費行動をとることを国策として奨励した結果、家族が壊れ、個人が消費単位となり、「市場のビッグバン」をもたらし、バブル経済を下支えした。ところが、原子化した個人は不愉快な隣人の存在にたえられなくなり、他者と共同生活を営むことを忌避する日本人を大量に発生させ、少子化をもたらし……となった。
さらに、男女雇用機会均等法によって求職者の数が急増したから、労働条件は切り下げられた。「政治的に正しい」政策を進めることで、労働者をより効率的に収奪することになった。だが、労働条件が悪化し、消費欲だけ亢進し、性差の社会的価値が切り下げられれば、結婚も出産もしなくなる。グローバル資本主義者たちに政治経済の舵取りを委ねたことで、絶対的少子化・絶対的貧困化にむけて坂道を転がり落ちようとしている--。
他者論は、「今・ここ」のかけがえのなさを実感するきっかけにもなるという。「他者である未来の私」の視座に立って「あのころは先が見えたつもりでいたけど、あんなことやこんなことが我が身に起ころうとは、思いもせなんだわ」と今を想像的にふりかえると、平凡な「今」が痛切にありがたく思えるという。「今・ここ」の大切さを「他者」の視点を借りることで理解するということだ。
--自分の将来の、「こうなったらいいな状態」について「どれだけ多くの可能性」を列挙できたか。多くの願望を抱いていた人は、願望達成率は高くなる。未来の未知性に敬意を抱く者は「宿命」に出会う。未来を既知の図面に従わせようとする者は「宿命」には出会わない。真に自由な人間だけが宿命に出会うことができる--という指摘は「他者論」で理解できる。未来の自分は、まったく理解しあえない「他者」である。それを意識しつづける大切さは、「死者」の大切さと共通するものがあるのだろう。
世界史未履修問題などは、「身体感覚」を切り口にする。「弾力的運用」「超法規的措置」が成立するのは、それが事件化したときに「言い出したのは私ですから、私が責任をとります」と固有名を名乗る人間が「生身」を供物として差し出す場合だけである、と説く。なるほど、と思う。責任を取る気のある人間がいない「前任者からの申し送り」による「弾力的運用」の結果、巨大な不正が見逃され、しまいにはシステムが崩壊する。そのことは、社保庁問題をみるとよくわかる。
3つの切り口とは離れるが、「日本の辺境性」という考え方もおもしろい。
江戸時代の子は、遠い海の彼方の中国という上位文化を学ぶことが「義務」だと感じていた。それが奏功してその時代の日本人の識字率は世界一の水準に達した。戦後は「アメリカの辺境」にとどまることによって経済大国になった。ところが、バブル以降、日本人は「オレたちが中心なんだ」という思い上がりにのぼせあがった。学力低下もモラル低下も、日本人が「辺境人」根性を失ったことにリンクしている……という。
----------覚え書き------------
▽9 「文明人」は「未開人」の段階を通過して現在の文明に達したという「物語」を信じ切っていたからこそ、「文明人」は「かつての自分」に対して残忍でありえた。=歴史主義。構造主義はこの歴史主義の野蛮に対するつよい嫌悪に動機づけられて生まれた。私とは違う時間の中に生きている人に世界はどのように見えているのか私にはよくわからない、という謙虚な知性が構造主義者を特徴づけている。自分自身のことも「よくわからない」。「私にはよくわからない」から始まる知性の活動が構造主義。
▽27 昔自分が書いたビラを読む。 「言い方」こそが私にとっては一次的であり、「言いたいこと」の方が副次的・派生的。語調やリズム感はまぎれもなく私のものであるが、「メッセージ」は、当の私でさえ覚えていないくらい。
▽46 「言葉の力」というのは、ひとつの語を口にするたびに、それに続くことのできる語の膨大なリストが出現し、そのなかのひとつを選んだ瞬間に、それに続くべき語の膨大なリストが出現する、というプロセスにおける「リストの長さ」と「分岐点の細かさ」のこと。
▽50 白川静、マルクス、フロイト、レヴィ=ストロースの共通点は、「人間の諸制度はそもそもどういうところから始まったのか」という起源にかかわる問から決して目を放さなかったことにある。
人間社会の起源には、非文化から文化に「テイク・オフ」する瞬間の劇的な快感が存在する。この浮遊するような快感をもう一度味わいたいと願った人々が反復した行為が集団的に模倣され、制度化したのが文化。
人間的諸制度の基本には「気分を高揚させる」か「悪い気分を抑制する」身体的実感があったはずである。そうでなければ、文明が始まるはずはない。
白川先生の漢字学は、地に瀰漫していた「気分の悪いもの」を呪鎮することが人間たちの主務であったという仮説の上に構築されている。
白川漢字論は「コミュニケーションの道具としての言葉」という功利的言語観と隔たるところ遠い。私たちが言葉を用いるのではなく、言葉によって私たちが構築され変容される。この言語観は、構造主義言語学や構造主義記号論と深く通じている。
▽58 レヴィ=ストロースの「女の交換」。どうして男が「交換の対象」にならないのか。男は再生産しないから交換物としての価値がないから。再生産のためには女100人あたり、男1人いれば十分。99%の男には生物的価値はない。無価値なものをもらっても、反対給付の義務は動機づけられない。
▽61 成人の条件とは、「どうふるまってよいかわからないときに、どうふるまうかを知っている」ということ。だから、子どもたちは、矛盾と謎と葛藤のうちで成長しなければならない。父と叔父は「私」に対してまったく違う態度で接し、違う評価を与える。
▽68 家族というのは、起源的には「礼」を学ぶための集団。「そこにいない人」の「不在」を痛切に感知する訓練が「礼」の基礎となるからだ。死者の弔いという形をとることもあるし、生まれてくる子供への期待という形をとることもある。「もう存在しない他者」「まだ存在しない他者」の不在を「欠如」として感じとることは、人間が種として生き延びるために不可欠の能力。
▽73 「穢れ」は貨幣よりも階級よりも交換よりも古い。穢れという概念をもつことによって、ほかの霊長類と分岐したと考えるほうが論理的だろう。「すでに死んだ者」と「これから生まれてくる者」はアンタッチャブルであるということを私たちに教える。
死体を埋葬するのは、「汚いから」ではない。葬礼をおこなうのは、それをしないと死者が「死なない」から。死者の祟りで苦しめられ、死者の気づかいで護られ……。死者とはアンタッチャブルなものであるという仕方で「新しいカテゴリー」を創出するため。死者は「存在しない」が、「私たちは何のために生きているのか」という存在論的な問いを起動させる。
ヘーゲル的にいえば、「死者」という概念をもつことによって、人間ははじめて「自己意識」を有した。「死者」という概念を祖先がつくりだしたのは、死んだ人間は「モノ」ではないという感覚を基盤にして、「他者」という概念を導出するためである。
「他者」という概念をもつものだけが共同体を構築することができ、交換や分業や欲望や言語を創出することができるあkら。「他者」とは、私たちと同じカテゴリーに属さず、言葉も通じず、共感の基盤もなく、……「存在しないのだけれど、存在する」というねじれたかたちでしか私たちにかかわることができない。
葬礼はその「他者」という概念を導出するための制度的な迂回である。
同じロジックが「これから生まれてくる者」に対しても適用され、葬礼の「隔離」の制度に準拠して、生殖にかかわる隔離の儀礼が成立した、というのが「穢れ」にかかわることの順序ではないか。
▽81 構造主義者たちは、「ヨーロッパ的主体には、第二次世界大戦の死者を弔う資格はない。ヨーロッパ的・近代的主体は喪の場から去れ」と告知していた。
柳田国男の「先祖の話」〓 敗戦直後、鎮魂のために、日本人は何をすべきかを民俗学の立場から説いた。祖霊を祭る伝統的な祭式を守って絶やすなという。(死者とともに生きる〓=他者)そうした儀礼なしに人間は生きて行けない。
▽93 「これこれでなきゃだめ」というのが原理主義。「使えるものがこれしかないから、これで何とか折り合いをつけよう」というのが機能主義。正しいか否かではなく、そのソリューションが機能的かどうか。
目の前に「なまもの」があるときに、とりあえず「手が勝手に動いておろしてしまう」というのが機能主義者の骨法。
▽117 個人の原子化 家族解散で個人が消費単位となり、「市場のビッグバン」をもたらし、バブル経済を下支えした。原子化した個人のアキレス腱は、不愉快な隣人の存在にたえる共同体を作れないこと。……国民全員が思い通りの消費行動をとることを国策として奨励したのは日本政府。その結果として、他者と共同生活を営むことを忌避する日本人が大量に発生した。
▽135 苅谷剛彦の「階層化日本と教育危機」〓 学力低下は自身の学力の低下に満足感や達成感を覚える社会集団の出現の帰結。同じ理路は「うまく働けない若者たち」にも当てはまる。「格差社会についての洞察は、格差社会の最底辺にいる人間がもっとも深い」というロジック。古くはマルクス主義者が、近年ではフェミニストが愛用した。
▽148 「未来は他者である」(レヴィナス) 「最も穏健な意見に従って自分を導く」(デカルト)
想像的に先取りした未来の私の視座にたち「あのころは先が見えたつもりでいたけど、あんなことやこんなことが我が身に起ころうとは、思いもせなんだわ」と考えるのは、「未来の他者性」をなんとか現在に繰り込むための「方便」だが、「判で押したような風景」の「かけがえのなさ」が痛切にありがたく身にしみるという現実的効果をもたらす。(今・ここ の輝きを他者の視座をもつことで感受)
▽159 「弾力的運用」「超法規的措置」がぎりぎり成り立つのは、それが事件化したときに「言い出したのは私ですから、私が責任をとります」と固有名において引き受ける人間がいる限りにおいてである。
法理と現実のあいだの乖離を埋めることができるのは固有名を名乗る人間がその「生身」を供物として差し出す場合だけである。〓(世界史未履修問題)
責任を取る気のある人間がいない法規の弾力的運用は、単なる違法行為である。
責任をとるつもりでいる人間が生身を差し出している限り、常識的にありえないような度の過ぎた違反はなされない。「度が過ぎる」のはいつだって「前任者からの申し送り」を前例として受け容れ、違法性について検証する気のないテクノクラートたちである。
▽170
▽175 誰が犯したミスか知らないけど、放置しておくとまずいから、「私の責任において」これを今のうちに片づけておこう。そう考えるのが予防的発想。
「予防」はマニュアル化できない。マニュアルは責任範囲を明文化することであるが、ミスは、ある人の責任範囲と別の人の責任範囲の中間のグレーゾーンにおいて発生するもの。誰もミスを看過したことの責任を問われないようなミス。グレーゾーンにはそのようなミスが構造的に誕生する。
「それは私の仕事じゃない」ではなく「いいよ、これはオレがやっとくよ」という言葉で未来のカタストロフを未然に防ぐことができる。
だが、「未然に防がれて」しまったので、誰も「オレ」の功績を知らない。成果主義はこうしたふるまいをゼロ査定する。
▽193 均等法以後、労働者の労働条件は一貫して劣化してきた。求職者の数が増えれば、労働条件は切り下げられる。雇用機会均等は、誰からも文句がつかない「政治的に正しい」コストカットだった。財界が文句を言わなかったということから推して、労働者をより効率的に収奪するための法律であることに気づいてよかったはず。
労働者を、ぜんぶ同一規格で揃えることがグローバル資本主義の夢。そなれば賃金は減り、市場は増える。しかし、労働条件が悪化し、消費欲望だけ亢進し、性差の社会的価値が切り下げられた社会に投じられればとおからず結婚も出産もしなくなるだろう。という未来予測をグローバリストは見落とした。
グローバル資本主義者たちに政治経済の舵取りを委ねたことで、絶対的少子化・絶対的貧困化にむけて自滅の坂道を転がり落ちようとしている。
▽209 自分の将来の「こうなったらいいな状態」について「どれだけ多くの可能性」を列挙できたか、その数によって未来は変化する。多くの願望を抱いていた人間は、当然、願望達成率は高くなる。〓
願望達成の可能性は、本質的なところでは、自分の未来についての開放度の関数なのである。「未来を切り開く」という表現からは遠い。未来の未知性に敬意を抱くこのはいずれ「宿命」に出会う。未来を既知の図面に従わせようとするものは決して「宿命」には出会わない。真に自由な人間だけが宿命に出会うことができる。
▽213 世界に少しでも「よいこと」を積み増ししたいと思うなら、「ほうっておいても、どんどん世界をよくする非人称的システム」について考えるよりも、とりあえず自分の足元のゴミを拾いなさい、ということ。
正義は一つところにとどまるものではなく、正義は開かれたものであると考えることが、重要。ある社会を一気に慈愛深いものにしようとかすることは、スターリン主義の危険を冒すこと。スターリン主義とはつまり、個人的な慈悲なしでも法律によってやっていけるという考え方。
(正しさ、は静止した状態ではなく、絶えず過程にある、ということ。〓25条と13条)
▽224
▽227 障害者差別も性差別も……「被収奪感」がすべての「マイノリティ」の権利要求の基本感情をなしている。
正義の実現が「被収奪感を感じている私」を基体とする限り、いかなる社会理論も、この世界に「親密圏」を立ち上げることはできないだろう。慰めも癒しも「喧嘩腰の言説」によっては基礎づけることができないからである。
正義は「奪われたものを奪い返す」ことを求める。だが、無償での贈与は正義に悖る。収奪と贈与は、同一次元には存在できない。それを両立させるのは、矛盾を矛盾として生き、引き裂かれてあることを存在の常態とするような人間の成熟だけであると思う。
▽232
▽246 日本の辺境性 江戸時代の子は、遠い海の彼方に中国という上位文化があり、それを学ぶことが辺境の民としての「義務」だと観念されたからそうした。実用性なんかない。江戸時代の子どもたちが学んだのは、「子どもには決して到達しえない知的境位が存在する」という信憑である。それが奏功してその時代の日本人の識字率は世界一の水準に達した。「辺境」は「中央」を知的に圧倒することができる。戦後は「アメリカの辺境」にとどまることによって経済大国になった。……80年代のバブル以降、日本人は「オレたちが中心なんだ」という夜郎自大な思い上がりにのぼせあがった。学力低下もモラル低下も、日本人が「辺境人」根性を失ったことにリンクしている。だから「属国」「辺境」でいいじゃないか。
▽259 愛国心がもっとも高揚する時期は「非国民」に対する不寛容が絶頂に達する時期と重なる。「世界に冠絶する国家」という自己幻想と「あまりぱっとしない現状」のあいだを架橋するため、「国民の一部が祖国性を理解し、愛するという国民の義務を怠っているからである」という解釈を愛国者はあてはめる。「愛国」の度合いが進むにつれ、愛国者は同国人に対する憎しみを亢進させ……
ナチスも同様。「真にドイツ的たりえないのいはユダヤ人が国民の中に紛れ込んでいるせいである」と600万人を殺した。が、戦況は悪化した。そこでナチスは「スターリンもルーズベルトもチャーチルも、すべてユダヤ人の手先である」と説明した。さらにベルリン陥落直前になったとき、宣伝相ゲーリングは「ヒトラー自身がドイツを滅ぼすためにひそかに送りこまれたユダヤ人の手先だった」という解釈を思いついた。
▽274


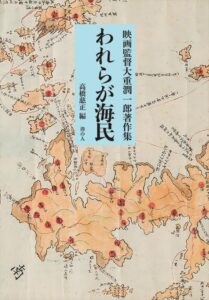

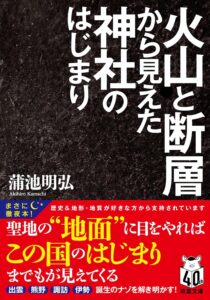

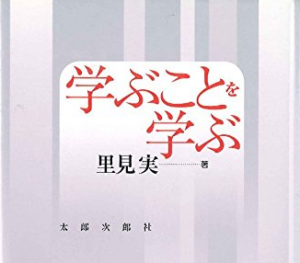

コメント