朝日新聞社 20080809
明治以来、日本の教育は管理しやすい「小粒の人間」をそろえ、「みんなとおなじ」という均質化することを目標にしてきた。それがみごとにうまくいき、うまくいきすぎたことが、最近の教育問題だという。
「小さい粒」は管理しやすいが、あまりに小さいと今度は管理の「網目」にもかからなくなる。子供たちの均質化がうまくいきすぎて、「みんなと違うことを心から恐怖する子ども」を作りだしてきた結果、「世界一勉強しない子どもたち」が生まれた。
だからこうした問題に対処するには、教育システムの効率を「上げる」のではなく、バグやノイズを注入して効率を下げることを考えた方がよい、と説く。教育基本法改正で政治家や官僚たちがめざす方向は、日本人をさらに小粒にする方向だと指摘する。
教員組合などによる管理教育批判とは似て異なる論法だ。システムの維持のためには適当な跳ねっ返りがあり、不純物があったほうがよい、という、ある意味で保守的な立ち位置から教育を論じている。
そういえばフーコーあたりがそんなこと言ってたような……と、ふと気づくから構造主義を勉強する刺激にもなる。
大学がそろって規模拡大にはしり、「現代社会学科」なんてものができれば右向け右でメダカのように真似をする異常な競争も、「均質化」の結果なのだろう。「みんなの真似をする」ことで利益を得られるのは市場が拡大している時だけであり、市場規模が縮小するなかでは逆効果であることは目に見えているはずなのに……
農業もそうだった。「ミカンをやれ」と国が号令をかけると、一斉に植え、10年か20年後には大暴落して痛い目にあったが、だれも責任は取らない。「均質化」は日本社会全体に浸透し、現代のような後退局面ではとりわけその弊害が噴出することだろう。というか自分自身も「均質化」に毒されているのだろうと思う。
論文の書き方やら、メディアリテラシーの問題、学問におけるブレークスルー(自分の知的枠組みの解体構築)の楽しさ……などの指摘も、なるほどなあ、とうなずきながら読んだ。
———抜粋・メモ———–
▽27 教育基本法改訂は日本人を「小粒」にする。明治維新まで、日本の教育は当時の世界最高水準にあった。私塾の送り出した英傑たちの破天荒な活躍によって日本の近代化は成し遂げられた。近代日本史上もっとも成功した教育システムである「幕末の私塾」がなぜ放棄され、明治の公教育のシステムは構築されたのか。……「政体を転倒するほどのスケールの大きい人間を作り出す教育システムはもういらない」ということを暗黙の前提として明治以降の公教育システムは構築された。「小粒の人間」をそろえるのが目的だった。
「小さい粒」は管理しやすい。が、あまりに小さいと今度は管理の「網目」にもかからなくなる。管理できなくなっているから、文部官僚は慌てはじめた。
教育基本法を改訂しようとしている政治家や官僚たちがめざしているのは日本人をさらに「小粒」にするという政略である。
▽35 日本の教育の目的は「子供たちを均質化すること」にある。「みんなと同じであることを最優先に配慮し、みんなと違うことを心から恐怖する子ども」を作り出すシステムを徹底した成果が「世界一勉強しない子どもたち」なのである。国民の均質化・知性徳性身体能力イデオロギー価値観の均質化。システムがみごとに機能した結果こうなった。……対処を講じるとしたら、教育システムの効率を「上げる」のではなく、バグやノイズを注入して効率を下げることを考えた方がいい。
最悪なのは、全国一斉一律に「勉強する子ども」はどうやったら作り出せるかの「模範解答」を処方しようとすることである。
▽43 「こうやって勉強していれば、きっといつか『いいこと』がある」という未来予測の確かさに支えられて勉強したわけではなく、「こうして勉強できるという『いいこと』が経験できるのは、いまだけかも知れない」という未来予測の不透明性のゆえに勉強していた。……学徒出陣で応召した学生の中には入営の直前まで専門書を手放さなかった者がたくさんいた。……たぶんいまの学校教育でいちばん言及されないことの一つが「学ぶことそれ自体がもたらす快楽」である。
▽67
▽80 言葉が聞き手に届くために必要な条件。「聴き手に対する敬意」と「メディア・リテラシー」。「自分がいま発信しつつある情報」に対して適切な評価が下せるかどうか、ということ。伝えつつある情報の信頼性、重要性、適所性(いつどのような文脈のなかで差し出されることで聴き手によってもっとも有用なものになるか)について評価が下せるかどうか。人間は「自分がいったん口にした話」はどれほど不合理でも信じようと努力する不思議な生き物。
▽114
▽131 首都大学東京 高等教育史に残る劇的な失敗例となるだろう。
▽149 大学郊外移転で社会的機能を損なう 学園紛争に懲りたから郊外へ。学外者が跳梁することはなくなった。青山学院は厚木の山奥にキャンパスを作ったため、志願者が急減した。お茶の水の中央大学はまるごと八王子に移転したせいで、都心にとどまった明治大学に人気で大きく水をあけられた。青学は厚木キャンパスをすてて都心回帰。
▽156「私、こんな職場でくすぶっているわけにはいかない」とか焦る。こういうことを言う人は、ごく少数の例外を除いて、「キャリアダウン」のコースをたどる。不充足感につきまとわれている人間は「いまの自分の正味の能力適性や、いまの自分に期待されている社会的役割」をクールにみつめることがなかなかできない。「分相応の暮らしのうちに満足感と幸福感を感じる」ことがなかなかできない。
▽184 「金になる」「就職に有利」というような幼児的な動機で勉強している学生は、どれほど努力しても、それによっていかなるブレークスルーも経験することがない。一度でも「脱皮=成熟」を経験したことのあるものは、それが「どういうこと」であるかを知っている。経験したことのないものにはその感覚がわからない。自分の知的枠組みの解体構築を喜ぶのは、単に「それが楽しいから」である。
▽187 学術論文は「未来のあなた」から「現在のあなた」への贈り物になるようなものでなければならない。初学者だったとき、「ぜひ読みたい」と思うし、「読んでよかった」と思えるような論文。
▽191 学術論文に書いてある99%までが私が先人から教えてもらったことである。残り1%が私の「リボン」である。その1%が、学術論文を「贈り物」たらしめるために不可欠。
「先人の知見」と「自分のオリジナルな意見」をきちんと分ける。引用出展を明記する。脚注をつけて、引用出展のページ数を示しておけば、読者はそれをすぐよめる。「追試可能性」 あとから追試する研究者のために贈ってあげることのできる最良のプレゼント。


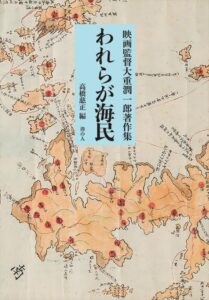

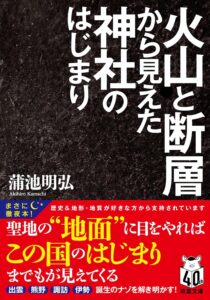

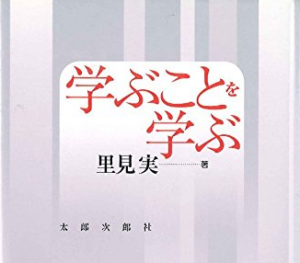

コメント