角川oneテーマ21 20080419
「自分」がまずあって、それが世界を切り開く、という「自我」の立場にはたたない。
他者との関係、つながりのなかで「自分」をとらえる。まさに構造主義の考え方なのだろう。
「キャリア形成」とか「自己実現」というのは、「まず自分」という姿勢だからダメだ。「自分の力で世界を切りひらく」というのではなく、私はほかの人にどんな形で役立つか、世界の方が自分に向けて呼びかけてくるものにどう応えるか、という対話的な枠組みで考えたほうがよい、という。無言のメッセージを読み取れない人にかぎって自分でドアをこじあけようとしてしまう……。
はたして私は世界からの呼びかけを読みとれているだろうか。自分の「使命」を感じられているだろうか。
限られた時間のなかでいったいなにができるのか……と考えると、だんだんと人間関係を閉じていってしまう。縮こまってしまう。
……そう思っていたら、こう書いてあった。
「病んでいる人というのはミニチュア志向になって自分の世界が縮んでいく。健全な人というのは自分の世界が広がってゆく人。いろいろな人とつながって、ゆるやかな共同性のなかで、まわりの人が自分をどんなふうなものとして受容しているか、自分に何を期待しているか……という仕方で自分をとらえていく……」
痛いなあ。——————————
▽31 「気分の悪さ」を解消するには、「なかったことにする」か「自分自身の知的OSをバージョンアップする」の2つしかない。ある知的フレームから別のフレームワークに移行する過程においては、どちらも無効であるような「真空地帯」があるのは仕方ない。一時的な「酸欠状態」を何とかしのぐ力を「知的肺活量」と呼んでいる。その肺活量がすごく下がっている。
▽46 人間って「現状維持」が多い。口ではあれこれ言ったって、やっぱりやらない。みんな変化が嫌いですから。だから相田みつをみたいな「ありのままでいいんだよ」というのが一番売れる。「変化に憧れつつ、変化しない」
▽51 「自己実現」ということばも死語にしてほしい。「自己」って単体で存在するわけではなくて、社会的ネットワークの中でどういう役割を演じるかということで事後的に決まる。
病んでいる人というのはミニチュア志向になって自分の世界が縮んでいく。健全な人というのは自分の世界が広がってゆく人。いろいろな人とつながっていって、ゆるやかな共同性のなかで、まわりの人が自分をどんなふうなものとして受容しているか、自分に何を期待しているか、……という仕方で自分をとらえていくというのが一番たしかな自己把持。〓
キャリア形成、といいながら、「これをしたい」ということは一生懸命言うんだけど、「自分は他人のために何ができるか」という問い方は思いつかない。でも「誰が自分の支援を必要としているか」という問いを自分に向ける習慣のない人は社会的にはほんとうは役に立たない。
▽56 キャリアアップとか自分の力で世界を加工し切り開くという図式でとらえるのはやめた方がいい。世界の方が自分に向けて呼びかけてくる、それにどう応えるか、という対話的なスキームでとらえた方がいい。無言のメッセージを聴き取れない人はどうしても自分でドアをこじ開けようとしちゃう。
▽66 私の使命とは何か、というふうに考える人は、自分が他人と「どう違うか」ということを考える。「これは私以外の誰にもできないことじゃないか」「ここは私以外にも誰も行きそうにないところではないか」と。
▽81
▽81 「自分探し」ということばの欺瞞は「その『探す』という行為の主体は誰なのか」と言う問いを主題化しないこと。だって、「探している私」は「未知の領域」を歩くごとに「別人」になっていくわけだから、「探しているもの」だけが同一であるということはありえない。
▽87 雑用増 自分を学者だと考えると、余計な仕事が増えて大変だなあということになるけど、自分のことをサラリーマンだと考えれば拘束時間はすごく少なくて、あとは全部「趣味の時間」というお気楽サラリーマン。頭を切り替えるだけでバラ色に見えてきた。
あとは、苦手だったり嫌いだったりすることも「アイロンかけ、大好き!」と宣言しちゃう。しかたなしにしているうちに好みが身体化する。
▽99 変人というのは最初からマジョリティの端っこにる。群れの中にはいるけど、いつでも逃げられるように端にいる。変人とはいえマジョリティに属していると余禄にあずかれることも多々あるわけで。
▽無防備 攻撃をしかけるんだったら、とにかく退却路も用意しておくとか、何も考えずに平気でやっちゃうとか。ロングスパンで勘定することができず、ショートスパンでしか自分の状況をとらえられない。
▽102 論文を書いているときに、最後まで全部見通せたと思うときがある。あ、できた、と思った次の瞬間には消えてしまう。でも「見通せた」という確信は揺るがない。「アカデミック・ハイ」 これを得るためには「助走」がいる。毎日何時間書くというルーティンを決めて、それを繰り返し2週間ぐらいつづけると、ある日「来る」。
▽107 多幸的な体験。夕焼けをジーッと眺めていると、だんだんそういう変化のリズムとこちらの体がシンクロしてきて、「あ、今、宇宙のネットワークの中におさまっているんだな」って感じがする瞬間がやってくる。自分はこの世界の構成要素なんだって。この「つながってる」という感覚は、ほとんどの子が自然の中に一定時間放り込まれると必ず体験する。
▽121 核家族のおかしさ。基本構造を4項にしたい。男の子だったら、母親の兄か弟。父母とほぼ同じくらいの社会的地位にいる人間が、ドミナントな価値観とは「ずれた」価値観を示すというかたちで、親族が固定化することを防ぐ。「おじさん」というのはそうして家の中の風通しをよくする役割。
▽170 明治生まれの人達は、若い世代が何かやろうとしても、「まあ、やめとけよ」「どうも気にくわないね」とか、うだうだ言いながら、社会のグローバル化に静かに抵抗していたんじゃないか。その人たちが表舞台から消えた後、ぺらぺら舌のまわるロジカルでクリアカットな世代が登場してくる。……でも……明治の人は早口だった。志ん生の落語なんかものすごく早口。……むしろ戦前戦中の方が科目だったのでは。「物言えば、唇寒し」でもあったから。
▽186 嘘をつくときって、体が共振しない。深く確信を持ったことを言うときって、自分の身体全体がブーンってうなるような感じで共振してくれる。嘘をついているときは、だんだん声が単調になる。身体が声についていかない。
▽201 「正味の自分」 自分が世界に受け入れられていて、世界の一部をなしているという確信を持てた特権的瞬間が人生のどこかにあれば、そのときの身体感覚を絶えず参照して生きてるから、社会的評価みたいなものにあまり囚われない。
▽216 寺男は、精神障害者の最後の逃げ場だった。教育機関であり、医療機関であり、授産施設であり……アジールだった。寺が果たしうる社会的機能も見直されていい。


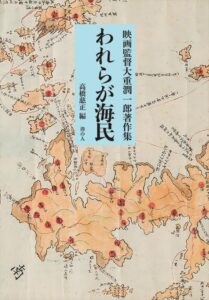

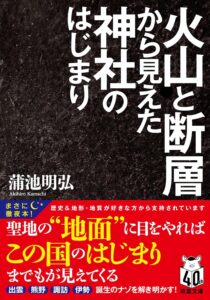

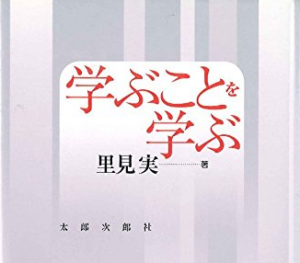

コメント