■対称性人類学<中沢新一>講談社選書メチエ 20160717
人類の思考の様式は、1万年前にはじまった新石器革命の時期にすべて獲得されていた。それが「野生の思考」だった。
第一次の「形而上学革命」である一神教は、こうした「野生の思考」を抑圧することで成立した。その抑圧された「野生の思考」が、第二次の「形而上学革命」を通して科学として復活する過程で生まれたのが構造主義人類学だ。
レヴィ・ストロースは、科学の思考も神話の思考も、二項操作を駆使して世界を理解しようとしていることを発見し、「科学的思考が現段階に達してはじめて、神話に何がこめられているか理解できるようになったのです。二項操作という考え方に慣れるまでは、私たちのほうがまったく盲目だったのです」と書いた。
ホモサピエンスである人間は、ネアンデルタール人などと比べて、「子ども時代」がきわめて長い。この未熟状態のあいだに、人類に特有の「無意識」の構造が発達した。ネアンデルタール人には言語はあっても、現実用途から離れた装飾品をつくったり、たくさんの意味を圧縮した「象徴」をつくったりすることはできなかった。無意識の支えがない言語では、詩的なものは生まれようがなかった。
無意識(夢)の世界では、時間も空間もごちゃまぜで、全体と部分がひとつながりになっている。そうした高次元的なリアリティが三次元的な論理のグリッドにぶつかるごとに、そこに圧縮や置きかえが起きて象徴や夢が出現する。「高次元の成り立ちをした流動的知性」こそがフロイトのいう「無意識」であり、それを特徴づけるのが「対称性の原理」だという。人類の「心」の基体となっている流動性知性=無意識から直接出現する、新しい知性の形態をつくりだす試みを筆者は「対称性人類学」と名づけた。
生と死、有と無を分離するアリストテレス以来の「非対称性の原理」をつきつめて科学も西洋哲学も発展した。対称性の原理はそれとは逆で、生も死も、未来も過去も、全体も部分も……すべてのものがすべてのものとつながりあう世界を構想している。それは「夢」や精神分裂症の形で出現する無意識の世界でもある。
対称性の原理は、現代社会では主流ではなくなり、芸術やエンタテイメントなどの領域での活動や心の病理としての扱いを受けることが多い。
だが、折口信夫は「人の知性には類化性能と別化性能という異なる傾向があり、自分は類化性能ばかりが異常に発達しているために古代人の思考がよくわかる」と言っていた。別化性能は「非対称性」の思考に、類化性能は「対称性」の思考に関係しているのは明らかだ。南方熊楠も強烈な対称性の人だった。生と死を分離して考えるのは妄想であり、生と死のあいだには同質性と対称性があると考えた。動物と植物のあいだでも対称性が存在すべきだと考え、動物と植物とがお互いの存在を行き来しているように見えた粘菌の研究に没頭した。
「贈与」と「交換」を「対称性と非対称性」に置きかえる考えも興味深い。贈与は、使用価値だけではなく、贈ることで得られる社会的信用や名誉、愛情などたくさんの価値を「圧縮」して、一つの贈り物に詰め込んでいる。一方の交換は、売り手と買い手の間に人格的関係は発生せず、むしろ、物と人、人と人とを分離する働きがある。「贈与の環が動くとき霊力が動く」という古い表現は、贈与によって社会全体に停滞を打ち破る動きが発生するという意味だが、交換ではこういうことはおきない。貨幣が行き渡ることで贈与の関係がいたるところで破壊され、贈与と交換のふたつのロジックのバランスが崩れてしまった。社会の主要な部分がすべて交換の原理で作動するようになったところで、資本主義が登場した。そこに現代の不幸の一端があるという。
一神教が出現したことで、「無意識と意識」といったバイロジックな均衡が壊されて、矢のような一方向の時間意識に突き動かされる「歴史」の感覚が蔓延した。
国家をもたない社会では、非対称性の論理と「時間と空間がひとつに溶け合う」対称性論理の働きとが結合し、人間の社会には権力の源泉はなく、人は簡単に無意識に入りこめた。ところが、王と国家への権力集中が進むにつれて権力が形而上学化し、無意識領域から「力の源泉」としての権威が奪われ、世界の表面から見えなくなってしまった。そして、王権の中から法律的・秩序維持的な側面だけが生き残り、王が現実の人間であることさえも不要になり、「主権者は国民である」という国民国家の考え方が生まれてきた。民主主義による国民国家は、「力」をめぐる形而上学化のなかで出現したものにすぎず、けっして普遍的な価値ではない、ということになる。
「一神教の神の出現」と、経済の領域におこった「資本主義の出現」と、政治権力の領域におこった「国家の出現」とは、深いつながりがある。それらによってつくられた一神教型資本主義社会こそがグローバリズムの正体だという。それに対するオルタナティブを提案できるのは、「対称性の思考」を追求し、堅固な哲学の体系にまで鍛え上げた仏教しかないと筆者は考える。
無意識(流動性知性)のなかにある「対称性の思考」は、人間の心を自然や宇宙と直接つなげることができる。そして、度を過ぎた功利的な行動をとろうとするたびに、部分は全体とつねに一致しているとする対称性の思考がストップをかけてきた。
仏教は、そうした対称性の思考に磨きをかけ、それを完成形にまで発達させようと試みており、「野生の思考のもっとも高度に洗練された形態」という。
だから仏教を宗教として見るべきではないと筆者は考える。人類の「心」の基体である無意識の働きを抑圧する一神教の宗教とちがい、仏教は、無意識(流動性知性)の働きを全面的に発達させ、世界を変えようとする思想だと位置づける。
===========
▽2 近現代の科学学資してきた思考の道具一式は、1万年前にはじまった新石器革命の時期に、ホモサピエンスの獲得した知的能力のなかにすべてが用意されていた。量子力学と分子生物学でさえ、3万年前の旧石器を用いていたころのホモサピエンスの脳に起こった革命的な変化が可能にした。
第一次の「形而上学革命」である一神教の成立がもたらした宗教は、新石器革命的な文明の大規模な否定や抑圧の上に成立している。その抑圧された「野生の思考」が、第二次の「形而上学革命」を通して、装いも新たに「科学」として復活をとげたのである。
▽22 科学の思考と神話の思考との間には、根本的な違いなどは存在しないようなのです。どちらの思考も二項操作を駆使して、世界を理解しようとしている。レヴィ・ストロース「化学的思考が現段階に達してはじめて、私たちは神話に何がこめられているか理解できるようになったのです。二項操作という考え方に慣れるまでは、私たちのほうがまったく盲目だったのです」
▽25 アリストテレス論理。一番重要なのは「矛盾律」
▽31 生と死の間には、もっとも深刻な非対称性がある、といっても言い過ぎではない。しかし、神話はそんな生と死のあいだにさえ、同質性と対称性を見出そうと努力する。「(殺した雄羊は)本当に死んだのではなく、家に帰るのですから。肉と毛皮をあなたはとりますが、本当の彼ら自身は家に帰るのです」
…科学は、生と死は分離されなければ、思考が動き出すことはできない。そのために科学は、死というものを全体性としてとらえることができない。死の現実のもつ表面的なことしか、扱うことができない。
▽36 神話の思考の二項操作は科学の思考が駆使しているのと基本的同じものですが、対称性の論理の方は神話的思考に特有のものです。
▽37 できあがった理論は、厳格な非対称性の論理にしたがって書かれることになるが、はじめてその考えがあらわれてくるときには、科学者の思考も対称性の論理によって動く無意識の領域に深く沈潜することがなければ、めったに画期的な発見など生まれてはきません。(夢で粘菌の生息場所を発見する熊楠〓)
▽40 現代の社会は三次元で構成された現実だけが、唯一の実在であると信じているために、高次元でのみ自由に動くことのできる対称性の論理そのものが、危険であったりいかがわしいものに見えるでしょう。しかし人類は3万年以上もの長いあいだ、自由な思考の動き回れるそういう高次元の実在を疑っていなかったのですから、私たちの社会が対称性の論理や高次元的なものにたいしてとっている否定的態度こそ、むしろ異常といえるのではないでしょうか。
▽43 象徴では意味の圧縮がおこなわれます。ひとつの表現の内部に、たくさんの意味が一度に詰め込まれているからです。…「夢の語法
が愛用する圧縮法とまったく同じやり方なのです。夢をとおして無意識が語ろうとしている内容は、高次元のなりたちをしています。これをイメージ化するために夢は、複数の意味が圧縮されたイメージをつくりだして、高次元な内容の「翻訳」をおこなっているのです。
▽49 イニシエーションの儀式を持った社会では、「全体と部分が一致する」という思考こそが、日常的な思考よりも明らかに「高級」なものとして扱われる傾向にあります。…量子力学を建設したハイゼンベルクのような科学者は「全体と部分が一致する」思考方法こそが、物質の神秘を解く鍵を握っていると主張していました。
▽51 神話の思考の特徴
1)対称性の論理を用いる。
2)高次元的なリアリティを表現しようとしている。そのためにイメージの圧縮や置き換えが頻繁におこなわれる。
3)全体と部分がひとつながりになるような思考法をとることが多い。
▽53 分裂症はカオスに見えるけれども、その背後に特有の「原理」にしたがう論理があることをマッテ・ブランコは見出すが、その原理は、フロイトが無意識の特徴としてとりだしたものと完全に一致していたのです。そこから、分裂症と呼ばれる精神現象は、無意識の活動が「生な形」で表面に浮上してくるときに現れる現象なのではないかと考えるようになったのです。
無意識の原理。「対称の原理」が適用されるとき、時間的継起はありえない。部分は全体とかならず同一になる。
▽58 神話の知恵と分裂症の妄想とが、深いレベルでの構造的一致を示している。
▽60 非対称性の思考が暴走をおこして、傲慢にふくれあがった知性の乱用が横行することに歯止めをかけ、自然と人間の関係に致命的な破壊がもたらされることを防いできたのは、ひとえに人びとの心に神話が生き続けていたからにほかなりません。神話はむしろ、人類に正気をもたらしてきたのです。その神話と同じように、無意識の働きにナイーブな通路を開いているにすぎない心の持ち主たちは、私たちの社会では病理の扱いを受けて、排除されるのです。
▽65 ネアンデルタール人は十分成長した状態で生まれ「子ども時代」がとても短い。ホモサピエンスの子どもは、長期間にわたって母親との、きわめて密着度の高い状態を経験することになります。フロイトの考えでは、この未熟状態の長く続くあいだに、私たちに特有の「無意識」の構造が発達することになります。
…ネアンデルタール人は、言語を使っていたが、現実用途から離れた装飾品を考案したり、たくさんの意味を圧縮して詰め込んだ「象徴」をつくったりすることをこの脳はしませんでした。
…無意識が豊かに発達するには、長い未熟期間が必要。ネアンデルタール人の子たちがすぐに大人に成長をとげてしまっているから、無意識発達に必要な未熟期間が十分になかったと考えられます。
…無意識に支えられていない言語には、詩的なるものは生まれようがない。
▽73 高次元的な無意識が三次元的な論理のグリッドにぶつかるたびごとに、そこに圧縮や置きかえをほどこされた「喩」や「象徴」が出現してくることになるわけです。
▽75 高次元の成り立ちをした流動的知性の活動は、たえまなく三次元的な構成をした通常の論理への「翻訳」がおこなわれていく。次元数を下げて、普通の思考にも理解しやすい形へ「翻訳」されるたびに、そこには圧縮や置き換えの現象が起きることになる。夢はそうやって製造される。
「高次元の成り立ちをした流動的知性」こそ、フロイトが「無意識」と呼んだもの。…現生人類とははじめて無意識を持ってこの地上に出現したヒトである、と定義することができるでしょう。現生人類の「心」の本質をかたちづくっているもの、それは無意識なのです。
…私たちの「心」にそののちつくられるすべての仕組みは、この無意識の基体を素材にしています。その意味では、この「高次元の流動的知性」を無意識と呼ぶことじたいが間違っているかもしれません。仏教のような思想伝統では、いっさいの心的現象の基体をなす「心そのもの=心性」と呼ばれる。
▽80 情報伝達系としての言語などは、すでにネアンデルタール人の知性として、単純ではあってもすでに完成の域に達していたはずです。流動的知性の生みだす無意識系が誕生することによって、ヒトのおこなう言語活動は根本的な変質を体験することになりました。
…非対称性の原理と対称性の原理とが一緒になって、人間の「心」をつくっているように見える。対称性の原理とは無意識の働きを特徴づけるものです。この原理は現代人の社会ではもはや主導的なものではなく、芸術やエンタテイメントの限られた領域での活動や心の病理としての扱いを受けることが多いのですが、現生人類の「心」の基体をつくるものとして、決定的な重要性をもっています。
▽90 折口信夫。人の知性には「類化性能」と「別化性能」という異なる傾向があり、自分は類化性能ばかりが異常に発達しているために、古代人の思考のことがよくわかるというようなことを弟子たちに語っていたようです。
あきらかに類化性能は「対称性」の思考に関係があり、別化性能「非対称性」の思考に深いつながりがります。
南方熊楠も、こと思考構造にかんする限り、強烈な対称性の人でした。
(〓熊楠も同じ。超人的な自然とのつながりを感じる勘のようなもの〓)
熊楠の考えでは、生と死を分離して考えるのは妄想であり、生と死のあいだには同質性と対称性があるはずなのでした。動物と植物のあいだでも対称性が存在していなければならないと熊楠は考えました。動物と植物とが自由におたがいの存在を行き来している、高次元の領域を発見できるにちがいないと信じて、粘菌の研究に没頭していました。
▽94 「贈与」と「交換」。歴史的には交換よりもずっと早くから出現した贈与は、本質的な点で対称性の原理と深く結びついています。贈与されるものの「価値」は、使用価値ばかりではなく、贈ることで得られる社会的信用とか、名誉とか、愛情とかたくさんの「価値」を「圧縮」して、一つの贈り物に詰め込もうとしている。「価値」は多次元的な性質をもつようになります。
点交換の場合は、売り手と買い手が交換をおこなっても、何の人格的関係も発生しません。交換は物と人、人と人とを分離する働きがあるわけです。「贈与の環が動くとき霊力が動く」という古い表現には、贈与物が移動をおこすとそれにつれて高次元的な流動する力まで動き始め、社会全体に停滞を打ち破る流動が発生するという感覚がこめられていたものですが、交換の場合はこういうことはおこりません。
…私たちの社会活動H、贈与と交換という二つの原理のバイロジック的な組み合わせとしてつくられています。…資本主義社会では、交換の原理が強くなりすぎて、社会全体でバイロジックがうまく作動しなくなっている−−このことが現代社会に重大な危機をつくりだしているのです。…社会の全域が交換の論理(非対称、物質的冨の増殖、アトム化された社会)だけで覆われてしまうと、そういう社会で不幸を味わうようになるでしょう。現生人類にとっての幸福は、無意識という心の基体が自由でリラックスしている状態と結びついているからです。
…現生人類の「心」に高次元な無意識が働きつづけているかぎり、バイロジックな社会でなければ幸せになれない、というのが厳然たる真理なのでしょう。
▽100 (無意識と意識)このバイロジックの状態に終止符を打ったのが、一神教の神の出現。この神は意識的な思考と一つにつながっていて…一神教が出現したことで、いろいろなレベルでのバイロジックな均衡が壊されて、矢のような一方向の向きをもった時間意識に突き動かされる「歴史」の感覚が、地球上に蔓延することとなりました。(マルクス主義も〓一神教)
…一神教や、一神教と結合した資本主義にたいして、私たちは、精霊の主張する対称性の思考の側に立った、誇り高い立場からの批判的解明を試みるべきです。
…「三位一体」の思考。キリスト教の神は正統教義では、「父」と「子」と「聖霊」の3つの位格をもつと主張されます。聖霊はスピリットの仲間です。高次元的で流動的、しかも対称性の論理で動く無意識の活動と直接的な結びつきをもつ、「心」の働きが示すものを「聖なるスピリット」と言いかえて、神の本質の一部に取り込んであるのです。
▽106 交換と贈与は、長いことバイロジックの関係を保ちつづけていました。ところが、交換の中から出現した貨幣が、社会の全域に行き渡るようになると、交換は贈与の関係をいたるところで破壊して、経済の領域での覇権を握ってしまうことになります。社会の重要な部分が、すべて交換の原理で作動するようになったところで、おもむろに資本主義が登場してきます。
▽112 「一神教の神の出現」と、経済の領域におこった貨幣経済の発展形態としての「資本主義の出現」と、政治権力の領域におこった「国家の出現」とは、不快内在的なつながりがあります。…キリスト教と産業資本主義と国民国家がひとつに結んで、強力な統一体をつくりだしたのです。
▽120 現生人類の「心」の基体をつくりなしている流動性知性=無意識の中から直接出現する、新しい知性の形態を創りだしていくこと。そのような試み自体を、「対称性人類学」と名づけようと思います。
かつては神話が、そのような対称的知性の一形態でした。そして、「構造人類学」がそのことをあきらかにするための、現代人の強力な知的武器となりました。私たちは今、その構造人類学の先に出ていこうとしています。(構造人類学の「次」を切り開く対称性人類学〓)
▽147 「グローバリズム」と呼ばれる一神教型資本主義にたいして、力強いオルタナティブを提案できるのは、仏教の思想だけかもしれないという気もします。対称性の思考がはらんでいる思想的な可能性をとことんまで展開し、それを堅固な哲学の体系にまで鍛え上げておいてくれた仏教の力を借りなければ、私たちはグローバリズムの大海を、向こう岸まで渡っていくことなどできません。
▽152 乱獲を抑える心理的ないし、思想的な歯止めがあり、…このような考え方の生まれ出る源泉を、私たちは「対称性の論理」または「対称性の思考」のうちに見出してきました。それは現生人類の「心」の本質をなす流動的知性の中から直接生まれ出て、神話的思考をとおして個人と社会に有効な働きかけをおこなっていました。そしてこの無意識(流動性知性)をとおして、人間の「心」は自然に、そして宇宙に直接つながっています。
▽155 功利的な目的を追求しようとするたびに、対称性の思考による倫理がストップをかけてきました。対称性の倫理にしたがえば、部分は全体とつねに一致していなければならないのですから、全体性のバランスを破壊する恐れのある個人的利益や功利主義的追求は、否定されなければならないからです。
▽156 仏教こそ、対称性の思考という原初の知性形態に磨きをかけて、それを完成形にまで発達させようと試みてきた、ほかに類例のない倫理思想だからです。
▽163 「仏教は野生の思考のもっとも高度に洗練された形態にほかならない」
…一神教の場合、野生の思考にたいする否定は徹底していたために、そこに発達した文明はどれも頑固な「非対称性」の特徴をおびることになりました。ところが仏教だけは、野生の思考と共通地盤に立つ対称性の思考の可能性を、最後の帰結にまで発達させるという試みに挑戦してきました。
▽165 仏教の考えでは、自己というものは実在していません。それは無限に広がりをもつ出来事の連鎖(縁起)のささやかな結節点に、つかの間のあいだ生じてくる「結び目」のようなものにほかなりません。…自己が実在しないのなら、他者や対象も実在しない。すべては広大な縁起の相互作用のうちに発生する泡の効果にほかなりません。
▽173 仏教が語っている思想は革命的。なのに、宗教化した仏教の生命は、現代においてはすっかり衰えてしまっています。 私たちは仏教を宗教として見ることを拒否しなければなりません。仏教はむしろ、私たちがこれから生みだそうとしている新しい対称性知性の、もっともすぐれた先行者とみなすべきです。
▽174 フロイトは宗教の本質は神経症にあると喝破していました。超越的で完全なる神を人間の外に立てることで、人間の「心」を脅迫神経症的な状態に追い込んでいくと。…一神教の宗教というのは、「心」の奥底におこっている原初的抑圧という根源的な出来事を重要視しました。その原初的抑圧にこそ人間の<徴>があると認めて、そこに彼らの神を置いた。こうラカンは考えた。
…仏教は宗教ではない。人類の「心」の基体である無意識の働きを抑圧するどころか、無意識の働きを全面的に発達させ、その働きを完成に近づけていこうとしているからです。
▽178 仏教は、」「原初的抑圧」の向こう側に広がる、流動的知性の働きの中に踏み込んで、その働きを全面的に開花させ、ふつうの論理で動いている世界にその働きを持ちこんで、世界を変えようとする思想。
▽180 華厳経
▽204 神話的思考を生みだしてきた無意識は、芸術・哲学・科学的創造・経済生活などにおいて、いぜんとして大きな働きをしている。
無意識は数万年前ホモサピエンスの脳組織におこった革命的な変化をきっかけにして形成され、私たちの「心」の基体をかたちづくってきた。このとき、分化された知性領域を横断する流動的知性が発生したのである。
流動的知性の作動は、フロイトの見出した「無意識」の働きと一致する。私たちの「心」の基体は、流動的知性=対称性無意識にほかならない。
流動的知性である無意識は、過去と未来が1つに融合して、神話的思考における「ドリーム・タイム」と同じ無時間的表現をつくりだしている。自己と他者の分離がおこなわれない。「心」の基体では、部分と全体が一致する。「心」は無限の広がりと深さをもつものと思考されるようになる。
▽206 私たちホモサピエンスの「心」は何を幸福と感じ、どんな幸福の実現をめざして努力を重ねるのか。私たちの「心」の基体をなす、流動的知性=対称性無意識は、どんな状態が自分のなかに実現されているとき、それを幸福と感じるのだろうか。
▽211 happiness bonheurの概念。日常的な時間意識をつくりだす交換と贈与のサイクルを引き裂く、垂直的ななにものかの侵入を意味します。過去・現在・未来という時間系列の外にあるものが、時間のサイクルに割り込んでくるときhappiness bonheurの状態が実現されます。時間系列の外にあるもの、すなわち対称性原理に属する何かが、非対称に進行していく時間の系列に、裂け目をつくりだすとき、幸福はやってくるわけです。(無意識との接触?〓)
▽213 happinessもbonheurも「幸福」も、時間的ないし空間的な反復を示す順調平凡な流れをいっとき破綻させて、そこから無限にかかわる力が人間の世界に流入してくる、という感覚が含まれています。限界づけられた世界を壊して、無限の領域に触れる−−そんな恐ろしい語感でさえ、そこには感じとることができます。
▽214 セックスをしているときにもたらされる感覚こそ、幸福感の原型であるように思える。「無限の愛」というように、幸福感のなかにある恋人たちは、自分たちのいま体験している状態が、際限もなくいつまでも続いていくような感覚に包まれるものです。この無限の感覚は、そのとき恋人たちの「心」が、対称性の原理に支配されていることを物語っています。
▽221性的体験も宗教的体験も、同じ対称性無意識を舞台としてあらわれる、よく似たタイプの二つの異なる悦楽の表れにほかならないのだ。無意識が自由に対称性の運動を楽しんでいるときに、「心」は言いしれぬ幸福感にひたされます。
▽225 アインシュタインの特殊相対性理論。無意識を動かしている対称性の原理をそのまま生かして、それを科学の非対称性の論理のなかで正確に表現する−−それが対称性人類学の視点からとらえた特殊相対性理論の本質ということにあんりますが、同時代の芸術家たちは、同じ主題をもっと感覚的なレベルで表現しようとしていました。キュビスムの表現にたどりつく前のピカソが、熱心に「高次元の数学」の研究に没頭していたことはよく知られています。…無意識に内在する知性の可能性がさまざまな方法で探究され、その産物として、芸術ではキュビスムと抽象絵画が、化学の理論としては相対性理論と量子論が生みだされたのでした。…アインシュタインは、科学的アイデアは自分の場合、言語的知性のレベルには浮かんでこないと断言しています。sれは視覚的で運動的な性質をもつ「自由意志的」な思考レベルで発生するというのが彼の考えですが、それは夢や音楽の生まれ出る、対称的無意識の活動している思考の空間にほかなりません。
…ロシア人のはじめた社会主義の実験も、少なくとも理念では「抑圧されない無意識」に基礎づけられた人格と対称性の社会の形成というものを、めざしていました。
▽234 よみがえる普遍経済学 ジョルジュ・バタイユの思想の「転倒」。経済活動の原点に「生産」ではなく「消費」をすえた。生産は利潤をつくりだし、その利潤を元にしてもっと生産を拡大していく、そのために生産がおこなわれているが、バタイユの考えでは、人類が生産のための生産をおこなうようになったのは、ごく最近のことで、それ以前の3万年を超える長い歴史の中では、むしろ生産がつくりだしたものを盛大に消費するために、生産はおこなわれていたというのです。
たしかに昔の人は、買う得した冨を、ただいたずらに貯め込んだりするのは悪であり…。
▽237 対称性無意識を突き動かしているのは、死の衝動なのです。流動的知性の働きそのものの中から超越性の思考が発生してくる様子。その超越性というものが、同時に死の衝動をはらんでいることが、はっきりと理解できます。バタイユはそれを「至高性」と名づけましたが…
▽246 ポトラッチの儀式では、気前のいい威厳のある首長の特権として、最大の価値物である紋章入りの銅板の破壊がおこなわれます。そのとき首長はこう言いたいのでしょう。この贈与の聖なる環を動かしているのは、こんな物質に表彰化されている冨への欲望なんかじゃない。贈与を動かしているのは、環の外にあって、どんな物質的な形にも表彰できない価値なのである。それが、人間に「崇高な価値」というものの概念を与えることのできる、唯一の権威なのである。
▽261 純粋贈与の概念は、極限状態でおこなわれる破壊や消費として、かすかな物質性がともなっていなければならない。超越神の絶無ではなく、超希薄な(無限小の希薄さ)物質性・現実性をそなえた概念、それが純粋贈与の概念なのです。
たしかにそれは天使とそっくりです。天使は、肉体をもたない不可視の存在であると言われていますから、質料的身体をともなわない聖霊の仲間であると考えられてします。しかし、いっぽうで天使は神の被造物であるとも言われています。つまり、天使は無ではないわけです
▽264 国家をもたない人々の社会では、「心」のマトリックスをかたちづくっている部分の働きが、社会の表面まで踊り出して、豊かな活動をおこなっていました。その一つの表現の形が神話や儀礼でした。非対称性の論理の働きと、「時間と空間がひとつに溶け合う」神話的な対称性論理の働きとが、バイロジックに結合した作動をおこなっていたために、人はいつでも簡単に、自分の「心」のマトリックスである無意識に入りこんでいくことができたのでした。
ところが、王の出現とともに国家というものがあらわれるようになると、このような無意識の領域から「力の源泉」としての権威が奪われt、世界の表面から見えなくなってしまう現象がおこりました。思考が生まれ出る大地である無意識のマトリックスなども、その見えなくなったもののうちの大きな存在でした。
▽274 人類最古の哲学とは神話であると考える、レヴィ=ストロースや私たちにとって、「形而上学は哲学の最初のものである」という考えは、自明なことではありません。仏教の伝統を見れば、哲学的思考に形而上学とは別の可能性が開かれていたことは、まぎれもない事実です。
▽276 対称性知性の領域が「無意識」として抑圧されるとき、そこには「多神教」の特徴を持つ宗教的思考が生まれるようになります。…しかし多神教の社会では、まだ原初的抑圧の「壁」は薄い膜状の構造をしているために、対称性の論理で作動している「無意識」の領域と、非対称性の論理で作動している現実の世界とのあいだには、たくさんの空孔がありました。
…そこから、原初的抑圧の壁を自由に行き来できる聖霊や天使のような存在についての、生き生きとしたイメージが保たれていました。…流動的知性を「無意識」につくりかえていく形而上学化への道の一歩が、すでに踏み出されているとはいえ、その抑圧の壁はまだ薄かったので、原初的抑圧の壁をとおして、ふたつの壁をとおして、ふたつの違うタイプの「心」の作動は、媒介的なバイロジック結合を維持していることができたわけです。
…多神教の世界では、流動的知性=対称性無意識の働きそのものを、神話や図像として表現しようと試みていました。
…モーゼの前に出現した「ヤーヴェ」という名前だけを持つその神は、無意識の作動の図像化を禁じます。自分については名前だけを教えます。対称性無意識を言葉の論理によって抑圧する「原初的抑圧」を、神聖な輝きで包み込むことでした。この神は「ヤーヴェ」という名前だけがあって、ほかのいっさいの感覚的要素はない、と断言することによって、自分はあらゆるシニフィアンがそこから生まれて出てくることになる「純粋シニフィアン」であると語っているわけです。
…「革命」の影響は拡大して、いまや地球上の人類全体の思考を「形而上学化」して、ついには今日のような科学と経済のグローバルな秩序をつくりだすにいたったわけです。
▽280 宗教的思考の領域におこったことと、まったく「同型」のプロセスが国家とその権力の領域でもおこっています。「熊から王へ」。人間の社会の首長は、権力などというものは与えられておらず、もめ事を調停し、人々の暮らしに平和をもたらすような働きをしていました。つまり、人間の社会には権力の源泉がなかった。
「王」という存在の出現が、そういう状態に決定的な変化をもたらします。
近代がはじまるまでの長い期間、自然の内包する神秘性にたいする感受性は、人の心から消え失せることがありませんでした。王権そのものが一種の「両義性」を帯びることになりました。
…ところがヨーロッパに「近代」の萌芽があらわれはじめたころ、いちばんの標的になったのが、権力の集中点であり体現者であった王のもつ両義性だった。近代は一神教が開始した「形而上学革命」の継承者として、科学的合理性を武器として、こんどは「権力概念」の徹底的な形而上学化を推し進めようとします。…王権に秘められた両義性やトリックスター性そのものが、否定され、その結果、国家権力を成り立たせた原初的抑圧の機能そのものがさらに抑圧をうけて、社会の表面から見えなくなるのです。そして、王権の中からは法律的・秩序維持的な側面だけが生き残ることになります。そうなると、王が現実の人間であることさえ、この権力の形而上学化の運動にとっては、不必要なもの、存在するだけで迷惑なものとなっていくことになります。
王の権力は「法人」である、という解釈が登場し、そうなれば王などは必要なくなってしまうので、「主権者は国民である」という国民国家の考え方が生まれてくるのも時間の問題でしょう。かつては熊のような偉大な自然の王の持ち物であった「力の源泉」は、王の手に渡って国家の権力に姿を変え、ついには国民の所有に帰したのです。
…民主主義による国民国家は、けっして人類の「自然史」から生みだされたものではなく、「力」をめぐる形而上学化の運動の果てに出現した。、権力形態のひとつにほかなりません。それは「形而上学の変遷」にしたがって、別の形態に変容しうるものなのです。
…フロイトはそういう抑圧がおこっている場合には、人は必ず悪夢を見るようになると語っている…形而上学化された世界は、私たちに悪夢を見させつづけるのです。このようなとき仏教は、原初的抑圧の機構そのものを解除するための方法を探るようにと、教えています。…私たちの世界が、権力のもたらす悪夢から本当に目覚めるときがくるとしたら、「自然=神」の象徴であるあの熊が、形を変えて、未来の世界にもどってくることになるでしょう。
▽285 資本主義という経済システムをなりたたせている機構もまた、一神教や国家の成り立ちと「同型」を示すのです。贈与→交換。贈与や消尽の原理によって動いていた普遍経済的社会が、蓄積と拡大生産への欲望によって突き動かされる資本主義的な限定経済の社会につくりかえられていく過程で、どのようなことが起きるのか。
▽288 古代社会に置いて、「無」に方向づけられた純粋贈与の概念を、大切に守って、伸びやかな贈与の精神をもって、社会とつきあっていこうとしていました。対称性の論理に基づく社会関係を重視していたのです。
そういう社会では、自分が獲得した富を、自分のために蓄積し、自分のためだけに消費しようとする「勤勉で賢くてわけても倹約なえり抜き」を警戒した。
…対称性の論理によって突き動かされる贈与の原理と、それを支えていた純粋贈与という経済生活の「理想」が抑圧された。
…贈与経済で動いていた社会において、富をめぐる思考を形而上学化して、そのなかから資本主義を出現させた。国家や科学が生まれるのと同型のプロセス。
「一神教」と「国民国家」と「資本主義」と「科学」(形而上学の形態として「同型」をしめす)。これらが有機的に結合できる条件を備えていたのは、西ヨーロッパをおいてはほかにはありませんでした。社会生活のすべての領域で、数百年をかけて「形而上学革命」をとことんまでなしとげていたので、こういうことが可能になったのです。
…「同型」による支配が全面化されていくことーーこれがグローバリズムの正体なのだと思います。形而上学化へ向かおうとする因子が「心」にセットしてある。その因子の危険性を昔の人間は知っていたので、全面的に発動するのを、対称性の原理を社会の広範囲で作動させることによって防いできました。それを最初に飛ばしたのが、一神教の成立だったのです。
▽294 仏教の例を見てもわかるように、対称性無意識の働きを抑圧したり、形而上学化することなしに、その能力を全面的に発達させていくことのできる文明を構想することは、けっしてユートピア的な夢想なのではありません。私たちの「心」の基体は、すべてのものを商品化していく資本主義によっても、無意識の大規模な抑圧の上に建築されたキリスト教的一神教によっても、満足を得ることがありません。


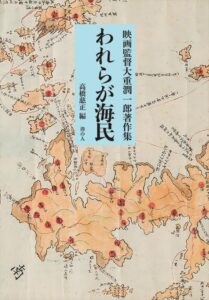

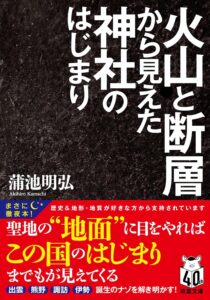

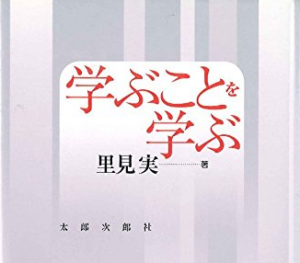

コメント