■熊楠の星の時間<中沢新一>講談社 20160602
思考が真の天才の火花を散らし、人生が星の輝きに包れる「星の時間」は、熊楠ほどの天才でも、那智の山ですごした数カ月だけだった。この時期に、現代科学や哲学をも凌駕する思想が手紙の形で表現されたという。
近代を形成する基礎となったロゴスは、①同一律(AはAである)②矛盾律(Pであり非Pであることはない)③排中律(PであるかPでないかのいずれかであること)という3つの法則に従う。同一律はカント、矛盾律はヘーゲルによって取り除かれた。だが粘菌はこのふたつだけでなく、③の排中律も破っているという。生と死は分離されず、植物であり動物でもある。粘菌を通して熊楠は、ロゴスを拡張した別種の論理がなければ生物現象はとらえられないと考えた。その論理が、大乗仏教が発達させた「レンマの論理」であるという。
事物を目の前に並べる知性作用であるロゴスは、言語と本性を共有している。これに対してレンマは、ものごとを抽象的に理解するのではなく、具体的に直感的に理解することを意味する。
仏教は、ロゴスの3原則を知的構成物として否定し、事物をレンマ的な直観でとらえようとする。存在と非存在、非連続と連続といった区別を否定し、不生不滅、不断不常…が現象の真のあり方だとする。
日本における華厳経の中興の祖である明恵上人は浄土宗の念仏を批判した。明恵にとって仏教は、世界という「大不思議」に踏み込むめの方法を与えてくれる実践的な学問なのに、念仏はその学問を宗教に作りかえてしまうからだった。その批判の論理は、熊楠の近代科学批判の論理構造と似ていた。
近代生物学では、あらゆる生物が植物界と動物界のいずれに属し、生物に関しては、現象界は象徴界(動植物という二分法)で把握できると考えた。
だが粘菌は、動物と植物がまざりあい、生きていながら死んでいる。「動植物」「生死」という象徴界の分類では把握しきれない。そこで、こうした粘菌を説明できるような象徴界での対応物(理論)を熊楠は求め、そのヒントを華厳経のなかに見出した。
「自然状態にある知性」は現実のなかで分離しているように見える事物の間に、隠されたつながりを発見し、世界が一つの全体として変化していくと理解する。これを熊楠は「マンダラ」と呼び、因果律に拘束される自然科学の思考法に対置させた。
日本の農民たちは、人間と人にあらざるものが渾然一体となっている「里山」や、「自然」と「文化」の相即相入する「庭」をつくりだしてきた。こうした相即相入が起こるには、すべての個別的存在が根源的なナニカとつながる場(法界)を考えないといけない。これはロゴスではなくレンマの論理ではじめて把握できるのだという。
以上のような熊楠の思想が実践面で現れたのが神社合祀だった。
神仏分離で、神社内部から仏教的な要素が排除され、修験道の山伏は神官にならされた。当初は経済的な苦境に陥った神官たちが「神社整理」を推進し、後に政府が旗を振って合祀を進めた。これによる神社数の激減で、森や樹木が切り倒された。
明治政府は当初、神道を国教化しようと考えたが、諸外国の反対で断念した。そこで、神道は民族の道徳だという考えが出てきた。だが、多くの祠には、道徳に合致しない、エロチックな道祖神のような神々も祀られていた。合祀運動は、明治の近代神道の矛盾から発生したものでもあった。
従来の神道は、道徳を超えた、人間的価値の外にある自然に開かれていた。ところが「神社整理」以後の神道は、「人間ならざるもの」の領域につながる要素を隠してしまった。神道は自らを道徳化することで、人間世界の外に広がる自然の領域に触れようとしない、貧しい宗教になってしまった。
廃止された神社の土地は売却され、聖地だったアジールにカネが侵入し、自然力を経済や軍事の力につくりかえていく過程がこののち一気に進行した。
伊勢が「神々の国」と呼ばれたのは、おびただしい数の神々を祀る小社が存在したからだが、神社合祀運動によって87%が壊滅してしまった。海岸部のエビス神は、道徳を涵養するものではないと判断され、漁民の多い和歌山などでは全滅に近い状態になり、農村部の大きな神社だけが残された。以来、漁民は農民の祭りへの参加を拒むようになり、長年の相互関係にひびが入ってしまった。
熊楠は自然環境悪化を語るだけでなく、人びとが築いてきた互酬関係や相互扶助ネットワークが破壊されることも合祀反対の根拠としていた。フェリックス・ガタリの提唱した三つのエコロジー(「自然のエコロジー」「社会のエコロジー」「精神のエコロジー」)という概念ととてもよく似た考え方だった。
============================
▽23 チベットの僧院でも「素読」から学問が開始される。習熟すると、どんな経典があらわれてもすらすら読み通すことだけはできるようになる。文字列のなかに「息」を吹き込んで、意味を立ち上がらせる行為。
▽ 事物を集合させて目の前に並べる知性作用であるロゴスは、言語と本性を共有している。
これに対してレンマのほうは、「手でつかむ」「とらえる」「把握する」などという語源から生まれた概念で、ものごとを抽象的に理解するのではなく、具体的に直感的に理解することを意味する。
…レンマの学を打ち立てたのは仏教だった。仏教ではロゴスお3原則を知的な構成物として否定し、あくまでも世界の事物をレンマ的な直観でとらえようとした。存在と非存在、非連続と連続、一と多様…を否定し、不生不滅、不断不常…が現象の真のあり方だと主張した。
…夢のなかで、難問題が突然解かれることがあるのは、夢がレンマ的知性作用に通路を開いてくれるから。多くの「東洋の学問」では、こういう夢の働きが重視されています。
…華厳経。同時代におこった天台宗のように、特定の経典だけを重視するという考えをとらない。曼荼羅の姿をした法界の全体性が重視された。
そのせいか、世の中が一言論的な思考を好みはじめる古代末期から中世になると、華厳経はふるわなくなる。そういう時代に高山寺の明恵が登場して、華厳教学の復興に取り組んだ。(親鸞の本に出てくる?〓)
▽34 明恵は仏教思想は全体性の把握を本質とすると考えたが、熊楠もまた森羅万象の全体性をとらえうる学問を夢見て、華厳経のなかに偉大な先行者を見出していた。
▽38 明治時代の知識人たちは親鸞の思想に強く惹かれた。カントやヘーゲルなどの近代思想と構造的な共通点を多くもっていた。
…明恵にとっての浄土宗の問題は、熊楠にとっての近代科学の方法論の問題だった。明恵の念仏批判の論理構造は、熊楠の近代科学批判の論理構造と驚くほどよく似ている。明恵にとって仏教は、世界という「大不思議」に踏み込んでいくための確実な方法を、人間にあたえてくれる実践的な学問をいみしていた。念仏はその学問を宗教に作りかえてしまう。それゆえに明恵は法然に反対した。
□アクティビスと南方熊楠
▽53 「神社合祀反対運動」の本質とは?
神仏分離で多くの神宮寺が破却され、神社内部から仏教的な要素の徹底的な排除がおこなわれた。神仏習合の修験道では、山伏たちは仏教を捨てて神官にナルコとを強制された。神社合祀による神社数の激減にともなって、森や樹木が切り倒され、売却されていった。
▽55 幕末の国学者たちは、神仏習合では、日本の自生的な思想である神道と、インドで発生し中国で発達した仏教という外来思想が、ごちゃまぜになっていることを憎んだ。そこで、幕末の水戸藩では、神道と仏教を分離する過激な運動が繰り広げられた。廃仏毀釈。
維新後は、この運動が全国に波及した。村の者が寄り集まって寺へ押しかけ、仏像を破壊したり装飾品にいなおしたり。権力になびきやすい日本人の性質。破壊をまぬがれた仏像仏具の多くが、海外に流出した。
▽57 日本人の心を均質化して強化するため、道徳教化をを進めようとした。神道をキリスト教のような宗教につくりかえようとした。
▽58 明治政府は初期は神社に補助金を与えて手厚く保護しようと考えたが、諸外国からの反対でできなくなると、神社への補助金も打ち切られるようになる。…かつては村人が自ら管理し祭りをしていたが、明治になって神道の価値が称揚されると、神社の神主は村の小さな祠まで責任を負うようになった。信仰心が薄まり、神主への謝礼の額も減り、神官の生活はますます困窮していった。
神道を国教にするのは難しいことがわかり、神道は宗教ではなく民族の道徳だという考えが出てきた。
鎮守の神社だけでなく、大小さまざまな祠が存在し、そのなかには、国民道徳を養うとは思えない神々が、数多く祀られていた。合祀運動は、明治の近代神道の矛盾から発生してきたものであり、それを推進したのは、責任の重圧に苦しんでいた神官たちだった。
▽64 道祖神は淫祀の典型。甲信越のどんな村でも、小字ごとにさまざまな意匠の道祖神がまつられ…エロチックな道祖神像前で、子どもたちが中心になって、わいせつな唱え言を合唱しました。先生も黙認せざるをえなかった。
▽67 エリートたちは、神道は道徳の最高形態であり、…と考えた。鎮守の森の神社こそが村の中心とならねばならない、と。大きな神社には国の扶助が出たが、小さな神社や淫祀邪教の祠などには出ない。そうなると合祀しようという発想が自然に生まれる。
この運動は神道界からの要請ではじまった。官民を巻き込んだ運動は、近代日本における最大の「文化大革命」であったといえる。
…廃止された神社の土地権利は「一社」の管理に委譲され、伐採の権利も神主にゆだねられる。多くの神社が率先して森の破壊に乗り出した。
▽69 明治35年から神社界が「神社整理」をはじめた。神官の経済的立場は改善されたが、神道は内面的な変質をとげた。それまでは道徳の側面を持ちつつも、道徳を超えた価値、すなわち人間的価値の外に広がる自然と宇宙に開かれた価値に通路を開いていた。ところがこれ以後の神道は、「人間ならざるもの」の領域につながっていく要素を隠してしまう傾向を持つようになる。人間世界の外に広がる自然の領域に触れていない神道という、空恐ろしいほどに貧しい神道が生まれてくることになる。神道という日本人の自然宗教の命は、自然との強い結びつきのうちにある。みずからを道徳化することで、当時の神道は自殺行為をおこなったともいえる。
…伝統的神道が保っていた宇宙的な全体性を分解して、秩序と道徳の機能だけを残して、神道の一翼をかたちづくってきた非人間領域への通路を破壊してしまった。
…非人間の領域と結ばれているものは、村や町の中心にはいない。端っこにいて、境界の外からやってくる諸力を受けとめ、自分が変換装置になって…人間世界の内部で活用できる「和の力」とする。その重要な境界の変換装置を破壊してしまった(道祖神や庚申さんなどは境界にある?〓折口信夫のまれびと)
…更地になった土地の売却が進む。それまでお金の侵入できなかった神社の森のアジールに、お金の力が侵入を果たし、自然力を経済や軍事の力につくりかえていく過程がこののち一気に進行した。(〓カネがすべてを巻き込む社会に)
…コミュニティの中心にある神社と、自然に開かれた境界の社とのちがい。
…「神社整理」は神道界からの「下からの運動」だが、「神社合祀」は国家が旗振りする「上からの運動」。…なかでもひどかったのが三重県。敬虔な人びとの多く暮らす地帯で、少し道を行けば小さな社や祠をたくさん見かける土地柄だった。伊勢が「神々の国」と呼ばれたのは、伊勢神宮があるというだけではなく、おびただしい数の神々を祀る小社が存在していたから。合祀運動によってそのうちの87%が壊滅してしまった。
▽74 合祀を定めた勅令によると、神社は境内が150坪以上なければならず、本殿・拝殿・鳥居などを完備して、氏子が50戸以上なければならない。はじめは相手にされなかったが、明治40年に入ると、にわかに激しくなる(和歌山で)。
…熊楠の「南方二書」が全国に配布され、反響を巻き起こし、ついには内務省も「神社合祀は強制ではない」という訓示を出すに至った。明治45年に入ると嘘のように沈静化した。
▽78 海岸部のエビス神様は、道徳を涵養するものではないと判断されることが多く、漁民の多い和歌山などでは全滅に近い状態に追い込まれた。農村部の大きな神社だけが残された。以来、漁民は農民の祭りに参加を拒むようになり、和気あいあいとつづけられていた相互関係にひびが入ってしまった。=合祀は村民の融和を妨げる(〓漁民の信仰が消え、農民化する?)
…合祀は地方衰退の原因になる。…合祀は村民の慰安を奪い…。
神社の本質は建造物ではなく、森林にあるというのが熊楠の考えだった。森は神社の付属物ではなく、森が神社の本体。
…「平成の大合併」によって多くの地名が消え、それといっしょに土地にまつわる伝承記憶が失われていった。まさに熊楠の言うとおり。
▽84 三つのエコロジー 「自然のエコロジー」「社会のエコロジー」「精神のエコロジー」(フェリックス・ガタリ〓が提出した概念)ガタリと熊楠の思想は驚くほどよく似ている。
〓熊楠は自然環境悪化を語るだけでなく、人びとが築いてきた互酬関係や相互扶助ネットワークが破壊されてしまうことを論じている。これはガタリの「社会のエコロジー」。
□南方熊楠のシントム
▽95 柳田国男と折口信夫。「民俗」の概念が通用する上限を室町時代に設定する柳田国男や、弥生時代後期に「古代」の概念の出発点ないし上限を据える折口信夫とコントラスとなしている。3人とも「日本民俗学の父」と呼ばれながら、熊楠の思考法には上限も下限もない。いっさいのものが土台を持たない深見のなかにつながっていくという、特異性を持っている。
▽シントム(症候) ラカンが見出した概念。
▽110 古代のお通夜は、昔話と謎解きをする一種の祭りでした。近い親族が泣いている横で、酒盛りの宴会が開かれる。…人が亡くなると、共同体を結びつけていた象徴界の輪がひとつはずれてしまう。共同体は危険なシンプトムを示す。その空隙を埋めるために、生と死、笑いと悲しみなどのあらゆる相反した価値の同居する、矛盾にみちたお通夜の空間をつくりあげ、それを共同体のシントムとする。輪の外れた危険な時間には、このゆおなシントムがどうしても必要。
▽112 夢のなかで発見する。体験する
…現実化した事実だけを集めて因果関係を示してみせたとしても、それは不完全な世界理解しかもたらさない、というのが熊楠の考え。事物や記号はいったん潜在空間にダイビングしていく見えない回路を介して、お互い関連しあっている。潜在空間ではあらゆるものが自由な結合を行う可能性を持って流動している。
▽115 熊楠の文章はアブノーマル。真面目な話と猥談が共存し、抽象的な話題はやおら下半身的な身体論につながる。難しい論理と快楽が一体になっている。
文章そのものが、多次元的・重層的に伸び広がっていく自らの思考を、言語の線形構造に無理矢理合わそうととして難儀している様を示しているようにも見える。
文章自体が、彼の心の症状のシントムなのです。
…モーツァルトは、作曲する前に曲がいちどに全部頭の中に現れると自分で書いている。曲全体がかたまりになって一つの和音として聞こえてくる。作曲とは、その一つの和音のかたまりのなかから、時間軸に沿って展開していく紐のようなメロディの線を引っ張り出し…というやっかいな「仕事」にすぎなかった。
▽118 トーテミズム=想像界のシントム
熊楠という名は彼にとって特別な意味をもっていた。
…神話に古代人の社会思想や王権思想を見出そうとする人びとと異なり、熊楠は神話が人間と「自然」をつなぐ働きを持っていることに興味を抱いていた。
…その世界で、想像界を拡張し補填するシントムをつぎつぎと発見して自ら楽しんでいた。
「南方民俗学」とは、熊楠が想像界に補填した巨大なシントムの集積体と私は考える。
▽124 粘菌=現実界のシントム
生命はもともと現実界に属する現象で、人間的な心がその上に形成されるところの想像界にも、その想像界を言語で組織化したところの象徴界にもおさまることのない本質を持っている。その生命現象に対して、人間は「分類」をほどこし、象徴界の秩序におさめようとする。近代生物学が発達するころには、あらゆる生物が植物界と動物界に二大分類され、どちらかのカテゴリーに属しているものと考えられるようになってきた。生物に関しては、現象界は象徴界でで押さえられると考えられた。(界を3つにわけることで、限界を見えやすくする〓)
…生命現象を捕獲するには、拡張された象徴界が必要。象徴界の輪が外れてしまった場所を埋めて、現実界との絡み合いをとりもどすことができる存在。それが熊楠にとっての粘菌という生物。粘菌は生物分類の秩序を混乱させる「シンプトム(症候)」。そのシンプトムを創造的なシントムに転換するとき、破綻した象徴界は自らを拡張することによって、現実界トトの絡み合いを回復できるだろう。粘菌は熊楠にとって、生物学上の「シントム」だった。
…熊楠には、★想像界におけるトーテミズムの主体や★現実界における粘菌にかみ合うことのできる、象徴界での対応物を探し出す、という課題が残された。(それが華厳経)
▽134 物質界の「縁」の構造を探る最初の量子力学。華厳経は驚くほどそれとよく似た考え方で、物質界と心界をつなぐ複雑な「縁」の様相をとらえようとしている。その中に熊楠は、将来の科学の形でもある「来たるべき象徴界の体系」を見てとろうとした。
…現代、人間を人間たらしめている想像界や「自然」そのものであるところの現象界から、科学という象徴界の秩序の乖離していく現象が進んでいる。計座員の領域でも。象徴界から出現した貨幣という存在が、科学や自然環境を脅かしている。
▽137 遊戯の原型は賭博にあり、さらにその原型は占いにある。その基本は象徴界にいかにして「偶然」を導入するかにかかっている。賭博もまた、象徴界への偶然の取り入れの試みと考えられる。
□二つの「自然」
▽フランスの人類学者フィリップ・デスコラ氏。
▽142 インドや中国の仏教では「人間」と「人間ならざるもの」という対立軸によって存在者を分類するのではなく「有情=意識をもったもの」と「非常=意識のないもの」という対立軸にそって、存在者を分類する。動物は有情だが植物は「非常」に分類され、ベジタリアンの主張に根拠を与える。
ところがこのような仏教思想が日本に入ると、境界線を自然の領域へと大きく拡大していく試みがなされる。東北地方の山にはしばしば「草木塔」がある。きこりたちは樹木も有情の一員と考え、慰霊をおこなったいた。
▽144 「人間」と「人間ならざるもの」との間に、連続と分離が両立できるシステムを「里山」としてつくりだそうとしてきた。
▽146 自然と文化を分離して、人間だけの思考や人為的プログラムだけでつくられる新しい世界に根強く抵抗しながら、見事な創造をおこなった芸術家や哲学者。夏目漱石や柳田国男や西田幾多郎ら。今日でもなお高い価値を持った思索を残したといえるのは、近代においては実はこの人たちだけ。
▽147 仏教は世界のなりたちを「縁(relation)」としてとらえる。存在しているものも、非存在のものもすべては縁によってつながっているから、そこには実体がないという仏教の考え方からすると、人間の外にある自然を「自然」という自律的な実体として認めてしまうことは許されないことだった。
ところが中国の道教は、人間の外に客観的に存在する自然と、概念作用によらない「自由な状態にある心」という二つの意味を含んでいた。中国の思想的伝統では、「外的自然」と「脳内自然」という二系列の「自然」を同一のスキームのなかで思考することが可能になる。
日本人は中国仏教によって創造的に変形された「自然」の概念を受け取り、利用してきた。
…江戸時代には「自然」と「文化」の相互貫入を表現することが文学の使命と考えられた。「外的自然」と「脳内自然」との共鳴。(古池や…)
▽152 「自然状態にある知性」は現実のなかで分離されているように見える事物の間に、隠されたつながりがあるのを発見する。世界が一つの全体として変化していく様子が理解される。どこにも中心がなく、あらゆるものが「対称性」の関係を保ちながら運動をつづけている。これを熊楠は「マンダラ」と呼んで、因果律に拘束されている自然科学の思考法に対置させた。
▽154 日本文化は「自然」を双対としてとらえてきた。いっぽうには「文化」や「人為」に対立する「自然」があり、もういっぽうに、「自然の奥にあるもう一つの自然」であり、後者の「自然」は人間の脳内活動をとおして出現する。二つの自然が「文化」に相即相入する状態を、生活と芸術の形に実現しようとしてきた。
「庭」。前者の「自然」の概念からは農民たちによって「里山」という生産の場所である「庭」がつくりだされてきた。後者の「自然」からは、職人によって、高度な芸術品であり哲学の表現でもある非生産的な山水空間としての「庭」が創造された。双方とも、それぞれのやり方で「自然」と「文化」の相即相入するハイブリッドとしての構造では共通している。
…日本を訪れたレヴィ・ストロース氏は、日本を「現代文明と神話思考のたぐいまれな結合が果たされている国」と。
□海辺の森のバロック
▽165 哺乳動物の胎児。「魚期」の段階の胎児の形に似せて、縄文の勾玉はつくられていた。エラを示す切れ込みも。
…真脇遺跡の木柱列 私は、この木柱列は象徴的な「子宮」を表現しようとした者に違いないと考える。
海辺に立つと思考が特別に敏感な活動をはじめる。感覚がとらえている「自然の圏」が「思考の圏」のなかに、ほぼ忠実に情報を運び込んでいる。感覚の捉えた構造を忠実な関手の働きによって「思考の圏」の内部に運び込み、そこで疑似同型のの構造を持つ表現につくりかえるというやりかたで、感性と思考が同時に「海辺」の本質をとらえようとしている。(〓海辺に哲学が生まれるということ)
…海辺に立った人間は、豊穣な感覚と感動をおぼえることになる。まるで自分が自然と一体になったように感じる。「思考の圏」と「自然の圏」とが同じ型に近づいている現象。=野生の科学は、「思考の圏」を「自然の圏」と同型に変形していくことによって、化学的思考に柔軟性と力強さを回復していくことをめざしてる。
▽174 漁民が神島の森林伐採に猛反対したのは、その島がとりわけ豊かな「魚つき林」であったから。「魚は緑が好きやから」。…農民にも海岸の森林が大切だったため、南紀あたりでは農民が漁師と一緒になって、森を守ろうとした。神社合祀に反対する熊楠の活動は、そういう漁師や農民たちの古くからの「知恵」にも支えられていた。
▽181 事物のなかに相即相入が起こるためには、事物がそれ自身「レンマ構造」をしている必要がある。…すべての生命現象の奥にセットされたレンマ構造を、むきだしの形に可視化している生物として粘菌に注目した。
…すべての個別的存在が根源的な一心と相即する場としての法界。これはレンマの論理でなければ把握できない。
…個物それぞれがすべての他の個物の一々と相即し、お互いの間にあらゆる分割線もなくなる法界。
□あとがき
▽185 私のなかでますます重要性を増していったのは、生きた哲学的概念としての粘菌と、その粘菌と概念として同一構造を持つレンマの法則、そしてそのレンマの法則に基づいて巨大な宇宙を構築した華厳経の存在。本書では、粘菌、華厳経、レンマという3つの視点から熊楠の思想をあらためて問い直す試みをした。



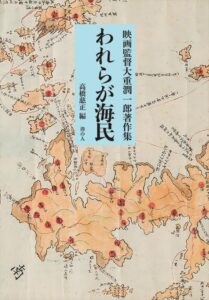

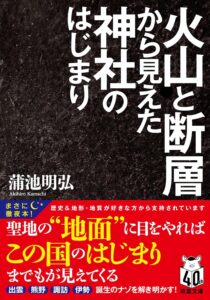


コメント