■エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグアを知るための45章 <田中高編著> 明石書店 20100912
3カ国の歴史や現状を知るのにぴったり。政治・経済から文化まで簡潔にまとめられている。
==================
▽19 エルサルバドルは自然林がほとんど残存しない。森林は国土の10%を占めるがその8割は植林。
□エルサルバドル
▽22 イサルコ山 コアテペケ湖は保養地。セロベルデ(2030メートル)の頂上からの眺望がよい。頂上近くにホテル。
マヤ時代はカカオの産地だった。ピピルの伝統も残る。
▽28 1932の虐殺。エルサル西部はピピルという先住民族文化が残っていた。ピピルの風貌をもつ農民が無差別殺害された。80年代の内戦中左派ゲリラが西部で活発でなかったのは、32年の虐殺の恐怖心があまりに大きかったせいという指摘もある。
▽34 コーヒー価格下落で、輸出の4%を占めるだけに衰退。40-50年代は80%、80年代でも50%以上だった。
▽36 「14家族」と呼ばれる支配層の起源は、コーヒー生産だった。バナナ生産とその輸出が、多国籍アグリビジネスの手で独占的に行われたことと比較すると、一部の富裕層に集中したとはいえ、コーヒーは国内資本家の形成につながった。……アグリビジネスではホンジュラスでは、金融機関はもちろん、政党活動さえ影響下においた。バナナは外国資本でコーヒーは自国資本。エルサルは大西洋岸に面していないため、輸出向けバナナ生産は皆無。
▽43 14家族は単なる俗説。Eduardo Colindres 1977年にUCAから「エルサルバドルのブルジョアジーの経済的基盤」 富裕層の実態について詳細に調査・分析。
▽45 クリスティアーニ家はイタリア系移民。大地主リストでは4455ヘクタールを所有して9番目。(80年代に大規模な農地改革があり、現在は極端な大地主は存在しない)
▽47 富裕層を代表するヒル一族 1997年に巨額不正流用。富裕層の苦境を象徴。
▽49 軍事政権長期化。だが、任期をまっとうする大統領は数えるほど。軍事政権による権威主義の3類型。軍部官僚型、軍部派閥型、個人独裁型。エルサルは軍部派閥型。パトロン・クライアント関係(擬制的な親族関係を媒介とする温情的な主従関係)にもとづく派閥を形成。
政権交代の循環。権力集中→国民の不満と弾圧→軍内部の進歩派台頭→クーデター→改革案発表→保守派台頭→クーデター
▽57 FMLN……1989年11月には大攻勢。市内各地にゲリラが自由に闊歩し、市街戦を展開し2000人が犠牲に。このときUCAに政府軍部隊が入り、神父ら6人を殺害した。これが和平合意の間接的なきっかけになった。それまでは軍部は、軍の削減や機構の再編にはかたくなだったが、UCA事件によって譲歩せざるをえないところまで追い込まれた。
▽65 経済を下支えしているのは、アメリカにいるサルバドル人からの送金。年間20億ドル。この金額は輸出額と輸入額の差額(赤字幅)と見合っている。
▽68 大戦後の日本企業の最初の工場進出先はエルサルバドル。呉羽紡績(66年に東洋紡と合併)が1955年に合弁会社設立。ユサ社(Industrias Unidas)。内戦時代も乗り越える。
▽71 平生三郎(ヒラオサブロー) サブロー・ヒラオ公園 日本庭園がある。
▽77 東部地域は貧しい。産業がない。ラウニオン港を大規模に整備しなおす取り組みに日本が重要な役割。円借款。03年から港の整備スタート。06年から操業開始。
▽81 ホヤ・デ・セレン 世界遺産に。サンサルバドル北西35キロ。火山噴火で火山灰に埋もれた家などが残った。ボンベイのよう。
▽84 マヤの藍 1974年に最後の藍工房が閉鎖。93年にサンタアナ工房で藍染めが再開された。チャルチュアパのマヤ文化遺跡公園のカサ・ブランカに、ODAで藍工房を兼ねたミュージアムが02年につくられた。専門家を派遣して、藍染め技術を教えている。
天然藍の大半は欧州に輸出されている。
▽91 「星の王子さま」の故郷 サンテグジュペリ生誕100年の00年、妻のConsuelo(79年没)が手記「バラの回想」〓で、赤いバラは自分のことであり、星の王子さまは自分のために書かれたと告白していた。
▽96 03年、「星の王子さまを魅惑したバラ」といタイトルで、親戚のアビガイル・スンシンがコンスエロの伝記を出版した〓。
箱根には世界で唯一の「星の王子さま」のミュージアム。(平尾行隆)
▽101 フェルナンド・ジョルト チャラテナンゴ県ラ・パルマ出身。絵を教え、民芸品をつくるコミュニティをつくった。「セミジャ・デ・ディオス」という工房が活動の中心だった。内戦でサンサルバドルで「エル・アルボル・デ・ディオス」と称する工房をつくった。
□ホンジュラス バナナ共和国
▽125 UFC バナナ生産とその流通組織の発達が企業の近代マネジメントのスタートになったといわれる。
▽135 サッカー戦争 10万人以上の移住者が帰還。土地も仕事もない彼らの存在が、中米紛争の要因のひとつになった。
▽141 東祥三さんはUNHCRの難民保護官として、コロモンカグア難民キャンプにいた。難民のなかにゲリラ戦闘員が紛れ込んでいて、ホンジュラス軍との間に緊張を生んでいた。
▽171 ミスキートは、スモと黒人との混血。ガリフナは、奴隷船の黒人が、セントビセンテ島に先住していた南米起源のアラワクと混血したのがはじまり。その子孫が1797年にイギリス人によってロアタン島に遺棄され、そこからカリブ沿岸に広がった。
▽176
□ニカラグア
▽185 レオン 郊外の旧レオン跡は世界遺産。マサヤ火山は火口まで車で行ける。カタリーナ展望台。
▽191 中米連合が瓦解した後の10年間、レオンとグラナダが対立して、中央政府は存在しなかった。グラナダのチャモロ一族の本家筋が「ラ・プレンサ」を設立。
▽212 革命直後、街を包む熱気。人間の顔がこんなにも生き生きとして明るいものかと感心した。その後、85から87年までニカラグアに在勤。熱気は冷め、内戦と生活難にあえいでいた。
▽216 国際金融機関からの融資停止。輸出向け農作物を生産する大土地所有者や民間経済部門の実業家と政府が対立して、外貨収入急減。日常生活物資も不足し、ガソリンも配給制に。レストランから紙ナプキンが消える。インターコンチネンタルさえ、昼は断水。でも、路上で物乞いする子の姿はなく、治安もよかった。
差泣く225 幻の大空港 プンタ・ウエテ。Timalという巨大サトウキビ精製工場。キューバが5千万ドルを投じて建設したが、放置されている。
▽228 コントラ FDNは総兵力1万4千人。ARDEは千人から2千人。ミスキートのKISANやMISURASATAはそれぞれ千人。
▽239 中米5カ国で最下位の経済力。ホンジュラスの2分の1。輸出不振。コーヒー、サトウキビ、食肉、水産物の輸出に占める割合は50%で、従来と変化がない。……貧困も悪化。全世帯の65%が貧困ライン。格差も激しい。
▽242 内戦終結の時期にグローバル化の流れが襲った。中米の自由貿易圏、中米諸国とメキシコ、さらにはアメリカとのFTA(2003年署名)。ニカラグアには、葉巻やラム酒などは有望で、絵画も評価されているが、汎用品の分野では有望なものがない。
▽263 詩人の国 革命時代、政権の主要幹部はほとんど全員詩人だった。
▽272 葉巻 キューバと並ぶ産地。エステリのものが最良。キューバ革命で、キューバから来た葉巻関係者が技術をもちこみ、栽培をはじめた。だが、国内ではよいものは入手できない。
▽275 ラム酒 カサ・ペラス社のフリール・デ・カーニャ。 コーヒー
マサヤ街道のカサ・デ・カフェ。外国人も多い社交場。メトロセントロにも開店。
▽279 参考文献
テキサス大学ラテンアメリカ情報ネットワークセンター
http://lanic.utexas.edu/ が現地情報は便利
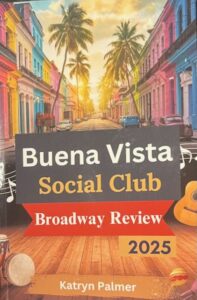

コメント