■毎日が日曜日 <城山三郎> 新潮文庫 20100418
左遷されてもそれにくじけず「なにか」を求めつづける人、不遇の境遇のなかに次への芽を見いだす人を描くから、城山の小説は多くのビジネスマンに愛読された。
総合商社につとめる主人公は京都支店長という閑職に飛ばされ、社長や相談役のおもり役をさせられる。おべっかは使いたくない。でも、ちょっとは気に入られたい……と揺れる。社内では傍流である支店長としての仕事とは別に、商社マンとしての大プロジェクトも手がけ、どちらも中途半端になることに悩む。単身赴任に伴う家族との葛藤もある。
どんな生き方をするべきだと城山は考えているのか、読んでも彼の価値観は見えてこない。上司にゴマをすることも、家族をうち捨てて働くことも、逆に会社に見切りをつけて「家族」に軸足を置くことも、どれが「正しい」とは示そうとしない。
準主役は、パッとしないまま定年で悠々自適の一人暮らしをはじめた男だ。はじめこそ「自由」を謳歌するが、そのうち孤独と寂しさにおそわれる。主人公の息子が入院し、彼のところに通うことが日課となる。責任がふりかかってこない程度にだれかのためにナニカをしたい、と願う。そういう生き方に対しても、城山は「正しい」とも「ダメだ」とも言わない。
登場人物の一人一人にただ寄り添う。
生き方の処方箋を求めて読んでも解答は得られないが、城山の人間の見方のやさしさと鋭さは十分に感じられる。
目次
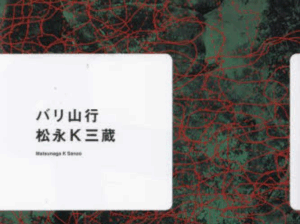






コメント