■文芸社20210908
北前船の終着駅だった北海道・江差がどれだけ繁栄していたのか知りたくて入手した。
松前藩の中心である福山(松前)や箱館(函館)と比べても、入船数が圧倒的に多く、回船問屋の数も圧倒していた。
大きな回船問屋は、現在の江差町の年間予算に匹敵する数十億円も稼いだ。大規模な問屋だけでも13軒もあった。
そんな発展が花街をつくりあげた。春のニシン漁の時期になると秋田や津軽、南部方面から大勢の雇い漁夫がやってくる。「ヤン衆」と呼ばれた雇い漁夫が江差の町にあふれた。
彼らは浜辺に春から夏のあいだだけつくられた「浜小屋」に殺到した。
最盛期の1807年ごろは小屋100軒以上、遊女300人もいた。遊女は、秋田や津軽地方の貧しい農家の娘だが、江差では半年足らずで20両、30両も稼いだ。1両は6万円から10万円だから、200万円近く稼いだことになるという。東北地方は、飢饉で餓死者が続出していたが、蝦夷地の江差浜には小判が打ち寄せると噂された。
旅芸人や瞽女などの芸で稼ぐものも集まった。旦那衆向けの料亭や茶屋、庶民向けの浜小屋などの花街が発展するにつれて、唄や三味線、踊りなどの芸を身につけようとする風潮が芽ばえ、暮らしのなかに芸文化が根づいていった。
そのなかから追分節が育った。
今でも江差町は、人口1万人以下の町としては飲食店の数が多いという。
====================
▽江差は日本海航路が経済の動脈として動き始めたときから北の終着港だった。
松前藩は石高のない大名だった。津軽から敗走して蝦夷地に渡った当時の豪族が、米にかわる生産物として目をつけたのが蝦夷地のヒバ材、海産物、金山、アイヌの狩猟であった。アイヌの交易はアムール大陸に及んでいた。
▽丘陵から急斜面が海岸に落ち込むような地形だから、海沿いの街道筋に回船問屋がつらなり、飲食店や人家は坂道を登った丘の上に開けていく。飲食店や茶屋は前浜を上がった切石坂や影ノ町からはじまるが、……
▽江差の入船700、福山(松前)300、箱館200。「松前蝦夷記」(1717)の記録からも江差が群を抜いている。浜小屋が酒場や茶屋をはじめるようになったのは文化年間あたりだという。
▽江差港の回船問屋(御用商人)は13軒、その下役に小宿7軒が沖の口業務を取り扱う問屋となっている。天保元年は13軒。
▽関川家は千石から500石の船13艘、岸田家は12艘を所有。
▽北前船の1航海で1000両の利益があったという。
▽回船問屋は数艘から10艘以上の船を抱え、年間2航海から3航海した。関川家、岸田家など大問屋の利益は現在の換算で数十億円。現在の江差町の予算に匹敵する。問屋株が13軒、小宿7軒のほか一般の回船問屋20数軒というから、その膨大な取り引きは予想を超えるものだったろう。
▽ニシン漁や北前船によるめざましい発展が、つぎつぎと花街をつくりあげた。
▽3月のニシン漁時期になると秋田や津軽、南部方面から大勢の雇い漁夫がやってくる。江差の浜には小判の波がよせてくると噂されたという。……松前藩は場所請負制という政策で、余市、小樽方面まで漁場を開いた.奥に向かう漁夫たちも一時江差に集結する。ヤン衆と呼ばれた雇い漁夫が江差の湊にあふれ、浜小屋に殺到した。
浜小屋の地割りはわずか二間四方(3.6平方メートル)。筵で囲った掘っ立て小屋で八畳間程度。2階3階4階の蚕棚のような小屋もあった。
……そのにぎわいは、ニシン漁が終わればヤン州も去り、7月北前船が出港したあとは浜小屋も取り壊し浜から灯が消えていった。
最盛期は1807年ごろからで、当時小屋は100軒以上遊女は300人もいたという。
浜小屋の遊女は、秋田や津軽地方から来る者が多く、貧しい農家の娘たちにとって半年足らずで20両、30両という稼ぎは大金だった。今の価格にすると1両は6万円から10万円だから、200万、300万という額になる。(海女のよう)
▽遊女や後家たちは秋田、津軽方面からの貧しい農家の婦女が多かったが、ニシン場景気でヤン衆男に劣らぬ稼ぎをしたようである。旅芸人や瞽女などの芸で稼ぐものも加わった。
料亭茶屋をはじめ浜小屋など花街の発展につれて、唄や三味線踊りなど芸を身につけようとする風潮も芽ばえる。親方衆の料亭茶屋から浜小屋に群れるヤン衆庶民まで、暮らしの中に芸文化が根づいてゆく。
……筵張りの仮小屋からはじまった浜小屋がやがて花街の原動力となって、芸能文化をつくりあげてゆく。
▽東北地方は、飢饉や凶作で餓死者が道端にころがっていたというのに、蝦夷地の江差浜には小判が打ち寄せると噂されたらしい。ニシン漁のヤン衆たちが群がる浜小屋の景気がそう噂されたのだろう。
南部や越後から旅芸人や瞽女たちが大勢きて夜通し太鼓、三味線の音が鳴り響き、江戸両国の夜見世にも劣らないにぎわいだったと幕府の巡検視が伝えている。
▽追分節 北前船の船頭たちが、越後地方の港町でうたわれたものを伝えたという。
▽49 明治中期以降、ニシン漁も不漁にかたむき、北前船の取り引きも落ち込んで、浜小屋や影ノ町遊理も姿を消していく。
……明治34年、新地の戸数168戸、裏町101戸、このうち妓楼13軒娼妓(遊女)35名多いときは70名にもなった。料亭は17軒。
花街の顧客は大手商人や北前船の船頭船乗りたち……一方、料亭や芸者たちも大手商人や漁場の親方衆には、盆暮れのあいさつまわりを欠かすことなく、店の行事には出向いて応援を惜しまなかった。伝統芸能の江差餅つきばやしは、年末に商家の餅つきに出向いて、芸者衆が太鼓三味線で景気づけをした風習を伝えている。
▽大正2年を最後に江差の浜からニシンが消え、町も不況に。料亭や貸座敷はどんどん取り壊されていった。1907年函館に大火災があって2400軒が焼失した。このとき建物を解体して発動機船に積み込んで函館に運んだという。
大正に入ると北に去ったニシンを追うように芸者衆も小樽、余市方面に出ていく者もいたが、新地花街には50人以上の芸者衆が残っていた。大正2年の新地の料亭は19軒。
▽昭和の年代の料亭は、10店ほど。遊郭は二葉楼だけとなった。芸者衆は30人あまり。戦時中には料亭も姿を消していった。
▽戦後、1955年ごろ、料亭2店と遊郭1軒が復活。
▽江差では女の子は芸者に男の子は教師に育てるという風習が古くから根づいていた。
▽江差町は、人口1万人以下の地方の町としては飲食店の数が特段に多い。それは江戸時代からの集積した花街文化の影響による者。
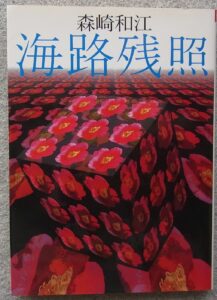


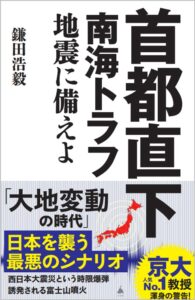
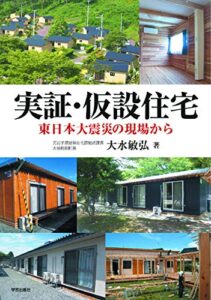
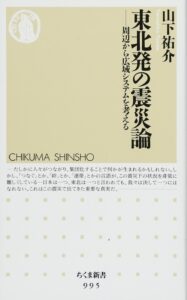
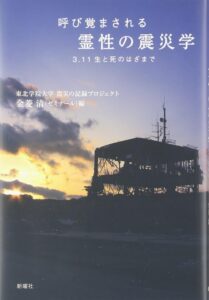
コメント