■ワニブックス20200709
著者は飯舘村の村長。
「人づくり」を重視して独特の村おこしを展開してきたが、福島第一原発事故で全村避難となってしまった。それでも村の未来をあきらず、「人づくり」を通して復興をめざす村長の気概が伝わってきた。
著者は若いころ、アメリカで農業研修を受け、村でトップクラスの60頭を飼育する酪農家になった。
肩書きを取り払って個人の資格で参加する「夢想塾」で「新春ほら吹き大会」を開き、そのほらのひとつを公民館長時代に「若妻の翼」という海外研修事業を実現させた。若妻がヨーロッパに出かけ、一人ずつ別々の家庭に滞在する。
「若妻の翼」に参加した女性は村で活躍しはじめるが、一方で「生意気になった」「こちらを見下しているような気がする」といった苦情も届く。女性たちをバックアップするため「夫婦で学び合うゼミナール」もひらいた。
49歳で酪農を廃業して村長になると、飯舘中学の校則を変え「男子の長髪」を解禁した。目につくかぎり、村の閉鎖性を打ち破ろうとつとめた。
村民1000人に、項目ごとに5段階で評価してもらう「村への通信簿」事業を実施。役場の考えと村民のニーズにずれがあるから熱意が評価につながらなかったと判明し、20の行政区の要望を聞いてから予算をつくる制度を導入した。
第5次総合振興計画のスローガンに「スローライフ」を提唱すると、スローを怠けると誤解した住民から反対にあった。そんなとき、村民のひとりが「そのスローライフって、までい、ってごどなんじゃねーべか」と口にした。左右にそろった手を意味する真手の方言で、「丁寧に」「大事に」「思いやりをもって」という意味だ。「スローライフ」と同じ、あるいはそれ以上の意味が含まれていることに感心し、「までい」をスローガンに決めた。
市町村合併の誤りに気づき、合併協議会からの離脱を表明した。村議の多くは猛反発したが、村長選で勝って独立を貫いた。
そうした村づくりが着々と発展しているところに2011年3月の放射能汚染が襲った。
すぐに村民のスクリーニング検査をして、長崎大の高村昇教授の講演会を開き、「基本的な事項さえ守れば、そんなに心配することはないよ」と話してもらった。
「こんなところに住めない」と言う反原発の学者や避難をうながす報道には「村民の生活を根底から崩すリスクをいっさい考えず、拙速な即時避難だけが唯一の道であるかのようだ」と批判した。「ともかく村をゴーストタウンにすることだけは避けたい」「放射能の害よりも、避難の害のほうが大きい場合だってあるのだ」という一念だったという。
復興させて住みつづけることを考えるから、避難先は車で1時間圏以内の場所にすることを求めた。線量が下がった際に気楽に帰村できるし、村の存在を見失わずに避難生活を送ることができるからだ。
緊急雇用創出基金事業を活用し、「いいたて全村見守り隊」を組織し、村民400人の臨時雇用を生み出した。各部隊は、自分の行政区をパトロールする。仕事がない人に稼ぐ手段を与え、同時に自分の地区を自分たちで守ることによる安心感を与える狙いだった。仮設住宅などの避難先にコミュニティバスを運行し通院や買い物をできるようにした。
震災後に村外に転校した人も含めてすべての小学6年生を対象とする「沖縄の旅」や、中学生の「ドイツ研修ツアー」も企画した。「この未曾有の事態だからこそ」人づくりを重視するのだという。
▽18 「までいな家」
▽23 3月22、23日村民のスクリーニング検査。1330人。
専門家による講演会。長崎大学大学院の高村昇教授「基本的な事項さえ守れば、そんなに心配することはないよ」という趣旨。
▽31 4月5日の時点では、「村民の生活を根底から崩すリスクをいっさい考えずに、拙速な即時避難だけが唯一の道であるかのような」著しく公平性を欠いた報道があったと今でも思っている。
…本村はこの事故のみをきっかけとして「反核の旗手」になるつもりはない。むしろ飯舘村が、原子力事故における放射能汚染被災地の範となって復旧・復興を果たすことこそが、日本にとっての最大の利益となり、世界の範となるものと考える。
▽35 「いま政府を悩ませる脱原発問題では煩わせないことを約束する」ので、「我々の村をモデル地区にしてほしい」と言った方がはるかにインパクトがあると思う。私は、ともかく村をゴーストタウンにすることだけは避けたかった。
▽40 昭和31年、飯曽村と大舘村が合併して飯舘村に。大火が発生して、2つに別れていた選挙区を撤廃してひとつの村として村議選をおこなうようになった。
▽48 県の事業でアメリカで農業研修。農業を「経営する」という感覚を学んだ。村でトップクラスの60頭を飼育する酪農家になった。家族以外の人を雇うこともアメリカで学んだ。
川俣町にチーズ工場をつくったことも。
昭和61年、「いいたて夢想塾」。肩書きを取り払って、個人の資格で参加する集まり。村の新年会で「新春ほら吹き大会」。・・・ホラをホラで止めずに、実現にこぎつけた第一弾が「若妻の翼」。このホラを口にしたのは生活改良普及員だった女性である〓。ヨーロッパへ。一人ずつ別々の家庭に滞在するホームステイも。パリではガイドなしの自由時間もつくった。
わざわざ農繁期にした。
▽67 計画避難で転校した生徒も含めてすべての村の小6を「沖縄の旅」へ、中学生の「ドイツ研修ツアー」を募集。この未曾有の事態だからこそ、次世代の子どもたちにかけるのだ。
▽68 「若妻の翼」に参加したM子さん 無人野菜直売所をつくって生きがいをみだしていた。30歳でツアーに参加。「天かけた十九妻の田舎もん」を出版。5刷に。夫と自家焙煎の喫茶店アグリを始めた。
だが一方で「生意気になった」「こちらを見下しているような気がする」といった苦情の投書が役場に届けられる。
…女性たちをバックアップするために公民館で「夫婦共学ゼミナール」。夫婦で参加。「男と女の関係」をしっかりとアタマにいれてもらわないと「村おこし」には取りかかれない。
韓国へ「嫁、姑キムチの翼」。韓国の婦人団体も来た。
飯舘村は「明るい農村」だったのだ。
▽82 公民館長時代、私をいじめた村職員もいる。村民の意識とかけはなれた行政のあり方を変えたい。
60頭の牛を処分して平成8年に49歳で村長に。
▽85「職員や村民の研修制度充実」「特別養護老人ホーム建設」
▽99 助役人事を否決される。「Tさんは村内に住んでいない」という理由で。三春町などは、わざわざ民間企業から優秀な人材を引き抜いて役場に迎えているのに。閉鎖性の問題。
村長就任翌年の平成9年、飯舘中学の校則を変え「男子の長髪」を解禁した。・・・目につくかぎり、村の閉鎖性を打ち破ろうと努力した。
特養「いいたてホーム」
▽102 飯舘村は、村民一人あたりの平均所得は県内の90市町村でもっとも低かった。税金の未納分が2億円、農協が農家に貸し付けていた20億円超のお金のうち、かなりの部分が不良債権になっていた。
▽102 平成11年、「村への通信簿」プロジェクト。村民1000人にたいして、無記名で、項目ごとに5段階で評価してもらう。…役場の考えと村民のニーズにずれがあるから熱意が評価につながらなかった。…そこで「全部で20区分されている各行政区の要望を聞いてから予算をつくろう」と提案。職員は全員反対だった。「今でもみなを満足させられていないのに、さらに課題が挙げられたら、ますますできないことが増えてしまう」
▽116 第5次総合振興計画のスローガンとして「スローライフ」を提唱したところ、スローを怠けると誤解した住民からたいへんな反対にあった。そんなとき、村民のひとりがふと口にした。「そのスローライフって、までい、ってごどなんじゃねーべか」。左右にそろった手を意味する真手の方言。「丁寧に」「大事に」「思いやりをもって」という意味。「スローライフ」と同じ、あるいはそれ以上の意味が含まれていたとは。
(コトバを探す。)
▽118 合併はまちがっていると決意し、合併協議会からの離脱を表明。村議の多くは猛反発。次の村長選は合併の賛否を巡るものに。
▽118 県内初の「どぶろく特区」。村で農家レストランを営むSさん。
立村50年の翌年には、「いいたてまでい子育てクーポン」。地域通貨的なクーポン。3人目以降のすべての子どもにつき、15歳まで毎年5万円を支給する。幼稚園や給食費など、自由に使ってかまわない。
平成21年には、「パパクオーター制度」。役場の男性職員に育児休暇を義務づけ。休暇をとっている期間を「研修」と位置づけ、昇進にも影響しない仕組みとした。
平成22年、不要になった絵本を村へ寄贈してもらう「絵本リレー」。10日間で1万冊を超えた。
「村内産食材100%給食」
▽139 避難を巡って政府に要望。…避難先は車で1時間圏内に…将来線量が下がった際には日常の行動として帰村できるし、常に飯舘村の存在を見失わずに避難生活を送ることができる。
▽153 マスコミが毎日のように役場に。よくわからない外国のメディアも。…ヒステリックな政府批判だけはつつしもうと決めていた。「世間の人気や一時の反響ではなく、実を取らなければ意味がない」と考えていた。
▽163 「いいたてむら 丸ごと防犯プラン」「いいたて全村見守り隊」。緊急雇用創出基金事業を活用し、村民400人の臨時雇用を生み出した。…各部隊は、自分の住む行政区をまわる。…仕事がなくなってしまった人にお金を稼ぐ手段を与え、同時に自分の住んでいる行政区を自分たちで守ることによる安心感を与える。村民を離散させないための取り組みの中核事業になっている。
▽177 「2年で村にもどれるようにしたい」と断言。
全員を対象とした健康調査を長期にわたってつづける。
仮設住宅などの避難先にコミュニティバスを運行し通院や買い物をできるようにする。
▽190 「放射能の害よりも、避難の害のほうが大きい場合」だって、あるのだ。
▽198 復興の一番のエネルギーは、そこに住んでいる人の故郷を思う気持ち、家族を思う気持ち以外にはないと思うのだ。あるいは農地や動物を思う気持ち、底に駆ける情熱、努力、知恵。そういうものを活用していくことが、復興の一番の原点ではないだろうか。…国はもう少し地方自治体を信頼して、裁量権を与える方向で議論していただきたい。
…「までいライフ」は「引き算の思想」だった。村民には今、その素晴らしさがさらに強く感じられていると思う。一見変化のない暮らしが、いかにすばらしい日常であったか。それを、思い知らされざるを得ない状況になってしまったのだから。
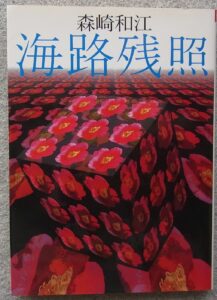


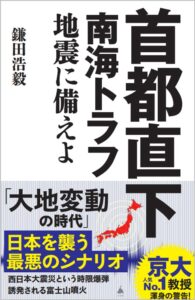
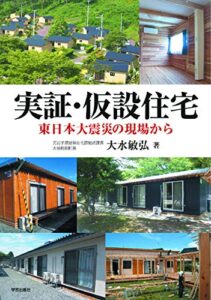
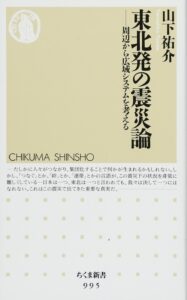
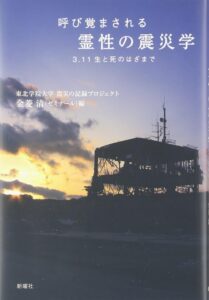
コメント