■20200804
岩手県一関市郊外の本寺地区という山村が舞台。キャストは全員地元住民で、中学が廃校になるという事実をふまえて、ドキュメンタリーとフィクションを融合させて物語を編んでいる。
おばあさんの葬儀で、おじいさんが臼と杵で餅をつくことをかたくなに主張し、中3の孫娘ユナともちをつく場面からはじまる。
ユナたちは本寺中学最後の卒業生だ。親友はまちに引っ越し、あこがれの先輩もムラを離れる。
生徒たちが練習するムラの踊りは、ムラの絆を支える大切な行事だった。もちつきは夫婦や家族をつなぐしかけだった。それらが今、失われようとしている。
踊りや餅つきが忘れられれば、ムラの魂が失われてしまう。その危機感の表現はレヴィストロースの「悲しき熱帯」を彷彿とさせる。
ユナは友達や先輩を失うことに喪失感を感じている。
「大切なことを忘れたくない。どうしたらいいの?」とおじいさんに問う。おじいさんは「努力することだ」と答える。「努力しないとわすれてしまうものなんて、なんだか本物じゃないみたい」とユナは答える。
おじいさんは、亡妻とともに守りつづけた先祖伝来のムラを失う寂しさを感じているから「努力する」しかないと思っている。
ふたつの喪失感が溶け合って共感して、ムラと家族の物語を祖父から孫へバトンタッチをしているように見えた。
(個人的には「G線上のアリア」は聞きたくなかったが)






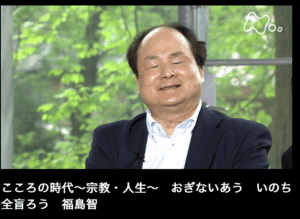

コメント