■コモンズ 20200702
福島県の旧東和町は有機農業の町だった。青年団運動や社会教育活動、産直運動、産廃処分場反対運動などに取り組んできた農民がその担い手だった。
2005年に二本松市などと合併する際、つちかった地域自治の受け皿をつくろうと、NPO法人「ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会」を立ち上げ、「道の駅ふくしま東和」を運営してきた。牛の糞や籾殻、醤油製造所の鰹節やこんぶ、麺のくず、カット野菜のくずなどの食品残渣を堆肥として再資源化した。産直の販路拡大で、2010年度の事業高は2億円に達していた。
2011年の原発事故で、浜通りから多くの被災者が押し寄せ、つづいて放射能も降り注いだ。
農地も山も放射能で汚染され、自殺する農家も出た。もう農業なんてつづけられないのではないか、という瀬戸際の生産者の会議で「命を絶った農家の悔しさと無念に、耕すことで応えなければ…」「耕して種をまこう」と営農の継続を決める。「出荷制限されたら、損害賠償を請求しよう」と考えた。放射能の自主測定体制もつくりあげていった。
そこに助っ人してあらわれたのが、有機農業の学会でつながりのあった新潟大の野中昌法教授らのグループだった。野中氏は水俣病にもかかわり、蛸壺に入った研究スタイルを批判し、農家の立場で研究する「総合農学」を提唱していた。農家と共に課題を設定して、どれだけの放射性セシウムが田んぼに流れこみ、どれだけ稲に吸収されたかを農家と共に測定し、具体的な「実践ノウハウ」を共有して不安をぬぐい、やる気と自立をうながす。これはまるで愛媛の稲葉峯雄先生の地区診断だ。
根の深さのセシウム濃度を薄めるため、可能な限り深く耕す。セシウム吸収をおさえるため石灰などの土壌改良材をほどこす。農家にとっては、これまでの土づくりをしっかり進めることであり、新しい技術を覚える必要はない。それがよかったという。
測定の結果、稲藁と籾殻からは放射性セシウムが検出されたが、玄米からは不検出だった。稲わらと籾殻が玄米を守ってくれた。阿武隈山系の土には雲母が風化した粘土が多く、粘土と雲母がセシウムを土に強く固定し、作物の根から吸収されないことがわかった。「肥沃な土づくりに励んできた農民たちの力だ。この地に踏みとどまったお年寄りたちの営農の力だ」。研究者のひとりは「福島の奇跡」と表現した。
子や孫でさえも「福島の野菜は食べたくない」と言っていたが、客観的な測定が安全を裏づけ、高齢農家の自信を回復させた。
阿武隈山地は、昔からたび重なる冷害に襲われた。
天明大飢饉などの教訓から、特産物(養蚕、葉タバコ)や酪農、綿羊を振興し、小麦、大豆、じゃがいも、粟、きび、えごまなど多様な雑穀も栽培し、冷害に備えてどの農家もじゃがいもをつくっている。零細農家ばかりだが、多品種少量生産だから道の駅には多くの種類の野菜や穀類がならんだ。大規模生産による系統出荷にあわない中山間地だからこそ多様な食文化が根づいた。その経緯は愛媛県内子町の道の駅「からり」に似ている。
阿武隈山村は、農家の規模は小さく、特産品に特化することもできないきわめて遅れた農業地域だと考えられてきた。だが、そんな自給的な農業を支えたお年寄りたちこそ、大混乱のなかでもたじろぐことなく種をまき、田畑を耕してきた。自分たちが食べ、家族が食べるからこそ、放射能測定に真剣に取り組んだ。原発事故と復興を振り返ると、阿武隈山村こそが強かった。
ゆうきの里東和では、事故後に農家民宿の設立を呼びかけ、2018年には22軒になった。多くの大学が農業体験や調査研究にきて、夜な夜な暮らしや人生談義が繰り広げられた。それが里山の活性化につながった。
事故後に立ち上げた「ふくしま農家の夢ワイン」年間6000本以上のワインを製造する。里山は「限界集落」どころか「希望の集落」だという。
こうした経験を通して、反原発の研究者にも違和感を感じてきたという。
ある人は、福島とその周辺については住民の避難退去をただちに指示すべきだと主張した。「福島での農業継続などあり得ない」という人もいた。そうした研究者が大勢入ることで、飯舘村は村民の混乱と、研究者への不信感を招いたという。
一方、野中教授ら日本有機農業学会有志グループは、まず現地に赴き、農家の話を聞いて、そこでできることを考えるべきだという立場だった。徹底した測定をふまえて「大丈夫だ」とはげましつづけた。被害者が出たらすぐに現地で調査をするというスタンスは水俣病患者に寄り添ってきた原田正純さんと共通するものだった。
100年200年という長い時間の流れを考えると、農業がしっかり継続し、農地や農業用水が維持されていくことが大きな意味をもつ。その点では、原発事故によって影響を受けたのはごく一部であるはずだ。「土を耕して作物を育てることで地域が育ち、人が育つ」との立場だったという。
==================
□菅野正寿
▽道の駅ふくしま東和を運営するNPO法人「ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会」
原発事故で避難者が押し寄せると、その夜には暖房器具を提供・・・
19日には地元でも6マイクロシーベルトに。
23日、須賀川で有機農業を30年続けてきた樽川久志さん(64)が自殺。
二本松市の大内信一さん(1941年生まれ)「太陽に向かって大きく葉を広げたほうれん草が、放射能から土を守ってくれたんだ」
命を絶った農家の悔しさと無念に、耕すことで応えなければ。・・・
二本松市は放射性セシウム含有量が1000~3000ベクレル/キログラムなので耕作可能と発表された。福島県は5000ベクレル以下なら可能と判断した。放射性セシウムの移行係数指標を0.1としたからである。
飯舘村や浪江町津島地区は1~3万ベクレル/キログラムだった。
・・・セシウム濃度を根圏において薄めるため、可能な限り深く耕す。石灰などの土壌改良材はセシウム吸収をおさえる。・・・農家にとっては、これまでの土づくりをしっかり進めることであり、新しい技術を取り入れるわけではない。
「耕して種をまこう。出荷制限されたら、損害賠償を請求しよう」
▽16 2005年、二本松市との合併(二本松、安達町、岩代町、東和町)を前に議論。青年団運動、産直運動、文化運動、産廃処理場建設反対運動など、ふるさとをこよなく愛してきた仲間たちだからこその危機感。
農家と商店が中心となり、ゆうきの里東和が2005年4月に発足「有機質堆肥による土づくり」をベースに、地域コミュニティと都市の交流など「有機的な人間関係」をはぐくみ「勇気をもって取り組む」新しいふるさとづくりへの挑戦。
▽19 牛の糞、籾殻、醤油製造所の鰹節やこんぶ、麺のくず、蕎麦殻、カット野菜のくず、あめ玉のくずなどの食品残渣を堆肥として再資源化する。
・・・ゆうき産直の販路拡大で、2010年度の事業高は2億円に達した(うち道の駅が9300万円)。
▽23 2011年9月の予備検査で二本松でも500ベクレル/キロの放射性セシウムを含む玄米が見つかり・・・取材カメラマンが来た。「あなたたちが取材に行くべきは東電だろう。農家に責任があるわけではない」
私は怒りが収まらなかった。
野中先生 どれだけの放射性セシウムが田んぼに流れ込んだか、どれだけ稲に吸収されたかの調査は、農家と研究者との連携によって進んだ。
・・・私の水田では土壌に含まれる放射性セシウムは1500~4000ベクレルだったが、2012年には1500に低下する。玄米からはすべて不検出だったが、、稲藁と籾殻からは30~100ベクレル検出された。(2014年以降は稲藁や籾殻も不検出)。稲わらと籾殻が玄米を守ってくれた。放射性セシウムの吸収を抑えた「土の力」が証明されたと確信した。
・・・阿武隈山系の土には雲母が風化した粘土が多く、粘土と雲母がセシウムを土に強く固定し、作物の根から吸収されないことがわかった。
「肥沃な土づくりに励んできた農民たちの力だ。この地に踏みとどまったお年寄りたちの営農の力だ」。中島先生は「福島の奇跡」と表現した。
放射性セシウムを抑え込んだ「土の力」と「稲の力」こそ、福島の経験として伝えていかなければならない。その力は、土着した農民のどんな災害にもどんな支配者にも屈しない、したたかな不屈の精神があったからだと思わずにおれない。
▽28 野中先生は、有機質が入って土が肥沃になっていれば、ゼオライトやカリ肥料の投入は必要ないと考えていた。
2013年春、布沢集落では、全員が米作りを再開した。全員で用水路の除染に取り組んだ。落ち葉や泥をさらい、黒いバッグに入れて仮置き場に運ぶ。・・・集落営農の力を感じる。
▽31 飯能市の自由の森学園高校の給食の米や野菜を1991年から提供してきたが、原発事故でストップしたままだ。
・・・農業、農村には、子どもたちからお年寄り、障害者まで、協同と共感するコミュニティがある。それは自然との共感である。だから、むやみに農薬はまけない。
・・・「迅速な復興」の名のもとで、大規模基盤整備や・・・ドローンを使った農薬散布・・・が進められている。そこには、命をはぐくむ教育の視点も、集落営農の協働の力も、地域コミュニティの姿も見えない。
汚染された福島県だからこそ、多様な作物による有機農業を軸にした環境保全型農業と環境教育を提起しなければならないのではないか。
▽33 天明大飢饉などの教訓から、特産物(養蚕、葉タバコ)や酪農、綿羊を振興していく。さらに、小麦、大豆、じゃがいも、粟、きびなどを奨励して・・・。
阿武隈山系では大豆、小麦、えごまをはじめとして、多様な雑穀も栽培されてきた。冷害に備えて、どこの農家も現在もじゃがいもを作る。道の駅には、大豆、青豆、黒豆、ささげ豆、白豆、小豆など多様な豆が並んでいる。
冷害や大雨などの災害を乗り越えてきたからこそ、多様な食文化が息づいてきた。
▽34 ゆうきの里東和では、原発事故後、農家民宿の設立を呼びかけ、2018年には22軒になった。新潟大、東京農大、東京学芸大、甲南大などが毎年、農業体験や調査研究にくる。
長女の瑞穂が2013年に起業した(株)きぼうのたねカンパニーには、毎年200人以上の学生や市民団体が農業体験にくる。
事故後に農家8人で立ち上げた、ふくしま農家の夢ワイン(株)は6ヘクタールに1万2000本のブドウを植え、年間6000本以上のワインを製造する。
▽36 過密化と孤独死とネット社会の弊害が噴出している都市こそ「限界集落」ではないか。里山は、食べ物と再生可能エネルギーとコミュニティと豊かな土と持続可能なくらしのある「希望の集落」ではないかと考える。
□原田直樹
▽44 α線はヘリウムの原子核 β線は電子、γ線は電磁波。
γ線は非常に短波長でエネルギーが大きい。γ線よりやや波長がないのがX線。
▽49 セシウム固定能をもつ・・・鉱物は花崗岩質の土壌に多く含まれる。阿武隈山系はまさに花崗岩質。放射性セシウムは粘土鉱物に保持され、それゆえ農作物への影響が出にくい。
▽51 水口、中央、水尻で土壌や稲を採取して調べると、水口は放射性セシウム濃度が高い。
▽59 飯舘村。冷害に対応するため、1960年代から畜産に力を入れた。トルコギキョウなどの花卉栽培を産業化した
▽61 除染農地で大豆栽培。他の作物の土壌から可食部への放射性セシウムの移行は、一般的に大豆よりも低い。
2017年に米の安全性が確かめられ、食用に販売されるまでになった。
▽63 福島県の、全量・全袋の放射性セシウム濃度検査の結果は「ふくしまの恵み安全対策協議会」のHPで公開されている。・・・2015年以降の全検体が1キロあたり100ベクレル以下におさまっている。
□吉川夏樹
▽69 山地のセシウム。河川を通じて流出するのは1年間にわずか0.1から0.3パーセント。・・・ダムがあったからこそ、大雨時の濁水に含まれる放射性物質が流出するのを抑えていた。
・・・ダムは巨大な減容化装置。
□金子信博
▽90 いわきと阿武隈山地は緩やかな地形で、スギなどに加え、シイタケの原木となる広葉樹の生産が盛ん。原木生産は日本のトップだった。
・・・原木に使われるコナラの樹皮はセシウムを強く吸着する性質をもつ。・・・シイタケはほかのキノコと同様、放射性セシウムをよく吸収する。
▽92 コシアブラはとくにセシウム濃度が高い。
▽102 化学肥料以前の里山は、伐採利用以上に落ち葉を収奪されて土壌が劣化し、森林の生長も悪かった。貧栄養な土壌に生育する
アカマツが多く生えており、土壌浸食も深刻だった。そのため、山地から土砂が河川に流れ、海岸に砂が堆積してクロマツが生育した。白砂青松の景観はその結果である。
□飯塚里恵子
▽104 復興をとげている地域での決定的なかぎは、放射性セシウムを固定吸着していく「土の力」と、この地で生きるという「人々の意志と取り組み=人びとの力」「人々が結びあい取り組む=地域の力」のたゆまぬ協働であった。
道の駅「ふくしま東和」の売り上げは、2011年を下限に3年間でV字回復した。2014年度は震災前年度の売り上げを超えた
▽108 福島農業の特徴は、小規模、自給的、高齢者の3点。東和地区もまさにそう。
▽112 「ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会」合併に際して、旧東和町の住民が協議を重ねるなかで、培われてきた地域自治や地域農業をこれからも東和として守り育てたいという思いが結集していき、その母体組織として設立された。
▽114 事故後、生産者会議で、リーダーは農家に営農継続を呼びかけた。放射能の自主測定体制づくりへ。
▽118 桑事業の展開。パウダーの加工を2017年から東和地区内の施設で、行うようにした。
新規就農も。約30人が移住し、2011年にも7人が移住した。
▽122 菅野正寿氏(1958年生まれ)は集落で唯一の専業農家。長女は2013年に「きぼうのたねカンパニー株式会社」を設立して、ブログやイベントを通じてつながった県内外の援農者の受け入れもしている。
集落営農に力を入れる。
▽123 武藤長衛(1961年生まれ) 農業をしながら道の駅の店長。
▽128 太田集落の女性Bさん 「東和海外研修友の会」で米国人の研修者を自宅に受け入れ。「県民のつばさ」でドイツ訪問。夫とともに自給的農業。事故後、道の駅で測定し、安全を確かめながら自家野菜を食べるようになると、不安は解消されていった。
▽130 「ふくしま農家の夢ワイン株式会社」酒類製造免許交付は2013年。女性事務員のEさん。地域史の聞き取りも。・・・ワインづくりの夢はかつての桑畑をブドウ畑に再生させ、地域農業の展開へとつながった。
▽133 40代の役員F氏は農水省在職中に旧東和町役場に勤務。退職して2006年に移住。新規就農した。自家製ビールも製造。2010年に「オーガニックふくしま安達」を組織。F氏が事務局となって2013年春に「あぶくま農と暮らし塾」(中島紀一塾長)が開講。
塾生が中心になって公民館事業「とうわ地元学」。木幡集落の隠津島神社の社務所で昭和時代の「祝言」や「祝言料理」を再現し・・・
▽135 戦後から1980年代半ばまでつづけられた青年団活動や社会教育活動が背景にあった。青年団を通じて、同年代が語り合うという気質がつくられてきた。青年団がなくなってからも、農家の跡とり層は農業や社会活動の幅を広げ、仲間づくりを再組織してきた。それらが町村合併を契機に再結集し、「ゆうきの里東和」という協議会設立の気運と力となった。
G氏は沖縄の高校を卒業後、関西、関東で住んでいた。自給的な暮らしがしたくなり、東和地区に。2013年に農家民宿を開業。
東和地区には、外から来た人たちを地域の仲間として迎え入れ、ともに活動をしようという気質がある。
□小松崎将一
▽156 野中先生「主体はあくまでも農家である」という立場にたち、農家とともに課題設定を行い、科学的な手法で解明し、そのデータを農家と共有する。(地区診断〓)
□横山正
▽165 土壌表層に局在する放射性セシウムを除去する場合は、農水相が試験したヒマワリやアマランサス〓以外の作物を試みる必要があると考えた。例えば、セシウムが局在する部分に大量の根を発達させるアブラナ科の作物。
▽176 圃場の土壌には長石の風化物が大量に存在しており、カリウム供給力を餅、それが放射性セシウム吸収を抑制している。中島紀一先生が
東和の農家さんがすばらしかったのは、genpatu事故後の五里霧中の中で、とにかく農耕地を耕し、作物の生産を試みたことである」と話された。…耕すことで放射性セシウムと細粒雲母…との接触を促進し、粘土鉱物の中へのセシウムの固定をうながした。同時煮、阿武隈山地北西部のペグマタイトを含む地質が放射性セシウムへの天然の要塞になり、幸いした。
□石井秀樹
▽191 国際的な放射線防護の原則は「無用な被爆を避ける」である。市民が許される被曝量は、年間1ミリシーベルト以下であり、事故が生じた場合でも、年間20ミリシーベルト以上の被曝が想定される場合は、1ミリシーベルト以下にすることが要請される。
日本政府の方針は、20ミリシーベルト以下であれば避難指示は解除され、帰還がうながされる。避難指示が解除となった地域で外部被曝の評価をすると、実際には年間20ミリシーベルトもの外部被曝はなく、大半は数ミリシーベルト前後の被曝に収まるケースが多い。…被曝の基準が変わることで、補償や賠償を受ける正当性が失われる点。
▽196 在廷基準値を超過する玄米が発見されたのは、生産者自らが民間の測定所に玄米を持ちこみ、測定したからである。民間での放射能計測がなければ、汚染米が見過ごされたり発見が遅れたりする可能性があった。
▽200 ベラルーシ共和国では、山火事による放射性物質の再拡散を抑制するため、の森林管理を導入している(林道整備など)
▽202 被災地に出入りした研究者のなかには、自らの技術の応用、仮説の検証を最優先し、研究費が取れるか、論文になるかが行動原理で、被災地支援は二の次の研究者も見られた。…原子力災害で「専門家」と呼ばれる人々の信頼が損なわれていたことに加えて、水俣病などの公害問題では、被災者救済がなければ、被害の実態把握すらままならないことが指摘されていたことである。
▽208 福島大では2019年4月に食農学類(仮称)を発足する準備を進めている。その設計にはひとつのモデルがある。野中先生をリーダーとした新潟大学の復興支援研究である。
□武藤正敏 農家と研究者の協働
▽221 大学や企業と情報交換や活動に取り組めたのは、「ゆうきの里東和」が長いあいだ、住民主体のNPOとして、地域活動や社会貢献に努めてきた結果、事業や活動の受け皿になり得る団体と認められたから。多くの人が迷い悩んでいたとき、リーダーたちは状況をよく認識し、一丸となって迷わず方向づけをしました。
▽222 多くの研究や調査の皆様に農家民宿を利用いただき、里山は活性化したように思います。…民宿では、暮らしや人生談義が繰り広げられました。それは最高の復興支援ではなかったのかと、いま振り返っています。
□座談会
▽224 2011年4月、事故後はじめての生産者会議で、「耕して種をまこう」と訴えた。
▽226 怪しげな人もたくさん来た。放射性物質が抜けるという「マジックウォーター」を100本置いていった方もおられました。…知ることが生きることと考えた大野さんが理事長として引っぱってくださり、汚染の実態を調査してみようという方向へ進みました。
▽228 たくさんの研究者らが支援を申し出てくださるなかで、どなたを信用すればいいかがわからなかった。
野中先生のグループの先生方は、とにかく頻繁に現地へと足を運んでくださいました。親身になって話を聞いてくれ、農業の継続を強く勧めてくださいました。放射性物質が危険だという世論が圧倒的だった当時にあって、大丈夫だとおっしゃってくださった先生方にはとてもはげまされました。
▽229 福島は危険だからすぐに避難すべきだという意識をもった方が、現場にどんどん入りこんでいました。飯舘村は、そういった研究者が大勢はいられたことで、残念ながらかえって村民の混乱と、大学研究者への不信感を招いてしまいました。
…徹底した反原発の立場の権威ある先生、子どもや妊婦の避難を強く主張しておられました。
(〓当時は逃げるべきと思っていた。現場の人の思いから出発するべきだった〓。基本的な態度を問われる)
▽231 お母さんたち。元気はつらつで野菜を作っていたお母さん方が、家族からその野菜は食べない、もう野菜は作らないで欲しいと言われたことで受けたショックは大きいものでした。家の食事に自家野菜が使われていることを知った若夫婦がコンビニで惣菜を買ってきた、と離す人もいました。…
▽233 これまで農業と里山を守ってきてくれた先輩たちへの思いをここで途絶えさせたくないと思い、桑の葉や実の血糖値を抑える機能性に着目し、2000年に桑薬生産組合を先輩たちと設立して桑畑の再生に取り組んできました(菅野)
▽235 農家民宿の展開は野中先生の言葉がきっかけ
…夜遅くまで公私にわたる話をして、…農家民宿の効果には、研究者と農家という立場を超えて人間的な関係をつくるということもあったのです。(大野)
▽236 道の駅。ここに来れば地域の誰かしらに会える。地域をあげて有機農業をやって来たことで、日本有機農業学会とのネットワークがつくられていたことも大きかった。原発事故以前の我々の歩みが土台になっていまがある(菅野)。
□根本洸一
▽238 原発20キロ圏内の南相馬市小高区で有機農業の稲作。
□奥村健郎
▽242 南相馬市原町区大田地区 大田地区復興会議では野馬追に合わせた「ひまわりプロジェクト」に取り組んでいた。耕作をつづけ、課題を見つけながら対策をたてていくことで、農地の再生と地域コミュニティの維持が可能になると考えた。
▽244 野中先生「最後は土が答えてくれる」100年200年という長い時間の流れを考えると、農業がしっかり継続し、農地や農業用水が維持されていくことが大きな意味をもつ。その点では、原発事故によって影響を受けたのはごく一部であるはずだ。「土を耕して作物を育てることで地域が育ち、人が育つ」
□長正増夫 飯舘村第12行政区
▽246 「いいたて復興志士の会」「早期帰還を目指します! 一人一人の復興と再生をめざします! 住むことに誇りが持てる村をつくります」
野中先生らと相談を重ね、2013年10月に、飯舘村第12行政区(大久保・外内地区)の私が住む集落で、宅地と農地の測定活動を実施。この行政区では地区会報を月刊で発行した。名前は「おいとこ」。
▽249 2016年夏には、「復興研修」。長野県長和町の韃靼そばづくりや、秋田県由利本荘市の菜の花と菜種油づくりを視察に。ダッタンソバは、耕作放棄地を適作地に変える見事な取り組み。2018年に入って、長和町の皆さんから分けていただいたタネを蒔いた。
菜種をいただき、2016年の秋に一部播種した。
2017年には期間が開始。農業を中心とする村づくりの再開に向けて、復興研修はつづけていく。私自身は、そばなどの雑穀がおもしろいのではないかと思っている。小麦も楽しみ。多様な農地の利用が、村を豊かにして、人も育てるのだと思う。
□中島紀一 野中昌法の仕事
▽253 主体はあくまでも農家である。「測定」することを復興・振興の起点にする。研究者・農家報告会では、議論ではなく、「実践ノウハウ」の共有を行う。
▽255 測定結果は現地にわかりやすく報告し、情報を整理し、共有し、話し合いを重ねる。それが住民への励ましとなり、筋道となり、自信となっていった。
……住民たちは一歩ずつ自治主体としての力をつけていった。データは少しずつだがほぼ確実に安全側に移行していった。
▽258 7年という、原発事故からの復興としては、実に異例に、短期間に、見るべき成果をあげてきている。「一歩ずつの着実な復興」。「福島の経験」は復興に向けての正の経験。
……作付けを再開すべきかどうか、迷いの局面に直面した時、丁寧に測定しながら、まずは農作業を開始してみよう、はじめなければ何もわからない、とはげましてくれる科学者が身近にいることは何よりの支えだった。……収穫物の放射能を測定してみた。思いのほかに、農作物への放射性物質の移行は少なかった。このデータを手にして、多くの栽培者たちは涙を流した。
▽261 早く避難退去すべきだ、食べ物生産などあり得ない、という強い警告が地域外の識者たちから次々に発せられた。……こうした非難の暴圧のなかで、農民たちは田畑を耕し、種をまき、栽培を開始した。結果として正解だった。福島の土には大変強いセシウム吸着固定の力があって、耕すことでその力を大きく発揮させた。
▽262 国は、ゼオライトやカリ肥料を強制した。効果は明らかではない。農水省も環境相も、効果についての実証、検証すらしていない。……野中さんらは、落ち着いた営農努力の重要性を説き、その成果データを示し、農家を励ましつづけた。こうした農業の復興は、農家の自給の場面から開始された。自給的な農業はお年寄りたちに担われている。このお年寄りたちこそ、大混乱の時期にもたじろぐことなく、タネをまき、田畑を耕し……てきたのである。まず自分たちが食べ、家族が食べ、ご近所での無償の贈り合いに供された。だからこそ、放射能測定の取り組みは真剣だった。〓
▽264 町村合併は、自治の意思を希薄化させてしまった。そんな状態の地域に原発事故が襲いかかった。……東和地区は大きく状況がちがっていた。二本松市への合併協議の過程で、地域の暮らしの体制、地域文化の伝統、地域農業の大勢、地域自治の気風などが失われないようにするにはどうしたら良いかという話し合いが熱心につづけられた。合併した2005年4月に「ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会」が設立され、10月にNPO法人に。その前身は循環型農業の推進を課題とする「ゆうきの里東和」で、そのほか自主活動をつづけてきた諸団体が加わって設立。担い手の中心はかつての青年団活動の有志たちで、会員数は300人弱。
▽267 小出裕章さん「放射線管理区域」という既存の制度を踏まえて、福島はもちろんその周辺地域について住民の避難退去を国はただちに指示すべきという見解があった。群馬大学の早川由紀夫さんからは汚染地図の整理が逐次公表され、福島での農業継続などあり得ないという警鐘が発せられた。今中哲二さんや糸永浩司さんから、国や県からは安全地域だと区分されていた飯舘村に関して、高濃度汚染にさらされているという情報提供が強くなされていた。
日本有機農業学会有志グループは、これらの選考研究者の提起には同調しなかった。まず現地に赴き、農家の話をよく聞いて、そこで私たちのできることを考えるべきだという立場で一貫していた。……当時としては、これはとても重要な独自の立場の選択である。
……何より重視したのは、農家とともに測定する、農家自身の測定を支援するというあり方だった。
▽269 国は事故後、設定されていなかった食品の安全基準地をあわてて500ベクレル/kgに設定し、あまりに甘すぎるという強い批判を浴びて、2012年4月から100ベクレルに引き下げた。この基準値をオーバーする農作物が続出することはなかった。
▽271 2011年冬ごろから、特殊技術がさまざまに提案され、さまざまな団体から試行プロジェクトが持ち込まれた。しかし野中さんのグループはそうした提案におおむね冷淡だった。こうした時だからこそ、被災地での営農推進においては農の本来のあり方をしっかりと追求すべきではないかと主張していた。
▽275 阿武隈山村はきわめて遅れた、きわめて弱い農業地域だと考えられてきた。経営規模は小さく、力のある特産品に特化することもできず、農業の目的は自給的で、担い手の高齢化が著しく……。しかし原発事故と復興を経てみれば、阿武隈山村こそが強かった。
□野中昌法
▽277 多くの大学で「農学部隠し」の学部改組がおこなわれ、これが農業と能楽を乖離させる要因となってきた。
▽278 1888年に最初の化成肥料、過リン酸石灰の国内生産が始まり、……1908年に日本窒素肥料株式会社が設立され、1914年に熊本水俣工場で劉安の生産がはじまった。第一次大戦の影響で、爆薬の原料ともなる硫安が輸入されなくなったことで、日本窒素は大きな利益をあげた。1932年にアセトアルデヒドの生産がはじまり、その工程でメチル水銀が垂れ流された。1929年、新潟県鹿瀬町に昭和肥料(のちの昭和電工)が設立。昭和電工は1988~89年にかけて、健康食品であるLトリプトファンの生産過程で、遺伝子組み換え大腸菌が原因と考えられる、多くの死者を出す健康被害事件を起こしている。
水俣工場と鹿瀬工場の設立に共通することは、国家の全面支援の元、ダムを利用した水力発電の利用であった。原発立地とその電力利用による経済優先の構図と変わらない。
▽288 有機農業発展に必要なことは、専門家が科学の限界を認め、農家と共同の調査研究をおこなうだけでなく、農業の基本である人の行き方や地域の文化、歴史までを含めた有機農業の大切さを自治体を含めて多くの人たちと意見を交換して進めることだと感じている。
学問分野が細分化され、他の分野には「見ざる、聞かざる、言わざる」の日本の科学界に対して、「変人」と言われても、日本有機農業学会は「科学者と農家」が協同で作り上げる雑学集団として「本道」を歩みつづけて欲しい。
▽290 事故から2年2カ月のちの講演でチェルノブイリに関する論文が紹介されていた。国の研究機関で多くの調査研究結果があるはずなのに。パネリストの菅野典雄村長が「チェルノブイリの知見はもういらない、日本で何が起きたか、詳細な調査をもとに公開することが大切である」
…国や県が行う環境放射線調査・試験研究に関わる研究者によると、3年経過した今でも、それらの結果については国・福島県との調整が必要で、発表するかどうかも含めて、結論が出るまでに長時間を要するという。しかも、結果の公開が制限される場合もあるという。
私たちは、全データを公開してきた。それは、過去の公害事件でわかるように、多くの人たちとの情報の共有によって新たな被害が防げるからである。
▽294 原発を否定している研究者にも、現地調査を行わずに発言する人たちがいた。現地調査を行い、情報をすべて公開し、多くの科学者が被害者に寄り添いながら正確な議論をしてこそ、科学は発展する。……原田正純さんのように、被害者が出たらすぐに現地で詳細な調査を行い、被害者に寄り添い、解決に向けて進むことが、科学者の責任である。
□「農と言える日本人」書評
▽300 農家とともに一歩ずつ前へと進んでいく。そうしたなかから「生きる道を断たれるような衝撃ですが……それでも私は農業の道を選ぶ。農業をすることは誇りです」と宣言する若い女性農業後継者の誕生(東和地区)、「自立の村づくりを諦めない」として、全村避難のなか、自らの内の放射線計測をおこない、そのなかで生活と農業の復興を探る動き(飯舘村)などへと話が広がっていく。
……野中氏に「どうしてあれほど詳細に農家の皆さんの言葉を記録できるのですか」と尋ねた。すると「(農家の言葉を)一つ思い出すと次々出てくる」とのことだった。農家の声を聞き、それを出発点として、つなげて考えるという謙虚な姿勢が、その声を正確に捉えることができるのだと思われ、それがまた農家を一歩前へと進ませていく力を生み出している。
▽302 現在の農学研究が細分化して、多くの研究者が木を見て森を見ない。彼らは農業の多様性を理解していない。だから、現場で詳細な調査が行われず、風評被害が拡大し、多くの情報が隠され、国民の不安を助長していった。風評被害を払拭するには、研究者が現場で農家とともに、正確な情報を発信しつづけるしかない。
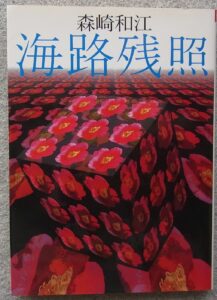


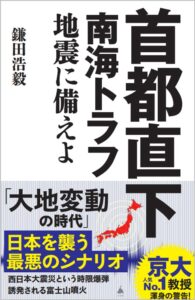
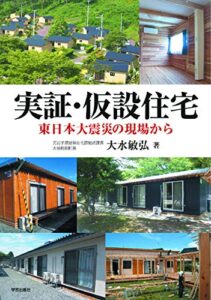
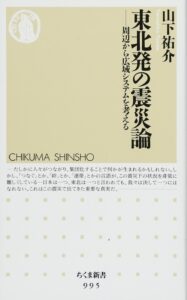
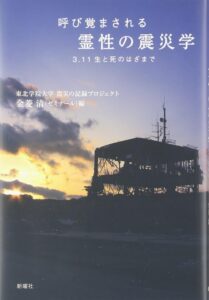
コメント