■作品社20200623
大熊町の住民たちは、原発事故によって故郷に住めない難民となり、さらには行政から見捨てられ棄民化している。マスコミの扱いも小さくなり、忘れ去られようとしている。そんな人々に寄り添う研究の成果をまとめている。
国・県は放射能被害を過小に評価し愛郷心によって帰還をうながす。それとセットになっているのが、「福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想」などの「創造的復興」だ。生活再建を後回しにしながら、新自由主義的な帰還政策が進められている。
一方、中間貯蔵施設問題では、国が「30年以内」という約束を反故にして、なしくずし的に最終処分場化を目指している。
避難をよぎなくされた町民はそんな政策に翻弄されつづけている。
原発事故で避難した際、「元あるコミュニティをそのまま移動」するという国交省の方針のもとに、行政住区ごとに仮設住宅に入居させた。それ自体は阪神大震災などの教訓を踏まえた対応で、能登半島地震などでは一定の結果を残していた。
仮設住宅では、区長経験者を自治会長に据えた。そうやって形成された「国策自治会」は行政の下請けが精いっぱいで、、賠償・補償・除染・中間貯蔵施設・復興公営住宅・帰還などについて避難者のニーズをすくい上げることができず、むしろ「棄民化」をうながすことになった、という。
なぜそうなったのか。「元あるコミュニティー」が「なかった」からだと筆者は言う。
区や班を通して原子力防災訓練を何度も繰り返していたのに、事故後の避難では区や班からは連絡も避難誘導もなく、人々は家族や親せきと車で避難した。
「区ー班」というコミュニティは「あるけど、なかった」。仮設住宅の自治会の多くが「あるけど、なかった」コミュニティーをもとに結成されたから、行政の下請け以上の機能を望むべくもなかった。
原発建設時から私生活主義が進行し、すでにコミュニティは実質的に解体されていたという。大熊町のコミュニティは個人主義が進んだ都市部に似ていた。「元あるコミュニティ」がある能登のような効果が得られるはずがなかった。
そんななか、筆者が期待を寄せるのが、社協の支援で自発的につくられたサロンだ。ボランティアという外部の人を受け入れ、地域住民が「異なる他者」と出会う。ガバメントに回収されない「共同性」に根ざした「新しい近隣」が育つ可能性があるという。「土地から切り離された」ボランテイアを「人と人をつなぐ」コミュニティの基軸に据えるべきだという。
=====
▽32 国、県は放射能被害を過剰診断などと揶揄し、過小に評価するとともに、メディアなどを動員して愛郷心を喚起し「帰還幻想」をふりまいている。それとセットになっているのが、新たな成長戦略の拠点として位置づける「創造的復興」である。・・・2014年からは帰還政策と共振しながら中間貯蔵施設の建設とリンクする形で「福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想」が打ち出され・・・帰還幻想と創造的復興が表裏一体となって、被災者の生活再建を後回しにしながら、新自由主義的な帰還政策が進められている。
▽33 野上1区「大熊に帰らない」宣言。宣言を起草したK(木幡)氏。もともと地主。
旧熊川時代、天明の大飢饉で人口が急減した。そのとき、富山県あたりから多くの人々が移住してきた。以来、移住者がくる前からいる人々を「在地の人」と呼び、移住以降にきた人々を「外から来た人」と呼ぶようになった。K家の祖先は、旧熊川時代に相馬氏とともに移住してきた生粋の「在地の人」である。
妻のMさんは郡山市の女子校を中退後、地元の短大に入学したが中退。社会活動を経てK氏と知り合い、結婚して大熊町に移り住んだ
3.12後、避難先で「大熊町の明日を考える女性の会」を立ち上げた。
「帰らない」ことを前提として、将来世代の生活の再生に照準した取り組みを行うようになった。医療無料化や被爆者手帳の発行・交付を国や県に要請する運動。
▽41 大熊町は有数の「出稼ぎ」の供給地だった。原発誘致には「出稼ぎからの脱却」という悲願が込められていた。
電源開発の「先進地」である西会津が経験しているような限界集落化を回避することはできたが、それ以上に「近代の宿痾」に苦しめられている。
▽77 おおくま町会津会 みなし仮設住宅入居者は加入率が低い。2014年8月1日現在、会津地方にとどまる被災者数は2357人であるのに対して、会津会への加入者数は60人にすぎない。(仮設住宅はほぼ全員が自治会が加入している)
▽122 中間貯蔵施設問題 国が30年以内という約束を反故にして、なしくずし的に最終処分場化を目指している。…賃借権は20年が上限だが、地上権には制限がない。国が圧倒艇優位な立場になってしまう…
▽135 大熊町仮設住宅 国交省の「元あるコミュニティをそのまま移動」するという方針の下に、行政住区ごとに入居させ、区長経験者を自治会長に据えた。「国策自治会」。しかし自治会は賠償・補償・除染、中間貯蔵施設、復興公営住宅、帰還などについて避難者のニーズをすくい上げることができず、町と共に「棄民化」をうながしている。
F自治会では社協の支援でサロンを立ち上げ、ボランティアを受け入れ、地域住民が「異なる他者」と出会うのをうながしてきた。ガバメントに回収されない「新しい近隣」
▽135 3.11直後の避難行動は、区会や班からの連絡も避難誘導もなかった。家族や親せきと車で避難した。
定期的に行われていた「区ー班」をあげての原子力防災訓練がまったく役に立たなかった。「あるけど、なかった」
立ち上げられた自治会の多くが、「あるけど、なかった」状況を踏まえないで「元あるコミュニティの維持」というかけ声のもとに「上から」結成された。
「上から」のコミュニテイ動員。
▽149 サロンは国家や行政と「対峙」しつつ「対話」している「創発するコミュニテイ」。「新しい近隣」同一性によってではなく「相互性」によって媒介される「共同性」に根ざす。「隣り合うこと」が「外に開かれたもの」としてあり、多様性、非排除性にもとづいている。
▽164 経済産業省「福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想」 被災者ひとりひとりの生活再建を後回しにしてでも経済「復興」をめざすというスタンス。復興を「新しい成長戦略」とつなげる新自由主義的な経済「復興」の論理が大熊町の「まちづくりビジョン」にも通底している。
▽172 自治会をベースにして結成されているサロンに注目。…語ることをしないで、上からもしくは外から鼓吹された「助け合い」や「支え合い」に一方的に身をまかせたために、いつの間にか孤立していたという状況を暗黙裏に回避している。筆者は「絆」や「つながり」が連帯ではなく分断に導くといったことを、、サロンを透かしてみることによって確認できる。
▽177 宗教学者や民俗学者らによる…実態から乖離したコミュニティへの過剰な期待や願望がふくらんだ。現実的なありようとの関連をもたないままにコミュニティがアクティブであるという言説が目立っている。結果的に新自由主義的な経済「復興」を支えることになっている。
▽183 特定の行政区住民を特定の仮設住宅に振り分けることによって、「従前のコミュニティの確保」を行った。だが…避難行動で浮き彫りになったのは、区会や班といったコミュニティは存在はしていたが、事実上機能しなかったという事実。(〓能登とのちがい)
▽190 国県町は、仮設入居者に対して帰還か災害公営住宅かの二者択一を求めており、…
▽196 コミュニテイの解体は、原発立地によって受益体制が構築されるようになった時点までさかのぼって検証されるべき。原発立地にともなう受益構造によって私生活主義が進んでいた。「原発さまの町」のはじまりはコミュニテイ解体のはじまり。
▽2011年12月19日現在、仮設住宅の自治会組織状況は、岩手県99.4%、宮城県99.7%、福島県100%となっている。
▽202 「土地から切り離された」ボランテイアを「人と人をつなぐ」コミュニティの基軸に据えるべき。
▽204 「元あるコミュニテイの維持」ということ自体、原発被災地域ではほぼ虚構に近いものだった。…「土地」と結びついたコミュニテイがあったにもかかわらず、そうしたものを見ないで避難している。「あるけど、なかった」コミュニテイ状況。
▽247 3.11直後、論壇では何かが変わると期待が高まった。5年を経て、こうした議論はあとかたもなく消え失せた。…「変わるべき」「変わるはず」論が等の被災者を置き去りにして、もっぱら「上から目線」でなされた。戦後の論壇が一貫して保持してきた啓蒙主義的な論調が見え隠れしていた。
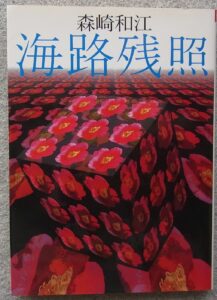


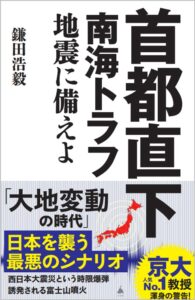
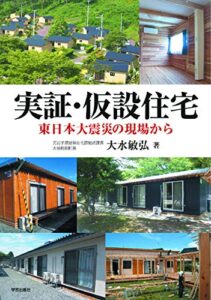
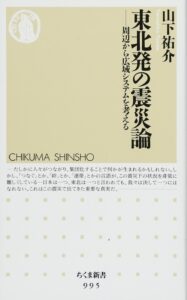
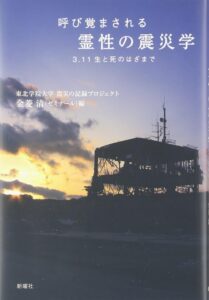
コメント