■ホセ・ムヒカ 世界でいちばん貧しい大統領<アンドレス・ダンサ エルネスト・トゥルボヴィッツ 大橋美帆訳> 角川文庫 20160722
若いころは左翼ゲリラ・トゥパマロスに参加し、軍事政権によって幾度も投獄された。軍政が終わって「拡大戦線」の政治家になり、大統領にまでのぼりつめた。
農場に住み、大統領になってもひとりでこっそり抜け出して町を歩き、儀礼をことごとく無視する。ベルギー王宮でネクタイ着用を求められると、「そういうことなら帰るぞ」ときびすを返して大騒ぎになった。無礼そのものなのに、その独特のキャラクターで、中南米の政治家だけでなく、オバマやメルケル、プーチン、ローマ法王とも親交を結んだ。
キューバのカストロらとも仲がよいが、「この国の問題は、全国民に仕事が与えられていて誰も冒険を冒さないことだ。成長を促すにもまた資本主義だ」と批判した。チャベスが貧困層を重視することは評価するが「ベネズエラを見ろ。企業や投資家を追い出した結果、状況は悪化している」と評した。そして、企業家がいるから世の中の進歩があると考える。協同農場や労働者協同経営は新しい発想や冒険心に欠けてうまくいかないことが多いということは、かつてのニカラグアなどの革命政権を見ているとよくわかる。
「大事なのは、現実を生きている人の生活がよくなることなのだ」とムヒカは言い、政治家が自らの理想の国家像に国民をあてはめようとすれば、大事なのが「国の形」になってしまい、現実に生きている国民を忘れてしまうと考える。「最悪なのは、政党のイデオロギーのせいで、現実を現実として受けとめられなくなってしまうことだ。私は随分前にそういう思想は捨てて、白か黒かというよりも、現実の微妙なニュアンスが重要だと気がついたんだ」。まさにプラグマティストだ。
ムヒカは世界の左右両陣営に広がる人脈と人気を生かして、キューバとアメリカの間をとりもち、シリア難民を受け入れ、米政府からテロリストとして訴えられているグアンタナモの収容者を受け入れ、コロンビア内戦では政府とFARCの和平を仲介した。コスタリカのような積極的平和主義の外交を展開した。
物質至上主義の働き過ぎ社会を批判し、もっとつつましやかに人生を生きられるのではないかと考え、その理想を北欧に求めた。
では、ムヒカはウルグアイに革命をもたらすことができたのか?
本の著者はムヒカの大統領時代を振り返って、「国の構造にまでは影響しなかった。ムヒカが政権への切符を手にしてから、別の種類の破壊が起きたような印象を受けるが、抜本的な改革はおこなわれなかった」と評している。それでもムヒカのような「揺れ」を許容するだけの民主主義は育ってきたし、「革命」を必要とせず、改革によって改善できるプラグマティックな社会ができてきたと評価しもよいのだろう。
「生きる喜びを全身で深く感じることを止めてはならない」というムヒカの言葉は、独房に長年監禁され、精神錯乱状態に陥る極限状況を生き抜いたからこそ出てくるのだろう。「生きることのすばらしさ」を体でわかっている人間は強く魅力的なものだ。
「私から読書と紙とペンをとられたら、もうどうしようもない。ネットには…新しいアイデアは書いていない。…私は本を読んで考えるほうが好きだ。時間があるときには、頭の整理のために時々アイデアを書き出してみるんだ」。本が彼の人格の基盤を形作っていることも、なんだかうれしかった。ネットは「今」しかない。本からは過去の人々の知恵の蓄積を受け継げる、ということなのだろう。
==============
▽ 2012年の「持続可能な開発会議」(リオ+20)のスピーチ「伝説のスピーチ」となる。
▽ お花畑の理想主義者ではなく、合理的な現実主義者。「イデオロギーで政治をしてはならない。大事なのは、現実を生きている人の生活がよくなることなのだ」。政治家が自分で描いた理想の国の姿に国民をあてはめようとすれば、国はどんどんやせ細る。大事なのが「国の形」になってしまい、そこで現実に生きている国民を忘れてしまう(ニカラグアの協同農場、国営農場の失敗〓)
▽27 任期の終わりが近づいたころ、「生きる喜びを全身で深く感じること」を止めてはならないと、情熱的に語った。(〓極限状況を体験したからこそ。生きる喜び、という説得力)
▽35 1970年と72年の投獄は、どちらも1年以内に脱獄に成功している。…さらに捕まる…彼らの独房には換気扇もトイレも、流しもマットレスもないことが多かった。ムヒカは正気を失った。床をはっていたありに話しかけるようになり、精神錯乱状態になって軍病院に運ばれた。
▽42 議員になったときは、国内のできるだけ遠くまで足を伸ばすという計画を立てて、実行したんだよ。これほどの成果がこんなに早く出るとは思っていなかったが。
▽59 最悪なのは、政党のイデオロギーのせいで、現実を現実として受けとめられなくなってしまうことだ。私は随分前にそういう思想は捨てて、白か黒かというよりも、現実の微妙なニュアンスが重要だと言うことに気がついたんだ。〓
▽68 ムヒカは、一番重要なのは、教育、教育、そしてまた教育であると力説した。
▽72 私から読書と紙とペンをとられたら、もうどうしようもない。ネットにはつまらんことばかり書いているかr…くずみたいな記事を読むのはもううんざりだよ。新しいアイデアは書いていない。…私は本を読んで考えるほうが好きだ。時間があるときには、頭の整理のために時々アイデアを書き出してみるんだ。(〓本の大切さ)
▽76 今は合計25ヘクタールもっている…。
▽83 軍政時代の罪で投獄されていた退役軍人を、自宅軟禁にしようと試みた。鉄格子の向こうにいた多くの人は、ムヒカが投獄されたときの看守たちだった。ムヒカは和平の印として、彼らを自宅に送還することを試みた。しかし、まったく支持が得られず、措置は見送られた。
▽90 ムヒカは海外でも、儀礼典礼を無視した。国家元首にかかわるあれこれを担当する者たちを発狂させていた。…訪問先のドアや移動用の車のドアを、自分のためには絶対に開けさせない。…いつも運転手の横の助手席に座った。…その後は青いフォルクスワーゲ・ビートルを運転して出かける。
…料理も自分がつくる。料理人は来客があったときだけ。
▽96 「注意して出歩く必要はない。殺られるときは、何をしていてもやられるんだから」「トゥパマロスで学んだのは、御影を増やせば増やすほど、安全ではなくなるということだ」
▽97 チャベスの葬儀には、アルゼンチンのクリスティーナ・フェルナンデス大統領が自分の飛行機で連れて行ってくれたが、…「美容師まで乗っていたよ」。ダブルベッドにクローゼット、シャワーつきトイレにリビングなど…「いやまったく、あれこそが国家というものだね」と皮肉った。
…スウェーデンでは、国王への贈り物を王宮のテーブルに置き忘れ、爆弾対策部隊を動員する騒ぎになった。…ベルギー王宮では、「ネクタイをギフトとして用意させていただきました」と言われ、「そういうことなら私はどこにも入らんと伝えてくれ、さあ帰るぞ」ときびすを返し、大騒ぎに。ベルギー役人たちを驚かせた。
…前任者や他国の同僚たちとちがえばちがうほど都合がよかった。彼はそれを巧みに利用する術を知っていた。
▽102 私がいつも言っているのは、「自分の考えにしたがって暮らそう。そうしなければ、暮らしぶりに合わせて物事を考えるようになってしまう」ということだ。
▽108 ムヒカは、信念を持った無政府主義者だった。政権を握った無政府主義者。
▽115 ムヒカはいつも、予告なく、許可も得ず、どこへでも出歩いた。彼の哲学は、毎日同じことを繰り返さないことだった。そして、できる限り国民の前に姿を見せることだった。
▽119 毛沢東と面会し、…室内の至るところに置かれていた書物の量に圧倒された。
…ソ連に期待し、レーニンの国に行けると思って訪問したら…ロシア人の典型ともいえる人物は、初代ツァーリのイヴァン雷帝だったということがわかった。階級のない社会と言うよりも、マフィアのほうが多い過激派の国だった〓。
…工場に行くと労働者たちの陰鬱な表情が目に飛び込んできたが…要するに、社会主義は自由に反するものであってはならないのさ。確かにリベラリズムは理想ばかり追い求めているかもしれないが、哲学としては、人類にとって一段レベルの高いものだ。何ごとも自由を基本原則にするところからはじめなければならない。社会主義ブロックはこのことがどうしても理解できなかったので、失敗に終わってしまったんだ。(自由、の大切さ〓)
▽122 …1日6時間を読書にあてて過ごしていた。知識の引き出しがどんどん増え、多数派の左派からますます距離を置くようになっていった。
…ローザ・ルクセンブルグは、共産主義者の異端児だった。女性であり、礼儀に欠け、議論好きだった。今でもムヒカは彼女の著書に目を通し、彼女の思想を伝え、歴史に理由を見出している。
「あの女は非常におもしろい。民主主義を擁護し、社会民主主義やレーニンと対立していた。原則の問題、知的発展を実現するための自由への闘争の問題だと言っていた。
▽124 ムヒカはチャベスらを評価していたが、同じ意見ではなかった。キューバは、時とともに魅力を失っていくように思われた。キューバの素晴らしさをよく強調してはいたが、その失敗について語ることも恐れなかった。…キューバの要人たちに向かって、キューバが抱える問題は、この国では「全国民に仕事が与えられている」ことと、だから誰も冒険を冒さないことだと言い放った。「資本主義にも問題があるかもしれないが、成長を促すにもまた資本主義だ」と。
ベネズエラ 国民を貧困から救い出したことについてはチャベスを評価していた。それはムヒカにとっては社会主義ではなく、似ても似つかぬものだった。
▽126 ホセ・バジェ・イ・オルドニェスは、20世紀のはじめに大統領を二度務め、…8時間労働の実施など、さまざまな社会保障政策を進め、一連の自由主義改革を率いた…21世紀になると、拡大戦線がバジェ主義の旗を振るようになり、ムヒカもそのひとりだった。(〓)
▽129 ムヒカは、バジェを象徴的な存在としても尊敬している。1950年代に「南米のスイス」と呼ばれていたことをバジェの功績と認めている。
…社会政策の分野では、人工妊娠中絶や同性婚を合法化し、国の管理の下に大麻の販売を認めたことで歴史に名を残すだろう。これらはリベラルな改革であり…
「自由主義と無政府主義はいとこ同士みたいなものだ。今のウルグアイは、昔のウルグアイに似ていると思う。つまり、前衛的な国だ。それがバジェの時代に起こっていたことだ。女性に投票権が与えられ、離婚が認められ、国がアルコールの生産を始め、女性の教育を受ける権利が認められた。売春まで合法化されたんだ。
▽131 コロラド党のエレーラからは、アメリカと必要以上に接近することを止めることを学んだ。「彼のおかげで、この国にはアメリカ軍の基地がないんだ」
▽135 「歴史書を読まなければならん」とムヒカは繰り返し言う。…トロツキーとチャーチルの回顧録は、ムヒカがものを考えるときによく参考にする本だ。
▽140 文化人類学も。「人間は群れをなす、社会的な生き物なんだ。孤独では生きられない。…社会主義的な生き物ということができると思うのさ」
▽142 ムヒカは軍隊とカトリック教会という二つの制度を尊重している。ムヒカが関心を持っているのは、これらの制度がどうやって何千年もの間生き残り、存続しているかということだ。
…ムヒカは、軍隊は最高権威の表現であり、近代文明の起源であると考えている。そのためムヒカは軍人を敬っている。そして軍人たちも彼ら(トゥパマロ)を敬っている。なぜなら自分たちは共通の規範で動いていると思っているからだ。
▽150 (かみつきのサッカー選手スアレス)「下から這い上がってきた素晴らしい若者だ。…貧乏人ならではのずるがしこさも持っている。とてもいい青年だ」
▽158 ブルジョワは金儲けもするが、それと同時に自分からも与える。彼らはきちんと規範を持っている。じっくり耳を傾けて聞くべき連中もいる。…彼らの経営能力であり、管理能力であり、雇用を生み出す力だ。資本主義者たちこそ世界を創造するエネルギーなんだ。
▽164(老実業家)年を食っていてカネも山ほど持っているのに、それを楽しむためだけに生きているんじゃない。新しいものを生みだすエネルギーにあふれているのさ。これは尊敬以外の何ものでもないし…
▽171 ムヒカの逆鱗に触れる人。自ら模範を示そうとしない自称フェミニストも。
シングルマザーを支援するためのフェミニスト団体があると思うか? こういうフェミニストたちはみんなメイドを雇っているようなインテリたちだ。拡大戦線にはそういう鼻持ちならないインテリ女がたくさんいる。
▽182 第一次バスケス政権で、アメリカとの自由貿易協定の可能性について決定しとき、ムヒカは、この決定を覆そうと説得した。このように目立った形でアメリカに接近することは、他の南米諸国と拡大戦線内部、特に共産主義者とかなりの数のウルグアイ社会主義者にマイナスの影響を与えかねないというのがムヒカの主張だった。
▽195 2015年、70%という国民の支持率でムヒカはバスケスに大統領のたすきを渡した。
▽200 家に忍び込んで脅迫する軍部保守派。
▽202 国際紛争の解決に向けて中心的な役割を演じ、シリア難民を受け入れ、アメリカ政府からアラブのテロリストとして訴えられているグアンタナモの収容者を受け入れ、ハバナとワシントンの間を取り持つ使節までつとめた。
▽203 軍部の連中はニャトにも私にも敬意を払ってくれている。私たちはトゥパだし、連中とは長年つきあってきた仲だ。私たちも彼らに敬意を払っている。…社会と政府には軍隊が必要なんだ、とね。…深刻な混乱が生じたとき、私は意図的に軍部の連中を関与させることによって、連中が自分たちにも重要な役割があると感じられるようにした。燃料の分配について混乱が生じたときに、私は軍部に頼ることにしたんだ。この問題は、チリのアジェンデ政権に問題を引き起こしたからね。
▽206 企業に対しても、梅毒戦術を使っている。梅毒は感染者を殺しはしない。殺してしまうと菌は栄養源を失ってしまうからだ。企業や投資家をウルグアイから追い出したりすれば、カネを落としてくれる人がいなくなってしまう。彼らより私たちのほうがうまく経営できるという保証がどこにある? (〓ニカの例)ベネズエラを見ろ。企業や投資家を追い出した結果、状況は悪化している。
▽214 話題がマンネリ化してきたころ、海外メディアの関心を引きつける新たなテーマが登場した。人工妊娠中絶と同性婚の合法化、そして何よりも、政府の管理に基づくマリファナ栽培の合法化に代表される、さまざまな社会政策だった。
…「私にとって、結婚の平等や大麻の問題はあまり重要ではない。私の優先課題は貧富の差を解消することだ。黒人や問題を抱えている同性愛者はたいてい貧しい人たちだ。不幸のどん底にいる人びとを政策の中心に据えなければならん。
…私たちは本物の自由主義の国だ。自由主義と無政府主義は、従兄弟のような関係だ。私は、ウルグアイが、前衛的な国になってほしいと思っている。そのために、これらの社会改革を進めているんだよ」
「麻薬密売者は、取引が違法化されているおかげで生き延び、影響力を持つようになっている」フリードマンこそが、80年代の初めに麻薬合法化によってもたらされる恩恵を説いた人物だった。
…ムヒカは今世紀半ばまでには、大麻が完全に合法化されるだろうと予測した。
▽219 コロンビア革命軍FARCとコロンビア政府の和平を仲介。
キューバと米国の接近。カストロとオバマと対話。2014年にオバマを訪問。その数カ月前に米国の要請により、グアンタナモ収容所から6人の主人をウルグアイに受け入れることを決定していた。(米国に貸しを作る)
▽238 ブラジルのルーラとジルマ。
アルゼンチンのクリスティーナ・フェルナンデスの悪口を「片目がみえないあの男より、ばあさんのほうがひどい」と電源の入ったマイクの前で言ってしまい大騒ぎに。
▽242 ムヒカによるとベネズエラは「世界で最も腐敗した」国の一つだ。チャベスのやり方には賛同しなかった。それでも、貧困を軽減したこと、石油による利益配分を改善したことについてチャベスを評価していた。
…マドゥロについて「演説もうまく、資質もあって風采も立派だが彼にはチャベスのブーツは大きすぎる」
…マドゥロはチャベスの考えから逸脱したことお、ちがう道を進んだこともなかった。チャベスの成し遂げたことを継続しようとしたのだが、うまくいかなかった。ひとりの人物を中心に成立していたチャベス主義モデルはじょじょに衰えていった。
「マドゥロはいいやつだが、…独自のスタイルを確立する代わりに、チャベスのように話そうとばかりしている」
「後で管理できなくなるものをなぜ国有化するのか理解できん。…」
▽252 ムヒカは共産主義者だったことも、キューバ革命に同調したこともなかったが、カストロ兄弟のことは尊敬していた。…ムヒカは、左翼ぐるグループと話したわずか数日後に、右翼の代表とも話を合わせられる。
▽265 私は無神論者だ、ローマ法王には強く心を動かされた。訪欧は人びとに救いの手をさしのべたいと思っている。彼は素晴らしい法王になるだろう。私の生き方と同じだ。
▽267 ムヒカは外遊を終えて帰ってくるたびに、国民は怠惰だが、そんなウルグアイがますます好きになると言っていた。
▽271 ムヒカが繰り返し話題にするテーマは愛だ。ガールフレンドを追いかけて母と暮らしていた家を飛び出した16歳のころに、常に女性を中心とする人生がはじまった。うたかたの、けれどそれぞれ大切だった恋人たちのことは、今も思い出すと愛情と懐かしさでいっぱいになる。
▽281 いちばん大きな痛みは間違いなく、子どもに恵まれなかったことだ。二人は子どもをつくりやすい時期を刑務所で過ごし、解放されたときにはもう年をとりすぎていた。
▽292 ムヒカは、少年のころのようにもう一度自転車に乗って、誰にも邪魔されずに自然とふれあうことを夢見ていた。未知のものに直面するという感覚をもう一度味わってみたいと思っていた。(未知を求める冒険の時代を再び〓)
▽296 ムヒカにとって現代人は仕事をしすぎて、人生を謳歌していない。北欧諸国の特徴は勤務時間が短いことと、子育ての最初の数年間は両親ができるだけ子どもと一緒に過ごす時間をとれるように支援していること。…インターネットでSNSに費やす時間やテレビ画面を見ている時間は、無駄以外の何ものでもない。必要なのは日々のもっとも基本的なことに時間を費やすことだ。
フィンランド「この国では人生というものが最も大切にされている」。その逆の例として、人びとが働くために生きているようなシンガポールや、人びとが救いやより高位に到達するために死を選択するイスラム諸国の過激派をあげた。確かに快適に暮らすためには働かなければならないが、、何よりもまず人生を生きなければならないのだと力説した。
▽298 「人生をしっかり生ききると、素晴らしい視点がみえてくる。頭さえしっかりしていれば、皺や白髪は人間としてさらなる高みに達した証拠になる」
…ムヒカにとってFBやツイッターは、これらによって生まれた「アラブの春」のようにはかないものだ。SNSとは、シンの意味での交流を避け、意味のない運動や数時間しか存続しないリーダーを生みだす手段でしかない。
▽305 昔のヨーロッパでも採用されていた国境消滅モデルに向けて、ラテンアメリカも自然と進化している…とムヒカは信じている。
▽316 「賢い高齢者たち」が社会に貢献できるような国にするという考えは、ムヒカの強い関心を引いていた。高齢者を尊重するアジアの文化を例に挙げた。高齢者という社会の財産を活用し、経験豊富な人々の話に耳を傾け、新しい世代に知識を引き継ぐこと。
▽325 基本的に死というものは自然の法則だから、受け入れなければならない。重要なのは、自分の人生をとことん愛することだ。
▽330 ムヒカの世界的な人気については議論するまでもないが、想像していた国内の揺れは「〜すべき」という考えを揺るがしただけで、国の構造にまでは影響しなかった。ムヒカが政権への切符を手にしてから、別の種類の破壊が起きたような印象を受けるが、抜本的な改革はおこなわれなかった。
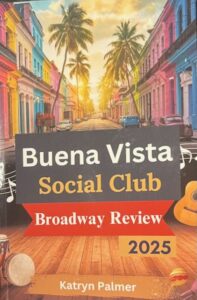

コメント