■ビルマの竪琴 市川崑 20160809
三國連太郎の演技を見たくてアマゾンの動画で見た。モノクロ映画だ。
ビルマの竪琴は、小説は読んだことがあった。
三國が演じる隊長は音楽の専門家で、彼の率いる小隊はことあるたびに歌をうたった。主人公の水島上等兵は竪琴の名手だ。
潜伏していた家を敵に包囲されたときも、歌をうたいながら準備をして切り抜けようとした。埴生の宿を合唱したら、相手もまた英語で合唱しはじめた。
降伏。まだ抗戦をつづける部隊を説得するため水島が派遣されるが、説得ならず、全滅してしまう。水島もけがをしてビルマ人の僧に助けられ、回復して部隊の行き先の捕虜収容所に向かう途中、無数の日本兵の骸を目にする。それらを弔わずに帰国するわけにはいかないと、僧としてビルマに残ろうと決意する。
一方の三國たちは、水島をなんとか探そうとする。水島そっくりの僧を見かけ、水島の竪琴の旋律を聴き……、最後は兵士たちの合唱の声につられて僧形の水島が収容キャンプの外に顔を見せる。「いっしょに日本に帰ろう」という呼びかけに対して、「仰げば尊し」を演奏する。「…今こそ別れめ、いざさらば」と。無言のまま背を向けて去ってしまう。
だれもが知っている歌。その歌によって気持ちが伝わる歌。そういう役目を唱歌は果たしていた。いろいろ問題はあるのだろうけど、世代をこえてうたえる歌は残すべきだったと思う。
音楽の可能性は、限界的状況になるほど見えてくる気がする。こんな物語が戦争体験者たちの共感を得たということは、これに近い体験をした兵士がいたということだ。
メルセデス・ソーサが、「ギターの音色が消えたあとに最後の星が消える」というような歌をうたい、ビクトル・ハラは処刑される直前まで歌をやめなかったという。歌の力は想像以上に大きいのだ。
映画のできじたいは、アラを指摘することはできる。でも、二枚目の三國連太郎の目の強さが印象的で、インテリ出身の隊長の迷いと風格をみごとにただよわせている。中国戦線であらゆる手を使って生き残った三國自身の経験が生きているのだろう。水島上等兵役もうまかった。
目次






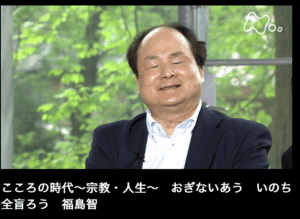

コメント