第七芸術劇場 20070812
すごいドキュメンタリーだ。
ひめゆり部隊の生き残りのおばあさんの証言をひたすらつなぐことで、当時の悲惨な状況を浮かびあがらせてしまう。米軍側のフィルムや、今のガマや壕の映像ももちろんある。が、ほとんどはおばあさんの証言だ。
彼女らの言葉はきれいな標準語だ。沖縄の言葉ではない。方言札によって標準語を強制され、教師になる訓練をうけたインテリだからだろう。けっして民衆の言葉ではない。何度も語り、語ることに慣れているから、証言の途中で涙を流すことも少ない。でもだからこそ、客観的に情景を描写し、私ら映画を見る者の脳裏に具体的な情景を浮かばせる力になっている。
15歳から19歳だった当時の写真を黒い背景に浮かびあがらせ、そこに台詞をかぶせ、今の姿をその後に登場させる、というパターンを何度も何度もくりかえす。
いかに無垢でかわいい女学生だったか、その子たちがどんな運命をたどっていくのか、追体験させられる。
はじめ、看護の要員として動員されたとき、赤十字の旗に守られた病院だと大半の学生たちは思っていた。壕のなかの陸軍病院ということになっても、はじめはみんなで歌をうたい、明るくすごしていた。
次第に戦況が悪化し、重傷の兵隊が次々運び込まれ、薬品も食料もなくなり、腕や足の切断手術にたちあい、兵士の傷にわくウジをピンセットがないから木の枝でとりのぞき……次々に死体を穴にほうりこむ。
はじめは1人が死ぬだけで泣きじゃくっていたのが、平気で作業するようになる。
首里の司令部が陥落し、本来はそこで戦闘は終結するはずだった。ところが、「最後の1兵になるまで」徹底抗戦、という美名のもとに、本土への侵攻を遅らせる捨て石とされた。
首里が陥落し勝敗が決した段階で降伏していれば、ひめゆりの悲劇はなかった。軍隊はけっして国民を守らない。むしろ殺す、ということがよくわかる。国民を守るためではなく、「国体」を守るだけ。これは奇しくも有事法制の議論のなかで栗栖だったかだれだったかが、私らとは逆の立場で言っている。
米軍が目前にせまるなか、病棟の壕に残された患者たちは毒を飲まされて殺された。これは「自決」とされた。
南部へおちのび、壕にかくれる。米軍に包囲され、グラマンが機銃掃射し、海からは艦砲射撃にさらされる。絶体絶命だった。このときでもまだ彼女らは、いつかは友軍が来援し、日本が勝つと信じていた。ところが、「部隊解散」の命令がくだされる。朝までには壕をでて、あとは自分の判断で生きていけ、という。国のため軍のため尽くしつづけたのに、最後の最後の段階で裏切られた。
「あとは個々人の責任で」という言葉。今もよくきかないだろうか。失政をおかした首長が、財政破綻をしたときに、「市民の責任で」などと言ってないか?
国のため、と、命をも捨てる覚悟で尽くしつづけた少女たちは最後の最後に軍に捨てられ、失意のなかでのバラバラの逃避行のなかで大半の少女たちは殺され、自決していく。
中央政府は沖縄を捨て石とし、沖縄の軍のトップは、みずからの忠誠をしめすために全住民を悲惨な運命においやり、無意味な死を強いた。
徹底した軍国教育のせいで、捕虜になれば悲惨な死が待っており、家族も親類も生きていけなくなると思いこまされた。白旗させかかげていれば助かったはずの少女がどれだけ死んでいったろうか。狂信的な「神の国」だったのだ。
いったいその責任はだれがとるのだろう。
権力者は「愛国心」を下に押しつける。それを信じてたたかった民衆は悲惨な運命に導かれ、押しつけた側は責任をとろうとしない。
無責任体制。これって今の安倍内閣と同じじゃないのか。「愛国心」を国民や教師におしつけ、みずからとその「オトモダチ」の誤りや犯罪的行為はのらりくらりと責任をとろうとしない。戦時中の軍の上層部となにがちがうんだろう。
ひめゆりの少女たちはだれもが「死は覚悟した」という。何度も手榴弾をにぎりしめている。だが最後の最後、死ぬ間際はだれもが「助けて!」「お母さん!」と叫んだという。本当は死にたくないのだった。
ひとつひとつの証言が重い。ぜったいに忘れてはいかない。伝えつづけなければならない。そう思わされる。






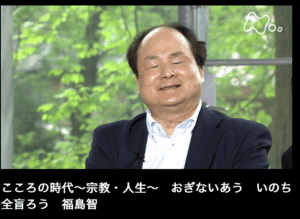

コメント