■岩波書店 241225
能登半島地震の復興の問題となにかつながるところがないかと手にとった。 2017年出版した時点で東日本大震災の復興政策は失敗だったと断じている。
本質的な問題は、震災以前からつづいているという。
大店法改正にともなう郊外の乱開発と中心市街地の解体、ゴルフ場・スキー場・宿泊施設の乱立に終わったリゾート開発。市町村合併は合併特例債という奇妙なカネつきの、東京発の公共事業だった。リスクを特例債で相殺する手法によって合併をうながし、その結果、吸収・合併された地域は衰退し、「だまされた」となってしまった。
これらの実行と失敗は、自治体が主体的に選択した形をとらされた。「国が示したものだから間違いはない」という見解が先行し、失敗しても「だまされた」と口に出せず、同じような構造を再生産しつづけてきた。
プロセスが東京発で、利益が東京と地方で分配されるが、失敗の責任は地方が負う。こうした非対称の関係は、原発事故の問題構造も同じだった。
東京がもたらす計画の虚妄性、絶対大丈夫と無責任にもちかける欺瞞性こそが問われなければならない。東京からの働きかけがなければだれも原発など望むはずがなかったからだ。
中心と周辺のこうしたゆがんだ関係は、医療制度改革、年金問題、公共交通問題、教育改革など……普遍的な構造となっている。
小さな社会を解体し、大きなシステムへととりこんで中央に従属させる。その過程で生じるリスクと失敗を、一時的に巨額な利益をつかませることでひきとらせ、結果として小さな社会へ負担を押しつけてきた。
そのなかで原発立地自治体だけが唯一、十分な財源を確保し、少子高齢化を克服してきたかに見えていた。しかし一度事故がおきると壊滅させられた。
原発事故の避難者は十分に結束できず集団として抵抗できない。だから、東電のめちゃくちゃな賠償のロジックもまかり通ってしまう。また原発事故は国が加害者だ。被害者を守る立場の避難元自治体は壊滅的な打撃をうけてしまった。その結果、国や電力会社の言うがままにされてきた。
避難者たちに対して帰還か否かの二者択一を迫るのではなく、時間をかけて通い、安全をたしかめ、「通いながらの長期復興」という道筋であるべきだ。そのためには、帰還するまでのあいだの地域外自治体を制度的に補償するため、二重住民票と二重行政サービスを実現する必要がある。避難元自治体に住民票をもちつづけることで、自治体が、加害者である国や電力会社に対抗して個人を守る最後の砦となりうるという。
津波被災地では、巨大防潮堤建設が進められ、その背後には住宅建設が認められないことから、地域からの被災者の追いだしが進んでいる。
防潮堤建設と高台移転などの事業に限定されて復興過程が形成されることで、被害者の選択肢はせばめられ、被災地再生の足枷になっている。被災者は、その政策に「のる」か「のらない」かの二者択一が迫られ、支援は「のる」被害者だけのものとなっている。
本来「減災」を前提に、コミュニティ回復をまず優先して、無理のない防災を計画するべきなのに、防災を絶対視することで、コミュニティ再生を阻害して減災を担う主体そのものを破壊している。巨大防潮堤という大規模土木事業をすべての前提にしたため、復興政策を進めるほど地域社会は破壊され、人間の暮らしの復興を阻むという悪循環になってしまった。
震災直後の「復興が遅い」というパニックのなかで、被災地に急いで帰れという「復興パターナリズム」と、なにがなんでも津波から命を守れという「防災パターナリズム」が生じ、復興の方向性を規定してしまった。現実の状況に適合しない、復興を破壊するような復興政策が展開されることになった。
防災を実現しながら原地で暮らすこと、「減災」による原地復興の道を探るべきなのだ。
戦後長らくつづいた上意下達の政策形成は1990年代から、官民共同、住民参加を基本にしたものへと転換しつつあった。97年の河川法改正でも住民参加が柱のひとつだった。なのに、東日本大震災では、完全に古い体制にもどってしまった。
東日本における「市民社会が不在だった」という指摘も重い。
阪神・淡路大震災のボランティア活動は、国家と市場の失敗に対する、新しい市民社会への期待とみなされ、市民活動がもつ、既存勢力への対抗性・変革性を重視する「市民社会論的アプローチ」が盛んになされた。98年のNPO法もこの文脈からできてきた。
だが東日本では、市民社会に期待されていた政府に対する対抗性や社会の変革性はほとんど見られなかった。
体系的で効率的・効果的な支援が実現し、95年にくらべれば、はるかに大規模に活動できた。だが他方で、しばしば「人の見えないボランティア」といわれ、ボランティア活動における無力感もただよっていた。ボランティアが「助けあい」ではなく、場合によってはNPOの道具になってしまった感さえあった。
「ボランティアはこう動くものだ」との常識が積みあげられ、災害後の「速やかな救援」という機能性が重視され、95年にあった躍動感や創発力、活動参加にともなう充実感、工夫や遊びといったものが縮減してしまった。
NPOは新しい業界として2000年代には定着した。市民活動領域を広げたように見えるが、活動維持のための補助や助成が必要になるという逆転現象も生じ、大震災においても、市民活動の政府の下請け化という形が見えた。政府への批判の声があげられないという事態になってきた。
この本が指摘する「東日本」の問題点は、能登の問題を先取りしている。
「死者3万2000人の明治三陸津波と比べると、システムは私たちの命を守ってくれた。だが広域システムは、壊れた際のリスクが非常に大きく、復旧は難しい」という指摘は、土木工事によって普及させた「水道」が老朽化することで、数カ月も水のない生活を強いられることになった能登の現実を示している。広域化だけでなく、井戸をのこす「ハイブリッド」であったなら、地震後でも生活を維持できる集落は少なくなかったろう。
「国の手にも負えない事態が明らかになってきたときに……一部地域ではシステムからの切り捨てが行われるのではないか」という懸念も、能登半島地震後、「過疎の集落を復興するのは無駄」という声がSNSのみならず政府関係者からもあがるようになっている。
「みなどこかで遠慮して、声の大きい人にひっぱられて、やるべきでないことを容認し、それが失敗すると、たいていは弱者に責任を押しつけようとする」(245ページ)という指摘も2,3年後を見るように思える。
「東北社会の復興は、東北に暮らす人々自身で決めていかなければならないはずだ」とも言う。
権威主義的で住民の声を聞きたがらない役所があり、それに対抗する市民社会が脆弱なとき、「復興を暮らす人々自身が決める」ってどういう形になるのだろうか。
=====
▽36 国家の失敗。国が加害者。被害者は泣き寝入りするしかないだろう。避難元自治体以外に被害者たちを守るものはない。そのための最低限の手続きが、住民票の二重化なのである。人々をもとの自治体の所属のままにしておくこと。そうした補償が避難者たちには不可欠なのである。(〓地方自治が個人を守る最後の砦)
▽45 問われているのは「東北の再生は可能か」「東北はどう生まれかわれるか」なのに、出てくる議論は、国政の問題であり、復興財源の問題であり、政府・民主党への批判であり、震災による経済的影響や放射能汚染に関する専門家の見解ばかりに見える。……東北社会の復興は、東北に暮らす人々自身で決めていかなければならないはずだ
▽48 死者3万2000人の明治三陸津波と比べると、システムは私たちの命を守ってくれた。しかしこの広域システムは、壊れた際のリスクが非常に大きい。システムは大きければ大きいほど、壊れた際の復旧は難しくなる。広域システム社会はたしかに人々の命は救うが、暮らしの復旧が難しいシステムでもある。
▽51 東北の震災では、大きな災害・システム事故に対面して、国の動きは緩慢である。……この震災・原発事故のなかで、このまま動きが進まず、もし国の手にも負えない事態が明らかになってきたときに、被災社会は……一部地域ではシステムからの切り捨てが行われるのではないかと。
▽52 大店法改正にともなう郊外の乱開発と中心市街地の解体……地域再生の新手法としてとりいれられた観光開発、ゴルフ場、スキー場、宿泊施設の乱立に終わったリゾート開発……これらの開発の実行と失敗は、各自治体が主体的に選択したかのような体をとらされ、かつ負担をおった地域はしばしば立ち直れないほどの痛みをうけてきた。
「国が示したものだから間違いはない」という見解が先行し、失敗のあとには「だまされた」ことに気づきつつも、口に出せず、同じような構造をさらに再生産しつづけてきた。
2000年代には、合併のリスクを合併特例債という利益で相殺する手法によって、多くの自治体が市町村合併を選び……その結果、とくに吸収合併された地域においては、暮らしの様相を激変させ、同様に「だまされた」ものになってしまった。
こうした中心と周辺のゆがんだ関係は、医療制度改革、年金問題、公共交通問題、教育改革などにも散見される普遍的な構造となっている。
小さな社会を解体し、大きなシステムへととりこんで、中央に従属させていく。しかも、その過程で生じるリスクと失敗を、中央から一時的に巨額な利益をつかませることによってひきとらせ、結果として小さな社会へと負担を押しつけていくこと。
……これまでは原発立地の自治体だけが、唯一、十分が財源を確保し、少子高齢化を克服してきたかに見えていた。しかし……
▽80 避難自治体の統合再編を口走る人もではじめているが、避難自治体の破壊は、避難する人々にとってマイナスにこそなれ、プラスにはならない。・まして人災ならば、その機能の維持・回復は補償されるべきもののはずだ。
……原発事故の避難者は十分に結束できず、集団として抵抗できないない。だからこそ、一見ありえないはずの、東電の賠償のロジックもまかり通る。
▽83 長期にわたる避難が予想される地域では、元の地に帰還するまでの間の地域外自治体を、制度的に補償する方法を確立するべきだ。何年か後にもどる可能性も視野に入れた二重住民票と二重行政サービスのありかた、分割納税の制度についての問題を早急に整理し、解決すべき。特例のような形ではなく、他の自治体にも応用可能なものとして構想すべき。……地方からでていった人口の環流や、排出先からの税収獲得の問題は以前から提起されており、そのなかで、ふるさと納税の試行もあった。
▽100 プロセスが東京発で、利益が東京と地方で分配されること、しかし失敗の責任は地方がすべてを負うこと、こうした非対称の関係は、今回の原発事故の問題構造と同じ。
▽101 平成の大合併は、つぶれる恐怖から逃れようと、……集団ヒステリーだったといえる。合併特例債という奇妙なカネつきの、東京発の公共事業だった。
▽103 東京がもたらしてくる計画に内在する虚妄性、絶対大丈夫と無責任にもちかけてくるものの欺瞞性ことが問われなければならない。こういった働きかけがなければ、誰も原発など望むはずがなかった。
▽131 東日本大震災においては市民社会が不在だったということである。……市民社会が不在のままの政策形成が、この震災からの復興をおかしな方向へと導いてしまった。▽132 阪神・淡路大震災のボランティア活動 国家の失敗、市場の失敗に対する、新しい市民社会への期待をボランティアのうちに見出し、市民活動領域がもつ、既存の勢力への対抗性・変革性を重視する「市民社会論的アプローチ」。1998年のNPO法もこの文脈から求められてできたものである。
筆者は、(市民社会論的アプローチではなく)共同性の新しい形と理解すべきだと主張した。
▽134 ……だが東日本……では、市民社会に期待されていた政府に対する対抗性や社会の変革性は……その気配はない。
非常に体系的で、効率的・効果的な支援が実現した。95年にくらべれば、動員資源の広さ・厚さも明確だった。
……他方で、ボランティア活動をめぐってはその無力感も現場を支配していた。「人の見えないボランティア」という言い方がよくなされた。
……ボランティアはもはや助けあいではなく、場合によってはNPOの道具になってしまったかの感さえある。「ボランティアはこう動くものだ」との常識が積みあげられ、災害後の「速やかな救援」という機能性が重視されてしまって、95年にあった躍動感や創発力、活動参加にともなう充実感、工夫や遊びといったものが縮減されていた。
▽137 復興計画が被災者たちの暮らしの再建に大きく立ち塞がっており、復興がもはや大規模土木事業や地域開発を作りだすための名目へと転換してしまっている気配さえみられる。
巨大防潮堤の建設がすすめられ、その背後には住宅地の形成が認められないことから、被災地域からの被災者の追いだしが進んでいる。
市民社会には、暮らすべき人々の側から国家の暴走を批判し抗議することが求められているにもかかわらず、……
▽139 多くの人が当面は帰れないと思っている場所で除染だけが行われている。……目標を達成できず、2014年4月1日に避難指示がとかれた田村市都路地区では、空間線量から個人線量へと基準を変更することで帰還が強行される事態となった。
▽141 NPOはある種の新しい業界となって2000年代には定着した。市民活動領域を広げたかのように見える。しかし実際は、活動維持のためには補助や助成が必要になるという逆転現象が生じており、大震災も活動維持・展開のためのよい機会になってしまったかのようである。市民活動の政府の下請け化といったきけつさもたらすことになり……政府への批判の声があげることさえできないという事態に……
▽145 阪神から90年代後半まで、ボランティアや市民活動、NPOの可能性を、国家と市民社会の対抗的な枠組みのなかで多くの人が議論していたはずなのである。
▽163 二重住民票は、福島大の今井照教授が提唱。
▽170 大槌町や陸前高田市、南三陸町などでは、市街地のほとんどが流され、自治体の庁舎までもが流失し、職員や首長を失った地域も……ソサエティとしての存立基盤までもが奪われてしまった。
……大熊町、双葉町では、ほぼすべてが帰還困難区域となり……
▽172 各政策の目的に見合う事業に限定されて復興過程が形成されていることで(原発災害では除染とインフラ整備、津波災害では防潮堤建設と高台移転など)被害者の選択肢はせばめられ、被災地再生にとっての大きな足枷になっている。……被災者・被害者たちに、その政策に「のる」か「のらない」かの二者択一が迫られ、政策は「のる」被害者だけのものとなってしまっている。
▽185 コミュニティが存続の危機に陥っているなかで、過度な防災施設の建設を強いることは、防災によってコミュニティを殺すことさえ意味しかねない。本来「減災」を前提に、被災したコミュニティの回復をまずは最湯煎して、無理のない防災を計画する責務があったはずである。防災を絶対視することで、津波被害で痛めつけられているコミュニティの再生を阻害して減災を担う主体そのものを破壊し、場合によっては防災で守るべき社会さえ解体させてしまう。……巨大防潮堤という大規模土木事業をすべての前提にしてしまったため、公共事業としても防災事業としても成立せず、復興政策を進めるほど地域社会は破壊され、人間の暮らしの復興を阻むという悪循環のプロセスに。
▽188「復興が遅い」と国民のパニックに。国民全体の意向を受けながら、復興スキームは決定されていき、かたやなにがなんでも被災地に急いで帰って復興せよという「復興パターナリズム」があらわれ、他方でなにがなんでも津波から命を守れという「防災パターナリズム」が生じて、復興の方向性を強く規定してしまった。被災者の回復を助けるべきものであるはずの復興政策が、初期のパニックに引きずられたために、現実の被災地の状況に適合しない、復興を破壊するような復興政策が展開されることとなったのである。
▽194 コミュニティの環境条件を整え、……社会参加や自治を促して、より広い社会に人々をつないできたのが自治体であった。地方自治体は、国家の行政末端機構ではなく、そこに暮らす人々から見れば最小限のソサエティであり、ソサエティはコミュニティが成り立たなければ成立しないから、コミュニティを守る方向へと自治を起動させようとする。……だが今回の復興政策はもしかすると、事態の大きさに対応すべく国や県があまりに前面に出てしまったために、かえってそれがコミュニティを解体し、住民を雲散霧消させ、自治体の崩壊さえもたらす結果につながりつつあるとも読み取れそうだ。
▽202 高さ10メートル前後の巨大な防潮堤が順に建設されている。……復興がこうした大規模防災土木事業の完成を前提にしているため、防潮堤ができなければ復興を進めることができず、4年たってもいまだに土木事業以外の進展が見られないという地域がある。
▽203 原発事故被害地域の第3の道は「長期避難・将来帰還」である。廃炉に30年以上かかるなら、少なくとも30年は避難する権利が保障されなければならない。「すぐには帰れない」と思いながらも、避難元自治体から住民票を抜いていない現実も鑑みて。
津波被災地における第3の道は、防災を実現しながら原地で暮らすこと。「減災」による元地復興の道を探ること。
▽210 福島のイノベーションコースト構想。被災地・被災者の思惑を完全に超え、独自の道を独り歩き。
一関市の国際リニアコライダー 「復興」の名のもとに、……科学の欲望が、妙な実践をはじめている。
……復興予算の獲得合戦に、無縁であった科学領域までもが参入し、国際競争を勝ち抜く経済・科学・産業大国化という新たな国家像を結びはじめているようだ。こうした現象の基点に、今世紀にはじまった大学改革の影響をおくのもよいだろう。
▽217 避難者たちの本意はひとつなのではないか。今すぐ帰るのではなく、時間をかけて通い、安全をたしかめ、確保し、じっくりと復興指定行く。じこから5年をすぎて、「通いながらの長期復興」という道筋があるべき復興の行程として語られるようになってきた。
……この事故をはやく、形だけでも終わらせたい勢力の思惑と帰還政策は通じ合っている。本当の終息は、事故の原因や責任を追及し、二度と同じ事態を引き起こさない、そういう体制をつくることによってはじめて到達しうるものだ。
▽234 巨大防潮堤 その背後に住む人はほとんどいない。陸前高田でも、いったいこの盛り土の上に誰が住むのかという奇態な高台造成が進んでいる。漁業や観光で生業を営んでいた人々にとって、復興事業が、復興の大きな障害になってしまった。
▽235 「仮の暮らし」をつづけるのは3年が限界。そして地域の復興も3年を超えれば難しくなり、3年までにもとの地域を建て直し、なりわいを取り戻さなければならない。
▽239 大規模土木事業による問題解決の否定。上意下達の政策形成から、官民共同、住民参加を基本にした政策形成への転換。90年代のこの転換は、1997年の河川法改正などにあらわれた。住民参加も柱だった。
……90年代までに反省し、00年代にはその制度で運営を進めていたにもかかわらず、こうした動きへの反動・反発がおき、この震災では完全に古い体制をよびもどしてしまった。
▽245 みなどこかで遠慮して、ホンネをいわずにすましている。……結局、声の大きい人に引っぱられて、やるべきでないことを容認し、そしてやったことが失敗すると、誰かに、それもたいていは弱者に、その責任を押しつけようとする。(能登〓)





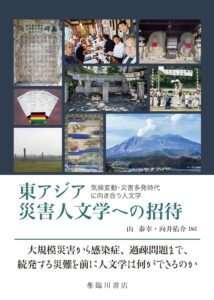


コメント