■221201
中村哲さんの35年の活動の経緯を丹念に記録したドキュメンタリー。
登山隊の医師としてパキスタンを訪れたとき、貧しい人が殺到してなにもしてあげられなかったことを悔い、ボランティア医師として再訪し、ほかの医師が手をつけないハンセン氏病の治療をする。
干魃にともなう飢えによってバタバタと子供や老人が亡くなる。いくら薬を処方しても根本解決にならない。逆に飢えさえ解決すれば9割の患者は救われる。
水源を得るために井戸を掘るが、その井戸も枯れてしまう。大河から用水路をひくことを思いつく。土木技術のあるスタッフはいない。中村みずから土木を独学する。用水路の護岸は農民たちが自分で補修できるように地元の石を積んだ。
問題は川から水を誘導する堰だ。川の流れに垂直に堰をつくろうとしても流されてしまう。筑後川の江戸時代の堰を参考にして斜めに突き出る形にした。
十数キロの用水路が砂漠に緑を復活させる。ところが今度は、大水害によって堰が崩壊する。これもまた江戸時代の堰にならって改修した。
一面の砂漠が用水路ができて2年、3年するうちに緑の森と小麦畑に変化していく映像の印象は強烈だ。
2011年に同時多発テロが起きると、反テロを理由にアフガンを爆撃する。日本もその尻馬に乗る。
中村は国会で「自衛隊を派遣するのは有害無益」と訴えた。
「正義」とか「民主主義」といった抽象的な概念よりも、そこにすむ人たちが助け合って暮らせるようにすること。まずは食料を配ること。「具体的であれ」と、中村は説く。
「反テロ」を理由にしたタリバン政権にたいする禁輸によって、食料も医薬品も貧しい民衆に届かなくなった。政治や思想は関係ない。まずは命を救うこと。
「平和」とは抽象概念ではない。小麦をつくり、ふつうに暮らせるれば、傭兵やゲリラになる人などでてこない。平和とは具体的な生活のなかにある、ということが、中村医師が復活させた広大な農地の映像をとおして伝わってくる。






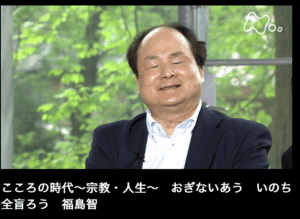

コメント