西表島の白浜と、目の前に浮かぶ島にある炭坑跡、船浮という集落にある私設資料館は訪ねたことがある。それで映画も見ようと思った。
主人公の90歳前後のおばあは台湾人。養父母とともに10歳で西表島にやってきた。
西表島のなかでも端っこの、亜熱帯の小島の森のなかにあった炭坑は、その過酷な状況から「緑の牢獄」と評された。
おばあの養父は台湾から労働者をつれてくる責任者だった。だれも来たがらないから日本人よりも給料は高く、優秀な労働者が多かったという。労働者のなかには「ならず者」が多く、警察の力を借りて働かせた。
管理者の立場から見ると「働かせるのに苦労した」。モルヒネを打てば疲れを忘れて気持ちよくなれる。モルヒネ中毒になり、台湾にもどってもモルヒネをほしいばかりにもどってくる人も多かったという。炭坑で亡くなった人の遺骨を養父がみずから台湾の家族に届けるエピソードは、「骨」が故郷にもどることを日本人以上に重視する中国文化を示す。
おばあの日常や、養父のインタビュー映像に加えて、戦前の炭坑の様子を再現するドラマ仕立ての映像も組み合わせる。
家族は死に、息子たちは島の外にでてめったに帰らず、おばあはひとり暮らしだ。隣の建物はゲームマニアのアメリカ人青年に貸しているが、「夫婦だというから受け入れたのに男1人では掃除もしない……」とおばあは不満を持っている。彼もまた仕事以外の時間は孤独でほとんどひとりでゲームをしてすごしていた。
その青年も関西に引っ越す。
蟻が出入りしないようにと丹念に掃除していたおばあも年を取る。しばしばお墓に参り、父母や先祖に「1人でふつうに暮らせる力を」と祈願する。孤独なおばあには先祖とのつながりが救いなのだ。先祖代々の墓の重みは、中国では日本以上に重い。
おばあはしだいに枯木のようになり、寝床でひとりで横たわっていることが増える。祖父母や養親の写真が飾られている家の壁も汚れ、天井も朽ちてくる。そして、蟻が列をなして家に出入りするようになる。
2018年、映画の完成を見ずにおばあは消えた。
炭坑に働いた台湾人一家の歴史が終わる場面を7年間かけて描いたドキュメンタリー。
目次






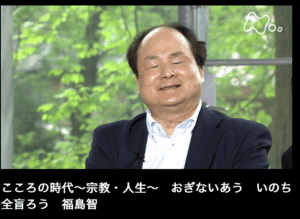

コメント