アマゾンプライムで見た。
13世紀から20世紀にいたる西洋美術史の主な作品を集めたロンドン「ナショナルギャラリー」の魅力をドキュメンタリーの巨匠が紹介する。
たとえばルーベンスの絵は、絵のなかに描かれた光と、設置された部屋に差し込む光を計算して描かれた。ローソクや教会の小さな窓から差し込む光で鑑賞した。夏は暑く、冬は寒かった。電灯の光の下とはまったく異なる見え方だった。
ガイドや学芸員が、絵の制作された時代の環境を説明し、その時代の目で鑑賞することをうながす。
女スパイであるデリラはイスラエルの勇将サムソンを誘惑し殺すために送り込まれた。でもデリラもサムソンを愛してしまう。その愛が成就したときはサムソンが死ぬ日だ。デリラに身も心もまかせるサムソン、それを悲しげに見つめるデリラ、壁の向こうには暗殺者たち……。
ペドロの死の場面を描いた絵には、聖書に描かれていない多くの木こりが描かれている。なぜ? と学芸員は問いかける。悲劇に気づかない人の存在こそがより悲劇的である、ということを示しているという。
作品の背景を知ると、1枚の絵が活劇のように浮かび上がってくる。本や映画などと異なって絵には「時間」がない。一瞬の間に物語を表現する。絵画は今の映画やドラマと同じで主要なエンターテインメントだったのだ。
金持ちが自らを描かせたはずの肖像に、死を象徴する髑髏の「歪み絵」が施されているのはなぜか? 人間の生の儚さ。見えないけれど死はいつもすぐ近くにあることを表現したのかもしれない……。
海や川を描いたターナーの風景画は光あふれている。単に風景をありのままに描いたのではなく、ある種のメタファーなのだという。大自然を前にした人間の無力さなのか、イギリスという海洋国家の不屈の精神なのか。その時代の精神を絵から想像するのも興味深い。
フェルメールは「理想的な世界」を描いたんだそうだ。遠くから見ると忠実に再現しているように見えるが、近づくと抽象画のようになるという。
作品を修復する作業も丹念に紹介する。古い作品はワニスで修復することでもとの絵の色彩が失われていることも多い。一度ワニスを取り去って、描かれた当時の色彩を復活させる。だけど、修復を施した部分はすぐに元に戻せるようにしておく。将来異なる解釈が生まれる可能性もあるからだ。
作品は作品として先入観なく鑑賞すればよい、とも言われるが、専門家の力を借りて絵を「解読」することで、作品の魅力をより深く感じられると思う。






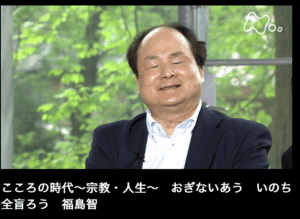

コメント