「陶王子」という磁器人形のキャラクターが、粘土をこねて器を作った2万年前から現在にいたる歴史をたどるドキュメンタリー。
土器を使わない民族は焼けた石の上で肉を焼き、樹皮などで包んで保管している。2万年前、そんな焚き火のなかに捏ねた粘土を放りこむことで土器が生まれた。普通に粘土を焼いたら黒くすすけるのに古い土器は赤色が多い。それはなぜ? そんな謎解きからはじまる。
幾何学模様を描くために、制作中の土器を回転させるロクロが生まれる。
土器では中の水がしみてくる。そこで岩石を砕いた釉薬が発明される。土器をそれにつけて焼くと、表面がガラス化して水が漏れてこなくなる。何よりつやつやした色合いに変身する。
さらに、粘土自体に岩石の成分を混ぜて焼くと、全体がガラス化して磁器になる。
磁器といえば中国の景徳鎮が有名だが、なぜ有名なのか知らなかった。真っ白な磁器や青色を出すのは当時の最先端技術で、それを持っていたのが景徳鎮だった。製法は極秘だった。それらの器が欧州に輸出され、宝石のように扱われた。
景徳鎮の白地の磁器を欧州ではじめて再現したのがドイツのマイセンだった。
一方、エジプトの青い磁器も独自の技術だったが、王朝の滅亡とともに一時技術が失われていたという。
その後、さまざまな色をつくりだし陶磁器は発展していく。発展の最終到達点として取りあげられたのが、スペースシャトルにも使われたファインセラミックだった。
陶磁器の壮大な歴史を学び、その価値を再評価することができた。「陶王子」というキャラクターを設けることで物語風に仕立てあげ、退屈せずに2万年をたどれるように工夫していた。陶磁器好きでなくても楽しめる映画だった。
目次






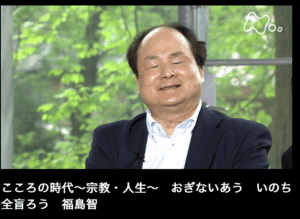

コメント