1080329
「突入せよ!浅間山荘事件」という佐々淳行作品の映画は完全に警察側の視点だった。連合赤軍という「不気味な奴ら」をたたきつぶす「正義の味方」という構図の、ハリウッドのベトナム戦争映画のような薄っぺらさだった。今回の作品はまさに「ベトコン」側を人間としてえがくことによって、その罪と、そのやりきれなさを浮き彫りにしている。
監督と主演2人の舞台あいさつもよかった。永田洋子は憎々しい役だが、女優さんはかわいい。森役の男優も学生ふうのかっこいいあんちゃんだ。その2人が「これはあの時代だけのことじゃない。自分が同じ立場だったら、と考えてほしい」と言っていた。たぶん彼らは撮影をつうじて、徹底的にそういう人間観をたたきこまれたのだろう。すごく成長したんだろうな、と思った。
作品は重く、息苦しい。
過去の話じゃない、今の話だ。今の会社組織などにはびこっている話だ。体質はなにもかわってない。克服してない。だから救いがない。
自分の生きている場、働いている場におきかえて、「今、勇気をしぼりだして生きているか」「権威に追随して人を苦しめてないか」……と自問しなければちゃんと「見た」ことにはならないような気がする。そういう意味ではノスタルジーでこの映画を見るのは魅力の半分も理解したことにならないような気がする。
「総括」という名の粛正の場面。自分だったらどうするだろう、と何度も何度もつきつけられる。
はじめは言葉での批判と自己批判だった。赤軍と革命左派という組織が一緒になって連合赤軍を結成し、革命左派側のトップだった永田洋子が赤軍側からつるしあげられる。その意趣返しが永田洋子から赤軍側の女性らにむけられる。
言葉によるイジメだけだったのが、行軍訓練という体罰を強いるようになる。このころにはもう「総括」の要求は上から下へと一方的に発せられる。次には殴打することによって、思想改造を「援助」し、共産主義的な人間になることを強いる。援助という名の暴力によって死亡した者は「敗北者」だった。ついには、森と永田の意に添わないものに「スターリニスト」といったレッテルをはって「処刑」するにいたる。
最初の1人が「総括」という名のリンチをうけるとき、一部は疑問に思い、目をそむける。でも森と永田がこわいからしぶしぶしたがう。でもそれが自分におよぶとはまだ思っていない。
次々に犠牲者が増える。
「過去の自分を自己批判せよ」とつきつける。なにも言わなければ「なにも反省することがないというのか」と責め、「彼と寝てしまいました」「資金をくすねてパンタロンを買ってしまいました」と言えば、それをもとにリンチされ殺される。逃げ場がない。黙っていても口を開いても殺される。
独裁者というのは、理不尽にふるまえばふるまうほど暴君の権威を身にまとう。独裁者が理性的だったら、それに理性的に適応すればよいのだから「専制権威」にはならない。それができないから独裁者は恐怖の対象となる。
本来は対等な議論のためにあるべき「自己批判」は、暴力がともなうと上から下への一方的な要求になる。永田洋子の女性同志いじめ(殺害)は嫉妬によるものだった。森は自分の無謬姓だけを信じきり、他人の小さな過ちをいっさい認めず、怒鳴り声による支配を確立した。
学生運動の組織じたい、もともとボス支配の体質はあった。声の大きいものが権力をもつ、という体質だった。実力と自信をかねそなえた人間がトップにいるあいだはそれでもうまくいっていた。
だがリーダーの森は、過去に組織から脱走するというトラウマをもっていた。幹部がすべて逮捕されたためにトップに立った。そういう「弱い」人間にかぎって、自分が権力をにぎると過去の自分のような弱い人間を許さない。
……そう、これらは、会社組織でよく見られる光景なのだ。連合赤軍は、会社組織の極端なアナロジーである。
でも唯一、ちがうところがある。会社では少なくとも直接的には人は殺さないということだ。
やはり「暴力」をふるう組織では支配の手段に暴力がつかわれる。戦前の帝国陸軍はまさに連合赤軍だった。今は軍隊という暴力が少なくともタテマエでは否定されているいからこそ、人殺しまでには至らないですんでいる。
憲法9条というタテマエの大切さはこの映画からも感じられる。






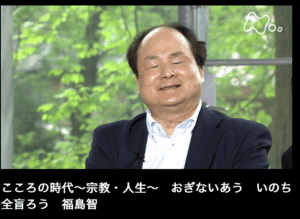

コメント