■ニュータウンの「夢」建てなおします 向島からの朝鮮 <杉本星子、小林大祐、西川祐子> 昭和堂 20151127
京都の南部にある向島ニュータウンといえば、荒廃した人工都市というイメージがある。公営住宅の収入による入居制限を強化した結果、社会的弱者だけが取り残されてしまった。その結果、自治が機能しなくなり、すさんできた。他方、ニュータウン内にある公団の賃貸や分譲部分は一定の収入がある人が住んでいるから環境が保たれている−−。向島ニュータウンについての私の印象はこの程度だった。
そんなニュータウンに、京都文教大学は20年間かかわってきた。その間の記録がまとめられている。
このまちの荒廃問題は私も一時期調べたことがあったが、どこからどう手をつければ改善できるのか、まったく見えなかった。一人暮らしの老人のデイサービスや配食サービス、子どもを集める活動など、個別にやるべきことは思い浮かぶが、それだけで巨大なまちを立て直せるとは思えない。
ところが文教大学の各分野の専門家や学生が入りこみ、住民と協力することで、ニュータウンの全体像を把握し、そのなかに芽生える個別の活動を大きな枠組みのなかに位置づけ、ニュータウン再生の動きに発展させてきた。
東京の高島平をはじめとして、高層建築が林立するのは荒廃の一要因とみられたが、密集した住宅群は多様な人材が集まっていると考えられるようになった。人が集まっているぶん、そこには新たな商売やサービスの可能性がある。荒廃に焦点があたっていた公営住宅は、自治会が組織されているぶん、公団の団地よりも人と人を結びつける活動がしやすいという側面もあった。生協や趣味のグループなど、地縁とは別の新たなネットワークも重層的に生まれていた。若者が熱狂するラップもこのまちから生み出されていた。
十数年前に数カ月間、公営住宅を取材したとき、その荒廃の実態は見えたが、将来の可能性までは見通せなかった。大学が地域にあり、専門家がチームをつくって住民と手を取り合うことで、あきらめに覆われたまちに「希望」をもたらすことができる。そのことに驚かされた。
=====================
▽5 共同研究はまず、ニュータウンを定義しようとした。…特殊な存在として見るのではなく、良くも悪しくも時代の先端部分、少子高齢化をはじめ社会全体が抱えている問題が最も先鋭な形を取っていきられている空間であるという共通認識が生まれた。ニュータウンで起こっている諸々の事態は、社会全体が今後進みゆく傾向の先取りではないか。
「ニュータウンは出自を異にする人々が居合わせて住む人工的な計画都市であり、国土開発の枠組みのなかで戦略的プランニングに基づいて創出され、空間設計のパターン化が見られる」という定義に。
(定義をつくってしまう、というすごさ)
▽10 日本型ニュータウンの特徴は、初期入居時から、それまで多かった三世代同居用の設計がキッパリとないこと。間取りそのものが三世代同居や傍系家族あるいは同居人の存在を前提にしてない。
▽「家」家族イデオロギーは親孝行を優先させるが、「家庭」家族イデオロギーは排他的家庭団らんが最優先だといえそうです。「家庭」イデオロギーはサラリーマンの夫と専業主婦である妻との性別役割分担を強固にさせる。
…個人主義で知られるフランスだが、石造高層集合住宅の住戸には必ずといってよいほど玄関に当たる主たる出入り口の他に裏階段に通じるもうひとつの出入り口がある。各住戸には少なくとも2つ以上の暖炉をつけることが法律で義務づけられていたそうです。…災害時に避難者の同居を受け入れるため。
…公共空間への開口部がひとつしかなく、臨機応変の同居受け入れがほとんど考慮されていない日本型ニュータウンの一住戸ごとの完結性・排他性はかなり特殊。
▽12 西山卯三 「家庭」家族が私生活をいとなむための容器として「これからのすまい」を建てなければならないと主張した。
▽15 ワンルームという居住空間モデルが創出されたのが、1976年。早稲田大学に近い住宅地に最初に建設されたワンルームは16.7平方メートルという極小空間にバス、トイレ、ミニキッチンを装備した設計だった。
▽オイルショック語、アメリカの圧力で、内需拡大へ。住宅を購入させ、ローンを組ませることが最も有効。
▽19 わたしは次第に住宅論から都市論へと研究対象を移し、都市論のなかでも郊外のニュータウンに焦点をあてて、社会学や文化人類学、心理学の研究者たち、建築家や都市計画の専門家たちの研究会に参加するようになりました。
▽20 個室の獲得こそが疎外を生み、ニュータウン問題の元凶がそこにあるというような短絡的な論評もしばしば見られる。しかし「一世帯一住戸」の次に「一人一部屋」という目標が人々を動かしたように、個人の自立、個人空間の獲得は、長い時間をかけてようやく実現させたものです。…良くも悪しくも「自立と孤独」という現実から出発して個人の生活とニュータウンの建て直しをするほかないという住民の気持ちを「ニュータウンを生き抜く」と表現しています。
…個室に閉じこもっているだけでは、生きてゆくことは難しそう。じょじょに身に迫る危機感に動かされて今、住民は、各住戸の思い鉄の扉を身長に開き始めているのだと思います。私領域/公領域の境界線が動き始めている。
▽22 国家>家族>個人の入れ子構造から脱出し……中間集団あるいはコミュニティを強化するだけでなく、他方でコミュニティの境界からも抜けて外につながるネットワークを形成しておくという知恵。…複数の所属を用意し、それによって個人の主体性が分裂するのでなく、逆に主体性が確保されるのだという考え方があるのではないでしょうか。(中間集団の消失がナショナリズムを生みだす。それを防ぐには中間集団を取り戻すだけでは足りない。中間集団があったころの閉塞感も思い出しておかなければならない〓)
▽23 ニュータウン建設時、入居者は与えられた選択肢から選ぶだけだった。開発時の輝く新都市の夢は与えられた夢でした。再建の時になってはじめて住民は再建の行為主体とならざるをえず、選択肢そのものの発明と創出をはじめている。(〓主体性が生まれる、という視点で見ると、希望が見えてくる。中間集団も主体性を制限している面があった)
▽25 鵜飼正樹の便所についてのコラム 男性用小便器がなくなってしまったことは、家庭内政治学的にも大きな意味があるのではないか。最近は「洋式便器 男は座って小用を」
▽31 京都市の団地再生計画
▽34 改良住宅 政策的な低家賃制度が廃止され、公営住宅と同様の「応能応益」家賃制度が適用され、公営住宅よりも人口減少と少子高齢化が急速に進んだ。
▽47 小林大祐 団地リノベーションコラム
市営桃陵団地 スターハウスが6棟現存。
公団桃山団地 近年大規模な改修工事がおこなわれ、昭和の団地の景観がよみがえった。
公団観月橋団地 2011年から「リノベーションプロジェクト」。多様な間取りに大胆に改造し、「KANGETSU-KYO DANCHI」に再生し、若者たちの申し込みが殺到した。
▽88 保見団地 居住者のほぼ半分が外国人。トヨタと関連会社につとめる労働者とその家族。地域住民やNPOによる長年の努力で、団地は、市内でも犯罪の少ない地域に。…いまや外国人住民が多いことは「問題」ではなく、地域の特色となる人的「資源」として考えるというような、発想の転換が求められています。
▽絵はがき展 西川祐子ゼミの我雨声たちが、1998年に大学と周辺の社会的文化的環境を調べはじめたことに端を発している。
▽100 大学とまちづくり協議会、向島図書館。三者が共同でひとつの事業を実施したのは、絵はがき展がはじめて。住民による資料提供、図書館による場所の提供、大学による撮影技術・加工技術・データ整理技術・機材の提供。
▽子育て支援
▽112 関西で子育て支援の実践と研究を行っている服部と原田は「大阪レポート」と呼ばれる、1980年生まれの子どもたちを対象とした大規模な子育て実態調査の集計分析をした。…
▽115 ママさんサポーター 大学生が三才未満の乳幼児をかかえた専業主婦の家庭に定期的に訪問。母親は、我が子を介してサポーターに基本的な育児を教えると同時に、子どもがサポーターに遊んでもらっている間に目の届くところで家事をしたり…。
…研究活動の側面から、サポーターには毎回の活動日誌をつけてもらっている。これは活動の様子を把握し、サポーターの心境の変化をつかむため。
…サポーターが馴れていない若者だからこそ、母親がいろいろ教えてあげたいと思えたり、構えることなく接したりすることができる。
▽131 障がいのある住民
▽151 中国帰国者が1000軒 中国向きのパラボラアンテナの数でカウント。空き家を含めた住戸の16.7%にのぼる。
ニュータウンの商店会に「煕麟商行」という中華食材や雑貨を商う商店が2004年にオープン。
2009年、NPO法人「中国帰国者京都の会」が設立。帰国者支援のNPOとしては、東京に続いて二番目。事務所は小栗栖団地に設置。日本語教室も。
▽ニュータウンに生まれた祭り
▽182「向島まちづくり憲章」 向島駅前の葬儀場建設計画への反対運動。その組織をもとに「まちづくり協議会」を結成。「憲章」を見た学生が「僕たちも一緒にやらせて下さい」と言ってきた。
▽184 1970年代から80年代にかけて、自治会を中心に夏祭りや運動会が盛んにおこなわれていた。子ども会活動も盛ん。しかし初期入居者の子どもたちが小学校を卒業し中学に入ると、住民同士の行き来も少なくなってきた。「いつも廊下にむけて開いていたドアがいつのまにか閉じて、我が家も隣家もなく出入りしていた子どもたちの姿が消えていました」
▽大学と向島駅のあいだの通学路にゴミが多く、しばしば朝から痴漢が出るため、たった15分の距離を歩くのを嫌ってスクールバスを使う結果、学生とニュータウンの住民との間にまったく交流がないということに気づいた学生たちがいました。「勝手に道路掃除します」と「文教ストリートプロジェクト」ができた。
…地域の農家とニュータウンの消費者を結ぶ。学生が地元の野菜を売る。
▽191 日本の祭りは、本来、生業や生活を支える心のよりどころである神を祀る行事。ニュータウンの祭りには、人々に祀られて祝福を与える神様がいません。子どもが成長して転出していくと、神様のいないニュータウンの自治会の祭りは、むしろ住民たちの負担になっていった。
住民と学生がはじめた新しい祭典にも神様はいない。しかし、様々な街区の自治会、近隣にある諸団体を巻き込むことで、ニュータウンの歴史のなかで育まれてきたさまざまなグループを重層的につなぐネットワークをつくりだしてきた。日本の伝統的な祭りが、長老を頂点とする垂直の村落構造に支えられた「むら」の祭りであるとするなら、ニュータウンの祭りは、水平構造の「まち」の祭り。
▽194 アナーキーさん〓という世界的に活躍するラッパーがここ出身。ニュータウンを舞台にラップが生まれた。MJ
▽197 高蔵寺ニュータウンの林明代コラム 地域情報紙「タウンニュース」発行。「NPO法人まちのエキスパネット」。「高蔵寺ミュージックジャンボリー」」(2014年に7回目)。高蔵寺駅北口に「バルカフェ ボーノ」をオープンさせた。
▽201
▽208 公団賃貸から戸建て住宅に移動した人たちが高齢化して、再び賃貸住宅を選ぶ「戻り入居」が増えている。…荒廃の側面ばかりが強調されるが、…わたしたちは、ニュータウンは衰退しているのではなく変化しているのではないか、高齢者のあいだでは閉じた住戸を安全にひらいて他者とつながろうとする動きが、若者のあいだには所有よりもシェアをえらぶ傾向など新しい価値が生まれているのに、それが見過ごされているのではないか。
▽211公営住宅の街区は問題地区というまなざしで見られがちだが、そうとばかりは言えないことがわかってきた。市営住宅は自治会がしっかりしているので、どのような人が入居しているか、だいたい把握されています。ニュータウンのなかで、今も年に一度の夏祭りをやっているのは、市営住宅の住棟だけです。…福祉関連の部局が積極的に関わってくれる。困ったときに助け合う老人たちの互助会グループもできている。
…公団分譲の街区では、同じ棟にどのような人が住んでいるか、管理組合の役員さんでさえも十分には把握できていない。公団賃貸となるとさらに隣人関係は希薄。福祉行政は公団の住戸に暮らす人々に目を向けない。こうした街区のほうがむしろ高齢者の孤立問題は深刻なのです。
▽215 ニュータウンにはさまざまな形の住戸があるので、住み慣れた土地を離れることなくライフスタイルに合わせた住戸を見つけることができる。
▽222 ニュータウンには、住民一人ひとりの生きた歴史が重層した壮大な歴史が埋まっています。…そこに暮らすさまざまな住民のつぶやきを聞き取り、住民の目線に寄り添うと、無機的な空間が懐かしい場所としての意味を帯び、そこに流れる時間がかけがえのない記憶となります(〓団地の記憶。街路樹)
▽230 …野火的活動がつくりだすのは、自治会や町内会を基盤とし、全体としてひとつの組織を形成するような地域コミュニティーではありません。さまざまな活動や団体がそれぞれ自律的に動きながら、いろんな場面で連動していくような関係の重層性によってつくりだされ、地域の外にも広がっていく地域コミュニティー/ネットワークです。ニュータウンの「夢」は、こうした地域コミュニティが生成されるなかでこそ再建されていくのではないでしょうか。





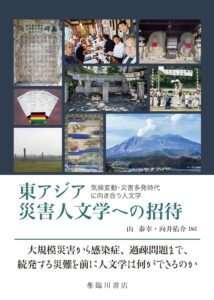


コメント