■日刊現代(講談社)250201
2011年の東日本大震災は、発生28分後に「緊急」災害対策本部。16年の熊本地震は発生44分後に「非常」災害対策本部を設置した。
能登半島地震では発生から1時間20分たって、もっとも軽い「特定」災害対策本部、4時間後にようやく「非常」災害対策本部となった。しかもその最初の会議は17時間後だった。その後の仮設住宅建設なども非常識なほどに遅かった。
能登半島地震のあまりにおそい対応の原因はなんなのか、どうすればよかったのか。「政治」側から解き明かしてくれることを期待して、この本を購入した。学べることもあったが、内容は薄かった。
1995年の阪神淡路大震災では、後藤田正晴の助言で村山富市首相が小里貞利を発災3日後に担当相として現地に派遣し、陣頭指揮をとらせた。各省庁から事務次官クラスを小里につけて現地に派遣した。現場ですべて決めることができる「もうひとつの政府」を作った。その瞬間から復興作業が進んだ。大災害が起きたとき、政治判断できるトップを派遣して「現地政府」をつくることがまず大切なのだ。だが東日本ではそういう対応にはならなかった。
中越地震では、新潟県や長岡市などは、「復興基金」の仕組みをつくった。「自由度が高いお金があれば、現場しかわからないような重要なところに使える」からだ。
能登半島地震はどうだったか。
東日本大震災で菅直人が批判された首相の早期現地入りは、警備負担が大きすぎる。だが岸田首相は14日後に被災地を訪れた。一方、早期に現地を見るべき県知事は岸田が来る日まで能登に行こうとしなかった。
東日本大震災被災地の議員は「なにが起きているかわからない。ならばすぐに現場に入るのが政治家でしょう。地元の政治家は歩いてでも入るべきです」と言った。だが能登半島地震では、国会や政党が現地入りを制限した。それを破って現地をたずねた山本太郎の報告を、維新の音喜多は「そんなことは現地にいかなくてもわかる」と口汚くののしった。ここまで現場の意味がわからない醜悪な政治家が生まれているとは驚きだった。
岸田は、被災地支援の予算を予備費で確保したと自負するが、各省庁の枠があり使い勝手が悪い。自治体が自由につかえる「復興基金」をつくるべきだと筆者は言う。
=====
▽16 2011年の東日本大震災は、発生28分後に「緊急」災害対策本部を設置。16年の熊本地震は発生44分後に「非常」災害対策本部を設置。
能登半島地震では、発生から1時間20分もたって、もっとも軽い「特定」災害対策本部、4時間後にようやく「非常」災害対策本部。しかもその会議は17時間後だ。
▽17 平時は政府の行政手続きというものは、だんだん段階を上げていくのが常道だ。しかし災害有事や危機管理はちがう。最悪を考えて最初に大きく広げ、大丈夫なら狭めていくべきなのである。
▽21 1995年の阪神淡路大震災では、後藤田が村山首相に「天災は人間の力ではどうしようもない。地震が起きたことはどうしようもない。しかし、起きたあとのことはすべて人災だ」と告げた。「生命優先でやれることはなんでもやれ。ルール違反だってかまわない」と叱咤した。
村山は、小里貞利を発災3日後に担当相として現地に派遣し、陣頭指揮をとらせた。「現場が欲しいものは何でもやる。法律違反と言うならば自分が法律を変える」とまで行って送り出した。官房副長官だった石原信雄は、各省庁から事務次官クラスを選び、小里につけて現地に派遣した。何でも現場で判断して決めることができる「もう一つの政府」を現場に作った。現地政府のトップは政治判断できる政治家でなければ意味はない。官僚では法や制度にしばられるからだ。
……
▽23 岸田首相は発生から14日目に現地入りした。警備のため県警の警察官は大量に動員され、自治体などからも多くの職員が動員される。
……東日本では、菅直人首相が現地に入り批判をあびた。その教訓を岸田は学んでいないのか。
▽32 地震国イタリアでは、キッチンカーやトレーラーハウス、トイレなどを大量に常備している。
▽41 中越地震 災害復興住宅の建設を決めたが、長岡市は急がなかった。住民が移転を決意するまで待った。市は、住民の会合のたびに民間アドバイザーをやとって参加させ、心のケアや集団移転の疑問点に答えるなどした。……5年後にようやく住民たち自身が復興住宅に移ることを決意した。
▽45 新潟県や長岡市などは、「復興基金」の仕組みをつくった。
「自由度が高いお金があれば、現場しかわからないような重要なところに使える」
▽49 岸田首相は、能登半島地震の支援について予算を確保したことを自負するが、邦がその使い道に関わるカネは現場のニーズとずれるということを過去の災害は残してきた。予備費ではなく「これだけの額を、復興基金制度を作ってそこにつぎこむ」「使い道は地元自治体が決めていい」といった対応はできないものか。【自治体がひどい場合は……】
▽59 「地震」の場合は「対策本部」を直後に設置していたが、「雨」の際は数十時間後に設置しているケースが多い。
▽68 現場でモノを決めることができる権限をもった政治任用のトップを置かなければならない。
▽106 メディア 災害報道においては、「誰のために」「何のために」という方向性や専門性がメディアには必要であり……
▽111 石巻市の「石巻日々新聞」は、津波で輪転機が水びたしになった。「壁新聞」しかないと決意。戦時中の言論統制があったときに、先輩たちが壁新聞を出したという歴史があった。
……地域紙の役割は、……生活情報を主に提供しようと……。
▽127 輪島の避難所に、コンビニチェーンからおにぎりが届けられた。おにぎりは500個。避難者は900人。自治体職員は不平等が生じるからと配らなかった。900個までそろうまで待って配ったという。「トイレ設置や毛布などについても、そろってからという避難所がずいんぶんあった……
▽138 災害対応というのは「徹底した現場主義以外にない」
▽140 阪神では、現場に「もう一つの政府」をつくった。この瞬間から現場の対応や復旧が飛躍的に進んだ。
熊本地震では、副大臣が派遣されたが、あくまでも政府の伝令役であり、決定権をもつ立場ではなかった。
▽155 石原 (阪神の際のように)仙台あたりに(第2の)政府を置けばよかった。なのに・・・
「非常事態のときは官邸の意思決定部門は少人数で決めるべきです。シンプルに決めてシンプルにやる……それが危機管理です」
▽石巻日々新聞 武内宏之 「絆の駅 石巻ニューゼ」館長をつとめた.住民がきて悩みを相談する場に。……
▽170 被災者にとっては、まず住居、次に仕事。町づくりのグランドデザインよりも、そちらを優先するべきでは。
▽172 復興住宅や町並みの再建など形ある政策を実行しても、いつまでも引きずるのが「心」。
▽175 武内「天国にいる大切な人とつながることを自分なりの形で見だした人は前を向き始めることができるようです。……私はもう20年ほど前に妻を亡くしています……」
▽176 武内「これからは東北が恩返しの出番になってくる……10年間のノウハウを我々は持ってきた。それを発揮するときがくると思います。……」
▽197 村井知事の掲げた「創造的復興」は、まちづくりのモデルケースをめざすものである
▽204 達増知事 単独省庁でできる仕事についてかなり早い。ところが複数省庁にまたがると、非常に遅いし、いつまでも決まらない。発災直後の燃料不足はまさにそうで……被災地になかなか燃料が届かなかった。
▽207 土地問題。2018年にようやく、所有者不明の土地については、地域の公共的な事業のために10年を上限として、使用権を設定できることになった。
▽207 災害時でも、霞ヶ関が権限を手放さない……復興関係の予算でも、かなり紐付き補助金みたいな感じが多い。自治体が自由に使えるようなかんじになっていない。……
▽217 森・長岡元市長 避難所の世話とか救援物資を配るといった初期のボランティア的な派遣の次は、事務処理などができる実務的な職員の派遣が必要です。その次に、土木技術の仕事が中心になってくる。中越のときは、62自治体から長い人で3年間も長岡に滞在した。
▽234 小野寺「なにが起きているかわからない。ならばすぐに現場に入るのが政治家でしょう。地元の政治家は歩いてでも入るべきです」
能登半島地震では、国会や政党が現地入りを制限した。いち早く現地に入るのが議員の役割なのに。【音喜多の醜悪さ】
【石川県の創造的復興は猿まね以上ではない】





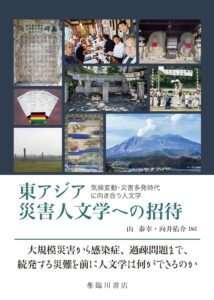


コメント