■宝島社新書20201223
ナショナル・ギャラリー展を大阪で見て、西洋美術史を理解したくなった。印象派とかバロックといった言葉は聞いたことがあるが、それがどんな意味を持つのか、初歩の初歩を理解するための格好の入門書。
ナショナルギャラリーは、西洋美術史の基本的な絵を網羅し、時代背景や美術史が理解できるように工夫されてる。
東ローマ帝国で花ひらいたビザンチン美術は二次元性と超人性を強調したのに対し、初期ルネサンス(13−14世紀)は、写実性が高かった古代ローマ様式を復活させて三次元的空間を表現した。二次元空間は天上世界を、三次元空間は人間世界を表すという。だから「復興」なのだ。
15−16世紀になると、アルプスの北方のフランドル地方で「北方ルネサンス」がはじまる。油彩技法はフランドルで完成た。
イタリアは古代の伝統が強く、古代ギリシャ・ローマの貨幣に刻まれた横向きの肖像に従い、1500年ぐらいまでは側面像が好まれた。4分の3正面像はフランドル絵画特有だった。
シンボリズムの解読も興味深い。りんごは原罪、オレンジは無罪。温暖な地域でしか取れないから、北ヨーロッパでは富の象徴だった。脱いだサンダルは神に誓いを立てている。風俗画においては靴を脱ぐことは性的に奔放であることを意味するようになるという。
盛期ルネサンス(15世紀)のレオナルド・ダ・ヴィンチは輪郭線のない描写が驚異的だった。ラファエロやミケランジェロが活躍した。
従来イタリアでは大壁面の装飾は壁に直接描くフレスコ画だったが、16世紀のヴェネチアでは湿度が高いため油彩画が好まれた。造船業が発達していたため、木製パネルよりもカンバス(帆布)が好まれ、色彩豊かなヴェネチア特有の絵画文化が発展した。スペインなど遠方からの注文に応えられたのは、カンバスに描く油彩画は移動が可能だったからだ。
15世紀末に大航海時代を迎え、香辛料貿易のルートが変わって、ヴェネチアの経済は落ち込むが、16世紀のヴェネチアは最先端のファッションの発信地だった。
16世紀、宗教改革期のドイツは絵画も影響を受ける。
プロテスタントは聖書を絶対的権威とする福音主義を取った。ルターは聖像崇拝に関して寛容だったが、カルバンは徹底的に批判し、祭壇画や彫像など聖像破壊運動が起きた。そのためプロテスタント圏の画家の収入源がなくなった。
歴史画、肖像画、風俗画、風景画、静物画というヒエラルキーが17世紀には確立している。歴史画以外の発展の背景には、都市経済の繁栄に伴う市民階級の台頭があった。
スペイン支配下のネーデルランドでは、プロテスタントが急増した結果、宗教画の注文が減り、風俗画や風景画といったジャンルが発展した。市民階級によるプロテスタント社会となった17世紀のオランダでは、風俗画同様に風景画が人気を博した。
一方、カトリックは一層、宗教美術の力に頼るようになる。信仰心を高めるため、感情に訴える「わかりやすさ」と「高尚さ」のある絵を求めた。それが17世紀のバロック芸術だった。
17世紀イタリアでは、風景を描く際も、高貴とされた歴史画的主題を組み合わせることが求められた。
1609年(1579年)にオランダがスペインから独立。
オランダはプロテスタントのカルバン派が国教となった。教会の祭壇画の注文が入らない一方で、プロテスタントは自国語で記された聖書を読むことを重視したから識字率が上がり、聖書の物語は馴染みのあるものだった。人気画家レンブラントらが活躍した。教会美術の需要はなくなり、絵画の購買層が市民階級になったため、サイズも小さめが多く、ジャンルも多様化した。画商が台頭し、現代的な絵画の流通システムが確立した。
市民階級が求めたのは、日常生活をあらわした風俗画や、風景画、静物画だった。人気を博した風俗画は、格言や教訓、信仰生活への導きが込められている。
「風俗画で鶏が描かれている場合は性的な意味が含まれる。空の鳥かごは純潔の喪失。楽器ははかない快楽の象徴。楽器を演奏中に描いた場面のほとんどが、売春宿か居酒屋」といった読み解きもおもしろい。フェルメールの絵でも、背景の壁に売春宿の光景を描いた画中画があるものは肉欲に対する戒めを意味したという。
食べ物を描いた静物画も、プロテスタント倫理観や禁欲的なメッセージが込められた。根底には「死を思え 死を忘れるな(メメント・モリ)」の思想があり、たとえばひっくりかえった銀製品や割れたグラス等は、食事が突然中断されたことをあらわし、人生の終焉といった「儚さ」を想起させるという。
写実的に描いた純粋な意味での風景画がジャンルとして確立したのは、市民中心の近代社会をいち早く樹立した17世紀のオランダだったという。
18世紀になると繁栄したイギリス人を中心に、イタリアへの大修学旅行「グランド・ツアー」が流行し、ベネチアが人気になった。写実的な都市景観図が「イタリア旅行の思い出」として求められた。
19世紀のイギリスは、工業化によって市民階級が台頭して愛国心が高まり、それまであまり美しいとみなされなかった自国の田園風景も、郷愁を誘う「ピクチャレスク」とみなすようになっていった。そうした絵画は、「理想的風景画」に縛られていたフランス人画家たちに衝撃を与えた。
ターナーの評価が高いのは、ただ自然を描くのではなく、人間のドラマも表現しているためだという。19世紀においても絵画は主題性(物語性)が重視され、感覚的なものに対する評価は低かった。
18世紀後半のフランスでは、市民社会の日常を美しく穏やかに描いた風俗画が描かれ、軽薄で官能性が強調されたロココ絵画は、堕落した貴族を象徴しているとみなされて勢いを失った。デッサンを重視する写実性の高い新古典主義の画家たちは、写真が登場するまでは肖像画家としても需要が高かった。
フランス美術界は、デッサン派(新古典主義)と、色彩派(ロマン主義)の2つの潮流がせめぎあう。
新古典主義の歴史画の主題である神話や聖書がラテン語で書かれたのに対し、ダンテやシェークスピアなどロマンス語で書かれたロマンスから生まれた「ロマン主義」が、歴史画至上主義だった新古典主義への対立語となった。
ロマン主義絵画には、中世の騎士物語や身近な近世史が好んで描かれ、同時代の事件も「歴史」として主題にされた。
19世紀のフランスでは富裕なブルジョワジーが台頭。より感覚的なロマン主義絵画の発展に影響を及ぼし、風景画に現実的な景色を求めるようになっていく(バルビゾン派)
一方、印象派は「なにを描くか」ではなく「どう描くか」を探求することで、近代絵画の時代を開いた。マネによってその定義が方向づけられ、モネとルノワールによって、印象派を象徴する技法「色彩分割」が生み出される。
見たものを忠実に描くのではなく、自分が受けた印象に対して忠実であろうとする。絵の具は混ぜるほど暗くなってしまうから、光り輝く自然の瞬時性を表現するため、絵の具を混ぜずに色彩分割法を使った。その結果、印象派の作品は眩しいまでに明るく、筆触が目立つものとなった。モネにとってこの技法を探求するのに水面が格好の題材となった。
ドガは「印象派」と呼ばれることに抵抗。中期以降の作品には浮世絵の影響も受けた。
セザンヌの形態を単純化し、三次元の対象をいったん解体し、再び複数の視点で対象を捉えて二次元の画面で再構成する造形性は、ピカソらによって、キュビスムの誕生へと発展していく。
ゴーギャンは、目で見た印象しか表現しない印象主義に不満を抱き、「主観と客観」、「現実と非現実」、「色彩とフォルム」を統合し、造形的に思想や観念を表現する総合主義を確立した。
ゴッホのヒマワリは、描く対象を写実的にではなく、その対象にまつわる自分の感情を作品に表している。こうして、印象をあらわした印象主義ではなく、画家個人の内面的な感情を表した表現主義が生まれた。絵画を外から受ける「印象」を描くものから、自分の内面を「表現」するものにし、印象主義を新たな方向へ導いた。






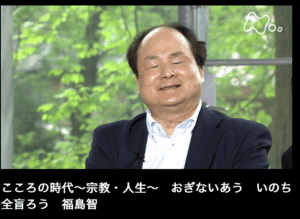

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 「魚市場」(1568)、「台所」(1620ごろ)などの日常生活を描くことがふえた。 以前に読んだ「教養としてのロンドン・ナショナル・ギャラリー」を思いだした。美術史を勉強するには最高のコーナーだった。 […]