■日本フォーク私的大全 <なぎら健壱> ちくま文庫 20120929
1960年代の大学生のキャンパスフォークから70年代のアングラフォーク、吉田拓郎や井上陽水らのニューミュージックに至る日本のフォークソングの流れを、自らその渦中にいた筆者がつづる。フォークをもう一度聞き直したくなった。
それまでの既製の音楽とちがい、フォークは歌い手自らが作詞・作曲をした。素直に本音を歌う姿に若者たちは共感した。
1963から65年にかけて森山良子ら大学生のフォークグループが次々にでき、「バラが咲いた」「若者たち」などのヒット曲が生まれた。お坊ちゃん、お嬢ちゃんを相手にする音楽というイメージだった。
高田渡や高石ともやは、フォークには人に訴えるものがなければいけない、と考えてお坊ちゃん路線を卒業する。高田は、ピート・シーガーらの影響を受け、自由民権運動での書生節であった添田唖蝉坊らの演歌の詞を積極的に取り上げた。
フォークの神様と呼ばれた岡林信康は、69年の労音のコンサートを最後に蒸発した。当時の労音では歌った後に「討論会」を求められた。ジャンボリーでは、大半のシンガーに「帰れ」コールを浴びせた。そうすることで観衆はジャンボリーに参加していた。もんたよしのりは、ロックバンドをしたがえていたから労音で批判のターゲットになった。
時代の熱が冷めるとともに、シングアウトの曲としてもてはやされた「友よ」も、シラケたムードでとらえられるようになる。日本のフォークブームは、岡林にはじまり、岡林と共に終わった。
その後、フォークは軟化していく。吉田拓郎はその転機となるミュージシャンだった。拓郎の周りには女性ファンが集まった。アングラ系のコンサートに拓郎がでると「帰れ」コールがすごかった。
拓郎らのナンパのフォークを支えたのは、アングラ・フォーク創成期に小中学生だった世代だ。兄や姉の聴いていたフォークを、自分たちの音楽として聴くようになった。彼らには反戦も社会に対する抵抗もすでに関係なく、フォークの匂いのする、心地よい音楽であればよかった。レコード会社も眼を付け、アイドルや歌謡歌手にフォーク調の曲を提供し、内容の薄っぺらな青春歌謡が増えていった。
アリス、イルカ、かぐや姫、さだまさし、ばんばひろふみ、オフコース、中島みゆき、浜田省吾、松山千春……それまでフォークと呼ばれていたジャンルの音楽はニューミュージックと呼ばれるようになった。
一時期衰退したフォークは95年ぐらいからまた若者の間で復活してきているという。どんな時代背景があるのだろう。
井上陽水・海援隊・チューリップ・甲斐バンドと、九州出身のミュージシャンが席巻した時期があったが、その理由と背景も知りたい。炭坑の閉鎖などと関係があるのだろうか。
========メモ抜粋===========
□高石ともや
▽15 63から65年にかけて大学生のフォークグループが次々にできる。森山良子ら。だが、お坊ちゃん、お嬢ちゃんたちを相手にしたような音楽というイメージだった。66年の「バラが咲いた」「若者たち」など第一次フォーくブームに。そんななか67年に異色の、フォークルの「帰って来たヨッパライ」。
高田渡「三億円強奪事件の唄」……フォークには、人に訴えるものがなければいけない、これが高石のいう、既成の歌謡曲とは違うところ。
▽32 73年、「宵々山コンサート」をはじめる。
□岡林信康
▽40「フォークの神様」 69年の労音のコンサートを最後に蒸発。歌った後に「討論会を」といわれ、「疲れてるから」というと「スター気取り」といわれることに嫌気がさしたようだ。
実際僕も、この討論会にはへきえきしていた。まるで賢者であるかのごとく自分よがりの批判を浴びせてくる。
▽46 「友よ」ちょっと前までシングアウトの曲としてもてはやされたが……ファンの間でもシラケたムードでとらえられていた。岡林伝説は終わりを告げ、同時に、若者が心酔していたフォークも、ニューミュージックというものに形を変え、違う方向に行ってしまう。
□五つの赤い風船 西岡たかし
▽62 「遠い世界に」
□高田渡
▽76 ウディ・ガスリーやピート・シーガーの影響を受けていた。……「自衛隊に入ろう」も、原曲はピート・シーガー。明治・大正の演歌も。演歌師の添田唖蝉坊。彼らの詞を外国の曲にのせて歌う。「冷やそうよ」「現代的だわね」「しらみの旅」など。
ここでいう演歌とは、北島三郎や八代亜紀らの流行歌ではない。明治にはじまった自由民権運動での書生節、壮士節であり、アジテーションを唄に託して街頭で行ったところ、演説調の歌であることから「演歌」と呼ばれるようになったものを指している。
▽83 ステージで酔っぱらって寝てしまう
▽90 「コーヒーブルース」「三条へ行かなくちゃ 三条堺町のイノダへね あの娘に逢いに」
フォーク好きの若者は京都にいくと必ずイノダを訪ねたものだ。
□遠藤賢司
▽98 アングラ・フォーク以前、カレッジフォークの時代には東京勢は関西に比べ一歩抜きん出ていたが、関西フォークが台頭してきてからは、肩をならべられるグループやシンガーは東京には数えるほどしかいなかった。
□加川良
□三上寛
▽132 主流だったURC系のフォークはアメリカのフォークの影響を受けていたが、三上は、ド演歌。怨歌。情念の世界を詞にしていた。ステージ外でも破天荒。ライブが終わったらもうそのソファーで女性とイタシている……
□斎藤哲夫
▽155 「今のキミはピカピカに光って」詞は糸井重里。
□吉田拓郎
▽161 拓郎の周りの女性ファンがフォークを違った方向に持って行ってしまう。……アングラ・フォークがもてはやされるようになってから、若い女性のフォーク・ファンが会場の前列を独占するなどという光景は久しく見たことがなかった。……キャーキャー騒ぐ女性ファンをみて、アングラ系のコンサートに拓郎がでると、彼に対する「帰れ」コールがすごくなってきた。
▽171 「帰れ」コールからデモ隊が舞台を選挙し一方的討論会がはじまり「入場料に対する疑問」「ジャンボリーの意義とは」……という時代。
▽174 フォークは硬軟にわかれ、ファンも二分される。拓郎らを支えたのは、アングラ・フォーク創成期に小中学生だった子どもたち。彼らにとっては、拓郎の音楽は非常に入りやすかった。
岡本おさみが作詞、拓郎が作曲した「襟裳岬」
……レコード会社も眼を付け、各社こぞってアイドルや歌謡歌手にフォーク調の曲を提供し、気骨があった精神を希薄なものにしていく。プロの作詞家・作曲家が入って、内容の薄っぺらな青春歌謡を與に送り出すようになる。
□武蔵野たんぽぽ団
□RCサクセション
□泉谷しげる
▽227 海援隊「泉谷に東京に出てこいといわれた」72年に上京。73年に「母に捧げるバラード」でヒット。それ以後、キャバレー回りをしたりするが、77年に「あんたが大将」で復活。
□もんたよしのり
▽250 もんたは、ロックバンドをしたがえていたから、労音で批判のターゲットに。
□友川かずき
▽264 東北弁 「しらけ鳥 飛んでゆく……」は友川が歌い始めた。
▽273 ぼろアパートに住んで、土方をして、ヒマがあればパチンコ屋に通う……いまだに70年代をひきずっているのは友川ぐらいじゃないか……
□井上陽水
▽284 九州出身のアーティストが続々登場。先駆けが陽水。「海援隊」「チューリップ」「甲斐バンド」などがそれに続く。(地方の時代)
▽289 陽水のフォークは、叙情的で自分の日常感覚、生活感情を詞にしたものが大半。よくいえば洗練されているが、悪くいえば軽い感じに見られた。「傘がない」にしても……
▽295 70年安保を控え、ベトナム戦争が勃発し……若者は唄で挑んだ。歌う事で、参加することで社会に対して疑問を抱き自問自答した。しかしそれもしらけムードという流行言葉とともに、若者の関心から去っていった。
▽297 兄や姉の聴いていたフォークを、自分たちの音楽として聴くようになった。フォークの匂いのする、心地よい音楽であればよかった。
□なぎら健壱
▽319「悲惨な戦い」「葛飾にバッタを見た」
▽323 「およべたいやきくん」とカップリングの「いっぽんでもニンジン」を歌っている僕は、こんなヒットするとは思わず、印税契約ではなく、買い取りで契約してしまった。3万円のギャラで手を打ってしまった。
▽329 金八先生につづく「仙八先生」に出演。
□解説
なぎらゆかりの15人のフォークシンガー。70年代後半から80年代にかけて、フォークは衰退の一途を辿っていたが、95年ぐらいから若者たちの間でもフォーク復活の兆しがあり……かつてフォークが嫌われたのは、鬱陶しいメッセージや特有のライフスタイルといった二次的要素に原因があったのではないか。






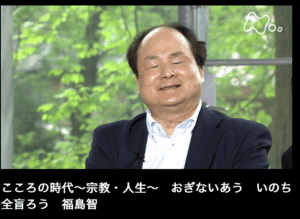

コメント