■講談社文庫 20190225(新幹線で)
磯辺という男は妻をがんで亡くそうとしている。子どもがいないから妻が死んだら一人になる。
妻は、「命は決して消えない」と樹木が語ったと言う。死を間近にすると不思議な感性が得られる。それは永遠の命とつながるものなのか。「この4,5日だと思います」と言われ親せきを集める。そうだ、言われた。「あしたにでも来てもらった方が」と。真に受けなかったが。
「必ず…生まれ変わるから、この世界の何処かに。探して…わたしを見つけて…約束よ、約束よ」
磯辺の妻はそう言い残して死んだ。
洋服の保管場所、冬服は押入の桐の箱Aにある。服は必ずブラシをかけ、季節ごとにクリーニングすること…。遺された「手帖」には、生活のやり方のひとつひとつが指示されていた。
辛いのは、帰宅して妻の使ったものを眼にすること。家計簿や電話帳に残っているちょっとした筆跡nあどが眼についた瞬間、鋭い錐を突っ込まれたように胸に痛みが走った。「妻が死ぬまでは、そんな死後のことなど、まったく無関心でした。死のことさえ考えたこともありません」
前世が日本人だと言っている子がインドにいると聞いて、インドツアーの説明会に行く。そこで病院にボランティアに来ていた成瀬美津子と再会する。
美津子は大学時代は遊び人で、まじめな大津という男をもてあそぶ。実業家と結婚してふつうの主婦になるが、離婚してしまう。愛に飢えながら、愛がわからない。
沼田という童話作家の男は、動物を描き、動物と対話する。結核になって死を意識したが、九官鳥が身代わりになってくれたと感じている。
木口という男は戦争中ビルマで死線をくぐってきた。命を救ってくれた戦友は木口を救うために人肉を食い、それがトラウマとなって酒におぼれて亡くなる。その弔いのためにインドに来ることにした。
これらの登場人物たちがインドツアーで出会う。
とくに磯辺の話は、読むのが苦しい。かわした会話が、激痛をともなって心によみがえってくる。
ガンジス川沿いのバラナシは、人が死ぬために集まってくる街だ。
ガンガーに流すため遺体があつまってくる。息を引き取るために巡礼者もつどう。「深い河」はそれらの死者を抱きかかえて黙々と流れていく。
一行と添乗員はここにやってくる。
磯辺は生まれ変わりと思った子とは会えなかった。彼にはこの世の中で妻への思い出だけがもっとも価値があるものに思えた。失ってはじめて妻の価値や意味がわかった気がした。
彼(イエス)は醜く、威厳もない。みじめで、みすぼらしい
人は彼を蔑み、見すてた
忌み嫌われる者のように、彼は手で顔を覆って人々に侮られる
まことに彼は我々の病を負い
我々の悲しみを担った
「信じられるのは、それぞれの人が、それぞれの辛さを背負って、深い河で祈っているこの光景です」
「少なくとも奥さまは磯辺さんのなかに、確かに転生していらっしゃいます」
(イエスは)昔々に亡くなったが、彼は他の人間のなかに転生した。今の修道女たちのなかに転生し、バラナシにあつまる人々を世話して、死者をタム大津のなかに転生した。担架で病院に運ばれていった彼のように修道女たちも人間の河のなかに消えていった。
「深い河」とは、人々が生きて死んでまた生きる繰り返しの流れ。転生のことを示すのだろうか。
水俣で村人たちがチッソを訴えたのは、廃駅を流したことだけでなく、祖先や亡くなった両親や親類や兄弟が魚になって生き、やがては彼等もそこに生まれかわる次の世を破壊したからだった。だが、次の世などを信じないジャーナリズムは、そんなことより環境破壊のことや病気のことに重点をかけてた報じた。
遠藤はキリシタンだけど、東洋の信仰に近いものをもっているようだ。


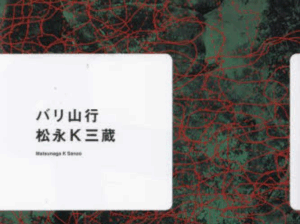





コメント