ベトナム帰還兵から写真家になり、アジアの民衆を撮ってきた夫が2003年に急逝する。妻である監督は、夫の死の遠因が枯葉剤かもしれないときき、ドキュメンタリー映画の撮影を決心し、ベトナムに飛び、かよいつづけている。
枯葉剤はベトナム戦争中に米軍が当時の南ベトナムの森林地帯に散布し、ダイオキシンによって健康被害が続出した。日本ではベトちゃん・トクちゃんが有名になり、1990年代までは、ぼくも関心をもっていたが、いつのまにかわすれていた。
2004年にベトナムをおとずれた監督はまず、産婦人科医としておおくの奇形児をとりあげた女医をたずね、その後、被害者の家を一軒一軒たずねる。
子供の障害にショックをうけつつ、ともに生きようとする努力する母親。兄弟の世話をしながら「将来は医者か先生になって助けたい」とかたる15歳の女の子。手足がなくてもバイクに乗って、仕事をしながら働く若者……にであう。
10年、15年後、彼らはどうなるか。
障害のある子をかわいがっていたお母さんは老いて笑顔をうしなう。1日中すわりつづける4人の子を一人で世話する老いた男性は「自分が死んだあとのことまでかんがえる余裕がないし、かんがえたくない」。
「医者になりたい」と夢みていた少女は学費が工面できず進学をあきらめ工場ではたらいていた。
ベトナム経済が急発展するのと裏腹に、年月とともに、被害家族の絶望はふかまっていく。
枯葉剤をまいた米国や製造した企業の責任もみとめられない。
米国は因果関係をみとめない。米国内でおこした裁判では、「枯葉剤は禁じられている化学兵器ではない」と相手にされなかった。
フランス国籍を取得した女性が製造企業のモンサントなどを提訴しても「米国を裁くことはできない」と門前払い。
世界の人々の関心はうすれ、加害者側もわすれる。弱い国の弱い被害者だけが苦しみつづける。
なんだろう。この既視感は?
そうだ。水俣だ。
何度も何度も裁判をおこし、国やチッソの責任はみとめられてきたのに、認定基準はきびしいままで、年齢とともに症状がでてきても水俣病と認定されない。世間からは忘れられていく。
被害者の子ども世代(第2世代)がたちあがるが、社会の関心がうすれるなかで裁判でもまける。
そんな状況にたいして、故原田正純医師はこうかたっていた。
「和解後の闘いをつづけたごく少数の関西訴訟の『反乱軍』のためにひっかりかえった(最高裁で勝訴)……世の中を動かすのは、僕は多数派じゃないと思うんですよ。だからね、溝口訴訟や第二世代訴訟をたたかうあの9人が問題をずっとあきらかにしていくんです。だからといって、いつも思うような判決が出るかというのはまた別問題。……だけど、異議を申し立てた人たちが少なくともいたっていうことは、裁判を通じて歴史に残っていくじゃないですか」
枯葉剤の被害者たちは、水俣の患者以上に絶望的な状況だ。この映画にも救いはない。だけど、苦難をのりこえるためにたちあがり、その苦しみを歴史にきざむ人がいるかぎり、「救い」はなくてもかすかな希望はあるのではないか。
それはたぶん、この映画をみたぼくらが忘却をこばみ、なんらかの行動にうつるところからはじまるのではないか……とおもった。






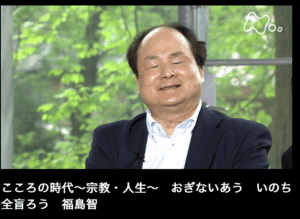

コメント