鹿児島港からフェリーで12時間、島民わずか100人というトカラ列島・宝島の介護施設を舞台にしたドキュメンタリー。
宝島は絶海の孤島として有名になったことがある。監督のことも映画のことも知らず、ただ宝島を知りたくて見てみた。
1992年生まれの若手の監督が半年間、島に滞在して撮影した。ちょうど同じとき、近くの島の出身だけど、東京に住んでいた25歳の若者が、その施設の責任者として赴任することになった。
その男性と監督はまるで双子のように、離島暮らしに閉塞感を感じ、少しずつ心がときほぐされていく過程を描いている。
宝島には飲食店はない。店は1軒だけで3時間しか営業しない。「想像以上につらいです」と赴任した若者は弱音をもらす。
施設には96歳のおばあさんが住み、ほかに2人のおばあさんが通ってくる。
96歳の女性は、ビニールひもでわらじをつくり、大切な言葉を書きとめ、田んぼの祭りでは腕だけでリズミカルに踊る。
おばあちゃんのそんな姿と接することで、「島の人に頼られる人間になるには、自分から飛びこまないと」と、老人会との交流会を施設で開く。こわばっていた顔が3,4カ月たつとほぐれていくのがよくわかる。
一方、離島の年寄りにとって一番問題なのは医師がいないことだ。治療のためではない。死亡診断をする医師がいないから島で死ねないのだ。
生まれて90歳になるまで島で暮らしてきた人たちが、死ぬときは島から引きはがされる悲しみ。
まじめにつくったドキュメンタリーだから、それらのことが伝わってくる。
孤島の老人はなにが楽しくて、なにに幸せに感じて島に住みつづけるのか。
たぶんそれは死者とのつながり。神ごとを大切にしていること。単なる介護ではなく、そういう生活を支えなければならない、ということが映画でも紹介されている。
でもちょっと弱い。死者とつながるからこその明るさ、死生観のようなものを見せてくれれば、もっと深みがでたのに、と思った。






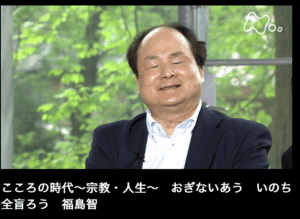

コメント