舞台俳優で演出家の主人公は、脚本家の妻と暮らしていたが、妻は突然死してしまう。
妻は主人公の目を盗んで浮気していた。そのことを主人公は知りながら、関係が壊れるのをおそれて知らないふりをしていた。
妻の死から2年後、広島で演劇の演出をまかされることになり、主人公の専属ドライバーとして若い女性がつくことになる。
負い目をもったまま主人公は妻を亡くし、女性ドライバーは、天災で救助を怠って母を亡くしていた。
身近な人を失い、欠落をもった男女が生きる意味をふたたび見出すという、村上春樹によくあるパターンの物語だ。
チェーホフの劇を劇中劇につかっている。その劇は、中国語、ロシア語、日本語、韓国語の手話というバラバラの言語で演じる。その練習風景の描写は興味深い。
3時間という長尺のなかに何を盛り込み、主題として何を伝えるのだろう、と期待した。
チェーホフの作品のなかに「つらく苦しい人生を自らすすんで引き受けよう。死んであの世に行ったとき『こんなつらい人生を送りました』と神様に語り、なぐさめてもらえたらそれでいいじゃないか」という主旨の言葉があったと記憶している。この映画の主題もけっきょく、そこのようだ。
でもいまひとつ説得力を感じなかった。
村上独特の抽象的でふわふわしたもってまわった言い回しは、「羊をめぐる冒険」を20代で読んだときは夢中になった。
明治の文豪たちは「家」や「伝統」との葛藤を描いていた。ガルシア・マルケスや中上健次らは血統や根っこを描ききった。
一方、村上からは「根っこ」や「伝統」を感ない。「根っこ」に依拠しないから文化の基盤の異なる欧米の読者にも受けるのだろうが、そのぶん薄っぺらい。
「ドライブ・マイ・カー」も、個人のトラウマや悩みを個人とその周囲の人間関係のなかだけで描き、ボヤッとした抽象的な「解決」を見つけだす。
チェーホフの作品は、ロシアの大地性が背景にあるから深みを感じる。「ドライブ・マイ・カー」に出てくるチェーホフの劇中劇は個人の精神は描くが、大地性や「根っこ」は表現されない。
若いころは、このふわふわ感に共感したのだろうけど、人生経験や取材経験をしてきた今は、歴史に影響されて歩んできた自分の人生の方がよほど刺激があるし、つらいし、心を動かされる。
この映画は、人生経験の浅い若者や、悩みや苦悩が抽象レベルにとどまっている苦労知らずの大人にはぴったりなのかもしれない。






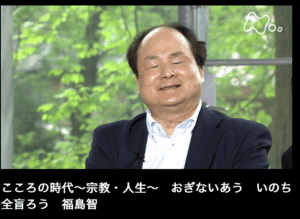

コメント