■タゴール・ソングス 20200711
アジア人初のノーベル文学賞受賞者であるタゴールの詩集は以前に読んだことがあった。自然描写の美しさと、意志の力を感じさせる作品が多かった記憶がある。
小説や詩のみならず、2000曲以上の歌もつくっており、「タゴール・ソングス」というジャンルになっているとは知らなかった。
1940年に亡くなっているが、ベンガル語圏では今もふつうの人が口ずさみ、苦しい時や悲しい時の生きる指針にしているという。
作品中何度も歌われる「ひとりで進め」は、映画を見終わった後も頭のなかでメロディーと歌詞がリフレインしつづける。「もし誰もが口を閉ざすのなら…本当の言葉を ひとりで語れ」
「誰も振り返らないのなら…茨の道を 君は血にまみれた足で踏みしめて進め」
「もし光が差し込まないのなら…それでも君はひとり雷で あばら骨を燃やして 進み続けろ」
きびしい歌だ。ガンジーもこの歌を好んだという。
タゴールはコルコタの大富豪の御曹司だけど、おそらくインドの独立を求めて悩み苦しんでいたのだろう。「ひとりで進め」はそんな時代の覚悟をうたっているように思える。
タゴールの歌をめぐって、人々が「愛」について語りあう場面も印象的だ。愛するというのは、明るく楽しいだけではない。本当の愛とは、苦しくつらいときに寄り添うことだ。だから愛は神聖なのだ……と。
人が悲しみやつらさに沈んでいる時、それまで何気なく口にしていたタゴールの歌は、生き抜くための知恵を光のように開陳してくれる。だからタゴールを追求する音楽家は、一生をかけて作品に潜む生きる知恵を学ぶ哲学者のようなものなのだ。
聖書やコーラン、仏教の経典などは、その多義性ゆえに、聴く人の状況や年齢によって、さまざまな知恵をもたらしてくれる。タゴール・ソングスはベンガルの人々にとって聖書のような存在なのだろう。しかも「歌」だから文字を読めなくても自然に頭に刻まれる。その点で、お経やバイブルよりすぐれている。すごい文化だと思う。
インドの音楽は「神」をうたうことが多いが、タゴールは「人」を中心にうたうから、ムスリムにもヒンズーにも共感されるそうだ。たぶん彼は宗教対立をふまえて、一方に偏らないようにするために、ヨーロッパ的な「人」を採用したのだろう。でも彼が暗示する世界はきわめて宗教的だ。「あらゆる宗教のその根源にあるなにか」を示しているように思えた。
目次






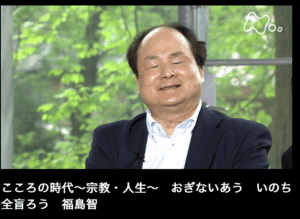

コメント