農家の会話の内容はぼくら都市住民には外国語のようにチンプンカンプン。生活から「農」をうしなったわれわれにとって「百姓の国」はもはや異国になってしまった……という場面からはじまる。
農文協の職員は、50台のスーパーカブで村々を訪ね農家の話をあつめ、雑誌「現代農業」を100年間だしつづけている。この農文協をとおして全国の農家を4年間かけてたずねたドキュメンタリーだ。
全国トップクラスの福島の米農家は、バケツで肥料や水の量をかえて稲を栽培する実験をくりかえす。トマトが「赤ナス」とよばれたころから栽培する千葉の93歳は「記録をとること、新しいことに挑みつづけること……」をモットーに20種のトマトそだてる。
甲子園球場123個ぶんという田んぼをつくる一家は、高齢化した農家の田も次々うけおう。30〜50ヘクタールをこえたらスケールメリットはない。農業機械を増やしたら出費がふえすぎるからだ。投資を減らす工夫を重ねる。田植機は1台だけにして、時期の異なる14品種をつくり、順番に少しずつ田植えができるようにしている。
佐賀県のきゅうり農家は、二酸化炭素濃度や温度、湿度を自動調整するオランダの最新技術を駆使する。ただ、ハイテクだけでは収穫にはつながらない。最大効率で光合成させるには、生育状態を観察する百姓の目が欠かせない。彼はそうした技術をおしげもなく若者に教える。
八郎潟は1964年に干拓されて589戸が入植したが、減反で多くが危機におちいり、「闇米」と陰口をたたかれながら「産直」をはじめる。農協や行政の精米施設をつかえないからみずから整備する。それによって出た大量のぬかを発酵させて田んぼにまくと良質な肥料になった。トマトなどを接ぎ木する際、砂糖とヨーグルト、納豆、酵母菌で手作りした発酵液をぬることで病気を防げた。減反政策への反発とその後の努力が微生物の活用技術を得させた。
福島県から原発事故で山梨に移住したタラの芽栽培の名人は、夏にタラの芽を収穫する方法を発見した。技術を惜しげもなく各地の農家におしえ、タラの株もゆずる。
土着天敵をつかって、コナジラミなどの害虫をふせぐ技術は、高知の農家があみだして全国にひろめた。
種苗法が2020年に改定され、登録品種は、許可がなければ農家が自家採種できなくなった。中国などに種苗が広がるのをふせぎ、農家の利益を守るというタテマエだ。だが、枝をポキンと折れば、盗むのは簡単だ。1房1万円の輸出用シャインマスカットをつくる農家は「肥料や水の管理などの技術で品質はおおきくかわる。タネが盗まれることは心配していない」という。
種子を牛耳ろうとするグローバル企業は「知的財産」をかこいこもうとする。「種子法」改正は農家ではなく、そうしたグローバル企業の利益を守るものだった。
「百姓の国」では、生みだした知恵も技術も種子もみんなで共有する。「百姓の共有財産を守りたい」というスタンスは知的財産のかこいこみとは正反対だ。
おそいかかる多くの危機をのりこえてきた篤農家・百姓のすごみは、「百姓ネットワーク」をきずき、技術や知恵を「共有する」ことではぐくまれてきた。農業の未来は、資本主義的な効率化ではなく「百姓」の経験のなかにこそある。
現在の「知」(知的財産)のありかたや資本主義は、けっしてあたりまえではないのだと気づかせてくれる。
=====
・福島の碓井勝利さんは、稲とリンゴ。米の反収は全国トップクラス。バケツ稲で実験をくりかえしている。リンゴは切って3日放置しても酸化して赤く変色することがないという。
・千葉の若梅健司さんは93歳でトマト栽培の先駆者。「農業は道楽、記録をとること、新しいことに挑みつづけること」という心構えで取り組んできた。70年前、「西洋の赤ナス」と呼ばれたトマトを栽培をはじめた。20種類を作っている。
・46歳の横田修一さんは、父と子ども6人と11人の社員で甲子園球場123個ぶん150ヘクタールという広大な農地をたがやしている。周囲の農家は高齢化し、田んぼづくりを託される。そのすべてを引き受ける。30−50ヘクタールをこえたらスケールメリットはなくなる。国の依頼で無人トラクターの実験もひきうけるなど、工夫を重ねている。田植機は1台だけ。ぜったいに増やさない。田植えが4月の品種から6月の品種まで14品種をつくり、少しずつ田植えができるようにしている。国は「担い手」づくりの政策をかかげたが失敗した。その失敗を百姓の知恵で克服しようとしている。
・山口県の村田洋さんは養鶏や畜産。大量に出る鶏糞をどうするか。周囲の農家に飼料米をつくってもらい、その肥料として鶏糞をつかってもらおうとこころみている。農家をあつめる「視察会」などでつながりと信頼をつちかう。
・佐賀県の山口仁司さんはきゅうり農家。二酸化炭素濃度や温度、湿度を自動で調整するオランダの最新技術を駆使する。ただ、先進技術だけでは足りない。最大効率で光合成をさせるためには、「農」の知恵や眼力が不可欠だ。そうして得た技術をおしげもなく教えている。「短期的な利益は長期的利益とはなりえない」という確信は、資本主義のあり方へのアンチをつきつける。
・八郎潟では、1964年に干拓されて589戸が入植したが、減反で5人が自殺した。1985?年から産直をはじめる。当時は「闇米」といわれた。農協や行政の精米施設をつかえないからみずから整備する。従来はもみや玄米の形で消費地に届けていたが、精米施設をもつことで大量のぬかが出た。それを田んぼにまくと、ぬかの菌が土壌の有機質を分解してくれた。トマトなどの接ぎ木をする際、病気が最大の敵だが、発酵液をつかうことで病気が防げた。発酵液は、砂糖とヨーグルト、納豆、酵母菌で簡単に手作りできた。減反政策に反発することから微生物の価値に気づくことになった。
・栃木県の上野長一さんは、赤米や黒米など600種の米を作っている。
・種苗法が2020年に階梯され、登録品種は、農家による自家採種も許可がなければ禁じられた。
百姓の国の知恵は、みんなで技術を共有する。
逆が、種子企業のような「囲い込む知」だ。
現場にタネが生きていなければ意味がない、と、魚住さんは訴える。
・シャインマスカットをつくる農家の深谷聡さん。1房1万円で東南アジアに輸出することも。種苗法改定はそうした農家を守るため、というスタンスだった。だが、悪意があれば持ち帰るのは簡単だ。さらに、土壌や水管理などの技術がことなれば味はまったく異なる。「ぜんぜん心配してない」という。
・農文協はタネの交歓会をしている。交換することで、自分のタネがなくなってもまた返してもらえる。「タネかえし」だ。硫黄島の野生トウガラシなど、さまざまなタネがある。
・国連小農宣言?には、小農の種子にたいする権利などももりこまれている。 128カ国は賛成し、米国など8国が反対。日本などは棄権した。
・南相馬小高の細川勇喜さんは原発事故で山梨に移住した。タラの芽の栽培の名人。山梨の花火大会で看板がおおわれてしまうからタラの芽を切ってくれといわれて切ったら、8月にも芽をだすことがわかった。全国初だ。そういう技術も惜しげもなくひろめ、タラの木の株もくばる。
・「百姓の共有財産を守りたい」そのスタンスは知的財産の囲い込みとは反対だ。
・岡山軒真庭市の清〓健二さんは、木材ペレットのバイオマスをつかったハウス栽培をしていたが、コナジラミなどの害虫が悩みだった。高知の安芸市のとりくみをきいた。野菜のとなりにクレオメをうえておくと、タバコカスミカメという地場の天敵をすいよせる。それが害虫をくってくれる。「土着天敵の利用」が高知では盛んだ。
・百姓がつみかさねる知恵や技術のすごみ、かこいこむのではなく共有することで発展したことがよくわかる。農業の未来は、百姓たちの経験のなかにしかない、と。






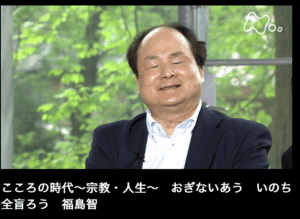

コメント